クローズアップテーマ
【その1】テレビの未来を見据え「ながら。」 ~真説・メディアの同時利用論~ 7. 真剣に見ない、見せない、社会の雰囲気を浴びる、というビジネスの重さ
2009年05月11日 井上忠靖氏 (電通総研 コミュニケーション・ラボ チーフ・リサーチャー)、倉沢鉄也、、叶内朋則、紅瀬雄太
7. 真剣に見ない、見せない、社会の雰囲気を浴びる、というビジネスの重さ
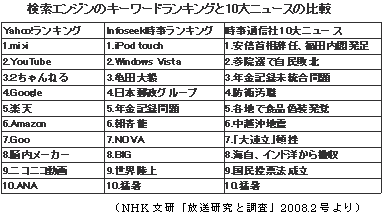 (倉沢)ニュースと世間の話題ということでは、ちょっと面白いデータをNHK文研が調べているので、ご紹介します。検索エンジンのキーワードランキングと10大ニュースの比較、なんですが、時事通信の重大ニュースを、我々の知っている本来の10大ニュースとしますと、これがインフォシークやヤフーでの上位検索キーワードとはまるでずれているのです。つまりPCしか見ていない人が肌で感じるのは、iPodはともかく、亀田、郵政、朝青龍、NOVA、というあたりが彼らの1年間の主な出来事であって、安倍総理辞任などいうのは検索数ベスト10に入ってきません。もちろん日本国民にとって本当に安倍総理辞任が本当に一番大事なニュースなのかという究極の吟味は必要かもしれませんが。
(倉沢)ニュースと世間の話題ということでは、ちょっと面白いデータをNHK文研が調べているので、ご紹介します。検索エンジンのキーワードランキングと10大ニュースの比較、なんですが、時事通信の重大ニュースを、我々の知っている本来の10大ニュースとしますと、これがインフォシークやヤフーでの上位検索キーワードとはまるでずれているのです。つまりPCしか見ていない人が肌で感じるのは、iPodはともかく、亀田、郵政、朝青龍、NOVA、というあたりが彼らの1年間の主な出来事であって、安倍総理辞任などいうのは検索数ベスト10に入ってきません。もちろん日本国民にとって本当に安倍総理辞任が本当に一番大事なニュースなのかという究極の吟味は必要かもしれませんが。こういう時代の中のニュース報道のあり方というのは、ここでは深く議論しないつもりです。一言で言うと、ネットでニュースしか見ていない人にとって、「世の中で起こっている大事なことを、自分は知らなかったかもしれない」と思う貴重な機会が、通信社や新聞社が提供しているニューステキストであったり、ふとつけたテレビのニュースだったり、ということであってほしいのです。そうでないと日本という国の将来はこわい感じがします。
ふと目にしたその情報は、自分の気づかなかった大事な出来事だと気づかせる役割が、今の新聞やテレビにできているのなら、若者もまだテレビや新聞の社会的役割というものをぼやっとでも認識しているのです。逆にそういうふうに気にかけられなくなったときこそ、報道という存在の本当の危機であり、当然ながらマスメディアのビジネスの本当の危機ということなのだろうと思います。
(井上)それは大事な議論です。テレビを衰退させたい議論が盛んですが、では仮にテレビを衰退させたときに次はどうなるのか、今のテレビが担っている社会的な機能をだれが担うのか、というのはインターネットや携帯電話のビジネスの今後にとって一番高いハードルだと思っています。つまり、「ながら」で見ることができて、みんなが話題にしているからそれとなくつけっぱなしで、たまに気がついて画面を見る、でもそんなに期待感もないよ、というメディアの役割をインターネットや携帯電話が果たさないと、その業界がうらやましいと思っているテレビのビジネスを食っていくことはできない、新しいメディアがそこを突破できるか、ということが壁なのです。そこを突破できれば、新しいメディアのビジネスはもっと花開きます。
(倉沢)テレビ以外に、真剣に見られないメディアが出てくる兆候がありますか。
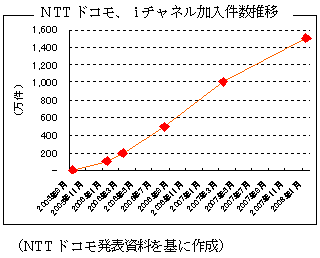 (井上)そういった意味で、ドコモのiチャネルやauのEZニュースフラッシュなどは面白い存在で、加入者も確実に増えています。あれは、携帯電話の画面を立ち上げるとテキスト情報が飛び込んでくるという点で、非常につくりがテレビっぽいです。将来的には絵もつくと思いますが、そうなるとテレビの競合としてかなりいい線行くと思います。ケータイはこのあたりを切り口に、どんどん「テレビ化」に向かっていくような気がします。
(井上)そういった意味で、ドコモのiチャネルやauのEZニュースフラッシュなどは面白い存在で、加入者も確実に増えています。あれは、携帯電話の画面を立ち上げるとテキスト情報が飛び込んでくるという点で、非常につくりがテレビっぽいです。将来的には絵もつくと思いますが、そうなるとテレビの競合としてかなりいい線行くと思います。ケータイはこのあたりを切り口に、どんどん「テレビ化」に向かっていくような気がします。そういった、単純さを追究するようなメディアの進化の仕方のほうが、生活者目線から見たときにはずっとリアリティーがある未来のように思えます。かつて未来学者が語っていたような、生活者が自らこれを見たい聞きたいと一生懸命探して、ビデオオンデマンドが一大市場になります、といった話は、結局リアリティーをもって受け入れられませんでしたね、というのが、生活者の実態から見たところの結論のひとつだという気がします。
(倉沢)iチャネルなどが受け入れられてきているのも、真剣に見ていないニュースが流れている、という程度の情報量でしか受け取らない人が世の中の大多数だということを示していると思います。情報処理能力の相当高い人でも、だらだらと受け取った情報をときに思い出しながら、それって何だっけ、と調べる、認識して終わり、という程度の「真剣に見られない感」が、おそらくマスメディアがマスメディアのビジネスを維持していることの根本的な理由でしょう。そういう単純なメッセージを、テキストではなくて、ステレオサウンドと20インチからのカラー映像が目の前から飛び出してくる、というメディアには現在誰もかなわないというのが、厳然たる現状です。
(井上)この、「真剣に見せない」つくりをインターネットなり携帯電話がしていかないと、マスメディアに近いビジネス規模にならないし、マスメディアのユーザーは奪えないだろう、と思います。メディアの未来論を語るときに、人々は情報を能動的に求めるように進化して、真剣に見られないメディアは消えていく、つまりいまのテレビを筆頭としたマスメディアは死滅する、という前提で議論するような風潮は、いい加減卒業した方がいいのではないでしょうか。
真剣に見聞きするメディアというのは、それはそれで一定のニーズがあって、そこの市場開拓はもっとできると思うのですが、たぶんそのマーケットは小さいです。人間、あふれる情報に対して真剣に向き合える時間とエネルギーは限られているからです。そして一番大きい市場は、真剣に見られないメディアがつくっているということに気づくべきでしょう。いまテレビが社会の雰囲気を支えている本質的な部分を奪い取れるようなメディアをこれからどう作るのか、作れるのか、という議論は、実はメディアに携わる人たちの中でもあまり進んでないと思います。
さらに言うと、その真剣に見る方のメディアも、ちゃんとビジネスを作れているわけではないという問題のほうも深刻で、課題山積みなんですね。なぜそうなるかというと、そもそもの出発点として、国民は真剣に見るメディアを欲しているのだろう、自分たちが欲しいから、みんな欲しいよね、という認識を出発点にしてしまっているところでボタンの掛け違えをしてしまっているからです。
その観点から一番将来性が懸念されるのは、ビデオオンデマンドがいつまでたってもビジネスとして花開かない話です。みんな見たいものがあるはずだ、それを探して、見せてあげたら、月300円くらいは払ってくれるはずだ、安いものだ、という思考回路ですね。しかし、一人ひとりに、いまなんとしても見たい映像や音楽というものは、そもそもないという発想に立つべきなのです。見たいものがない人に向かって、どうやって見たいと思わせるのか、どうその気にさせるのか、つまり需要を喚起するプロモーションが現代では一番必要とされていて、それがメディアバトルロイヤルと呼ぶべき状態の本質だと考えるべきです。
(倉沢)ビデオオンデマンドがレンタルビデオを駆逐するんだと夢見た人は1980年代からいましたね。そして2008年のいま、店でなんとなく借りてくるレンタルビデオの市場にすら届きません。レンタルビデオ屋は、これはこれでフランチャイズ制や流通経路を含めて店舗運営から離れられない事情もあるのですが、単に無店舗化してコストダウンすればいいというわけではないということがわかっているから店という形態をやめないし、宅配専門レンタルビデオ事業者が店舗の事業を食っていないのです。1本だけ借りたい、あるいは返すだけ、と思って店に来たが、棚を見て、なんとなく別のものも選んできてしまうという「プロモーションメディア」としての店や棚がなければ、現在の市場規模はできあがらないという簡単なことを、関係者は気づくべきでしょう。
(井上)DVDを所有したからもうそちらをずっと見るのだ、地上波で流れた同じ映画を見るやつなどいない、ということですらないのです。プロモーションがあるから見たくなるので、DVDをリリースした後に地上波テレビで上映するなんてばかげているという人は、その認識を根本から改める必要があります。
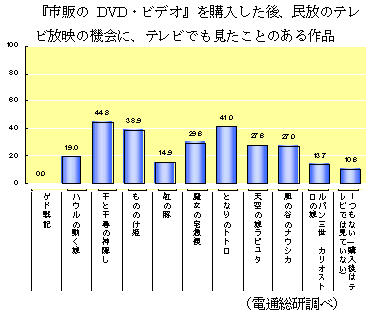 たとえば、あぁ8月だ、子どもも夏休みで、夏休みっぽいアニメでもちょっと見たいかな、と思ったときに、あぁトトロを金曜ロードショーでやるんだ、いいじゃない、なんだかちょっと見たくなってきた、金曜ロードショーってのは9時くらいからやるんだったな、あっもうはじまっていたけどテレビつけよう、あぁこのシーンからか、CMがここで入ったか、結局最後まで見ちゃった、面白かったー、11時過ぎだ子どもたちもう寝なさい、となる。でもこの家族は実はトトロのDVDを持っていたりするのです。
たとえば、あぁ8月だ、子どもも夏休みで、夏休みっぽいアニメでもちょっと見たいかな、と思ったときに、あぁトトロを金曜ロードショーでやるんだ、いいじゃない、なんだかちょっと見たくなってきた、金曜ロードショーってのは9時くらいからやるんだったな、あっもうはじまっていたけどテレビつけよう、あぁこのシーンからか、CMがここで入ったか、結局最後まで見ちゃった、面白かったー、11時過ぎだ子どもたちもう寝なさい、となる。でもこの家族は実はトトロのDVDを持っていたりするのです。これは実際に調査結果で出てきたものです。トトロのDVDを持っていた人のうち、4割が日テレが金曜ロードショーで流しているトトロの番組を「見ちゃった」というのです。持っているんだからいつでもどこでも見られるだろう、ユビキタスで映像を見る時代になる、ということにリアリティーはないのだという話です。
いまテレビが持っている、世の中の雰囲気を浴びせる機能に対抗するために、インターネットや携帯電話やその他新しいメディアにはどういう武器があるのか、どういう演出をすればコンテンツというものを引っ張りだしてお金を払ってくれるのか、ということを、真剣に議論できている人は少ないですね。
実際、数少ない成功事例といえるようなビジネスをインターネットや携帯電話の上でしている人たちの発言を聞いていくと、結構古めかしいことを言っているんです。たとえばヤフーの人の口から、「編成方針」とか「ワイドショー的」とか「わかりやすさ」とかいうキーワードが出てくるのです。気づいている方は気づいているし、気づかない人はいつまでも気づかないということのようです。
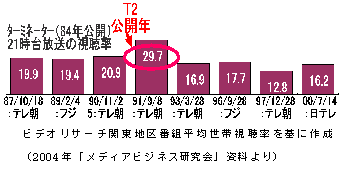 (倉沢)「家の外から飛んでくるメディアの雰囲気」というものの見方はとても重要です。今のトトロの話もそうです。雰囲気というのは何からできるかというと、平たく言えば人々が素直に納得できる宣伝です。ジブリの作品についていうと、ご存知のように最新作だったりDVDの発売だったりといったタイミングで、必ず昔の作品を金曜ロードショーでやっています。これがプロモーションになっているのです。
(倉沢)「家の外から飛んでくるメディアの雰囲気」というものの見方はとても重要です。今のトトロの話もそうです。雰囲気というのは何からできるかというと、平たく言えば人々が素直に納得できる宣伝です。ジブリの作品についていうと、ご存知のように最新作だったりDVDの発売だったりといったタイミングで、必ず昔の作品を金曜ロードショーでやっています。これがプロモーションになっているのです。これと似たようなことを、ターミネーター1という映画が地上波テレビで放映された時の視聴率について経年で調べたビデオリサーチのデータを見てみると、唯一ターミネーター2の上映年のテレ朝の放映だけが突出した視聴率を記録しています。ターミネーター1が面白いか面白くないかではなく、ターミネーター2の宣伝そのものが「1」も見てみたいという動機につながり、視聴率に効いた、言わばコンテンツ制作者自身が「2」のお金を使って「1」の番宣に加勢した、「1」を見たいと思う雰囲気を作った、見たいと思ったときに見る人ばかりであって、データで見るとこうなる、ということです。
(井上)雰囲気はメディアだけから出てくるわけではないということも、言っておく必要がありますね。それは地域という観点です。メディアの雰囲気とは実は東京の雰囲気なんですね。
(倉沢)それはローカルテレビ局がキー局の全国放送をそのまま流しているという、いわゆる「マイクロ受け」の番組が時間にして7割や8割にのぼっているという現実が証明していると言っていいでしょう。
(井上)日本全国で東京の雰囲気を感じたいということを誰も否定できないのですが、一方で地元の雰囲気を感じたいというケースがあります。具体的にはプロ野球ですね。東北には楽天があり、北海道では日本ハムファイターズがあり、九州にはソフトバンクホークス、仙台には楽天イーグルスがあって、これらの地上波テレビの視聴率が軒並みいいです。ゴールデンタイムで放映して、いま15%くらいは確実にとっているようです。サッカーは鹿島、浦和、清水などピンポイントなのでなかなか広域で視聴者を集めるコンテンツになりにくいところがありますが、地元としての盛り上がりはなかなかいいですね。
続きへ
このページの先頭に戻る
目次に戻る
関連リンク
- 1. テレビ視聴時間の減少が本質的な問題なのか?
2. テレビ視聴率という「通貨」の「信用危機」こそ重大問題
3. 「メディアバトルロイヤル」という現実と向き合う議論があまりにも少ない
4. 立ち位置先にありきの議論は、ビジネスの今後を見失う
5. 極限のコストカットと「面白さが命」の狭間に、コンテンツ二次利用の現実を見よ
6. 番組の質の低下?それは視聴者とビジネスの必然
7. 真剣に見ない、見せない、社会の雰囲気を浴びる、というビジネスの重さ
8. DVRのCM飛ばしは、正確な知識の上に、体験と切り離して議論すべし
9. インターネット広告をいかに見せるか、の工夫は続く
10. テレビを見ない女性、は依然マイノリティー。自己体験を消してデータを見よ
11. 不思議なメディアの国、ニッポン;欧米も個々に特殊。実情を踏まえて比較すべし
12. 制作費削減の煽りは、いずれローカル局問題へ
13. 広告主だって、そう簡単にテレビから離れられない
14. 見逃し視聴はユーザーが望むが、ビジネスにできるかが問題

