"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第31回「NTTの再再編問題を考える(下)――各プレイヤーの利得最大化のゲーム」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2003年7月24日
(1)IP競争時代のステイクホルダー(利害関係者)とは?
前回では、光0種会社(FP:ファシリティプロバイダー)の創設の意義について言及した。
これが実現するための要件は、ステイクホルダー問題に帰着する。つまり、光ファイバー(ダークファイバーを含む)を実質最も多く保有するNTT東西、 NTTの次に多くの光ファイバーを保有する電力会社(または電力系通信会社)などのホールセール(卸)が可能な事業者が、光0種FPの有力候補となる。ただ、アクセス回線として有効な光ファイバーを電力会社よりも多く持ち、かつNTT法問題の当事者であるNTT東西が最もふさわしいといえよう。
(注) 「ダークファイバー」:敷設されているものの、まだ使用されていない光ファイバーのこと。第16回「なぜ今ADSLか?――Yahoo!BBを分析する(上)」(2002/11/22)などでも言及。
その他のステイクホルダーとして、前回のとおり、その光0種インフラの上で事業を営むことのできる、いわゆる第一種および第二種事業者、あるいはISP(インターネット・サービス・プロバイダー)や、各種SP(サービスプロバイダー)、各種CD(コンテンツディストリビューター)、各種CP(コンテンツプロバイダー)を列挙できる。
さらに、わが国の国際競争力や市場競争の監視役である規制当局(総務省や公正取引委員会など)や、NTT自らの経営判断により、NTT東西から子会社への異動を余儀なくされたNTT従業員11万人の利害を代表するNTT労働組合、さらには自民党や民主党などの政治家(族議員)などの利害が、光0種FPの創設を巡り実質、鍵を握ることになる。
(2)ゲーム理論にみる主要プレイヤーの利得最大化の動き
図表をご覧頂きたい。これは一般的にゲーム理論における「ゲームツリー(ゲームの木)」と呼ばれるものである。
プレイヤー集合、戦略集合、ならびに各プレイヤーの効用関数というゲーム理論での基本事項を想定する。その上で、この光0種FPを巡る主要プレイヤーのうち、特に光0種ファシリティプロバイダー自身と、NTTグループ、さらにはその他事業者の3者の利害関係(利得)について、簡単に触れてみたい。
(注) ここでは、一般消費者への光ファイバー加入を促進するための方策として、IT 振興券の配布を巡る、江本・鈴木・竹内[2002]『日本のIT 戦略-ソフトウェアかハードウェアか?』なる興味深い研究にヒントを得ている。
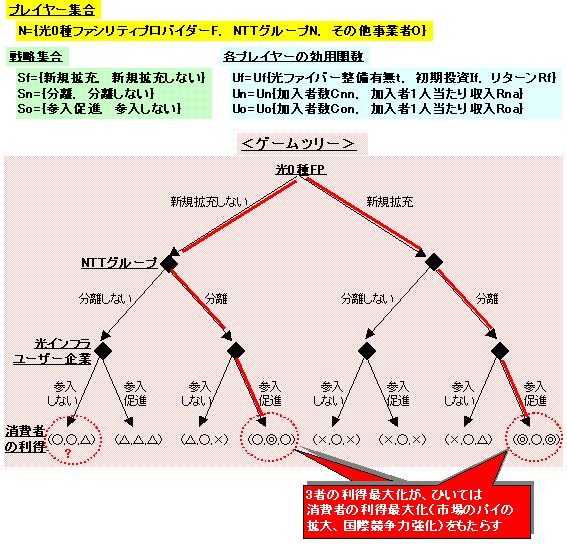
(出所) 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
ゲームツリーは、各プレイヤー、その行動(信念)、その結果としての利得で構成される。
まず「光0種FP」が、新規拡充しないという行動を選ぶ確率を例えばp、新規拡充を選ぶ確率を1-pと考える。そして、次に「NTTグループ」が、0種として光ファイバーインフラ事業を分離するかどうか、さらには、そのインフラの上でビジネスを展開できる「光インフラユーザー企業」が、そのインフラを活用したビジネスに参入するかどうか、などについて、それぞれのプレイヤーの行動に関する確率を推定(というよりも実際は想定)し、最後に、このゲームツリーでは8つのケースに関する利得を計算(または推定)することになる。
3者の利得最大化が、ひいては消費者の利得最大化(市場のパイ拡大、国際競争力強化)をもたらす。つまり、3者の選択する行動結果の組み合わせが、ブロードバンド時代の通信市場全体におけるパイの大きさを表すことにつながるはずだ。
ここでは、それら利得については簡略化し、◎、○、△、×といったように相対的に示している。この例では、破線の○印で囲んだ組合せが有望であることになるが、実際は今の段階では分からない。
実際には、「各プレイヤーの効用関数」を構成する、光ファイバーインフラ整備に関する初期投資、投資のリターン、同インフラを活用した場合の当該プレイヤーによる新サービスなどの加入者数、同加入者1人当たり収入(ARPU:Average Revenue Per User)などの要素を、具体化して推察することが不可欠となる。
この光0種FP創設の問題に加え、実際の創設の方法、FPの運用面での方法などについては、今回は触れない。
この種の議論でよく取り沙汰される、FP会社の従業員のモチベーション(動機付け)やインセンティブ(誘因)について、簡単に触れておきたい。つまり、光ファイバーといえども土管だけを建設し運営していく会社における従業員の士気の問題についてである。これは1996年当時のNTTの分離・分割問題でも議論になった。この士気についても、この種のゲームの鍵を握るある種の利得(効用、利害)と考えることができるからだ。
もしもメタル回線のみのFPであれば問題は解決しないであろう。しかしながら、光IP網ということであれば、その網がもつ経営の柔軟性(リアルオプション)を発揮できる。さまざまなサービスを展開できる潜在性が秘められている。
例えば、最近では、「ボイス・ミニッツ」といって、国際電話の計算料金問題をバイパスするなどワンビル化付加価値サービスが出てきた。管路、線路敷設権等でも専業事業者などとの取引があり、光0種FPの主要事業の一つとすることもできよう。また、「IPトランジット」という、キャリアが独自に敷設した海底光ファイバーケーブルなどの上にギガ級の帯域を確保するISPや企業向けのインターネット接続サービスも可能になる。さらには、「帯域幅」の市場取引の場としての意味もあり、いわゆる「エンロンモデル」が生かされる。
(注) 「エンロンモデル」:第6回「エンロンモデルは否定されたか?」(2001/12/06)に簡単に言及。
こうした新しいビジネスモデルを想定することで、光0種FPの存在意義や、同社従業員のやりがいの意味も俄然高まるに違いない。そして、高度な金融技術などを駆使した市場取引の場そのものの創設は、わが国にとってIP革命を世界に先駆けて成就する不可欠な社会・産業インフラになる可能性もあるに違いない。

