"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第30回「NTTの再再編問題を考える(上)――光0種会社の意義」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2003年7月17日
(1)NTTの再再編問題が浮上するだろう
先日、『IP革命のもたらす構造変革をどう乗り切るか?』なる小論で、IP(インターネット・プロトコル)時代の経営戦略を考えてみた。そこでは、戦略の経済性、リアルオプション、ゲーム理論、あるいは競争戦略などを少々解説している。もし読者の中でこれらにご興味があれば、次のページをご参照頂きたい。
◇ http://www.jri.co.jp/company/publicity/2003/detail/sbp_ip/
本稿で取り上げるNTTの再再編問題は、上記URLの中でも、「5. IPブロードバンド革命下のゲームの戦い方はルールを変えることが基本戦略 -----(4)ブロードバンド産業の行方に影響を与えるNTTの再再編問題」という項目で取り上げている。一方、本稿では、現在のブロードバンドの牽引役であるADSLに代わる本命の、光ファイバーを巡る見通しについて触れてみたい。
NTTの再編問題には筆者も1996年当時から、いろいろなかたちでかかわってきた。賛成、反対の意見が交錯するなか、当時のNTT経営陣と規制当局との間の取引もあってか、1999年7月に一応の「政治的な」決着をみたといえよう。わが国の情報通信(ICT)産業は、良くも悪くもNTT問題が中心にあり、今後も推移していく。
筆者は当時、NTTの分離・分割には反対の意見を述べていた。NTTのもつ地域網の人為的な分断によるNTTの一体的なネットワークの運用面での非効率性や、グローバル時代での国際競争力あるいは研究開発力の弱体化などがその理由だった。現在はいささか考えを改めている。
当時のインターネット(IP技術)は、おもちゃに見えた。IP革命が今ほどの影響を及ぼすことを十分予測できなかったことを認めねばならない。前述の小論では「1. 産業構造からの抜本的な転換を促すIP技術は破壊的である」として、ハーバード大学教授のクレイトン・クリステンセン氏による「イノベーションのジレンマ」の研究を参照しつつ、今のIP革命の様子を描写している。
現下の結論として言えることは、NTTの再再編問題が浮上することは必至だろう、ということだ。
なぜならば、1999年7月当時の再編の枠組みは、インターネット時代(IP革命下)のことがまったく考慮されていなかったし、また当時の関係者もそのことが十分に認識されてはいなかった。もちろん、1999年の少し前から、インターネットによる旧来通信産業へのインパクトの大きさ、意味合いなどについて、それらを明確に指摘する声も一部にはあった。筆者もその頃には同様のイメージがあった。しかしながら、少なくとも当時のNTTの構造的枠組みには明示的に反映されるには至らなかった。
(2)IP時代に馴染まない法律は見直す
その後、その年の12月末にはNTTドコモから「iモ―ド」サービスが開始され、翌2000年1月以降、携帯電話市場は大きな飛躍を遂げる。あるいは、 1997年をピークに固定電話のトラフィックや収入は減少に歯止めが効かない状況が続く。NTTにとっては期待のISDNや光ファイバーの普及を阻む、思わぬダークホース、ADSLサービスの普及が一気に進んだ。
(注)「ISDN」:Integrated Services Digital Networkの略で、総合デジタル通信網と呼ばれるサービス体系の総称。「ADSL」:Asymmetric Digital Subscriber Lineの略で従来の電話用メタリックケーブル上で実現される高速デジタル伝送方式の一つ。
1996年当時、NTTで唯一ADSLの研究を行っていたNTT光ネットワークシステム研究所研究部長の山下一郎氏は、「NTTはADSLサービスを行わず、光ファイバーをFTTHで敷設することに全力を注ぐ」と語っていたようだ。
(注)「FTTH」:Fiber to the Home:家庭まで光ファイバーを引き込むこと。
1999年以降、日本のDSLの牽引役、東京めたりっく通信が登場、そして、2000年以降にはアッカ・ネットワークス、イー・アクセス、ソフトバンクネットワークス(現在のソフトバンクBB)、@niftyやBIGLOBE、その年末にはNTT東西からの「フレッツ・ADSL」の提供開始があり、 ADSL回線ホールセール事業者などの参入で市場が拡大し、現在に至る。
こうしたなか、2003年5月22日、「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案」が参議院本会議、そして7月 10日に衆議院委員会にて可決。いわゆる電気通信事業法は廃止され、NTT法の一部が改正されることになった。
(注)但し、「第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の区分を廃止」については、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から」、また「日本電信電話株式会社等に関する法律(筆者注:いわゆるNTT法)の一部改正関係」については、「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行する」ことになっている。このNTT法の一部改正については、NTT東西間で特定接続料が同等の水準となることを確保するためものであり、NTT東西の足かせにもなっている(経営の自由度を縛っている)、ユニバーサル・サービスのあり方などについて論じているものではない。
これらの法律改正については、第一種や第二種といった事業区分の廃止など今更、といった感じでは否めない。現下のIP革命、ブロードバンドの進展についての追認といったところが実態であるからだ。
ただ総務省は、2000年当時、電気通信審議会に諮問した「IT革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方について」(平成12年諮問第29号)に対し、情報通信審議会(会長:秋山喜久)からの第二次答申を、2002年2月『IT革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方についての第二次答申の概要』として発表。IT革命の推進には、非構造的かつ構造的な競争政策も不可欠であるとの見解が示されており、その中でNTTの再再編問題が示唆されている。
(注)「IT 革命」:政府(総務省)やe-Japan政策などで多用されている言葉であるが、情報通信産業はITを意味する情報技術のみならず、通信(Communications)の意味を加えた、ICT(InfoCommunications Technology)革命、または、ICTにおけるより本質的なIP技術のことをクローズアップさせる、IP革命と呼ぶ方がふさわしいだろう。
その一部を次の図表に抜粋する。
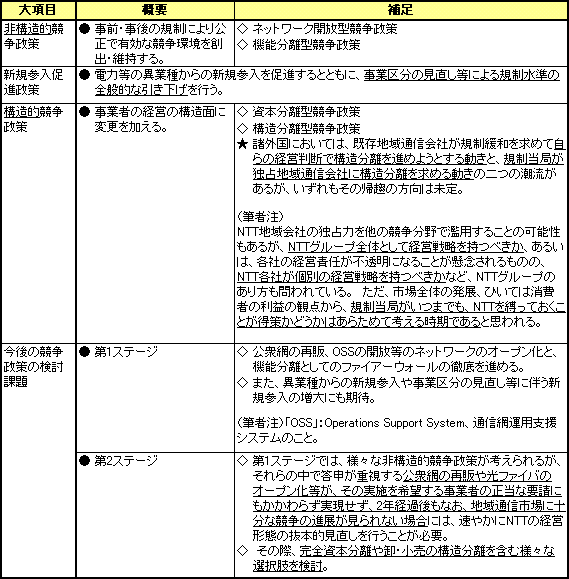
(出所)総務省『IT革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方についての第二次答申』(2002年2月13日)から抜粋。下線は筆者によるもの。
そもそもこうした答申がなされたのは、1999年のNTT再編が失敗であり、競争を機能させる手段としてNTTの完全民営化を必要とする声も背景にあるようだ。
(3)RENAおよび全国IP網を巡る各社の利得を考える
NTT持株会社は2002年11月、「"光"新世代ビジョン:ブロードバンドでレゾナントコミュニケーションの世界へ」を策定。その実現に向けた研究開発に積極的に取り組んでいる。その基礎にあるものが、次世代ネットワークアーキテクチャRENA(Resonant Communication Network Architecture)、すなわち光IPベースの基幹網である。
一方、NTT東西地域会社は、全国通信の可能なIP網を共同構築する構想を練っている。両社がフレッツ回線向けに構築した地域IP網とは別に、新たに構築する方針の模様。NTT東西によると、新IP網はトンネリング・プロトコルを使わないIP網とし、網内で利用するIPアドレスをIPv6ベースにするとのことだ。これらの特徴は、RENAが掲げる仕様と一致する。2003年6月の報道段階では、NTT東西は新IP網の構築時期などを明らかにしていないが、全国通信が可能な新IP網で、IP-VPN(仮想閉域網)やIPビデオ電話などの付加価値サービスが提供されれば、フレッツ回線利用者の利便性が飛躍的に高まることが期待される。
図表上段をご覧頂きたい。「×」「△」「○」「◎」などの記号により、3層モデルで見た場合の、NTTグループ各社のメリット(利得)を推定している。
(注)2002 年9月から2003年6月まで開催された、総務省総合通信基盤局長主催の「IP化等に対応した電気通信分野の競争評価手法に関する研究会」では、この3層モデルに注目した議論は皆無に近かった。今後のIP革命を推察するには、この3層別あるいは各層をまたぐ競争を議論する必要があろう。
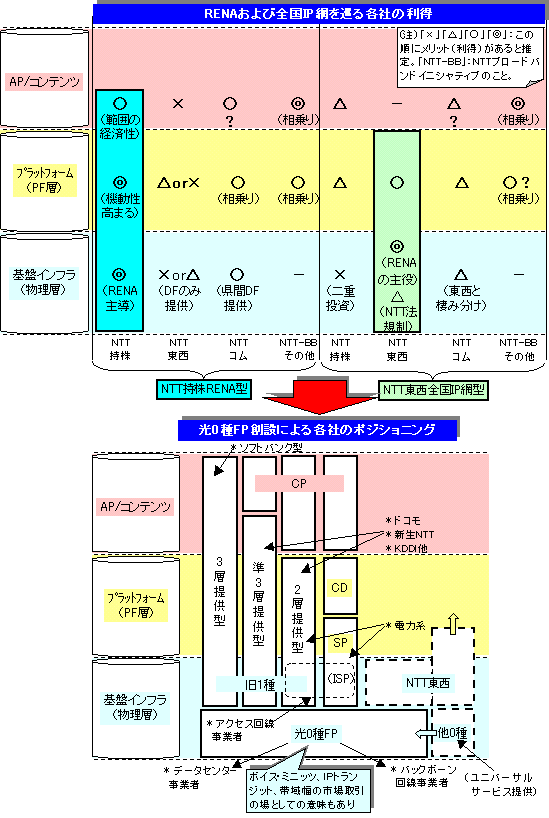
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
RENAと全国IP網の構築を巡りNTTグループ内で、明らかに利益相反が見出される。前述の構造的競争政策における「自らの経営判断で構造分離を進めようとする動き」が出ている例といえよう。
ここでは、KDDIなどの中継サービスを提供する通信事業者への利得については言及していないが、競合他社への事業戦略などにも確実に打撃を与えよう。経営のリアルオプション(RO)をもてるかどうかが、IP時代の新しい競争における鍵を握るため、新旧プレイヤーにおけるリアルオプションを行使するための、ある種のインフラ整備がにわかに重要になってきた。
(注)「リアルオプション(RO)法」:正味現在価値に加えて、投資の延期や中止、拡大、縮小、前倒しなど、将来の投資決定のフレキシビリティもプロジェクト評価の要素とすることにより、従来のNPV法やDCF法の限界を克服する実物資産投資の評価手法のこと。ある投資案件が投資タイミングの変更や段階的投資、オペレーション規模の切り替えなどの選択肢を持つ場合、そのことによる柔軟性が当該案件のキャッシュフロー(価値)創造にどのように影響するかを定量化することができる。
もしもNTT法廃止となれば、NTTの独占力を規制するため、市場支配力に着目したドミナント規制が必要だということになり、独占の見返りとして課されてきた、NTTの社会的責務(ユニバーサル・サービス)を、別途競争に中立的な形で担保することも依然問われるだろう。
(4)光0種FP創設による各社のポジショニングは?
前述のとおり、経営リアルオプションを持つ際のNTTグループ内での利益相反、IP時代にあって旧来の電話網の持つ意味合いが大幅に薄れるなかでのNTT 「自らの経営判断で構造分離を進める」ことの現実性・妥当性(1984年以降の米国AT&Tはそのケースに当たる)、あるいはスウェーデンのストーカブ公社などによるダークファイバーのホールセール専業化会社の設立(1993年)などの動きから、わが国において、いわゆる回線設備貸し事業を意味する0種(ゼロ種)の事業者として、NTTを再再編することの議論が必ず出てくるであろう。
そして、IP時代は光IPインフラがさまざまな通信回線のバックボーン(背骨)を支えることになる。ADSLは目下急速な浸透を見せているが、「全国あまねく適切、公平かつ安定的な電気通信サービスを維持する」というユニバーサル・サービス(NTT法)を今後も何らかの形で維持していくには、ADSLではその荷は重過ぎる。
再び上の図表の下段をご覧頂きたい。
IP時代に、こうした役割を担う存在として、「光0種FP(ファシリティプロバイダー)」のイメージを示している。
これは同様に3層モデルの中での、今後のブロードバンド市場における各プレイヤーのポジショニングを概観したものである。各レイヤーごとに、あるいは複数の各レイヤー間をまたぐ格好の、ある種の垂直統合的モデルについては、当コラムでも何度なく言及している。先の「IP化等に対応した電気通信分野の競争評価手法に関する研究会」では議論されなかった競争が今後は、わが国IP革命の行方の鍵を握っているのだ。
(注)
「垂直統合」:第21回「垂直統合型ブロードバンド事業モデルを規制するな」(2003/01/23)、第20回「AOL-TWの不振は垂直統合型モデル構築の失敗にあり」(2003/01/16)などで言及。
そろそろ、こうした抜本的な政策を打ち出す時期に来ているといえよう。
問題は、ゲーム理論などでも多少予測できる、こうした3層の枠組みでのNTT東西会社などの当事者、およびその他主要プレイヤーの利得最大化の動き、あるいは今後の情報通信市場のパイ拡大につながるか、消費者の利益はどうか、などといったことの現実性であろう。次回では、そのことについて簡単に言及してみたい。

