IP革命のもたらす構造変革をどう乗り切るか?
出典:SBP『IPコミュニケーション』ムック版 2003年6月号
IPという言葉を最近よく耳にするが、特集を組むほどのものなのか。こう思われている読者の方も多いに違いない。IPがそもそも、単にインターネット・プロトコルという通信の規約を意味するということを知らない読者もおられるだろう。このIP技術のもたらす経済的あるいは産業面での構造変化などへ与える影響は甚大であると思われる。革命の名にふさわしい筆頭格の概念であり技術であろう。
もちろん、どんな概念も技術も永遠なものはない。ただ私たちを取り巻く生活環境やビジネス環境の速度が、「ドッグイヤー」で進むとすれば、向こう5年間ほどの産業界に与える激震を見通しておくことは重要である。本稿は、筆者が日頃の経営コンサルティングの中、特にここ3年間において海外で見聞きし、あるいは国内のさまざまな専門家から教示いただいた内容などを基に、おおまかに整理したものである。
1. 産業構造からの抜本的な転換を促すIP技術は破壊的である
(1)IP技術により地殻変動が起きている
ハーバード大学のクレイトン・クリステンセン教授の「イノベーションのジレンマ」が2001年7月に日本でも刊行され有名になった。特に「破壊的技術」と「持続的な技術」という言葉は印象的だ。同教授は前者の例としてたくさんの技術群を挙げている。これらは玉石混交気味で、今となっては少々的外れなものも散見される。
しかし、その中に「パケット交換通信網」がしっかり記されている。IP網のことである。IP網ないしIP技術の劇的な進展は、同教授のその研究時期の後に起こったものだから、IP網のことはその著書ではほとんど扱われていない。
IP技術による破壊が進行中の様子は、同教授のお膝元の米国よりは、実は韓国や日本のほうが激しい。あるいは欧州では通信後進国のイタリアなどにおいて顕著である。ベンチャー企業が元気であり、腰の重かったテレコムイタリアを大いに触発している最近の動きは、どこかの国を連想させるものだ。
IPとはインターネット・プロトコルのことであり、デジタル化された情報は、パケット(情報のかたまり)としてカプセル化され、通信が行われる。RIETI(経済産業研究所)フェローの池田信夫氏は、TCP/IP方式のソフトウェアによる物理層の制御ととらえ、前述のデジタル化、カプセル化に加え、モジュール化をして、IP革命の本質的要素としている。
これまでの産業構造からの抜本的な転換の原動力という意味で革命といえよう。伝統的な垂直統合型企業が、その君臨してきた地位から引きずり下ろされ、おおむね水平分離化が促進される様子がいろいろと報告されている。【図表1】をご覧頂きたい。
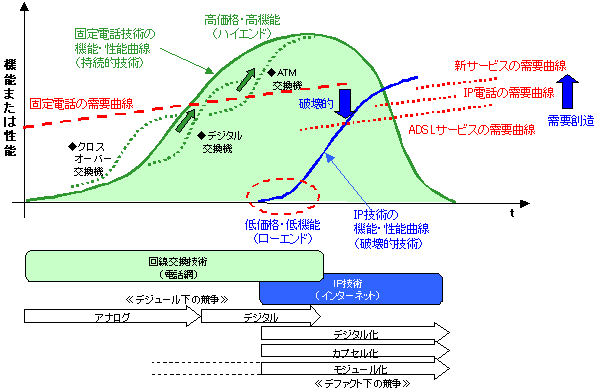
(注) 「ATM」:Asynchronous Transfer Mode、「ADSL」:Asymmetric Digital Subscriber Lineのこと。
(出所) 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
1967年当時画期的であったクロスオーバー交換機が導入されてから、1985年のD-60やD-70と呼ばれたデジタル交換機に至り、我が国の電気通信市場は大きく拡大した。そして、1990年代後半からのATM交換機(およびそれを基にしたメガリンクサービス)など、NTTの中では法人顧客向けのヒット商品となった。これらの中心技術はいずれも回線交換技術によるもので、今の電話網(電話システム)はそれで成り立っている。クリステンセン教授が指摘するようなS字形のカーブを描くかのように持続的に、代々その技術は継承されてきた。
電気通信の世界において、ここに来て思わぬダークホースが登場した。そもそもインターネットが商用化されたのが1993年なので、IPはそう目新しいほどの技術ではない。ハードディスクの要素技術など他の破壊的技術と同様、むしろ静かなスタートを切った感じに近い。持続的技術が高価格・高機能(ハイエンド)であるのに対し、IP技術は低価格・低機能(ローエンド)に位置付けられよう。つい2年前の2001年ごろでさえ、このIP技術はさほど重要視されなかった。正確にいうとレガシーキャリア(伝統的な通信会社)からは重要視されなかった。
これまでの固定電話技術の機能・性能曲線(持続的技術)とは別の(異質な)、破壊的な動きが顕著になってきた。それは下から上へ突き進んでいき、いつしか上位にある技術の機能・性能を上回ることになる。実際、IP技術の機能・性能曲線(破壊的技術)は、ADSLサービス、IP電話といった需要を生み出し、2003年4月から始まったIP放送、そしてやがてはケータイIP電話などの新サービスの需要が次々と創出されていく様子がうかがえる。
(2)競争基盤が変化し通信プレイヤーの戦略は変更を余儀なくされる
引き続き、クリステンセン教授の示す「機能」を縦軸にとり、横軸を時間軸とする平面において、需要曲線とそれを突き抜いていく技術の軌跡(すなわち技術の性能曲線)との関係を【図表2】に示し、我が国電気通信市場において当てはめてみよう。
最初に、主に固定電話の需要曲線とそれに交差するレガシー技術の機能・性能曲線を眺めてみたい。ATM交換機の開発や、FTTH(家庭までの光ファイバー網)技術などに並び、さまざまな持続的技術が連なる。これらはレガシーキャリアの技術戦略上にあるものであり、ドミナント的キャリアの研究所で開発されたハイエンド技術である。これらにより、下から突き上げてくるローエンド技術が、あるレベルに達するまでは、思い描いたビジネスを打てる。
最近のNTTのRENA(REsonant communication Network Architecture、レナ)戦略では、さすがに単に持続的なものではうまくいかないことが社内でも認識されてか、IP技術をベースに目下、最重要戦略として取り組みが行われている。
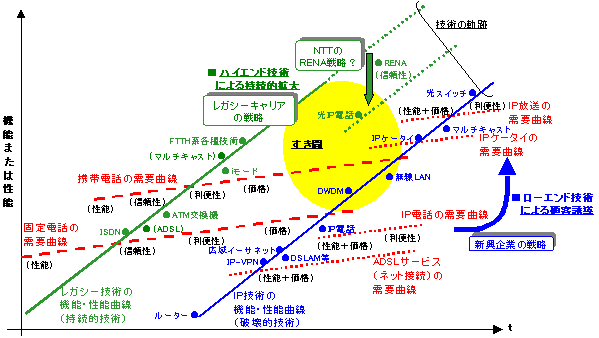
(注) 時間軸上の各技術のポジションはレイアウトの制約で多少ずれている。「ATM」:Asynchronous Transfer Mode、「IP-VPN」:IPベースのVertual Private Network、「ISDN」:Integrated Services Digital Network、「ADSL」:Asymmetric Digital Subscriber Line、「DSLAM」:集合型DSLモデム装置、「DWDM」:Dense Wavelength Division Multiplexing、「RENA」:REsonant communication Network Architectureのこと。C・クリステンセン氏(米ハーバード大学ビジネススクール教授)の論文等(1997年)を参考にした。
(出所) 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
米国のウィンダミア・アソシェーツによると、需要は「性能、信頼性、利便性、価格」の4つの「購買階層」から成るとされる。確かに電気通信分野のサービス(需要曲線)においてもおおむね、その順番にしたがいプロットできそうだ。しかし、よく注意してみると、携帯電話の需要曲線などでは1994年4月に端末の売り切り制が導入されて以来、固定電話に比べその市場への普及のピッチ、あるいは携帯電話の「プラットフォーム」上で動作する多様なサービス群の登場など、「利便性と価格」の購買層に至る速度が増してきているようだ。特に2000年12月末に商用化された「iモード」以降は顕著だ。
(注) 「プラットフォーム」:情報システムなどの基礎となる技術やハードウェア、ソフトウェアのこと。
一方、破壊的なIP技術の機能・性能曲線は、シスコシステムズなど大手ベンダーから提供される、ルータ(異なるネットワークの中継点に設置し両者を結ぶ装置)から描いた。
2001年から急速に普及し出したADSLは、消費者側のモデムに加え、NTTの局舎に置かれたDSLAM(集合型DSLモデム装置)などが大きな役割を果たしている。こうしたADSL技術には、韓国や米国のベンチャー企業が大きな成果を挙げている。また、無線LAN技術の目覚ましい進歩、マルチキャスト技術など、機能・性能曲線はぐんぐん上昇しているといったところだろうか。
実のところ、このADSLは1992~1994年のVOD(ビデオオンデマンド)が米国でブームになった時期に、ビデオ伝送のインフラ技術としてすでに姿を現していた。また、マルチキャスト技術についても、IP マルチキャスト技術の普及を目的とした業界団体が1996年に米国で設立されるなど、目新しい技術ではない。ゆえにローエンドと位置づけられるものだが、中にはハイエンド技術を追いつめるものが隠れているのだ。
技術が製品化され価格がつき商品になり、市場に提供されると需要が創造される。需要を予測して供給がなされる。IP技術群から起こったものとして、躍進中のADSLサービス(ネット接続)の需要曲線が描ける。
さらに、ADSLとのセットで提供され始めたIP電話の需要曲線、IP網の上で実現するIP放送の需要曲線といったものが描けよう。もしもIPケータイの本格的な需要が出てくるとなれば、NTT東西会社の次はNTTドコモか、となり当事者はうかうかしていられないだろう。
これらの選択権(オプション)を保有しそれを行使できるのは、サンクコスト(埋没コスト)に影響されない新興企業の戦略となろう。すなわち、ローエンド技術による顧客誘導を行う戦略だ。しかも、「性能(帯域、速度)+価格」のセットでいきなり提供される。この商品の普及期である現下、「信頼性」つまり品質などは二の次になっている状況があるのも特徴だ。
(注) 「サンクコスト」:すでに支出した費用で回収が不可能な費用のことで、固定費の非分割性に起因する。IPサービスを行うレガシーキャリアにとっての非IP網の技術や設備などがそれに相当する。
ハイエンド技術とローエンド技術の間の「すき間」に、ローエンド技術は押し寄せていく。NTT持ち株会社がRENAの売りに、「信頼性」を挙げているのは当然だろう。
たとえば、NTTにおいてATM交換機の投資については、これまで膨大な開発投資をしながらもそれを十分回収できないまま、昨今のIP技術のうねりを無視できず、2002年にその開発中止を公表せざるを得なかった苦しい胸の内は、察するに余りある。今般のRENAへの投資とその開発においては、そうした過去の投資を清算し新しいスタートに立っている。NTTはこれまでにも、いくつかの小規模なカニバリズムに直面してきている。しかし、自らのビジネスや組織を破壊するまでの抜本的な取り組みを、自らが行うのは不可能であろう。
ただ一方で、自社保有のサンクコスト化された光ファイバーや蓄積技術を踏まえた展開の度合いが大きければ、「規模の経済性」や「学習の経済性(ラーニングカーブ効果)」を発揮できるに違いない。それらを利用しつつ、極力、市中製品を活用するなどの「自製と購買」の決定に関する有効な手立てを講ずることができれば、コスト面でも新興キャリアのものに対抗できる余地はあろう。
(注) 「規模の経済性」:固定費が大きく変動費がほぼ一定であれば、ある範囲の生産規模で生産量が増えると、その商品・サービスの生産プロセスの中で平均費用が下がり始める(費用逓減)効果のこと。新規参入者の大きな障壁ともなる。
(3)3層構造の垂直統合化からアンバンドリング化が進み水平分離へ
「ネットワークの外部性」が顕著に出やすい電気通信分野では、産業構造もしくは企業の階層を、物理層、プラットフォーム(PF)層、コンテンツ層(アプリケーションを含む)なる3区分で整理する考え方が現実によく当てはまる。この各層を2つもしくは3つ統合することで、規模の経済性が働く場合がある。
(注) 「ネットワークの外部性」:一群の利用者のネットワークに新たに顧客が加わると、その顧客はすでにネットワーク(やシステム)に属している利用者に対し、消費の補完性としての便益(価値・効用)を生むこと。規模・範囲の経済性のような生産に関するものではない。表計算ソフトを持つソフトウェア会社などの企業間競争のほか、VCRでのVHSやベータなどの異種技術間の競争にも影響を及ぼす。
その典型はNTTドコモなどの携帯電話会社の例だ。端末や携帯電話網の物理層から、iモードなどの課金・決済プラットフォーム、そして、「自製」ではなく「購買」により、自社のPF上で稼働するコンテンツを積極的に調達する。こうした下層から上層までの3層構造を自社内にうまく垂直統合化している。
世界最大の携帯電話会社である英国ボーダフォンの月額ARPU(Average Revenue Per User、アープ)、すなわち1人あたりの月額収入が約4,000円であるのに比し、NTTドコモのARPUは過去2年間ほどで下がったとはいうものの、いまだ8,000円程度と世界でもトップ水準にある。また、最近のARPUの内訳として、iモード関連が約1,500円を占めているのは、3つの層のサービスをまとめて購入する方が割安となっており、消費者向けの「範囲の経済性」も出ているといえよう。
(注) 「範囲の経済性」:複数のサービスや事業を同時に、多角化した企業の内部で行う場合のコストのほうが、それら事業を別々の企業が担当した場合にかかるコストの総和よりも低くなる現象などのことで、補完性が問題となる。
垂直統合化が進み大きな企業組織になっていくと、規模の不経済性の弊害も出てくる。企業のヒエラルキー的な組織形態からくる、事業リスクの評価の差や情報コスト、事業活動のモニタリングコストなどのエージェンシー費用の増加によるものだ。
そこで、産業および企業の形態がおのずと水平分離的な方向へシフトしていく。【図表3】をご覧頂きたい。
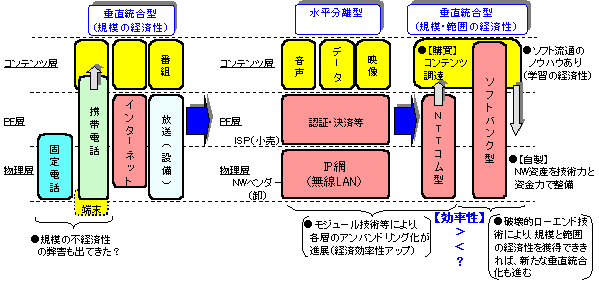
(注) 「PF」:プラットフォーム、「NW」:ネットワーク、「ISP」:インターネット・サービスプロバイダー、「LAN」:Local Area Networkの略。「ソフトバンク型」:ソフトバンクBBのほか、イタリアのe.Biscom社なども同様。左半分側のイメージはIT戦略本部資料(2001年12月)を参考にした。
(出所) 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
前述の3層が分離(アンバンドリング)され、それぞれの階層での効率化が追求される。特にIT分野では、意思決定のスピードなどが重要度を増しているため、水平分離的なメカニズムがうまく機能する場合が少なくない。IP技術を活用し、それぞれの持ち味を持った企業が大勢出てきた。2000年4月のIT・ネットバブルのクラッシュを経験した後でも、その動きは止まらない。
その範囲はドットコム企業などのネットビジネスから、伝統的なGEやIBM、あるいはシスコシステムズやデルなどの非ドットコムにまで及ぶ。どの企業も自社のバリューチェーンの強化を図るべく、IPベースのビジネス基盤モデルを構築している。この基盤の源泉を、米マーサー・マネジメント・コンサルティングのスライウォツキー氏は、企業が「プロフィット・ゾーン」を射止めるのに欠かせない23番目のモデルとして「DBD(デジタル・ビジネス・デザイン)」と呼んでいる。
注目すべきは、IPベースのインフラを用いて規模・範囲の経済性、あるいは学習の経済性を生かした、新たな垂直統合化の動きも出てきていることだ。
これは「ソフトバンク型」と呼べるものである。ソフトバンクBBは、約260万のADSL顧客、約220万のIP電話顧客を持ち、スケールメリット(規模の経済性)が出せそうなステージまでようやくたどり着いた。また、過去約20年間のソフト流通などのコンテンツ周りのノウハウ蓄積(ラーニングカーブ効果)は、伝統的な通信会社には皆無といってよい。あえていえば、2003年1月に両部門の内紛騒ぎに発展したAOL-TW(タイムワーナー)のような合併型の企業には見かけ上認められる。おまけに、NW(ネットワーク)資産を技術力と資金力で整備するなどの「自製」は、ソフトバンクBBのような新興企業ではなかなか難しいことである。
コンテンツの調達については、外部企業からコンテンツを「購買」し、3層構造間のシナジー発揮を追求する「NTTコム型」とは異なったモデルといえよう。
2. 世界で最も進んでいる日本のブロードバンドサービス
(1)クリティカル・マスを超えるまでが勝敗を分ける
米国の社会学者のE.M.ロジャース教授の経験則的な普及モデルを参考にすると、ブロードバンドサービスが普及するにあたっての、認知段階や口コミ普及段階でのターゲット顧客は、それぞれイノベーターおよびオピニオンリーダーと呼ばれる。普及が加速するとされる「クリティカル・マス」は、普及率にして10%~15%程度といわれる。これまでの固定電話の普及などにも、おおむね当てはまるとする研究も報告されている。
(注) 「クリティカル・マス」:商品が市場に浸透するための一定の需要規模、限界規模のこと。その規模を超えると、それまでの累積効果により爆発的な効果が表れたり、一気に普及が加速することがある。
クリティカル・マスを超えると、ネットワークの外部性が強まり、消費者への便益が高まり市場拡大するにつれ、競争は激化する。そして、寡占的な市場となる。ナローバンド市場ではすでに経験済みのことだ。【図表4】のとおり。
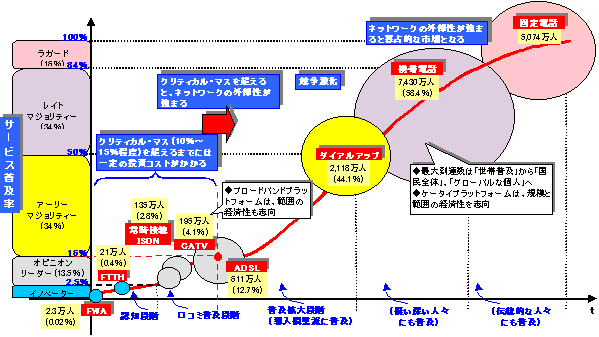
(注) 「サービス普及率」:2002年12月から2003年2月のデータを用い、携帯電話の場合、加入者数を人口(約1億2,000万人)で割り、その他サービスでは世帯数(約4,700万)で割ったもの。各サービス近傍の括弧内に%で表示。「FWA」:Fixed Wireless Accessの略で加入者系無線アクセスシステムのこと。「縦軸の5つの分類」:E.M.ロジャース教授(米国の社会学者)の普及モデルを参考にした。
(出所) 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
クリティカル・マスを超えるかどうか、あるいはそれを超えた後の「経路依存性」は、初期の偶発的な小さな事象によることが少なくない。これは初期値過敏性などとも呼ばれている。複雑系の経済学で大御所となった米サンタフェ研究所のブライアン・アーサー教授は、収穫逓増型市場と「ロックイン」効果、あるいはその経路依存性について興味深い精緻な研究を行っている。
(注) 「ロックイン」:歴史的な偶然として、いったん初期段階である経路に落ち込んでしまうと(経路依存性)、そこから出ることが難しい状況のこと。たとえ不合理なものであっても、いつも合理的なものが生き残るわけではなく、この状況にはまり込んでしまう(あるシステムに組み込まれる)と、そのシステムを使うことの効用が増加し(ネットワーク外部性)、その不合理は継続・拡大していくことになる。
産業史を概観すると、電気通信分野ではキャプテンやISDN、放送分野ではハイビジョン、コンピュータ分野では第5世代コンピュータやトロンチップなど官製主導的であったものは、初期段階からその後のビジネス展開としては、ほとんど日の目をみていない。
これらの原因が「小事象」とは別ものであるにせよ、持続的なハイエンド技術群が使いものにならなかった証左となるものだ。こうして見ると、確かに技術イノベーション上のジレンマや不合理といった法則が、一定の条件下で多くの技術群を支配しているように思われる。
そこで最近の動きに目を転じると、すでに設備投資が決定済みのデジタルTV放送などに加え、FTTHへの過剰的な期待、あるいはRENAへの膨大な投資などについて、それらが後戻りしがたいものであれば、後述のリアルオプション戦略やゲーム理論などの応用など、せめて失敗に至らない未然の方策を研究しておくことが不可欠となる。ブロードバンド競争の当事者にとって、IP技術のもたらす地殻変動が進行している。
(2)IP電話はキラーコンテンツとなるか
さて、今年の「横綱ヒット商品番付」ははたして何になるだろうか。
SMBCコンサルティング版の番付では2002年末の東横綱に「『ハリー・ポッター』シリーズ、西横綱に「FIFAワールドカップ」がランクインされている。両方に親しんだ筆者としては納得感がある。そして「写メール」と「Suica」が大関、「ブロードバンド」と「コンビニATM」が関脇。2001年の関脇に「ADSL」、「iモード」は1999年と2000年連続で大関にランクされている。読者の感覚はいかがなものか。
こうしてみると2003年末に、「IP電話」が関脇から大関ぐらいに入るかもしれない。たとえベスト10圏外であっても、かえって目立たないがボディーブローように、上位技術群に忍び寄りやがてノックアウトすることが予想されるさまは、前述のとおりである。
【図表5】で注目すべきは、ずばり「BBフォン」だ。2001年6月、月額2,300円前後という世界で最も安価な「Yahoo!BBショック」以来、加入者数が急増し、ソフトバンクBBのみでADSLサービスは前述のとおり約260万、IP電話で約200万(2003年4月末)。世界で最も多数のユーザーを獲得したことになる。そして、その達成のスピードも世界一とのことだ。2003年5月のソフトバンクの決算説明会で孫正義社長が強調するのは当然だろう。
同図表でデータが少々古いのをお許しいただきたい。たとえば、2003年6月時点のフュージョン・コミュニケーションズでは、距離、時間帯にかかわらず、全国の固定電話へ一律3分8円、加入者同士の通話は通話料無料など、BBフォンに近い仕様になっている。ただし、公衆電話からのIP電話の着信が可能になるのは2003年夏ごろからとのことだ。
データは一部を除き2002年12月時点のものが中心であるが、問題はネットワークの特徴と関連機器にある。こればかりはこの半年でそう大きく変わるものではなかろう。大きな投資額が必要とされ、またそのインフラ整備には莫大な人的エネルギーがかかるからだ。この差はなかなか埋まるものではない。
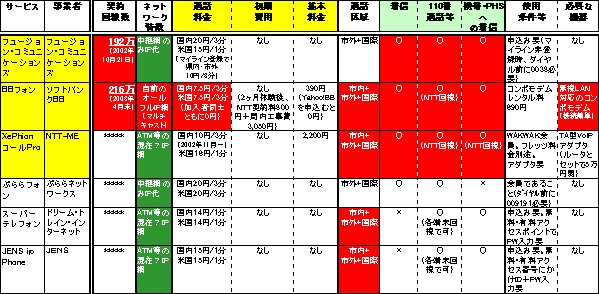
(注) 「赤い領域」:競争優位にあると思われる要素。「ATM」:asynchronous transfer modeのことでATM交換機を意味。「マルチキャスト」:単一のパケットで、複数のノードに対して同一データを送信する通信方法。「TA」:Terminal Adapter、「VoIP」:Voice over Internet Protocolの略。2002年10月22日発表のフュージョンの新サービス以外は、「日経ゼロワン」2002年12月号)などの雑誌情報を参考にした。
(出所) 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
中継網だけを活用した本格版がフュージョン・コミュニケーションズからまず開始された。NTT-MEなどの同業他社も、ATM交換機などの混在のIP網をベースにしたものと推定される。 そのほかの重要な点としては、各社の事業運営形態が挙げられる。
たとえば、Nifty(小売)型。ここに加入しているインターネット接続サービスの購入者(ユーザー)は、同社と契約しているNTTコムのその他のサービス(例:電話、FTTH、無線LAN)を利用する際、Nifty以外のこれらの会社と別に契約をしたりすることになる。また、契約後の開通においても、その状態が関係各社でまちまちであったり、あるいは何時開通するのかが、アライアンス先のどこか1社の遅れで、購入者はずっと待たされるなどの遅延も生じやすくなる。
水平的な統合(関係各社との連携)のよいところは、インフラ(例:NW)とサービスまたはコンテンツの分離による低コスト化であるが、Nifty型の場合、物理層には手を付けられないので、サービス層のみでの水平的な統合を図ろうとしているため、かえってコストアップになったり(範囲の経済性を購入者は享受できない)、サービスの遅れなどで、購入者のサービス享受までの便益の点で問題がなくはない。手間や心理的なイライラ、いろいろ購入者には感じられていることだろう。
もう一つのタイプは、卸と小売の兼業(ソフトバンクBB)型であり、物理層とサービス層が一体のものだ。Nifty型とは大きく異なる。コスト面での範囲の経済性をサービス購入者は享受できることに加え、1社で何もかもやってくれる、いわばサービス購入者はワンストップサービスの便益を受けることができる。このようなことがIP技術をベースにした仕掛けで、今や簡単にできるようになった。
ここでレガシーキャリアに与えるIP電話のインパクトを考えてみたい。
加入電話ユーザーがIP電話にシフトすることの減収として、たとえば5年後を考えると、加入電話とISDNの契約者数がブロードバンドIP電話加入者数と拮抗するほどの広がりをIP電話が持ち得るシナリオが描ける。
会員同士の無料電話は、1994年の端末売り切り制導入で普及の弾みが付いた携帯電話や、1993年以降の商用インターネットサービスの普及状況を彷彿させる。実際、「一過性ならショックはないが、この傾向は続く」(NTT和田社長)といった声もあるようだ。
携帯電話の加入者数が7,000万を超え、頭打ちになりつつあるまでのここ数年を経て今日、固定電話の契約者数の減少要因に、新たにIP電話が加わった。その影響はNTT東西に加え、NTT以外の長距離電話会社(KDDIなど)にとっても、距離に依存しない料金体系をとるIP電話は脅威になる。たとえば、KDDI小野寺社長は「2005年には音声トラフィックの4~5割がIP電話に」とみている。
過去のネットワークサービスの経験則から、FTTHユーザー増加とIP電話シフトが重複する要因ゆえに、たとえば、固定電話加入の約10%が解約する状況は要注意だ。その後、なだれを打って減少していき、減収額算定には、FTTHサービスの増加分を考慮すべきであるが、うまい代替を見いだせなければ数兆円単位の減収の可能性も出てこよう。そのインパクトは甚大である。
(3)投資効果の観点からも法人顧客向けにIP-PBXシステムが浸透し出した
事業者側には経営的に大変な状況を突きつけられる場合、ユーザーは得をすることがしばしば起こる。特に法人顧客の場合はどうだろう。
IP-PBXは実に投資効果の面で都合がよいようだ。IP-PBXの導入が最近相次いでいる。
導入効用面として、例たとえば配線設備については、LAN配線が使用できるので、電話専用に工事する必要がない点。ネットワークトポロジーではセンターに設備を集中可能である点。各地へのコントローラーが必要ない点。専用-公衆網接続では、各拠点に配備したゲートウェイにより簡単に実現可能な点。可動性(移設など)では、移動先で電話機をLANに接続するだけで、電話番号の変更は不要である点。機能追加(アプリケーション連動)では、オープンインタフェースのため、既存のアプリケーションを容易に接続し連動できる点。運用管理では、ウェブ画面による簡単な操作のみで、専門知識がなくとも、電話機の増設や管理は容易な点などなど。【図表6】のとおりだ。
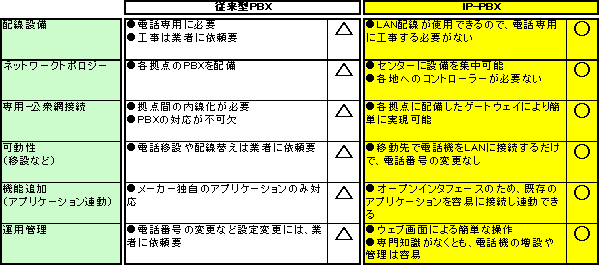
(注) 「△」よりも「○」印の方がメリットが認められる。「PBX」:Private Branch Exchangeの略で構内交換機のこと。
(出所) 株式会社ネットマークス山本毅氏資料(2002年9月)から
あるいは旧来PBXシステムによる電話機移設では、パッケージの追加、回線の張り替え、設定の変更などにより作業量・費用ともに毎回かかりコスト高になったこと。また組織変更に柔軟に対応不可であったため、1台あたりの基本構成には1万円~2万円もかかっていた。
一方、IP電話システムによる電話機移設の場合、IPでCall Managerと接続できていれば、IP電話をどこに持参しても、すぐに同じ番号で利用可能であるため、組織変更に柔軟に対応可であること、そして、スクラップ&ビルドを頻繁に行う必要のある組織などには特に有効で、その1台あたりの基本構成は0円といったほどだ。
こうしたIPコミュニケーションの柔軟な環境が十分でないケースでは、たとえば、個々の社員の行動・決断や、さまざまなビジネスシーンでの都度判断や代表番号からの転送による判断などの遅れが生じたりする。環境が整備されていれば、デスク不在時にも、どこでもコンタクト可能な環境ができるなど、ビジネスシーンには電話のモビリティが不可欠となる。
IP電話の投資効果についての事例が報告されているので、次にこれをみてみよう。
シスコシステムズのインターネット・ビジネス・ソリューションズグループ(Michael Gill氏)によると、同社オフィスでは、そのROI(Return On Investment)と1人あたりの正味現在価値NPV(Net Present Value)が測定された。
結果、英国の大規模オフィスではそれぞれ130%、$10.7K。ドイツの中規模オフィスでは120%、$12.2K。そして、フランスの小規模オフィスにおいては111%、$9.4Kといった具合だ。
また、リテールバンク大手のTCO(Total Cost of Ownership)については、英国オフィスネットワーク15ヵ所規模で45%、大規模グリーンフィールドサイト3,000人規模で26%、リテールバンク大手その建物内での現行PBXの拡張を4,100人規模で行った場合に3%といったところだ。
さらに同様にMichael Gill氏から【図表7】のような事例が報告されている。
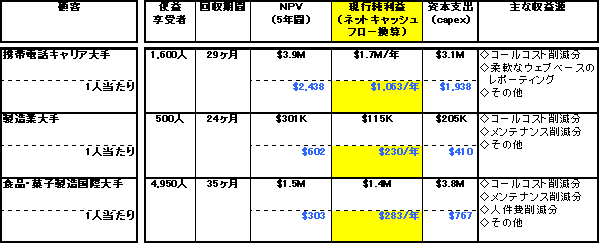
(注) NPV=Sum up [CFt/ (1+k)]。ここで、[t]は、一定の期間(5年間)。[k]は、その期間内における必要資金調達コストで10%を想定。[CFt]は、当該期間の間に予想されるキャッシュフロー期間内に出て行く資金の量が入ってくる分を上回る場合、この部分の数値は、マイナス。反対に、入ってくる資金の方が多いと予想されるときは、プラスとなる。
(出所) シスコシステムズ インターネット・ビジネス・ソリューションズグループ(Michael Gill氏)2002年11月資料から
これは、顧客タイプ別のIP電話の導入効果、その便益、調達コストで10%とした場合のネットキャッシュフローなどについてのものである。
携帯電話キャリア大手のケースでは、コールコスト削減分、柔軟なウェブベースのレポーティングを通じ、ネットキャッシュフローベースで年間1人あたり$1,063、製造業大手のケースでは、コールコスト削減分、メンテナンス削減分などにより同$230、また食品・菓子製造国際大手では、コールコスト削減分、メンテナンス削減分、人件費削減分などもあって同$283といった効果を出している模様だ。
(4)低価格がドライバーとなり、品質と差異化が普及のポイントに
IPコミュニケーションとしては、企業内での取り組みとしてIP電話のみならず、旧来の専用線やデータ通信網を見直し、最近のIP技術を用いたサービスに置き換えるなどの動きが、2000年ごろから活発になってきた。
【図表8】をご覧頂きたい。
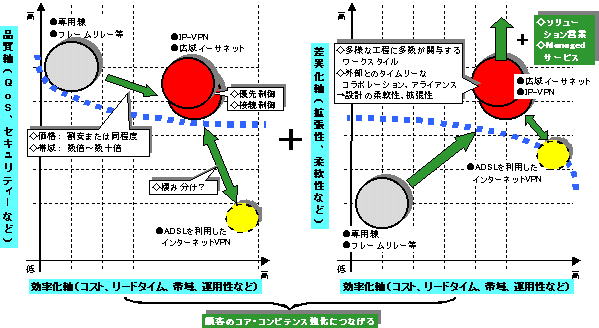
(注) 「QoS」:Quality of Serviceの略。「差異化軸」:拡張性、柔軟性など、競合他社に対するコア・コンピテンス強化(事業そのものや経営面での強化)につながる軸のこと。「Managed」:ノードの監視、障害対応、障害未然防止のためのプロアクティブな運用に関すること。
(出所) 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター 横軸にコスト、リードタイム、帯域、運用性などの効率化軸、縦軸にQoS(Qquality of Service)、セキュリティなどの品質軸を置いた平面で考えている。
専用線やフレームリレー等に比べ、IP-VPNや広域イーサネットは、価格は割安または同程度であり、帯域は数倍~数十倍であり、しかも優先制御および接続制御が可能であるため、QoS面での不具合もかなりの程度解消されるといった特色が浮き彫りになる。一方、ADSLを利用したインターネットVPNとは、主に価格面での棲み分けがなされている。
次に横軸を同じにし、縦軸に拡張性、柔軟性など、競合他社に対するコア・コンピテンス強化(事業そのものや経営面での強化)につながる差異化軸をとった平面をとる。
広域イーサネットやIP-VPNでは、多様な工程に多数が関与するワークスタイルや、外部とのタイムリーなコラボレーション、さらにはアライアンスなどに取り組む際、設計の柔軟性や拡張性などの効用を得ることができる。また最新の動きとしては、ソリューション営業に役立つといった報告に加え、ノードの監視、障害対応、障害未然防止のためのプロアクティブな運用に関するManagedサービスへの発展が米国などでも注目されている。
このように法人顧客向けサービスにおいても、消費者向けと同様に最近の傾向として、サービスの経済性(コスト性、収益性等)がドライバーとはなっているものの、品質面や運用面が重視されている。
安かろう悪かろうのサービスならば企業は困る。品質面では、QoS、キャリアクラスの耐障害性などがポイントだ。
一方、運用面では、運用上のマネジメント簡易性、ネットワークの拡張性・柔軟性などが求められる。それには、パケットの高速転送を可能にするレイヤ3スイッチングの技術であるMPLS(Multi Protocol Label Switching)や、DiffServ(Differentiated Service)などの最新技術が注目を集めている。また、通信ネットワークやサービスを統合的に運営管理するシステムOSS(Operation Support System)への投資にも関心が高まっている
。 これら課題の明確化が、今後の普及のポイントにあることは間違いないだろう。
3. IPサービスの需要と供給の法則により競争構造を再構築する
(1)今後の需要の変化がブロードバンド業界の参入と撤退に影響を与える
破壊的なIPサービスが登場し、その影響を直接・間接的に被る企業が経営戦略を策定する際、多くの場合、現状と将来の動向に関する分析の基礎的な手法に欠けることが少なくない。その手法の貧弱さについては、米ハーバード大学のマイケル・ポーター教授も指摘しているとおりだ。
特にミクロ経済学ではこれまで、市場の完全競争状態を善しとし、独占を悪と教えるような傾向があった。我が国の大学ではいまだにそのような状況があるに違いない。しかし、経営戦略の現場においてコンサルティング先のクライアントへは、いかにその独占的な条件を自らの周囲に築くかを伝授することになる。
通信キャリアは、これまで(1)自然独占(モノポリー)事業、(2)寡占(オリゴポリ)事業、(3)完全競争的事業へとシフトしつつあるかのようにみえるが、ポイントは合法下、独占的な競争構造(市場構造+収益構造)を再構築することにある。これが経営戦略の究極の目標となる。そのためには、たとえば、次のことが基本アプローチとなる。これはレガシーキャリアにおいても、新興キャリアにおいても同じである。
● 市場構造の非競争的な状況を作り出すこと。
● 収益構造において独占的な利益を手にできるようにすること。
これを検討する前に、【図表9】を眺めて頂きたい。
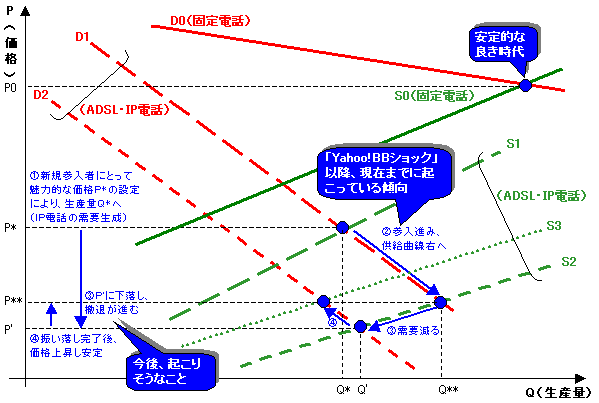
(注) 「D」:需要曲線、「S」:供給曲線のこと(それぞれ簡略化のため直線で示す)。デイビッド・ベサンコ氏(米ノースウェスタン大学ケロッグスクール副学長)他の著作(2000年)を参考にした。
(出所) 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
これは縦軸にP(価格)、横軸にQ(生産量)をとった需要曲線と供給曲線の関係を示した平面である。
ローエンドの破壊的なIP技術がクローズアップされる前、固定電話市場では、需要曲線D0と、供給曲線S0により決まる「安定的な良き時代」にあった。少なくとも競争者同士、持続的な競争であり、そこに大きな変化はなかった。
しかし、破壊的なADSL・IP電話技術と商品の登場で、ADSL・IP電話分野なる市場構造がすっかり変わったものが持ち込まれた。
そこで起きていることを、需要と供給の法則のもとに整理してみよう。
まず、(1)新規参入者にとって魅力的な価格P*の設定により、生産量Q*へ(IP電話の需要生成)のシフトが起こった。次に(2)ADSL・IP電話という新市場への参入が進み、供給曲線は右へ移動した。ここまでが「Yahoo! BBショック」以降、現在までに起こっている状況だ。
今後、起こりそうなこととしては、(3)需要曲線がD2まで左へシフトすることで需要が減り、価格はP'にまで下落し、参入者の撤退が進む。そして、(4)参入者の振い落としが完了し、結果、価格が上昇し安定となるといったところだろうか。
現在の価格コントロールは新興事業者であるソフトバンクBBに握られているといってもいいすぎではあるまい。しかしながら、この2003年5月の孫社長の発言では、もうこれ以上価格は下げる気はないとのことであった。
ただ孫氏の過去の発言からして、それを鵜呑みにすると競合他社は足元をすくわれる。彼は超一級の策士、いや戦略家でもあるからだ。相手の裏をかくことなど、常套手段といえる。破壊的なIP技術を手中に収める者(経営者)は、その揺さぶりのしかたも破壊的であるというべきであろうか。
(2)IP技術を用いることで費用構造が決定的に異なってくる
次に収益構造についての戦略はどうか。費用構造をまず考えよう。
【図表10】は、縦軸にP(価格)、横軸にQ(加入者数)をとり、平均費用曲線ACを示している。ACrは旧来(レガシー)キャリアの平均費用曲線、またACnは新興キャリアのそれを表す。Q'は「最小効率規模」といって、経済学では前述の規模の経済性が保てる最小の数量を指す。つまり、ここまで規模の経済性が働く。
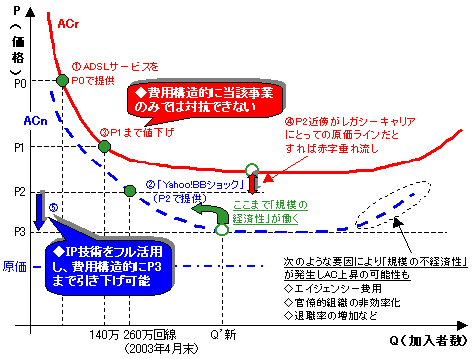
(注) 「AC」:平均費用曲線、「ACr」:旧来(レガシー)キャリアのAC、「ACn」:新興キャリアのAC、「Q'」:最小効率規模(規模の経済性が保てる最小の数量)。
(出所) 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
最初に、レガシーキャリアが、(1)ADSLサービスを固定電話よりもぐっと安い価格P0で提供したとしよう。我が国でのADSLサービスの開始は、主に米国のCovad Communicationsなどからの技術ノウハウを伝授されたかたちで行われた。
しばらくは価格P0から少々下がる程度で推移していた。そこに突如、(2)「Yahoo! BB」がまさに関係者への「ショック」として破壊的に登場。8Mbpsの広帯域版を業界最安値の価格P2で提供してきた。
これにたまらず競合者は価格を(3)P1まで値下げする。ただ、この状態では費用構造的に当該事業(この例ではADSL事業)のみでは対抗できない。
したがって、もしも(4)P2近傍がレガシーキャリアにとっての原価ラインだとすれば赤字垂れ流しとなる。シェアトップのソフトバンクBBでさえ損益分析点に未達の状況であるから、競合他社は皆そうである。
ソフトバンクBBは、全国のNTT局舎2,000以上に自らの設備を導入したギガ級フルIP網を、独自の通信インフラを効率的に構築・保有しているため、さらに(5)IP技術をフル活用し、費用構造的には価格P3まで引き下げが可能と推定される。
この「ギガ(G)級」とは、バックボーンが現在4Gクラスにあり(NTTの約80倍のキャパシティ)、ネットワークの規模に加え、その帯域(速度)においても世界最大である。FTTHなどと騒がれているものはアクセス網の話である。問題は、数百万(あるいは数千万)以上に及ぶ加入者増加にともない発生すると予想される、通信トラフィックの混雑(品質低下)に関するものであり、バックボーンの太さが重要になる。ソフトバンクBBは孫氏によると、さらに10倍にする計画がある。ここが競合他社との決定的な違いとなる。
杞憂かもしれないが、何もかも効率的に見える企業も、前述の「規模の不経済性」が発生するような、無用の取引コストが発生するなどすれば、現下の費用構造的な競争優位も当然減じられることになる。
収益構造というからには、費用構造に加え、収入構造もみなくてはいけない。これは次のリアルオプションの適用に関するところで触れたい。
4. IP市場競争下では「待つ」リアルオプション戦略が利益を最大にする
地球(1)状況に応じた代替案(リアルオプション)を持ち次期事業を展開
さて、従来のNPV(フリーキャッシュフローを現在価値に引き直した正味現在価値)法やDCF(キャッシュフローとそれをベースにした割引キャッシュフロー)法の限界を整理すると、次のようなことになる。
●キャッシュフローが確定している投資案件の現在価値を算出するためのもの。したがって、投資の最終意思決定は現在価値算出の時点で行われ、それ以降は投資計画を変更する等の柔軟性はない。
●不確実性に対応して予定変更できる柔軟性を考慮しその価値を評価に反映できないため、分析結果と実際の投資収益との乖離(投資収益の過小評価)を生み出している。
そこで最近にわかに注目されている手法が、リアルオプション(RO)法である。モニターグループのトム・コープランド氏によれば、これは次のようなものである。
●正味現在価値に加えて、投資の延期や中止、拡大、縮小、前倒しなど、将来の投資決定のフレキシビリティもプロジェクト評価の要素とすることにより、従来のNPV法やDCF法の限界を克服する実物資産投資の評価手法である。
●ある投資案件が投資タイミングの変更や段階的投資、オペレーション規模の切り替えなどの選択肢を持つ場合、そのことによる柔軟性が当該案件のキャッシュフロー(価値)創造にどのように影響するかを定量化する手法である。
RO法は柔軟な意思決定を行う権利がもたらす「フレキシビリティ価値」を定量化し、投資判断指標とするため、当面インパクトが大きい、次のようなケース(一定の条件を具備)への適用が妥当とされる。
A) 将来の不確実性が高い、かつ不確実性を減じるような新しい情報を将来入手できる可能性が高い案件
B) 経営上のフレキシビリティが高く、新しい情報に対して適切に対応できる余地がある案件
C) 従来のNPV法またはDCF法ではNPVがゼロに近くなってしまう案件
前者としては、現在のADSL・IP電話またはブロードバンド市場において、破壊的な技術やパラダイムの大きく変わった競争環境の出現など、従来の延長では予測しがたい不確実性が高まっている点、一方でたとえば、ソフトバンクBBであれば、そうした環境変化に関する情報を競合他社に比し有利に対処できるケイパビリティを身につけている点、具体的にはソフトウェアやコンテンツのノウハウが豊富、自らがこうした戦いを仕掛けていることなどを指摘できる。
後者としては、たとえば同社がギガ級フルIP網のインフラを持ったことで、経営ないし戦略のフレキシビリティを手にしている点、一方、NTTグループであれば、RENAなどの光ファイバーIPなどの、より柔軟な次世代IP網を構築しつつある点などが挙げられる。
ここまでを頭に入れておき、先ほどとほぼ同様の【図表11】を用いて、ADSL関連商品についての説明を続けよう。
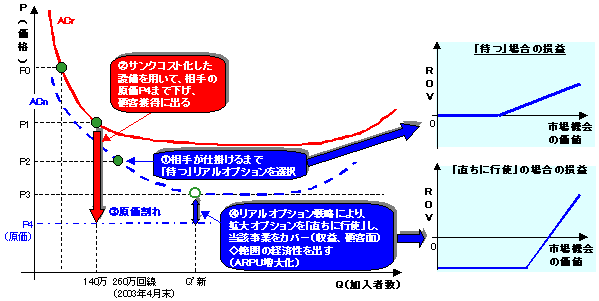
(注) 「AC」:平均費用曲線、「ACr」:レガシーキャリアのAC、「ACn」:新興キャリアのAC、「Q'」:最小効率規模(規模の経済性が保てる最小の数量)。「ARPU」:Average Revenue Per Userの略で1人当たり月収入のこと。リアルオプションについては、マーサ・アムラム(米Vocomo Software社長)とナリン・クラティカ(米ボストン大学ビジネススクール教授)の両氏の著作(1999年)を参考にした。
(出所) 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
ソフトバンクBBは次の戦いを(1)相手が仕掛けるまで「待つ」リアルオプション(戦略のフレキシビリティを持つ権利)を選択できる。
そして、この市場で最も手ごわい競合他社であるレガシーキャリアが、(2)サンクコスト化した設備を用いて、相手の原価P4まで下げ、顧客獲得に出たとする。つまり、旧来の交換機設備などの叩き売りを行うなど過去の減価償却費分までの、徹底した低価格攻勢に出る。するとソフトバンクBBもいったんこの市場で損益分析点を確保していた段階でも(3)原価割れに見舞われる。
そうした場合の策が次の手だ。すなわち、(4)リアルオプション戦略により、拡大オプションを「直ちに行使」し、収益面と顧客面の双方で当該事業(ADSL・IP電話)をカバーするよう、この時点の一定の規模の経済性を背景に、範囲の経済性を出すようアクションに出る。これによりADSL・IP電話事業の上に追加的な収入を見込むことで、関連IP事業全体のARPU増大化を図ることができる、というわけだ。
「直ちに行使」した場合の損益は、「待つ」場合の損益に比べ、損益線は急な傾きを持つ。それは、その企業が市場構造に影響を及ぼし、より大きな上昇方向の損益機会を創り出しているからといえる。つまり、早期に戦略を打つ(投資する)ことで、企業は段階的に成長オプションを購入したことになる。
もちろん、レガシーキャリアにおいても、別のリアルオプションを持つことが可能であるため、同様な戦略をその時の状況に応じ行使することが可能である。
リアルオプション戦略とは、自社のもつフレキシビリティからくるインフラなどの価値を計算し、その投資案件の大きさをレビューすることにとどまらず、こうした不確実性の高い環境下で、相手の動きを見ながら自ら打つべき競争戦略の判断(オプションの選択)に大きく資するものである。 (2)新NWインフラが新規事業の選択権を持つことで生み出すオプション価値
参考までにどのような計算をするのか、つまりリアルオプション価値(ROV)の計算の例を示そう。
ある事業者の保有するネットワークの価値を、次のように構成することができる。
●「オプション行使時のネットワーク価値」=「現下のネットワーク価値」+「ネットワークのリアルオプション価値」
この第2項を分解すると次のようになる。
◇「新規事業1のリアルオプション価値」+「新規事業2の投資額」+「ネットワーク投資分」
たとえば、上式の右辺第1項は、そのNTTの持つ加入者ラインの価値であったり、新興企業の持つADSLなど。同第2項は、その加入者ラインの上に乗せられるプラットフォーム網(システム)の価値など、あるいは新興企業であれば、IPテレビ(IP放送などの新規事業1)や無線LANを用いたケータイIP電話(新規事業2)などを実現するオプション価値となる。【図表12】にこのことを整理した。
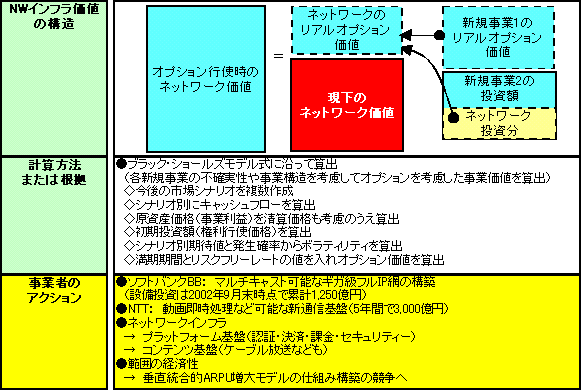
(出所) 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
こうした計算が可能なのは、つまりリアルオプションを行使できるのは、不確実性を考慮した価値があり、経営上の選択権があることに価値があるとみなせるからだ。こうした場合、不確実性をプラスに捉え、その価値を加えた事業価値を、ブラック・ショールズモデルなどにより計算することができる。
あるいは、差別化したネットワークインフラを持つことで経営上の選択権がもたらす価値がある。たとえば、前述のとおり、同ネットワークで実現可能な、ADSLやFTTH放送などの事業を、技術革新の度合いや市場の状況を踏まえ、適切なタイミングで他事業者よりも低コストでスタートできる。こうして経営上の選択権から生じる事業価値により、ネットワークの価値をさらに増大できる。
報道資料によれば、ソフトバンクBBはIP放送も視野に入れられる、マルチキャスト可能なギガ級フルIP網の構築設備投資において、2002年9月末時点で累計1,250億円を投じている。一方NTTは、動画即時処理などの可能な新通信基盤の整備に対して、向こう5年間で3,000億円を計画している。
前述の「収入構造」に関する説明をここでは行った。
フレキシビリティの高いIPベースのネットワークインフラを持つことで、その上にプラットフォーム基盤(認証・決済・課金・セキュリティ)が築け、さらにはコンテンツ基盤(ケーブル放送なども)を乗せることができる。
これら3層の資産を有効に活用できれば、範囲の経済性を発揮できる。つまり、IP時代の競争は、再び「垂直統合」的なARPU増大モデルの仕組み構築の競争ともなった、と読めよう。
(3)投資の重い第3携帯電話は無線LANに代替されるか
IPでいろいろできると、携帯電話(ケータイ)にも応用できそうだ。実際、2002年9月には三菱電機がIP携帯電話端末を発表した。
無線LANなどにアクセスできる環境下にあれば、どこでも格安通話が可能となるIP携帯電話技術(モバイル IP Talk)を開発したもようだ。これを使えば、IP電話(固定・携帯)間では加入プロバイダーなどを問わず、インターネット回線を利用し通話可能なようだ。
またIP携帯電話専用の無線LANカードを用いて、約11Mbps を実現する802.11b規格に準拠した無線LANにアクセスできれば、東京本社やニューヨーク支店のオフィスでも、街角の無線LANでも、また自宅の無線LANの下でも、端末を世界中同一番号で呼び出せる。本当に実現すれば、現在の携帯電話会社の大きな脅威になるものだ。ここにも、一見ローエンドであるが市場構造を大きく変え得る「破壊的な技術」の臭いがする。
2003年1月以降、米ウエイポートと米インテルが802.11b規格の Wi-Fi(Wireless Fidelity)無線LANサービスの普及促進で協力している。ただまだ、ホテルや空港で提供する無線サービスのプロモーションにすぎない。まだこれといったビジネスモデルが描けない状況にもあろう。
しかしながら、我が国でもホットスポット的な新拠点が全国に増加している。米国で広まるWi-Fiのような「草の根」拠点の増加は、目下最強の破壊的技術である、いかにも「インターネット」的な動きである。こうした動きが駅や空港やマクドナルド店舗に加え、個人宅や動く個人ベースで拡大していった場合、「持ち歩ける公衆電話(鷹山)」として、実用的なIPケータイのイメージが出てくる。それには、ポータブルベースのIPを駆使した新しいインフラが鍵になるだろう。
参考までに、持続的な第3携帯電話(3G)の設備負担がいかに重いかを【図表13】と【図表14】に示す。
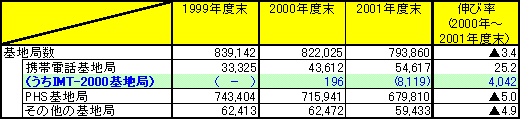
(出所) 平成14年版 情報通信白書
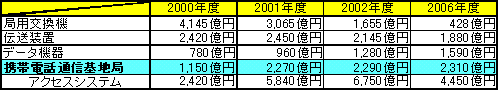
(注) 「局用交換機」: 内訳として加入者系交換機、中継交換機、データ交換機、SCP、STP。
「伝送装置」: SDH、SONET、クロスコネクト、光クロスコネクト、ADM、WDM。
「データ機器」: ハイエンドルーター、IPスイッチ。「携帯電話通信基地局」:cdmaOne、cdma2000、W-CDMA、PDC。「アクセスシステム」: FTTH、FWA、xDSLの数値が資料の方で個別に掲載。アクセスシステムの市場規模は、キャリアの投資ベースで算出しているため、設置工事費なども含まれ、FTTHの投資が大部分を占める。
(出所) http://www.bizmarketing.ne.jp/nbr/021009336.shtmlを基に作成
2001年度末のIMT-2000基地局数は、79万3,860局(対前年度比3.4%減)と2年連続で減少。携帯電話基地局は需要の増加に対応した設備増強等により、5万4,617局(対前年度比25.2%増)と大きく増加している。
全国の基地局数は、 IMT-2000で8,119局( 2001年度末)、携帯電話で5.5万局(同)。これだけでも数千億円に及ぶ投資がかかる。
NTTドコモ、auグループおよびJ-フォンがVoIPを採用する場合、レガシーであるこれら企業にとり「ケータイIP電話」は、期待の主力「3G」戦略をかく乱するものとなる。
一方、今のVoIPの流れを無視できないが、その改造費用は膨大であり、その改造そのものがカニバリズムを起こすものであり、自らを破壊的な状況に追い込むことは通常の条件下ではあり得ない。今の戦い方の問題として、「待つ」リアルオプションを行使することが、携帯電話会社の利得を最大にしているからだ。
5. IPブロードバンド革命下のゲームの戦い方はルールを変えることが基本戦略
(1)レガシーキャリアと新興キャリアの戦いに見るもの
リアルオプション戦略と並行して、最近はやりのゲーム理論を駆使することも、このIP競争時代を勝ち抜くには不可欠だ。【図表15】をご覧頂きたい。これはIPサービスの料金をめぐる簡単なゲームの例である。
N社とS社がその料金を現状維持するか値下げするかで思案している場合だ。セル内の記号は上段では利得の大きさ、中段では利得またはシェアの大きさを示し、それらは「××→×→△→○→◎」の順に大きいと考えていただきたい。利得とはこの場合、売上高(収入)、利益、顧客獲得数などのことを指す。
双方がその利得を最大化するような合理的な行動をとることが前提にある。
左下は①S社の都合、右上は①N社の都合である。すると、②右下が自動選択され、両者痛み分けとなる。いわゆる「ナッシュ均衡」である。読者の中には、米国人のラッセル・クロウがナッシュ役を演じた映画「ビューティフル・マインド」をご覧になった方も多いだろう。
一方、ゲームを戦うN社とS社にとって、結果考えてみると左上のセルが双方にとっては「市場のパイをうまくシェアする」よかった状態である。これは「囚人のジレンマ」と呼ばれるもので、「同時ゲーム」が進行した結果ゆえのことだ。
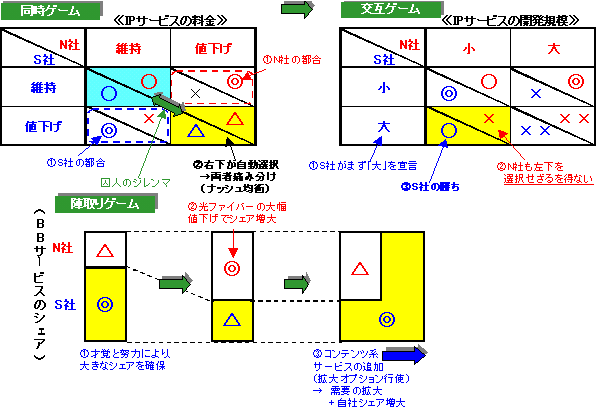
(注) 「セル内の記号」:上段では利得の大きさ、下段では利得またはシェアの大きさを示し、それらは「××→×→△→○→◎」の順に大きい。京大助教授逢沢明氏の事例資料(2003年)を参考にした。
(出所) 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
では別のゲーム、同じ【図表15】に示す「交互ゲーム」を見てみよう。戦略的なIPサービスの開発をN社とS社が行う場合、その開発規模において、例えば(1)S社がまず「大」を宣言(コミット)するとしよう。すると、(2)N社も左下を選択せざるを得ない。なぜなら、「大」を選択すると最悪の右下に位置することになるからだ。こうしてこのゲームでは、(3)S社の勝ちとなる。
さらに次のゲームに進もう。これはブロードバンド(BB)サービスのシェアの陣取りゲームである。
ゲームの初期段階にS社が、①才覚と努力により、大きな市場シェアを確保していたとしよう。これに反撃を加えるべくN社が、②光ファイバーの大幅値下げでシェア増大したとする。
ではS社はどう戦うべきか。ゲームのルールを変えることが基本戦略となる。たとえば、(3)コンテンツ系サービスの追加により、前述のような「拡大オプション」を行使し、新しい需要の拡大(市場の創造)を図りつつ自社シェアをその中で増大させていく。
ゲーム理論はこのように経済学者の机上の学問ではなく、現実の経営戦略の中に十分応用できるものなのだ。その一端を理解してもらえたことだろう。
(2)IPを軸とする新しい産業構造は3層の水平分離へ
再び本稿の冒頭の問題に立ち返るとしよう。
【図表16】は、通信、コンピュータおよび金融分野において、(1)物理層、(2)プラットフォーム(PF)層、(3)コンテンツ層の3階層で産業構造の変遷を3つの段階に分けて整理した。矩形や丸印などの各領域の大きさは相対的な市場規模をイメージした。
第1段階から第2段階でのそれぞれの産業変遷を概観してみよう。
電気通信ないしブロードバンド通信の分野では、(1)物理層つまり通信網からの収益が断トツで大きい時代から、やがてデジタル化やカプセル化、およびモジュール化などが進み、(2)PF層をベースとする課金・決済などのビジネスが活発になってきた。NTTコミュニケーションズの主力ビジネスなどが典型である。そして、(3)コンテンツ層そのもの、あるいはPF層との境界で活躍しているのがYahoo!や楽天といったところだろうか。
コンピュータ分野では、(1)大型汎用コンピュータなどのハードウェアがかつては収益力の高いビジネスの源泉であった。そして、(2)ハードウェアの「付随物」にすぎなかったコンピュータOS(基本ソフト)ビジネスが、ゲームの戦い方を熟知しているマイクロソフトのしたたかなビジネスにより次第に支配的になった。
(3)ソフトウェアビジネスは、総合電機メーカーやNTTデータなどのSI(システムインテグレーション)などのビジネスと結びつき、我が国でも大きな市場を形成するようになった。
【図表16】 水平分離的な新しい産業構造の変遷
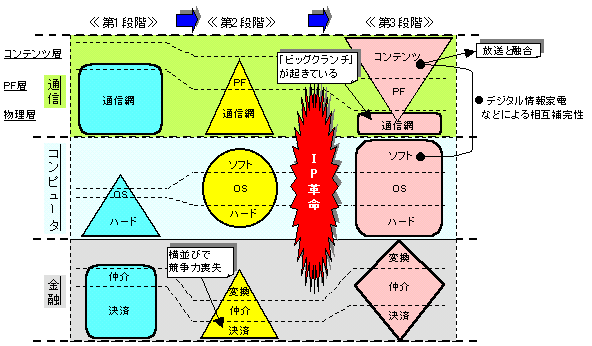
(注) 「各領域の大きさ」:相対的な市場規模をイメージ。「各領域の3層区分」:下から順に物理層、PF(プラットフォーム)層、コンテンツ層のこと。金融分野では「仲介」:投資銀行機能、「変換」:派生証券機能などを意味する。3層区分の名称や考え方などRIETI(経済産業研究所)フェロー池田信夫氏論文(2000年)を参考にした。
(出所) 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
金融分野では、(1)邦銀において従来からの決済ビジネスが最初は支配的であったが、第2段階あたりからは、(2)米国などの外資系投資銀行などの日本市場への参入なども相次ぎ、投資銀行機能などの仲介ビジネスが我が国にも一定規模の市場を形成するようになった。しかしながら、最近の邦銀の体たらくを見るにつけ、まだこの分野を含め、(3)派生証券機能などを意味する変換ビジネスなどは不十分といえよう。
では、第3段階への移行に、現在進行中の「IP革命」を位置づけるとどうなるか。電気通信とコンピュータの両分野に絞り予想してみたい。
第2段階から第3段階への移行期に、池田信夫氏の呼ぶ「ビッグクランチ」がまさに起きている。破壊的なIP技術により、ビジネススキーム、いや産業構造そのものが抜本的に変わり(だから「革命」)、収益基盤をつくれず、これまでの収益を取り崩す状況が生まれている。
固定電話は1997年に加入者および収入ベースでピークを迎えて以降、毎年減少の一途をたどっている。前述のE.M.ロジャースの普及モデルの「ラガード層」まで行き着き、市場は新しい需要になだれを打って移行しているかのようだ。NTTの約11万人の雇用問題を考慮しつつ、サンクコスト化した設備は物理層専用の事業会社として分離するなどの具体的な動きも出てこよう。このことを破壊的技術革新が突きつけている。
携帯電話においても次の大きな収益基盤を見込みにくい状況になる。大型の設備投資に見合ったリターンが得られないため、各社はカメラ付きケータイ技術や、利用者の今の状態を検知することを起点に多様なサービスを生み出すプレゼンス技術や、あるいはICチップ技術を用いたサービスによる横展開に奔走している。その動きから、固定電話ビジネスにはほとんどないプラットフォーム層を境界に、コンテンツ層との接触が、急速に増えやがて大きな市場を形成していく余地があるように見える。
コンテンツ層については、IP網の上に技術的には、放送コンテンツ(番組)も乗ってしまうため、産業効率化の観点から、ないし我が国の産業戦略の観点から、IPベースの枠組みを創ることが求められる。以前から「通信と放送の融合」として霞が関においてアジェンダにされてきた問題だ。このことを破壊的なIP技術がやはり突きつけているといえる。
加えて、ブロードバンド通信分野のコンテンツ層においては、コンピュータ産業におけるデジタル情報家電などに絡むソフトウェア層(各種アプリケーション)などとの相互補完性、言い換えれば範囲の経済性を追求できる。我が国の産業復権の鍵を握る、関係各社の戦略実施の桧舞台となる領域である。
(3)海外のブロードバンド通信市場はどうなっているのか
1999年7月、NTTの再編(分離・分割)問題に、当時の郵政省とNTT労使との間で政治的なけりがつき、実施に移された。すでにIP革命がじわじわと忍び寄っていたころである。
当時、インターネットによる電気通信市場への影響の大きさにおける認識が欠如していた。筆者は何人かの通信会社の幹部やスタッフからの話を記憶している。「インターネットでどうやって電話などできるのか。品質や、通信トラフィックの輻輳問題など解決できる術はない」などといったようなものだった。
それからわずか4~5年で恐ろしいほどに変わった。電話会社をもう退職してしまった幹部はよいかもしれないが、残された者はこの難関をどう乗り切ればよいのか。
これは我が国が最も進んだ(?)状況に置かれているといえる。筆者は2003年1月にも米国の通信会社幹部らと現地で接する機会があったが、米国よりも韓国や日本、そして、欧州ではイタリアやスウェーデンなどのほうがIP技術革新への取り組みが実質進んでいるように思える。実質という意味は、IP技術ベースの新興勢力が、当地のレガシーまたはドミナントキャリアへの対抗馬になっている、つまり「巨像にとまった蝿」のような存在ではなく、巨像を慌てさせている状況があるということだ。イタリアの例を示そう。
イタリアのe.Biscomがメディア総合型ビジネスを展開したのは1999年から。以降、年々業績を伸ばしているのは注目される。同社連結で2003年第1四半期は、101.7百万ユーロ(1ユーロ137円換算で約140億円。年換算で600~800億円ほどか)、そして、連結EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization:税金、支払利息および減価償却費控除前利益)は? 13. 8百万ユーロ(同約19億円)を稼ぐまでに成長した。立派なものである。
また、同社傘下のFastWeb(ブロードバンド通信会社)の収入は2002年第1四半期の収入に比し80%アップの75百万ユーロ(同103億円)、同社のEBITDAは15.6 百万ユーロ(同21億円)で収入全体の21% に達する。つまり、e.Biscom全体の中でインフラが中心になって収益を上げている。
顧客数は21万3,000人に達し、2002年3月時点の約3倍。光ファイバー対ADSLがほぼ7対3とのことである。年間ARPUは 2002 年3月の715ユーロ(年間9万8,000円、月間8,200円)から2003年3月には790ユーロ(年間10万8,000円、月間9,000円)に増加した。
VODサービスでの 月間ARPUは2002年3月の6ユーロ(約822円)から、2003年3月にはほぼ倍増の11ユーロ(約1,507円)となっている。
これらデータは、同社のアニュアルレポートと、筆者が3年ほど前にミラノを直接往訪した際、親切に出迎えてくれた同社幹部Mario Mella氏の最近情報による。
ソフトバンクBBの月間ARPUが約4,000円(国内のADSL市場ではトップ水準)ということであるから、e.Biscomの例は、ビジネスの規模はまだ小さいが、その先をいっているともいえよう。ただ、ブロードバンド通信においても、マイケル・ポーターの競争戦略を持ち出すまでもなく、その国の市場ならではの事情(国内産業の競争状態を決定する4つのダイヤモンド・フレームワーク属性)があるので一概には比較できない。たとえば、イタリアでは過去CATV市場の創出に失敗した経緯がある。そのため、前述のARPUも高めに出ているのだろう。
(4)ブロードバンド産業の行方に影響を与えるNTTの再再編問題
2003年5月にマスコミで報じられるなど、NTTの再再編問題がにわかにクローズアップされてきた。NTTの存在はブロードバンドIP市場の行方を握る鍵だ。したがって、この巨像がどう動くのか、あるいは戦略のリアルオプションをいかに行使するのかが注目される。
冒頭の産業構造における水平分離的な志向が、巨像のような大企業において効率的であれば、その再再編問題に総務省らから横槍を入れられるのではなく、自らの経営判断で選択すべきである。再再編問題は、インターネットないしIPを意識しないで一旦政治解決された事項なので、この問題が浮上するのは当然の成り行きである。
報道ベースによれば目下、NTT持ち株会社ではさまざまな企業形態を模索しているとされる。その断片情報からイメージ化したものを【図表17】に示した。
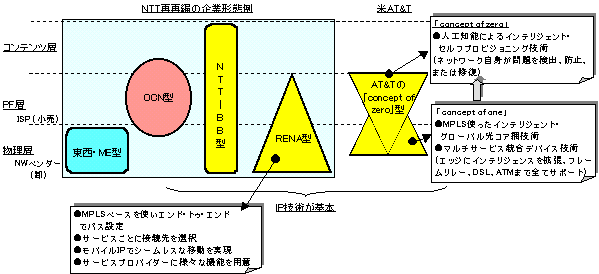
(注) 「MPLS」:Multi Protocol Label Switching の略でパケットの高速転送を可能にするレイヤ3スイッチングの技術。「AT&Tの2つのコンセプト」:AT&TのCTO(技術統括オフィサー)であるHossein Eslambolchi氏のAT&TのNGN(次世代ネットワーク)に関する発言(2002年12月)を参考にした。
(出所) 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
たとえば、「東西・ME型」では、電話の専門会社として、卸(ホールセール)専門の機能を志向するものだ。ダークファイバーを含め光ファイバーは、電力会社のそれらと同様に広く開放し、それと引き換えにユニバーサルサービスを除く、大半の規制を撤廃することがポイントとなる。マルチメディア時代のユニバーサルサービスについては、数年前に慶応大学大学院の林紘一郎教授ほか通信分野の研究者数名と研究したことがあるが、今のIP革命の進展状況を考慮しつつ慎重に対処すべきである。専門会社には国鉄方式を採るオプションもあろう。
「OCN型」はNTTコミュニケーションズを中心とした戦略的なモデルであるはずだが、現下においてなかなか盤石な収益基盤を構築できないようにみえる。スライウォツキー氏の収益基盤モデルを用いるなど、どこにプロフィットゾーンがあり、それを捕らえたらいかに長く持続化を行える仕組み構築などが喫緊の課題だ。
ただ、これまでの加入者線などの不可欠設備(エッセンシャル・ファシリティーズ)による自然独占的なうまみをIP時代には享受できない点。そして、PF層中心のビジネスはその上位のコンテンツ層との接触が増えるにもかかわらず、そのノウハウの蓄積ができていない点などから難しい問題が山積する。
クリステンセン教授の言う「(1)資源、(2)プロセス、(3)価値基準」が組織のケイパビリティ(人材・組織を含めた収益基盤)を決定するとすれば、コンテンツ層のノウハウを「購買」するにせよ、(3)価値基準の変革なしには十分戦えないだろう。モノ(物理層の技術)や人の購買を効率化できても、コンテンツ周りのノウハウ蓄積の効率は落ちることだろう。それは、著作権などを含めコンテンツ側に収益の源泉があるからだ。
「NTT-BB型」はどうか。これは、2001年10月にNTT持ち株会社が設立した、ブロードバンド向けサービスの戦略子会社のNTT-BB(NTTブロードバンドイニシアティブ)をベースにするものだ。誌面の関係でそうたくさんのことは書けないが、「OCN型」と同様にやはり、(3)価値基準の変革に関する根本的な課題が横たわっているに違いない。
e.Biscom社の幹部やスタッフは、通信、放送、メディア、コンピュータ、IT、金融、経営コンサルティングなどのさまざまな分野から構成されている。また、同国の国営会社(RAI)と事業提携を結んだり、米国ハリウッドと積極的に提携したり、マルチメディアあるいはブロードバンドにふさわしい取り組みを日々行っている。こうした分野にNTTが本格的に進出するのかどうかの問題でもある。こうなればこれまでの通信会社とは全く異なった会社と呼ぶべきであろう。
「RENA型」については、MPLSベースを使いエンド・トゥ・エンドでパス設定を行えたり、サービスごとに接続先を選択でき、あるいはモバイルIPでシームレスな移動を実現するなど、計画ベースでサービスプロバイダーにさまざまな機能が用意されているようだ。
孫正義氏がブロードバンド事業に賭けていると公言しているように、NTTもまたRENAに賭けているといえよう。「持続的」な発想がどうしても首をもたげるであろうが、クリステンセン教授のいうある種の破壊的な(革命的な)スキームが問われている、しかしながら、自国の為政者が自ら「革命」を起こした例が歴史にないように、産業界においても、自らの手で行うのは矛盾的でもある。 コンセプトや技術そのものについては、米AT&Tの「concept of zero」などが参考になるだろう。
しかし、本質的には、才覚と努力によって挑戦を仕掛け続ける新興勢力以上のパワーをトップマネジメントが発揮できるか、そして、そのIP時代にふさわしい柔軟なケイパビリティを早く獲得することができるかの問題となる。
また方法論としては、リアルオプション戦略やゲームの戦い方、そして、価値基準まで変革する取り組み(チェンジマネジメント)が、この難局を乗り切る鍵を握っている。
以上、IP革命のもたらす構造変革をどう乗り切るか、この革命に直接・間接に影響の及ぶ読者への理解の一助となれば幸いである。

