"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第13回「なぜKMはうまくいかないか?:知財立国の前に」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2002年7月18日
(1)知財立国を目指す日本
今月(2002年7月)、政府の知的財産戦略会議(座長:阿部博之東北大学長)が日本経済の再生を目指すべく「知的財産戦略大綱」をまとめた。また、同14日にはNHKスペシャルにて、企業の著作権などを扱った「知は誰のものか」という興味深い番組が放映された。最近、にわかに「知」が注目されてきた。
2000年4月のITバブル以降の昨今、中国勢などの近隣諸国の急追もあり、日本企業の競争力低下が目立っている。この2年ほどはSCMに代表されるようなIT手法を徹底導入し、自社の生産プロセスを見直し低コスト化をはかってきた。それでもなぜか、日本企業の競争力は抜本的に解決されたようには感じられない。
このような時、1980年代に日本企業の勢いに押されたかつての米国がそうであったように、競争力回復の大きな柱として、わが国においてあらためて知的財産の保護・見直しが今回クローズアップた。政府の先の戦略には、もちろん同財産の保護に加え、創造、活用に関することも重視されている。
ただ問題は、「知」の創造・活用において、知的立国のための特許などの司法制度見直しや、研究者への報酬還元率アップなどの制度設計といったマクロ的対策だけではうまくいかないことだ。筆者のコンサルティング現場の視点から、KM(ナレッジマネジメント)がその鍵を握るものと考える。
(2)業務遂行型KMの限界
一方で最近、業務遂行型KMに関する各企業の取組み事例が報告されている(日経BP「日経情報ストラテジー」2002年8月)。同事例の共通的なポイントは、「業務の質の平準化+従業員の教育」にある。
その内容は、マニュアルや営業日報、報告書などの様々な文書を蓄積し、目的に応じていろいろな形態に編集しユーザーに提供するといったものだ。ナレッジとラーニング(学習)が一緒になったパッケージソフトも米国などで開発されている。これはこれで大いにやる価値があろう。
しかし、この程度の業務改善的な域を出ない限り、知財企業にも、ましてや知財立国にもなれない。「並み」のナレッジやノウハウではブレイクスルーは決して期待できない。「革新(イノベーション)」を生起できるかが問題なのだ。
これを地でいったケースが、わが国で現在"ノーベル賞に一番近い人"と評価される、元日亜化学工業(徳島県)の研究技術者で現カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授の中村修二博士による、青色発光ダイオードの開発である。同博士の快挙に至るプロセスには驚くべきものがある。同時に、企業のマネジメントやKMにおいても見習うべく大きなヒントがある。
中村修二博士の場合はまったくの孤独な環境下での発見・発明であった。凡人すべてが同博士のようにはいかないが、博士が自問自答して成し遂げたプロセスの代わりに、組織内で有効なダイアログ(対話)による手法を示したい。古くはギリシャ哲学の世界から対話法(あるいは19世紀の弁証法)を通じ、私たちの先人は問題の本質を引き出してきた。 KMにおいても同様である。最近、企業がこぞって導入しているKMが、多種多様であるが「並み」に近い(あるいはジャンクな)知識を一生懸命にインプットし、単なるDB(データベース)づくりに化していることが多い。
(3)CKAが鍵を握るKM
企業の経営効率化、すなわち低コスト化、リードタイムの短縮などの業務遂行型としては、これらの取組みはある程度機能しているかも知れない。しかし、経営イノベーションにはつながらない。
ポイントは、失敗などを含む事案(ケース)の当事者およびその上司またはリーダーと、トップマネジメントとの間での緊張感のあるダイアログの場をつくることから始まる。職制上の上司でなければ緊張感が作れないのであれば、半ば強制的であるがそれも一定の効果がある。
イノベーション生起や現状の課題に見事にソリューションを与えてくれるナレッジは、お願いされて提出するようなものではない。提出しなければ、他の事務手続きは受理しないといった強引なことを行っても形式主義に陥るだけである。数だけは出るがジャンクの山となる。
このダイアログの場で、同ケースの本質を引き出す術が問われる。この場面では専門のコンサルタントの助力を借りるのも手だ。次に、両者のやり取りをその場で、第三者として一部始終観察し、その暗黙知的な情報を形式知に翻訳できるようなCKA(Case Knowledge Analyst)が不可欠だ(図表参照)。この翻訳もしばらくはプロの手ほどきを受けてもいい。
【図表】 ナレッジマネジメント(KM)の基本とCKA
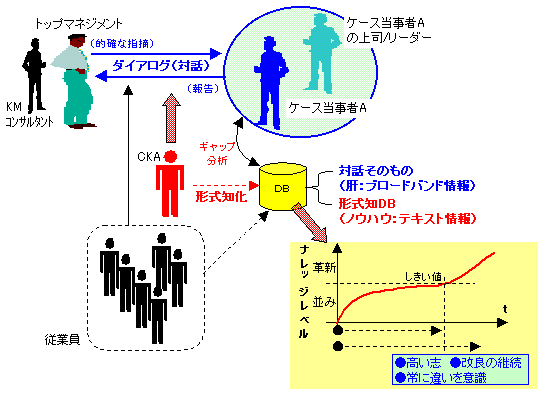
(注)CKA:Case Knowledge Analyst(作者の造語)
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
CKAは、決して名ばかりで実を出せないCKO(Chief Knowledge Officer)のような流行言葉ではない。
当面、CKAによる記録はテキストベースであり形式知DBの整備が重要となる。そして、しだいにブロードバンド環境をうまく利用し、映像を含めた対話そのものを丸ごと記録し、かつ記録後に一定の区切りやキーワードなどのモジュール単位で編集などが自在にできるKMシステムの構築につなげられると、これまでの商品開発や生産性の向上などにも増して寄与できる武器となろう。実際、これに近いITツール(ソフトパッケージ)が出てきているようだ。
こうしたITやIS(情報システム)環境の整備ができれば心強い。企業の経営やそれに影響を与える企業内に蓄積されたナレッジが、いかに経営イノベーションをもたらすか。また、グローバル競争において、過去の優良な知的財産の保護の段階から、今後の経営の舵取りに不可欠な新しいナレッジを生み出し続けていける仕掛けづくりの段階への移行こそがポイントとなる。
そのためには、もちろん中村修二博士に示されるような、高い志、改良の継続、常に違いを意識するといったイノベーション生起の基本要件を、私たちの日頃の現実の中でものにすることが不可欠である。この術については、近く次回以降で触れることとしたい。

