掲載情報
"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第32回「市場クランチと企業の競争力(上)――IIJが宿敵NTTの傘下へ」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2003年9月4日
(1)IIJがNTT傘下へ、引き金はCWCの経営破綻
世の中では似たことが起こるものだ。次は約2年前に起こった米国での出来事だ。当時の『WIRED NEWS』から引用(抜粋)させて頂く。
「2001年9月28日、ケーブルテレビ回線を使った高速インターネット接続プロバイダー大手の米エキサイト・アットホーム社は、同社のネットワークを3 億700万ドルで米AT&T社に売却するとともに、米連邦破産法第11条(日本の会社更正法にあたる)に基づく保護を申請すると発表した。 AT&T社との取り決めにより、かつては勢いを誇ったエキサイト・アットホーム社のネットワークは、AT&T社の一部として吸収されることになる。」そして、次はわが国に起こったことだ。先週の日本経済新聞社の記事から抜粋したい。
「2003年8月29日NTTは臨時取締役会を開催し、インターネットイニシアティブ(IIJ)の経営支援を決定。同日、IIJは総額120億円の第三者割当増資の実施を表明した。NTTは出資比率約3割(筆頭株主)となる模様。IIJグループは事実上NTTの傘下に入ることとなった。」2年間のタイムラグなどを除き、米エキサイト・アットホームがIIJに、米AT&TがNTTに置き換えると、両者は何とも酷似している。もちろん日米間で、単純に比較できないビジネス環境要因は少なくないが。
IIJがNTTの軍門に事実上下らざるを得なくなった直接の引き金は、2003年8月20日、子会社のクロスウエイブコミュニケーションズ(CWC)が会社更生法を申請したことにある。業容拡大に伴う先行投資負担に加え、データ通信市場の大幅な価格下落で赤字幅が拡大し、同年3月期の経常損失が約136 億円にも達した。
IIJはわが国インターネット接続サービスの草分けであり、筆者はこの企業がおかしくなる時は、日本のインターネット市場も深刻な状況に直面する時であると数年前から感じていた。IIJやとCWCは、技術力に定評があり、またIIJの鈴木幸一社長のビジネス野心は並々ならぬものがあり、提供サービスの先進性や経営手腕は当時、業界関係者には誰しも力強いものに映ったものだ。したがって、今回こうした事実に直面し大変残念なことである。
IIJグループとは特別なやり取りがあった東電グループは、NTT包囲網の一環として当時の日本テレコムの固定網買収による統合を強く模索していたようたが、原発事故隠し問題が響き2002年春、破談に終わった。
そしてほぼ同時期、東電とIIJとの経営統合の話が急浮上した。NTTへの対抗軸形成の意味で大変注目されたカードであったが、結果、約1年後の 2003年3月、IIJと東京電力グループとの統合は見送りとなった。この時期、日本テレコム(固定電話部部門)を、リップルウッドが買収することとなった。これらはわが国の通信市場では大きなターニング・ポイントとなった。
通信市場のこうした動きを、次の図表にまとめた。
【図表】 「5つの力とBSCに見るIIJグループのポジショニング
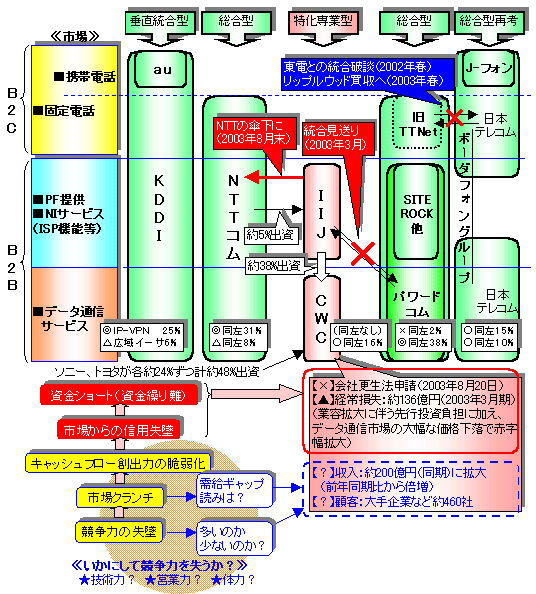
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
IIJと東電グループの関係は、前者が技術力、後者が財務力などの総合力といった相互補完的なまたとない強力かつ魅力的な組合せであった。両者の自負心の強さも理解できないことはなかったが、なぜあの時に、もっと歩み寄っておかなかったのか。
2002年春からその後の約1年ないし1年半の状況変化は、その後の両者にとって大いに裏目に出た。つまり、双方のビジネス上の展開シナリオ(経済的な経路)を決定付けるものとなった。
(2)市場クランチと競争力の失墜
CWCにはソニー、トヨタが各約24%ずつ計約48%を出資し。1998年10月、日本初のデータ通信の専業会社として設立された。設立契機は、次のような言葉に表れている。
「設立当時は、データ通信に重点を置いた事業者がいなかった。市場はポッカリ穴があいており、一刻も早く参入したかった。『時間を買う』というイメージだった。」(2000年 2月当時の同社幹部談)企業向けデータ通信サービスには、これまでのセキュリティに非常に強いが高価な専用線やフレームリレーに加え、新たなに主にIP技術を用いたIP-VPN、広域イーサネットほかインターネットVPNなどが、価格面や速度面などの点で注目されている。
(注)「専用線」: 通話時間と距離に応じて通話料金を従量制で課金する通常の電話回線ではなく、通信回線をまるごと貸し切りにして、通話時間や接続距離とは無関係に、固定料金で通話できる通信回線のこと。例えば、"OCNエコノミー"や"ディジタル・アクセス/ディジタル・リーチ"などのエコノミー専用線(128Kbps)に加え、高速デジタル専用線(64K~6Mbps)、ATM専用線(0.5M~135Mbps)などがある。通信内容を傍受することはできないようになっているので、セキュリティは非常に高い。
(注)「フレームリレー」: 従来パケット通信に使われていたX.25という規格の誤り訂正手順を簡略化し、高速化を図ったもの。フレームリレーを利用した1.5Mbps以上のデータ通信サービスが各社から提供されている。
(注)「IP-VPN」: 通信事業者の保有する広域IP通信網を経由して構築される仮想私設通信網(VPN)のこと。専用線やフレームリレーよりも廉価で、比較的セキュリティの高いサービス。最近では、QoS(サービス品質)、SLA(サービス・レベル・アグリーメント)、セキュリティ監視などの高度なネットワークマネジメントを行うMPLS(マルチプロトコルラベルスイッチング)型IP-VPNも登場している。速度は0.5Mから10Mbpsのものが普及している。
(注)「イーサネットVPN」: インターネット上で実現されるVPNのこと。バックボーンにインターネットを使うため、回線を維持するための費用が非常に安く、専用線などと比べて極めて低コストで運用が可能。インターネットを流れるデータはそのままでは盗聴されてしまう恐れがあるため、IPsec(インターネットで暗号通信を行なうための規格)を使用して通信内容を暗号化し、機密性の高いデータを通信できるようにしている。
(注)「広域イーサネット」: イーサネット(1976年に米Xerox社で考案され、1980年に同社と米DEC社が公開したLAN規格)で使用されているスイッチングハブ(レイヤ2スイッチ)を組み合わせて構築した100km単位の大型ネットワークのこと。複数拠点のLAN(ローカル・エリア・ネットワーク)をそのまま接続する技術で、バックボーンにはEthernet over SONETが使われる。イーサネットそのものをカプセル化するため、ルーティングプロトコルにIP以外のものも利用可能。IP-VPNではルーターが必須であるが、広域イーサネットではVLAN(バーチャルLAN)対応のレイヤ2スイッチがあれば接続できるため、簡単、安価、故障しにくいなどのメリットがある。速度は10M~100Mbpsが普及しているが、超高速(1Gbps)品目のギガビットイーサネットなどもある。
CWCの主力商品はバックボーン回線の提供のほか、広域イーサネットサービスである。一方、競合他社では、IP系データ通信サービス品目にはIP-VPNや広域イーサネットの両刀使いで追い上げた。再び前述の図表をご覧頂きたい。
結果、先行していたCWCは2003年7月時点の広域イーサネット市場でおよそ16%の支持を得たに過ぎない一方、競合のパワードコムは広域イーサネットでは同38%で業界トップ。大きく水を空けられた。
またレガシーキャリアであるNTTコムは広域イーサネットでは同8%に留まるものの、広域イーサネットよりも市場規模の広がったIP-VPNで業界トップの同31%の地位を確保。同様にKDDIは広域イーサネットでは同6%であるがIP-VPNで同25%、日本テレコムも順に10%、15%と善戦している。
会社更生法申請に至るまでの、CWCの事業に関する誤算は次のようなものであった。
直接には資金繰り難による資金ショートから始まったものであり、その前には市場からの信用失墜となる。そして、より本質的にはキャッシュフロー創出力の脆弱化に起因する問題があったと思われる。しかし、ここまではCWCに限らず、どの業界の企業でも同様の流れである。
今回特筆すべきは、市場関係者の大方の予想を遥かに超えた市場クランチ(縮小)であった。すなわち、従来、法人企業向けサービスではまったく無かったほどの急激な価格下落に見舞われた。回線数は伸びているものの、回線単価が大幅に下がった。IP技術は、一見取るに足らないほどのローエンドのものであるが、そのインパクトは破壊的な技術なのである(http://www.jri.co.jp/company/publicity/2003/detail/sbp_ip/参照)。
ただこの異例な状況は、競合他社も同様に直面していたことである。したがって、次の問題点は競争力の失墜にあった。
市場の需給ギャップの読みはどうだったか。約200億円の収入(2003年3月期)は前年同期比から倍増し、顧客も大手企業など約460社を獲得したと報じられているが、これは多いのか少ないのか。危険水域に達する前の予兆への対処はどのようなものだったのか。
また、企業データ通信サービスを巡る環境変化は、どれほどのものだったのか。IIJを含むCWCなどの花形企業が、いかにして競争力を失ったのか。それは技術力に起因したものなのか、いやそれは営業力や体力(財務力)の問題であったのか。次回ではこれらのことを考察してみたい。

