"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第26回「日の丸半導体産業の復権はなるか(中)――エルピーダは戦えるか」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2003年5月15日
(1)エルピーダメモリの挑戦
第25回では、わが国の半導体およびDRAM産業に関する収益モデルの検証について言及し、マネジメントの問題を取り上げた。
「ICTマネジメント」すなわち「Innovation(革新) & Change(変革) Technologyマネジメント」のうち、前者のイノベーションマネジメントよりも、現在では後者のチェンジマネジメントが求められている。ここでの「Technology」は、革新と変革をもたらす手法(術)となる。それは手法(術)に関するマネジメント(どのように扱うか)、あるいはマネジメント手法(術)のどちらでもよい。
2002年11月、エルピーダメモリ社長に坂本幸雄氏が就任した。日本で唯一のDRAM専業メーカーのトップとなった。日立製作所とNECが資本金を折半で出して設立されたエルピーダでは、社長を両社から交代で出すといった、「メガバンク」みずほ銀行誕生時の統合の二の舞になるところであった。
多くがコモディティー化した分野をもつDRAM事業では、売上高シェアで10%超を確保する企業は4社のみである。こうした寡占化が進み、競合他社の出方を読むゲーム理論的な発想やセンスなどの要素がますます重要になってきた。つまり、マネジメントに関する競争の様相が鮮明になってきた。思い切った資金投入のタイミングやスピーディーな開発、市場投入などに関する意思決定に、都度親会社の合意を取り付けることが不可欠としたら、競争には到底勝てない。
「再建はスピード」とする坂本氏の手腕への業界の期待は大きい。日本TI(テキサス・インストルメンツ)の副社長を務めた後の、神戸製鋼半導体部門の再建、そして台湾系企業のUMCジャパン(新日鉄半導体部門の買収後設立)再建などで注目を集めた。
坂本氏は、日本企業は技術では負けておらず経営者の問題だとしている。前述のチェンジマネジメントの問題と言い換えられよう。もちろんこれは、DRAM産業に限らず、わが国の企業の多くが直面する問題である。
(2)エルピーダの収益モデルはどこに
エルピーダメモリのとっている、いわば「コモディティー市場での専業型挑戦者の収益モデル」を簡単に考察してみたい。
次の図表は、半導体分野での市場・競争ステージ別の典型的収益モデルを整理したものだ。エルピーダに加え、日立製作所と三菱電機の半導体部門の事業統合により、2003年にスタートし"インテリジェントチップ・ソリューション・プロバイダ"を志向する、ルネサステクノロジのタイプ、そして、液晶ディスプレイ向けデジタル信号処理チップのベンチャー企業、ザインエレクトロニクスも併記する。
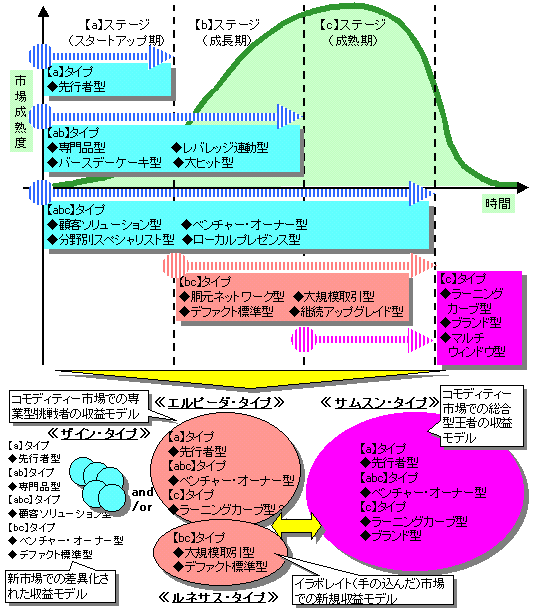
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
図表の下半分には、DRAM分野最強のサムスン・タイプと、これら3つのタイプを比較している。
それぞれの丸印の囲みに、前回の「典型的収益モデルの説明」で触れた、半導体分野へのかかわりの強いモデルを示した。
(3) サムスンと戦えるか
エルピーダがサムスンと戦うフィールド(ステージ)は、成長後期~成熟期であることを再認識する必要がある。競争相手の多かった時期から現在では寡占化が進み、その相手こそ少なくなったものの利益率の低いステージとなっている。
以下、3つのタイプを比較してみよう。
● |
「エルピーダ・タイプ」 |
|
|
こ のタイプは市場成熟度のうち、スタートアップ期【a】で有効な「先行者型」、あるいは衰退期前のすべてのステージ【abc】で有効な「ベンチャー・オー ナー型」、および成熟期【c】でとくに有効な「ラーニングカーブ型」や「ブランド型」での収益モデルを構築できるかがポイントとなる。 |
|
◇ |
「先行者型」収益モデルについて → 【×】 |
|
|
DRAM産業を見れば成熟期に位置づけられると思えるが、今でもイノベーション(技術革新)が生起している分野でもある。日立やNECなどの大企業では、成熟市場で事業を展開している場合が少なくない。実際、市場投入での1番乗り商品は少ない。 |
|
◇ |
「ベンチャー・オーナー型」収益モデルについて → 【?】 |
|
|
エルピーダでは米インテルからの出資引き出しに関する一連の積極的なアクションなど、親会社を必ずしも頼りにしない、即断即決の行動が早くも垣間見られた。坂本氏の強力なリーダーシップによるもので特筆に価する。 |
|
◇ |
「ラーニングカーブ型」収益モデルについて → 【△】 |
|
|
経済・産業のグローバル化が進み、半導体新興諸国の韓国や台湾あるいは中国の技術力が高まった。日本を含む先進国の技術移転が行われたためだ。 |
|
以上の比較から、「エルピーダ・タイプ」を取る場合、その先行きは厳しいように思われる。これら典型的収益モデルでの競争優位を獲得するには、「ICT(=Innovation & Change Technology)マネジメント」がどれほど徹底できるかにかかっている。
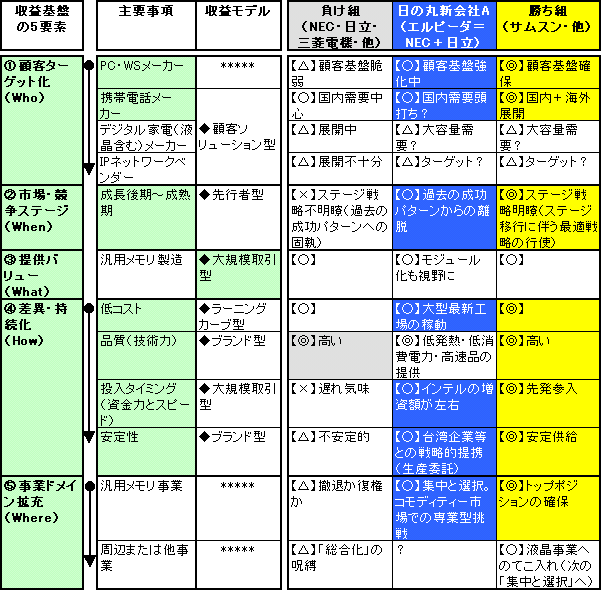
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
では次に、日立が三菱電機と設立したもう1つの企業、ルネサステクノロジを例に別のタイプを概観してみよう。
● |
「ルネサス・タイプ」 |
|
|
このタイプでは、成長期・成熟期【bc】で有効な「大規模取引型」や「デファクト標準型」での収益モデルが有効であろう。「エルピーダ・タイプ」とは異なる。このタイプをイラボレイト(手の込んだ)市場での新規収益モデルと呼ぶわけを、以下に具体的に示す。 |
|
◇ |
「大規模取引型」収益モデルについて → 【?】 |
|
|
ユビキタス・ネットワーク社会を視野に入れるルネサスは、「インテリジェントチップ・ソリューション」の提供や、マイクロコンピュータなどサムスンのDRAM製品などとは一線を画す事業ドメインを設定している。 |
|
◇ |
「デファクト標準型」収益モデルについて → 【?】 |
|
|
大量消費のドメインを見つけることができれば、次はそこでのデファクト標準を抑えてしまう。その製品が無くては、セット製品やシステム製品は機能が実現し ない、あるいは機能しても価値が大幅に下がって同製品なくしては売れないなどの存在に自社を押し上げることができるかがポイントだ。 |
|
実はこれに近い先例が東芝の取組みに見られる。
東芝は2002年1月、同社の米国関連会社の土地や建物、DRAM関連製造設備を米マイクロン・テクノロジーに売却した結果、汎用DRAM事業から事実上撤退した。その後は、民生機器向けやデジタルスチルカメラ向けなどのフラッシュメモリを、半導体メモリー事業の中核に据え目下好調である。
次の図表のとおりである。
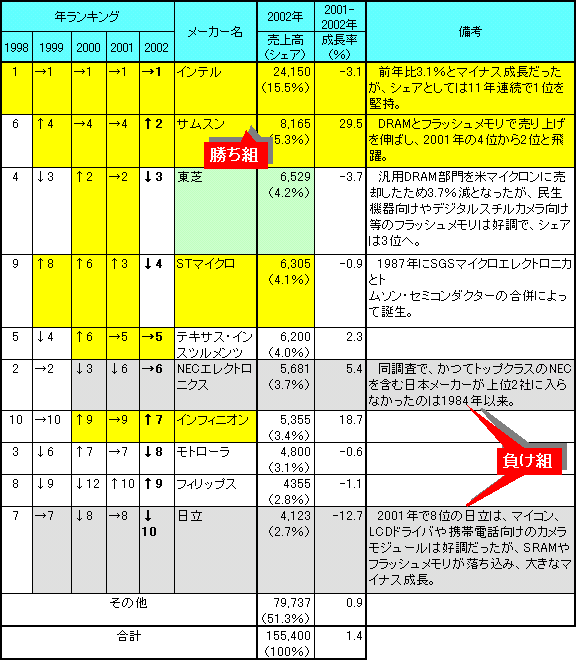
(注)単位:百万ドル。為替レート:2001年121.52円/ドル、2002年121.08円/ドル。日立とNECエレクトロニクスのDRAM(ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ)の売上高はエルピーダに計上。東芝の汎用DRAMの売上高は米マイクロンへ計上。「LCD」:液晶ディスプレイ。「SRAM」:スタティック・ランダム・アクセス・メモリ。
(出所)ガートナー データクエスト(2002年12月、速報値)に、日本総合研究所 ICT経営戦略クラスターが加筆
東芝はサムスンなどとの強者を牽制し、汎用DRAMとは別の活路をいち早く見出した点で、ルネサスよりも早い意思決定を行った。当時の東芝の選択は苦渋に満ちたものであったに違いないが、現下の取組みは、時代を読んだ結果だったといえよう。ただこれらの企業とは別の戦い方がまだある。
次の第27回では、「日の丸半導体産業の復権はなるか(下)-どこで戦うべきか」と題し、DRAM事業の直面する構造的な問題を取り上げ、上記のルネサスや東芝とは異なるやり方、具体的にはベンチャー企業による日の丸半導体産業への活路について言及してみたい。

