"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第25回「日の丸半導体産業の復権はなるか(上)――収益モデルの検証」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2003年5月8日
(1) 半導体産業の栄枯盛衰
半導体産業も「IT産業」として語られることが多い。お隣りの「IT先進国」韓国では、ADSLなどのブロードバンド通信の勢いも凄まじいが一方で、半導体産業への集中と選択には目を見張るものがある。
最近のわが国の半導体産業は守勢を強いられている。IT産業のコメと呼ばれ、半導体産業の牽引役たるDRAM(ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ)に至っては、NECや日立、三菱電機など日の丸メーカーは脱落寸前の状態にある。既に、沖電気、富士通、そして、2002年初めには東芝が汎用 DRAM製造からの撤退を行っている。
筆者はDRAMの開発(256K~16Mビット)に携わった経験が10年弱ほどあり、所属していた部門では、ことDRAMの設計や開発において世界トップの自負があったので、思いひとしおである。
かつては日本の半導体メーカーが売上高ランキングで「トップ10」の上位を独占したものだ。当時、日本のパワーに悲鳴を上げ、米国のインテルなどは脱メモリ戦略をいち早く選択した。ただそのインテルはCPU(中央演算処理装置)を武器に、過去5年間以上、同ランキングの1位を占め、半導体市場では一人勝ちの様相を呈している。
韓国の財閥系企業のサムスン電子は、大胆な投資戦略や同国の優秀で野心的(ハングリー)な技術者を集め、一気に日本企業を引き離した。特にDRAM市場の売上高ランキングでは独走状態にある。
いつまでもよい時代が続くものではない。栄枯盛衰は半導体産業においても例外ではなかった。
1999年からの次の売上高ランキングを眺めると、残念ながら、勝ち組はサムスンやハイニックスなどの韓国勢と米マイクロンといったところであろう。わが国を代表する企業は総崩れの感がある。しかも上位3社で売上高シェア60%超を超え、DRAM市場は寡占化している。
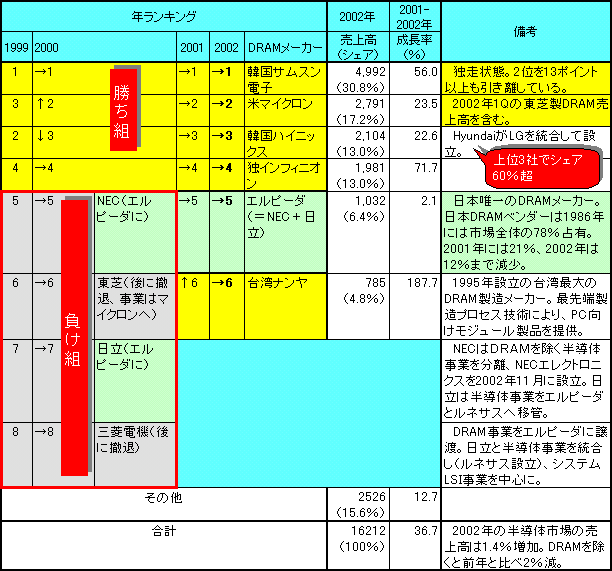
(出所)ガートナー・データクエストおよびIDC資料に、日本総合研究所 ICT経営戦略クラスターが加筆
(2)収益基盤はどのように形成されるか
本稿では、半導体ないしDRAMビジネスを例に、なぜ勝ち続けていた企業の競争にこれほどまでの変化が起こるのかを、米国のスライウォツキー(Slywotzky)の「プロフィット・ゾーン」による見方を参考に考察してみたい。
(注)
米『インダストリー・ウィーク』誌は1999年、「経営に関する世界6賢人」として、実業界からビル・ゲイツ氏(現マイクロソフト会長)、ジャック・ウェルチ氏(前GE会長)、アンディ・グローブ氏(現インテル会長)、学術界からドラッカー氏、マイケル・ポーター氏、そして、コンサルティング業界からは、スライウォツキー氏(米マーサー・マネジメント・コンサルティングのバイス・プレジデント)を選出した。
次はスライウォツキー(Slywotzky)の「ビジネス・デザインの4つの戦略次元」を参考に、新たなに「②When:市場・競争ステージ」なる要素を組み込んだものである。他の「4つ」は言い換えれば結局、「①Who:顧客ターゲット化」、「③What:提供バリュー」、「④How:差異・持続化」、「⑤Where:事業ドメイン(領域)拡充」となろう。この考え方は極めて基本的・本質的であるが、特段難しい代物ではない。
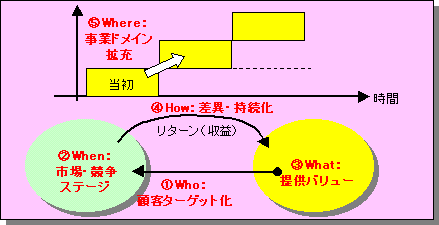
(出所) 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
DRAM事業でも、この「収益基盤決定の5要素」が明確であり、事業戦略や競争戦略に反映されているか、そのアクションがとれているか、これが基本にある。
日の丸半導体会社は久しく、この基本要素を忘れてはいないか。
● |
「①Who:顧客ターゲット化」: |
|
DRAMのエンドユーザーは、かつての汎用大型コンピューターメーカー(IBMやアムダール、バロースなど)から、当の昔にデルコンピューターや HP(ヒューレット・パッカード)などのPCやWS(ワークステーション)のメーカーへと代わった。また最近では、携帯電話やデジタル家電(液晶含む) メーカー、IPネットワークベンダーへとシフトしつつある。これら顧客にフォーカスされているか。あるいは、個々の顧客によって、市場に求められるもの・ ニーズは異なるものだ。このことが出発点にあるべきだ。 |
||
● |
「②When:市場・競争ステージ」: |
|
顧客に向けた市場やその市場を巡る競争環境がどのステージにあるのか。「イノベータ-(革新的採用者)」、「オピニオンリーダー(初期少数採用者)」、 「アーリーマジョリティー(初期多数採用者)」、「レイトマジョリティー(後期多数採用者)」、「ラガード(採用遅滞者)」の5つステージで説明する 「Rogersのイノベーション普及モデル」に従うのでも、あるいはプロダクト・ライフサイクルに従うのでもよい。 |
||
● |
「③What:提供バリュー」: |
|
どの顧客でどこのステージにあるかを明確にした上で、初めて自社の提供バリューを自問自答することになる。多くの企業では、自社のコア・コンピテンス(中核能力)に意識が行き過ぎ、上記①と②の要素をともすれば忘れがちである。 |
||
● |
「④How:差異・持続化」: |
|
上記3つの要素だけでうまくいかないのは、企業間には熾烈な競争が存在するからだ。そして、その競争は完全競争市場の均衡価格に近づくまで続く。もっとも最近は、原価割れ事態が起こっており、半導体市場での競争は異様な感がある。 |
||
(注) |
スライウォツキー(Slywotzky)は22(最近では23)の収益モデルがあるとしているが、うち6つは現実のビジネスはそれほど出現率の高いものではないように思える。 |
|
● |
「⑤Where:事業ドメイン拡充」: |
|
以上の4つの要素を明瞭にすることで、半導体事業の活動(アクション)や提供製品・サービスを拡充することができる(あるいは縮小しなくてはならない)。つまり、事業ドメインの変更の問題にぶつかる。事業ドメインを変えれば、別の収益拡大の機会を得ることになる。 |
||
(3)典型的な収益モデルとは
Slywotzkyの22(最近では23)の収益モデルのうち、出現率の高い16の収益モデルに集約・補足したものが次の図表である。
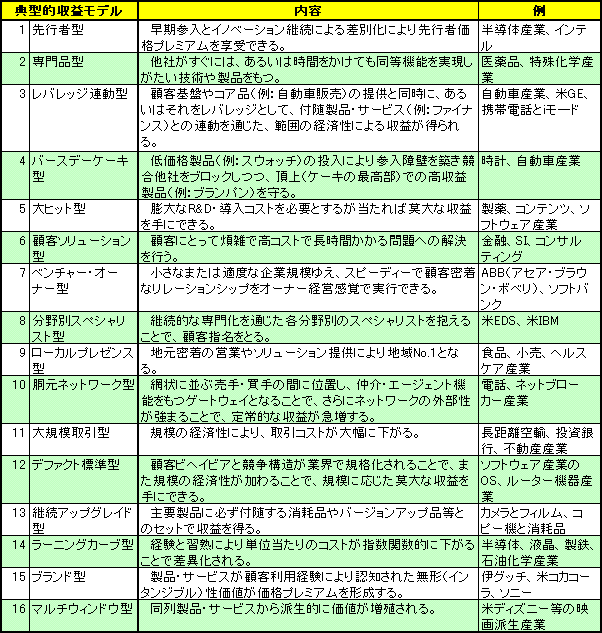
(注)Slywotzkyの22の分類(1997年)を参考に、出現率の高い16の収益モデルに集約・補足。
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
特に半導体産業全般にかかわりの大きい、7つの収益モデルのポイントを示してみたい。
● |
先行者型 |
|
い ち早くDRAM(メモリ)の製造から脱却した米インテルは、その後CPUの市場投入において常に先行。また韓国サムスンにおいても、大規模な設備投資など の意思決定やイノベーションを果敢に進め、DRAM市場の立ち上がり時期に得られる大きな果実(リターン)狙いを鮮明に打ち出している。そのことで、先行 者のみがコントロールできる価格プレミアムを享受している。 |
||
● |
専門品型 |
|
DRAM 製品がコモディティー化し、容量と価格のみが差異化ポイントになりつつあるなか、コモディティー化のジレンマ(罠)を回避すべく、専門品を打ち出すことで 差異化を追求するようになる。ただここでは、一定以上の価格を維持できたにしても多くは大きなボリュームを見込めない場合が少なくない。ベンチャー企業 や、大企業でも新規市場を狙う場合などには有効な収益モデルとなる。 |
||
● |
顧客ソリューション型 |
|
コモディティー化していくなか汎用市中製品であるDRAMでは、通常顧客へのソリューションまで行う場合は少ない。製造技術が驚異的に発達し標準化してしまった半導体分野では、出版・サービス業のような企画力や、顧客ニーズにかなった設計力が問われるようにった。 |
||
● |
ベンチャー・オーナー型 |
|
サ ムスンはオーナー経営ゆえの意思決定の大胆さや迅速さが強みとなって、半導体や液晶の両事業全体に優れたパフォーマンスが発揮されている。加えて、垂直統 合型の大企業であってもスピーディーで顧客密着的な行動規範があるようだ。この両立は普通大変難しいゆえ、サムスンのこの強み維持についてはさらなる研究 の余地がある。米シスコシステムズはオーナー型経営ではないが、同社の顧客に対するアグレッシブなアプローチには目を見張るものがある。 |
||
● |
デファクト標準型 |
|
DRAM 製造工程の標準化などでリーダーシップをとれた、すなわち製造特許などを保有できた企業には大きな見返りがあった。しかし、半導体分野での標準化は次の段 階を迎えている。液晶や次世代携帯電話やIPネットワーク機器・端末などの大量製品に組み込まれる、制御回路や信号処理チップなどでのデファクト標準をと ることで大きな収益を期待できることとなる。 |
||
● |
ラーニングカーブ型 |
|
新しい事業ドメインでの半導体分野においても、それが大量製品化や習熟度がモノをいう世界である限り、欠陥排除や品質管理のノウハウの蓄積を通じたラーニングカーブを急速に駆け上ることのできるモデルが勝敗を決する。 |
||
● |
ブランド型 |
|
CPU といえば依然インテルが強いが、ネットワーク・画像処理技術を生かしたFPU(Floating point number Processing Unit)ではウェイテック、液晶ディスプレイ向けデジタル信号処理チップのザインエレクトロニクスといった、新しい事業ドメインでのブランドを勝ち得る ことができるかが重要になる。ブランドを築くことで、顧客からの調達において常にショートリストに載ることができ、営業費や宣伝広告費をを下げることがで きるばかりか、流通交渉力を持つことができ、自社ファン基盤の構築強化につながる。 |
||
以上、収益モデルの検証について概観した。わが国半導体産業において、かつての代表選手(勝ち組)はその「収益基盤決定の5要素」あるいは「典型的収益モデル」において、大きな変更を迫られていることが分かる。
特にわが国のDRAMビジネスの場合、製造技術のみが突出した収益モデルを築きはしたものの、それ以外の独自の強みが育ちにくい環境ができあがってしまい、自縄自縛の状態になってしまった。これからは、製造技術そのものよりも、マネジメントの問題、特に筆者の造語である「ICTマネジメント」、すなわち「Innovation(革新) & Change(変革) Technologyマネジメント」が求められている。
次の第26回では、「日の丸半導体産業の復権はなるか(中)-エルピーダは戦えるか」として、エルピーダを中心に日の丸半導体会社の復権についての見通しに触れてみたい。

