"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第9回「在庫底割れ!製造業復権の処方箋とは?(1)」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2002年4月19日
(1)製造業のどこが駄目になったのか?
2002年2月には、電子部品の村田製作所やロームの在庫調整が進み、わが国製造業の一部ではようやく底入れの兆しが出てきた。村田の同月の連結受注が前年同月比13%減と14ヶ月ぶりに20%を下回った。
IT投資の有力な牽引役であるNTTグループやKDDIグループなどの主要通信会社の財務基盤が、最近脆弱になってきた。他社との競争激化や投資失敗などに加え、モバイル・IP(イーサネット・プロトコル)技術革新の急速な進展により、経営基盤が大きな打撃を受けている。イノベーションや企業競争のスピードについていけない。
この1年筆者は、情報通信技術(ICT:InfoCommunications Technology)分野のリサーチ・コンサルティングを通じ、通信の置かれた状況は極めて深刻であると実感する。その打開処方箋については次回以降に譲りたい。
米国でも電子部品、半導体、コンピューター機器などの産業は、地域通信会社のICT投資に依るところ大である。従って、通信需要などと関連する、部品や機器が組み込まれるセット製品やシステム製品の販売回復には、もうしばらく時間がかかりそうだ。
しかしこのような時期にこそ、製造業として取り組んでおかなければならないことがある。このコラムの中で、昨秋以来、製造業強化のためのCRB(Customer Relationship Building:顧客関係構築。筆者の造語)に関する示唆を行ってきた。今回、この概念を補足したい。ひいてはわが国製造業復権の一助になれば幸いである。
今日のわが国製造業は、時代に合わない経営システムになってきた。
NTT、東電、日立のようなわが国を代表する企業では、最近、変革の動きがようやく見えてきたものの、伝統的に垂直統合型モデルを堅持してきた。一方、米国では、元HPのCEOヤングによる大統領産業競争力委員会報告の発表以降、統合化の形態を水平型に転じた。デルやシスコシステムズなどがその代表格である。
【図表】 日米の経営システムの相違と今後のビジネスインフラ
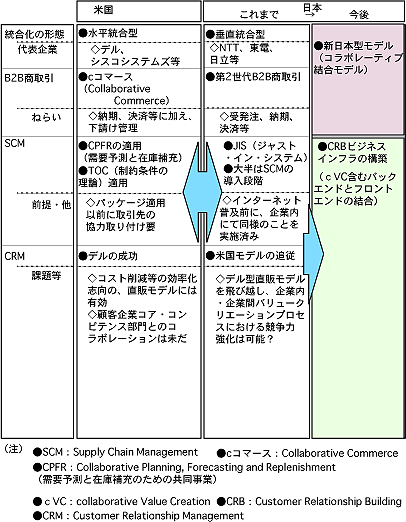
(2)エレクトロニクス分野での合従連衡にみる経営システムの桎梏化
わが国では最近、電子部品、半導体産業、ディスプレイ、デジタル家電など電機再編の動きが活発だ。筆者が総合電機メーカーにて半導体などの分野に携わっていた1980年代から1990年代初頭の頃を思い起こすと、考えられないような動きである。
半導体での、DRAM分野の日立とNEC、システムLSIにおける日立と三菱電機との事業統合、デジタル家電の開発に関する松下と日立のアライアンスなどは、まさに国内ライバル同士の組み合わせである。
国内企業同士が歩み寄ったのは、例えば半導体やコンピューター分野で、日の丸日本株式会社を設立せんとするMITI(通産省)の奔走ゆえの結果だった。しかし、最近の動きは異なる。
当該企業同士が自ら模索・選択を行っているのである。これは、先の垂直統合型経営システムにほころびが出て、立ち行かなくなった証左でもある。日本企業の強みであったコスト優位性は中国や台湾、韓国などのプレゼンスの高まりとともに、年々失われている。「ケイレツ」システムという水平的な動きもすっかり色あせた。むしろ多くの企業では重荷にさえなっている。
競争力の源泉は、1980年代にIBMがいち早くハードメーカーからの脱皮宣言を行い、現在のコア・コンピテンスとするに至った、サービスやソリューションビジネスにあたかもシフトしているようだ。
(3)コラボレーティブ結合型モデル
ここで再び、日米の経営システムの相違と今後のビジネスインフラについて見てみよう(上図参照)。
収益の源泉として各企業が最も注力しているB2B商取引において、2001年7月頃から、米国では「cコマース」(Collaborative Commerce)という概念のもと、納期、決済等の商取引に加え下請け企業の管理を視野に入れた手法が開発されている。この手法について筆者はすでに同年3月には、ある大手電子部品メーカーへのコンサルティングプロジェクトにて、米国の動きを知らずしてたまたま同様の見解を明確に示している。一方、わが国では従来の「eコマース」において、受発注、納期、決済等に限定した手法に終始しているケースがこれまで散見される。
SCMにおいては、米国では1999年1月(オリジナル概念は1996年頃)に、「CPFR」の適用がなされ、需要予測と在庫補充のための共同事業が取り組まれており、食品メーカーのNabiscoなどで在庫削減と需要予測精度を高め15%ほどの増益を達成したなどの報告がある。また、最近では「TOC(制約条件の理論)」の適用もなされ効果をあげているようだ。わが国では、さすがにもはや「JIS」(ジャスト・イン・システム)一辺倒ということではないが、このSCMにおいてもパッケージ導入段階の企業が大半だ。
この「CPFR」では、パッケージ適用以前に取引先の協力取り付けが必要であり、ここではパートナーシップのレベルや取引企業の与信などの問題が横たわっている。わが国の場合、インターネット普及前に、関係企業内(あるいはケイレツ内)にて同様のことを実施済みである。
以上SCMは、企業内部(あるいはイントラ内)アクティビティを主とする「バックエンド」領域のものだ。次に取り上げるCRMは、顧客や取引先等の外部アクティビティを主とする「フロントエンド」領域に属するものといえよう。
米国でのCRMは、デルコンピューターの成功に始まり、CRMブームが瞬く間に世界中に伝播した。しかしながら、この分野でも残念ながらわが国では、米国の追従の域を出ていない。
このCRMにも最近ほころびが見えてきた。デルの事例のような、コスト削減等の効率化志向の直販モデルには有効でも、顧客企業コア・コンピテンス部門(例:戦略、企画、研究など)とのコラボレーションは未だできていない。
今後わが国において、必ずしも製造業に限るものではないが、デル型直販モデルを飛び越え、企業内・企業間バリュークリエーションプロセスの再構築を通じ、企業競争力の強化を行うことはできないだろうか。
その鍵を握る、cVC(collaborative Value Creation)含むバックエンドとフロントエンドの結合によるCRBビジネスインフラの構築、そして、それを通じた、新日本型モデル(コラボレーティブ結合モデル)への示唆については、第10回に触れたい。(→第10回へ)

