"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第10回「在庫底割れ!製造業復権の処方箋とは?(2)」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2002年5月16日
●製造業の再定義
わが国の戦略産業は、やはり製造業が代表格であろう。まず、わが国の今後の製造業をどのようにデザインするか、その定義を明確にすることが重要であろう。
ひとつの答えは、「単純なIBM踏襲モデル」ではないだろうということだ。例えば、富士通の場合、ソフト・サービス部門の営業利益率は7%、IBMのサービスは税引き前利益率でその倍の14%でありソフト分野は23%である。富士通の場合、わが国では最もIBM型、すなわち同分野での利益率の高い事業を展開できている。
ここまでは正しいのかも知れない。ソフト・サービス分野における日本企業の努力の余地はまだ相当にあろう。今後、IP-VPN(IP網による仮想専用線)や広域イーサネットなどの企業向けデータ通信サービス網が、向こう3年以内に「上場企業+α」の約3,000社の多くへ浸透し、その後の5年程度でその予備軍である約1万社の中堅企業にも普及するものと筆者は見ている。ここで、わが国において年間売上高が500億円以上の企業の場合、IT(またはICT)投資に年間5,000万円ほどを割くといわれている。その企業の数はおよそ1万5,000社であるから、その3分の2程度と見ていることになる。
こうしたブロードバンドインフラ革命の進展は、まさにソフト・サービス分野にとっては追い風であり、このインフラを前提に企業内ので増速ニーズは高まり、企業スタッフの業務の仕方やコラボレーションでの緊密性が抜本的に変わっていく。
●ソフト・サービス業を超えるもの
従って、ソフト・サービス領域での顧客企業ニーズの潜在性は未だ膨大であり、ここを掘り起こすことの意味は大きい。だから、昨今の製造業の多くがここへのシフトこそ急務であると合言葉のように唱えているわけだ。しかし、この富士通のほかNECや日立らが単純に踏襲しようとしている「IBMモデル」とは、いわば上流・コンサルティングなどの領域であるクリームスキミングを明確に視野に入れた、ブランドと長年のノウハウを武器にしたオンリーモデルのことだ。もちろん、当のIBMには外資系であることの要素も、少なからず「利用可能な」別種の強力なブランドとなっている。
それゆえ、伝統的な日本企業がこのモデルに右へ習うことはそう簡単ではない。製造業にサービス業たれと言うはやすし、である。
このモデルの果実を手にできるのは業界No.1企業だけであり、それゆえオンリーワンということになる。類似ケースとしては、データベース市場におけるオラクルのようなポジションとなる。
日本企業においても、ニッチ分野を継続的に狙うロームや、周辺機器に特化するキヤノン、センサー専業のキーエンスなど成功モデルをもつ製造系企業は少なくない。
では、ブロードバンド時代において再び世界覇権をとるための、わが国製造業のめざすべきモデルとは何か。
●コラボレーティブ結合モデルこそ新しい日本型製造業モデル
日本企業は、伝統的に垂直統合型の経営システムを堅持してきた。それに対し、米国などでは前述の「ヤング・レポート」以降、水平統合型経営システムに転換している【図表1】。また、米国政府は個々の企業への支援ではなく、競争力のインフラ整備を国家戦略の柱に据えた。
【図表1】 垂直統合型と水平統合型システム
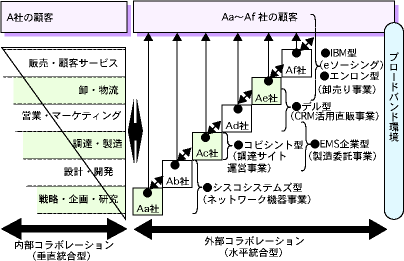
ただ一見、米国の企業による、バリューチェーンの一部領域に徹底的に特化し成功を収めているケースに本質的な要素が見え隠れしている。経済やビジネスがグローバル化するなかでは、従来のアライアンスを超えた、「コラボレーション」がより一層、企業の競争力を決定付けるキーワードになってきた。前述のSCMやCRMなどが、「cコマース(コラボレーティブコマース)」を志向しているゆえんである。
最近のビジネス環境を概観する限り、ここでのポイントは、スピードと異質な価値(バリュー)の提供をどの程度できるかだ。コラボレーションを通じたバリューチェーンの強化を担う、自社部門や他社カウンターパートとの強み・独自性の結びつきが、バリューの結合または再結合につながる。
スピードという観点では、ブロードバンド環境が後押しする。企業内外のコラボレーションを担う各スタッフ間でのアクションを時間的に制約するものは、今後ますます無くなっていく。
アジル(俊敏)なマネジメントが、この環境下でようやく実効性のあるものとなった。
●キャッシュフローにおけるERPパッケージの導入
ある事業戦略を立案し、戦略製品を企画し、関係技術を研究した上で、設計・開発のプロセスを踏むことに、どのケースも大きな差はない。
あらかじめ市場や顧客を想定した上で、マーケティングや営業活動に入る。その後、卸・物流プロセスを通じ、顧客へ製品を販売する、あるいは顧客サービスを行う。この一連のバリューチェーンを再構築することが問われている【図表2】。結局、製造業の再定義とは、ソフト・サービスであれ、原点回帰のモノづくりであれ、このバリューチェーンを巡るコラボレーティブ結合の仕方に行き着く。
【図表2】 バリューチェーンの中でみたCRB基盤の構築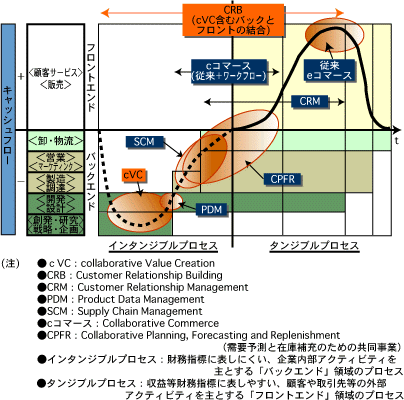
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
同バリューチェーンは時間軸の中で展開して考える。通常これまで企業は、収益等財務指標に表しやすい、顧客や取引先等の外部アクティビティを主とするフロントエンド領域の「タンジブルプロセス」の中では、数量化データを基に関係スタッフ(営業担当者など)の成果の評価も行いやすかった。
一方で、財務指標に表しにくい、企業内部アクティビティを主とするバックエンド領域の「インタンジブルプロセス」での関係スタッフや、顧客・取引先との成果が見えにくかった。
従って、企業内外の関係スタッフ間での「共視化」によるコラボレーションや、同スタッフによる各アクティビティ(行為そのもの)のストック化(アーカイブ化)、そしてその活用を前提にした戦略アクション、といった一連のコラボレーションプロセスが重要となる。何もリッチで優良なコンテンツがブロードバンドのキラーとなるわけではなく、このようなコンサマトリー(consummatory)な、すなわち人の行為そのものが完結した意味をもつ「コンテンツレス・コンテンツ」が鍵を握ることになる。
前述の通り、従来の「eコマース」は、キャッシュフローのピーク前後の安定時期に効果を発揮する。その手前段階、すなわち需要予測と在庫補充が必要な段階ではパートナー同士の共同事業が必要な場合にCPFRが適用されている。CRMでは、顧客フロントからのデータ収集を通じ顧客の動きを逐一追っている。ただ、このデータには顧客の気まぐれな性格が単に出ていることも少なくなく、顧客との関係レベルは単純なやり取りや取引の域を出ない。
また、SCMが効果を発揮する領域は、調達、製造、物流となる。いかに需給調整のレベルや予測を精緻化しても、不況が来て在庫の山だらけになればその意味は大幅に薄れる。さらに手前の、製品設計データなどの授受には、以前から設計者の手間を省くことを主としたPDM(Product Data Management)手法が適用されてきた。これらパッケージの導入効果には一定のものがある。
●cVCを通じたCRB基盤の構築
しかしながら、前回の通りこれらSCMやCRMは、デルの事例のような、コスト削減等の効率化志向の直販モデルには有効であっても、顧客企業コア・コンピテンス部門(例:戦略、企画、研究など)とのコラボレーションに正面切って取り組むものではない。
そのコラボレーションが目的とする、企業の「異質な価値(バリュー)の提供」については、未開拓領域である。本稿で「cVC:collaborative Value Creation」(筆者の造語)について簡単に示したい。
cVCは、先のCRB(Customer Relationship Building)の中の重要な概念となる。顧客コア・コンピテンス部門との取組むについては、例えば、わが国でも電子部品メーカーA社と総合電機B社との間で、特別なプロジェクトが組まれ大きな成果を出している。
電子部品A社としては、同プロジェクトを通じ、例えば世界トップクラスの半導体装置の中に組み込むための部品・部材のノウハウを得る。電機B社にしてみれば、安定的な供給と高品質な部品を調達でき、スピーディーな事業展開が可能となる。
さらに、両社のスタッフ同士のコラボレーションにより、創発段階でのアイデア創出につながれば、従前の領域を超えるバリューを創造できる。これらのスパイラルな関係により、バリューは増殖する。
最近、アリゾナ大学の開発した「GroupSystems」といったブレインストーミングツールなどの環境も整い始めた。これは、アイデア創出を行わんとするチームに対して、鍵となる問題のみに制限し、アイデアの創出、情報の整理、選択肢の優先順位付けを行い、一定のコンセンサスを得ようとするもの。そのプロセスを通じ、アイデア創発の促進や目標達成の手法を提供する。欧州紛争地域の首脳会議にも使われた実績がある。
上記A社とB社とのコラボレーションは、こうしたツールやブロードバンドインフラ環境が整えば、一層の効果を発揮することだろう。このcCV適用領域である、いわば「起点」からタンジブル領域であるキャッシュフローのピーク時に至る、大掛かりなCRB基盤構築には、最近のEAI(Enterprise Application Integration)技術の適用が着目される。何のために、そしてどこにこの種の手法を使うかがポイントとなる。
トライ&エラーも現実的で不可欠な要素だ。製造業復権の足がかりをつかむため、内外のコラボレーションを前提に、なぜ、何をどこに、どの程度の資源を振り向けるか、そして、それによりいかほどの定性かつ定量的な成果が得られたかを、ラフに時に精緻にモニターする。それを問題箇所にフィードバックし直ちにチューニングを行う。こうしたプロセスを通じ、新たな日本型モデル(コラボレーティブ結合モデル)の構築を一刻も早く実現することが急務になってきた。

