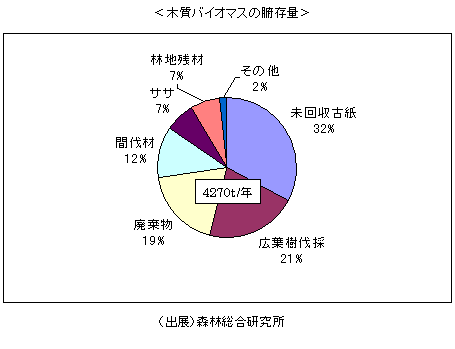PFIが創る環境事業官民協働の地域インフラ:バイオエネルギー
(5)腑存量多い木質系廃棄物
出典:日本工業新聞 2002年8月15日
眠りエネルギー
いま、再生可能エネルギー資源であるバイオマスとして世界的に注目されているのが、木質系バイオマスだ。これは、間伐材や建設廃材などの木質廃棄物のことを指す。ほかのバイオマスに比べてエネルギーの腑存量が倍近くもあり最も大きいことから、新エネルギー市場での成長性が期待されている。
木質系廃棄物全体の排出量は年間800万トンに上る。このほか、間伐材や未回収古紙などを含めて全体で焼く4300万トンに達する。しかし、未回収古紙が全体の33%、焼却処理が29%と、エネルギー源としての有効利用が進んでいないのが実情である。このほかにも、国内の森林には未間伐相当分が500万トンも眠っている。また、林道近辺の比較的利用しやすい広葉樹を伐期30年として換算すると、伐採可能量が900万トンに達する。木質系バイオマスが完全にエネルギー利用できれば、国内のエネルギー需要の約3.6%をまかなえる計算になる。
日本で現在、最も有効利用されているバイオマスは、黒液といわれている木質系で、バイオマス利用全体の100%に近い約460万lk(原油換算)になる。黒液とは、パルプ工場でチップからパルプを製造するときに出る、樹液を含む廃液である。通常は、パルプ工場の燃料として使用され、向上で必要な全エネルギーのおよそ1/3をまかなうことができる。
利用阻むコスト
これに対して、ほかの木質系バイオマスの利用は、日本ではほとんど行なわれていない。環境省によると、燃料として用いられる木材の割合は、木材使用量の0.01%に過ぎない。例えば、全国121ヶ所のチップ化プラントが建築廃材の再資源化施設として、建設されているが、廃材が十分に集まっていないのが現状である。
日本での利用が進んでいないのは、伐採にともなう人件費や輸送コストなどを考慮すると、採算が合わないからである。木質バイオマスによる発電事業は、処理物が廃棄物であれば処理委託費と電力販売費が収入となる。一方、支出としては、輸送費、伐採などの人件費、発電施設運営費が代表的である。一般に、処理委託費が1トンあたり2~3万円、輸送費が同1.5万~3万円。差し引きでほぼトントンになる。このため、人件費と施設の運営費等は電力の販売費用から捻出しなければならない。しかも、廃棄物以外の間伐材などの場合は処理委託費が得られず、事業者の算性が著しく低下する。
また、売電単価は今後RPS法の再生可能エネルギー導入基準によって上昇することが期待できるが、現時点では採算性が得られる単価ではない。ただ、木質廃棄物を利用する方法では、高い稼働率が得られれば、石炭火力よりも発電コストが下がる可能性がある。RPS法によれば、発電コストの低いものほど証書は得られやすいので、有利なエネルギー源と言える。
現在、各自治体が新エネルギーとして木質系バイオエネルギーの導入を検討している。バイオエネルギーの事業化が軌道に乗れば、農村や森林地帯で雇用の創出が可能になる。産業振興策とする場合は、官民協働の体制を構築して事業を推進することが重要だ。