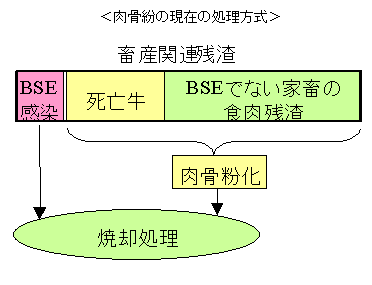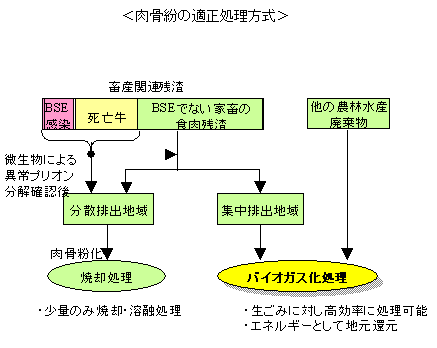PFIが創る環境事業官民協働の地域インフラ:バイオエネルギー
(4)肉骨粉をガス化処理
出典:日本工業新聞 2002年8月14日
BSEで課題に
農村地域における現在の最大の課題は、BSE(牛海綿状脳症、狂牛病)の原因とされている肉骨粉の適正処理である。これまで、畜産業では精肉残渣(ざんさ)を肉骨紛化することによって、循環利用の中でも有効利用レベルの高い飼料化というリサイクルを行なってきた。しかし、狂牛病の発生によって、飼料として生産されていた年間約25万トンの肉骨粉は、焼却することが義務付けられることとなった。BSE検査によって安全が確認された家畜の残渣から作った肉骨紛であっても、全てが焼却対象となっている。
肉骨粉は一般廃棄物として自治体のごみ焼却場にて処理されることとなり、各自治体に協力が求められている。しかし、全国で調査した1577ヶ所のごみ焼却場のうち、肉骨粉の処理を行っているのは135箇所しかなく、問題発覚から1年近くが経過した現時点でも約10万トンが処理されずに残り、現在も毎月1万トン以上が増え続けている。その理由は下記の3点である。
1.技術的に焼却が困難であること。あるいは、炉を傷めやすいこと。
2.肉骨粉が製造されるのは農村地域が多く、適切な処理ができる焼却炉がないこと。
3.焼却場の周辺住民の同意が得られにくいこと。
このような理由から、焼却炉での処理のみならず、新たな試みとしてセメント工場での燃料利用が行なわれるようになってきた。しかし、本処理方法も対応可能な施設が少ないために進んでいない。
2系統にわける
これらのような課題に対して、発酵によって有機物を燃料に変換するバイオエネルギーの利用は、新たな可能性を提示することができる。現在、肉骨紛はBSE検査で安全性を確認した精肉残渣と、BSE検査が実施されていない死亡牛を混合し、一括して肉骨紛に加工した後に焼却処理を行なっている。しかし、この処理は2系統に分けることが望ましい。1つは、BSE検査によって感染している疑いがあることが判明したもので、こちらはこれまでどおり一般廃棄物として焼却を行う。もう1つは、検査の結果、問題ないことが明らかとなった、食用の精肉残渣である。これらは焼却を行わず、家畜糞尿などの他の廃棄物と混合してメタン発酵によるバイオガス化処理を行う。
バイオガス化技術を用いれば、発酵によって有機物をメタンガスに分解することができるので、焼却等に比べて乾燥に必要な余分なエネルギーを投入しなくてよい。それに加えて重要なのは、処理の副産物として発生するバイオガスを用いて、発電ビジネスを実施することが可能となることだ。今後のRPS法(電気事業者による新エネルギー等ーの利用に関する特別措置法)などの新エネルギー普及策によって、バイオガス発電の販売単価が向上すれば、バイオエネルギー市場が形成されることが期待される。
こうした新しい産業にこそ、これまで畜産分野で活躍してこられ、現在、経営不安を抱えている事業者の再生のチャンスを見出すべきではないだろうか。