"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第7回「マイクロソフト.NET戦略は景気回復のカギを握るか?」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2001年12月25日
●「.NET戦略」は景気回復の切り札か?
2001年9月11日の米国での同時多発テロ以来、わが国の経済も大きくその影響を受け、景気は今も低迷している。この景気低迷を打開する切り札の一つとして国内外のIT(情報技術)業界から期待されているのが、米マイクロソフトの「.NET(ドットネット)戦略」だ。
折りしも、この12月17日に同社から「Microsoft.NET」の中の「.NET MyServices」(開発コード名:HailStorm)についての説明があった。これは、ユーザーのプロフィールや連絡先、スケジュールなどの個人情報をインターネット上に保管し、いつでもどこでも「ユビキタス環境」下で取り出せるものである。一見、通信業界とは直接関係のないような代物だ。
今回は、このマイクロソフトの新商品戦略が、関係業界、特にわが国の通信業界に与える影響について概観してみたい。この問題はNTTやKDDIなど、国内大手キャリア(通信会社)にとっては気になるところだろう。さらに、政府が掲げる「e-Japan計画」とも関係してくると考えられる。同計画を推し進めることは、現下のIP(インターネット・プロトコル)技術の革新とあいまって、わが国通信市場に対して一層の競争を促すとともに、かく乱状況をも生じせしめるものとなろう。
通信、金融分野はもちろん企業の情報システム部門の読者、さらには政府の政策担当者においても、マイクロソフトのこの戦略が通信業界の激震の引き金を引くものになるかもしれない点、そして、最近のビジネスのキーワードとなっている、「ITによる”コラボレーション”」の推進という観点からも参考になるのではないだろうか。
●通信会社の懸念
過去100年にわたり、通信業界ほど大きな技術革新の波をかぶっている分野もそうは見当たらない。今日に至っては、「通信そのもの」の定義さえ変更を迫られている。
「.NET戦略」はマイクロソフトにとって、新しい大きな収益源になる可能性が高そうだ。同時に、従来のコンピューティング分野、すなわちウィンドウズという強力な基本ソフト(OS)による情報処理分野を超えて、通信分野、さらに1対N(1つの発信者に対し、複数またはマスの受信者が存在する形)の通信である「放送」(最近のストリーミングから現行のマス型放送)にまで、同社のビジネス領域を拡大するものとなろう。
従来の巨大市場であった「音声通信」は、ブロードバンドの普及により、筆者の呼ぶ「個人向けビデオ通信」や「常時情報シェアリング」(後述の通知、登録、格納受情報の共有化)へ主戦場を移していくだろう。この領域へのシフトは、最近急激にユーザーを獲得している「IM(インスタント・メッセンジャー)」の動きが示唆している。IMはこれまでのウェブサービスにおけるポータル(ユーザーの案内役)機能とは異なる、強力なインタフェース機能をもつことになる。
通常の音声通信は、交換機経由のネットワークシステムの中で閉じている。これに対してこのインタフェース機能は、集中するトラフィックの拠点が交換機を経由しない新たなゲートウエー(サーバー)上にシフトすることを意味する。つまり、通信キャリアの料金徴収システム以外で、「個人向けビデオ通信」や「常時情報シェアリング」などの膨大なやり取りが発生することとなる。
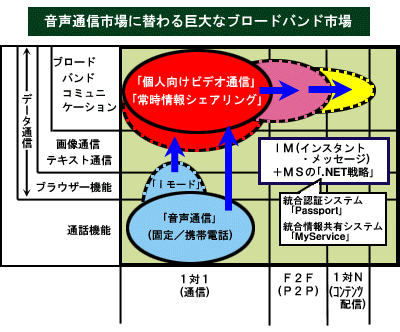
(注)囲みの大きさは、市場規模と想定。「F2F」とはFew to Few(少数同士)、「P2P」とはPeer to Peer(仲間同士)のコミュニケーション。
(出所)日本総合研究所ネット事業戦略クラスター(現ICT経営戦略クラスター)
1年前のわが国のIMユーザーは 二百数十万人、現在は400万人を超えていると推測される。ユーザーの伸びもさることながら、IMの持つ次の特徴が注目される。
1)ブロードバンド時代のキラーコンテンツとされる、IPテレビ電話やビデオチャットサービスなどの映像を交えた通信(会話、チャット、業務コラボレーション)が当たり前になること(トランザクションがHTTP上で行われるため、社内LANを越えた動きとなる)
2)ブロードバンド常時接続環境との組み合わせにより、コミュニティーの仲間や顧客などとの間で、通知(自分の所在・プレゼンス、仕事の状態など)、登録(前述の個人情報など)、格納(作成ドキュメント、金融機関の決済情報、よく使う通信デバイス・ツールなど)に関する映像を含むデータ・情報をリアルタイムにやり取りできること(この前提には、マイクロソフトの一大認証システムが基盤となる)
米国では民主党のクリントン政権から、共和党のブッシュ政権へ交替したこともあり、マイクロソフトの独禁法を巡る問題は、同社にやや有利な展開になっている。この問題は、具体的には当時最大のシェアを誇った米ネットスケープ社のブラウザーソフトへの対抗手段として、マイクロソフトのOSに同社のブラウザーをバンドリングした(組み込んだ)ことに起因したものである。
本稿では独禁法問題とは別の観点から「.NET戦略」に焦点を絞るため、同戦略の意味するところが、ブラウザー論争を大きく超えたところにあることを言及するにとどめたい。
●通信市場が抜本的に変わる可能性
前述の「別の観点」とは、通信業界が腐心している固定電話事業の収入の減少問題に大きく拍車をかけ、NTTやKDDIなど大手キャリアにおける同事業の縮小に拍車をかけかねないということだ。従来の音声固定通信から携帯電話へのユーザー移動に端を発して、通信の定義が変わってしまう可能性がある。すなわち、別の収益源を確保できない限り、音声固定通信は縮小均衡あるいは市場からの撤退さえ余儀なくされる運命にあろう。
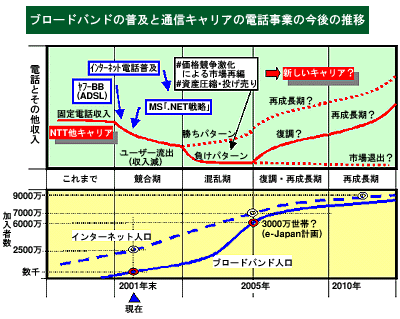
(注)政府「e-Japan計画」における「2005年で3,000万世帯」というブロードバンド普及世帯において、それを約 6,000万加入数と置き換えている。日本の全世帯は約4,600万世帯。特に固定電話収入については、インターネット電話およびIP電話のみの影響により、最大で現行の5分の1程度に減少しよう。横軸(時間軸)については、上段と下段では競争の進展状況など大きくずれる可能性もある。
(出所)日本総研ネット事業戦略クラスター(現ICT経営戦略クラスター)
政府のe-Japan計画の目指すブロードバンドの普及目標である「2005年に3,000万世帯」とは、ユーザー数にして6,000万契約ほどとなろう。これはおよそ1年ほど前の携帯電話ユーザー数に匹敵するものだ。携帯電話の場合、1994年の端末売り切り制や1999年のiモ―ドの導入など、市場をブレークせしめる強力なドライバーが寄与した結果である。
先日開催された、フィンランド科学技術庁主催の科学技術の将来予測と評価手法についてのワークショップで、日本側代表の一人であったNTTドコモのある課長が、「iモ―ドの誕生と成功はアクシデントだ」と述べていたことが思い起こされる。
「アクシデント」と形容されるほど、ネット上の、いわば気ままな消費者の心をつかむことは難しい。しかし、明らかに利便性があり、1対1あるいはF2F(Few to Few=少数同士)やP2P(ピア・ツー・ピア)という新しいタイプの通信から得られるだいご味があれば、消費者は必ずそこに集まる。それは、過去100年間私たちが享受してきた、人間同士の本来のコミュニケーションの大切さや楽しさに回帰するものといえよう。昨今話題となっている1対N型のストリーミングやN対N(複数の発信者と複数またはマスの受信者が存在する形)のマーケットプレースなどとは別の領域に、巨大な空間(場、市場)が横たわっているのだ。
●新通信会社「Your Service Enabler」が市場に君臨か?
政府の標榜するブロードバンド施策は、通信キャリアにとっては両刃の剣となろう。現在進行しているアクセス網やウェブ上のポータルをめぐる激しい攻防は、ソフトバンク・グループのヤフーBBによる格安なADSL(非対称デジタル加入者線)サービス、さらに同グループが12月18日に発表した業界最低価格による市内電話への参入、そして、マイクロソフトの「.NET戦略」などの多様で革新的な動きに対して、「競合期」をいかに乗り切るかが、各企業プレーヤーにとっては死活問題となってきた。
この「競合期」を経て、わが国通信市場がある種の「混乱期」に突入する可能性は低くない。NTTなどの通信キャリアにおいては保有する資産が重荷になり、資産の圧縮を通じた投げ売り(交換機による市内通話サービス、専用線サービスなど)も始まるだろう。そうでもしないと、新興企業によるフットワークの軽いアクションに対抗できないかもしれない。新旧両者による攻防は、市場の疲弊と再編を招くに違いない。現在、既にその予兆はある。
米国の通信法が1996年に改正され、米地域通信市場では意外に無風状態が続いているのと好対照である。米国の日本市場弱体化のシナリオだったのか、それとも単に予測しがたい結果としての皮肉と解するべきなのか。
いずれにせよ、この時期を経過した後に、わが国通信市場が「復調・再成長期」を迎えることができるかが、政府目標の高度情報ネットワーク社会(ブロードバンド社会)の実現と期を一にするだろう。政府がこのシナリオをどの程度描いているのかも、そしてこのプロセスをいかに切り盛りしていけるかといった政策立案、競争政策のアクションプランなどの力量が問われるところとなる。
市場再編の後、従来の通信キャリアが復活を遂げるのか、あるいはマイクロソフトのような新型の通信会社、いわば同社の「.NET MyServices」を基軸にした「Your Service Enabler」企業が新たな市場に君臨しているか、大きな関心がもたれるところだ。

