"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第5回「見えるコラボレーションのインパクト」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2001年11月22日
●新興情報通信D社IS部門の時代の読み
筆者はこのほど、ある情報通信企業D社への新しい情報システム(IS)構築に関するアドバイスをした。D社の親会社はわが国を代表する伝統的な「エクセレントカンパニー」だ。アドミニストレーション(管理)領域のシステムが古いため、新規に再構築しようというものだ。D社IS部門に対して行ったアドバイスは、おおよそ次のような内容になる。
(1) 定型業務のアドミニストレーション領域(調達、発注、総務、経理など)の効率化、すなわちコスト削減、業務の迅速化、運用の容易性実現は大変重要な目標である。
(2) しかし、せっかくISを再構築して他社との差別化を狙うのであれば、どのようなサービス品目がより戦略的であるかを併せて熟慮することが大事だ。
(3) そのためには、ブロードバンド時代、あるいはIT革命第2幕が始まった中、どのような企業イメージや企業システムを描くことが必要かについてもイメージしておくべきではないか。
この際、ある米国の新興ユーティリティー企業の例を示した。
●時代はブロードバンドインフラを用いた新しい仕組み構築へ
しかし、D社において古いのは、システムだけではなかった。
このとき、D社よりもビジネスにおいて1年以上先行する企業E社(あるマーケットではトップクラスを占めている)の経営戦略に関する相談も同時に受けていた。この企業の親会社は常に挑戦的な姿勢を持ち続けていることで知られる日本のトップ企業であり、その企業風土のためか、E社との話の進展は早かった。フットワークは軽く、しかも市場の今後の行方をよく見通していると感じられた。
一方、D社の場合には、その米ユーティリティー企業のビジネスモデルを示したが一蹴された。そのモデルは数カ月前までは、わが国でももてはやされていた。その目指すところは、金融技術とブロードバンド網を結びつけ、光ファイバーインフラ網のホールセール(卸売り)、同ネットワークでのVOD(ビデオ・オン・デマンド)やコンテンツ・デリバリーなどをビジネス展開していくというものだった。不幸にして、その米企業は経営的には最近窮地に追いやられた。ITバブル崩壊のため、資金繰り悪化などの問題が深刻化したためだ。
ここには学ぶべき教訓があろう。第一に、この米企業は、無策で手をこまねいたことによって失敗したわけではない点。第二に、企業マネジメントの観点では結果がすべてであり問題があったにしても、その目指すところに日本企業にとってのヒントが全くなかったのではない、という点だ。
「他社との差別化」などと言うのは簡単だ。しかし、実際にアクションをとろうとしたら、決して易しくはない。当たり前のことだ。簡単にできるなら、どの企業もとっくの昔にそんなことはやっている。
意外にも、欧州のある国では、IP-TV(インターネット・プロトコル・テレビ)などのサービスがFTTH(ファイバー・トゥ・ザ・ホーム)により、数万人に提供されている。CDN(コンテンツ・デリバリー網)上のVODもキラーコンテンツとして、回線売りだけのサービスに深みを添え、付加価値となっている。この欧州の企業では、前述の米ユーティリティー企業のモデルに近いものが、うまく機能している。
●見えるコミュニケーションとは?
本稿では、その欧州の企業もフットワークの軽いE社も、まだ行っていない新しいビジョンの概要を示そう。先のD社には、このビジョンは残念ながら時期尚早であった。言葉を尽くせばきっと理解してもらえると信じているが、あのときそれ以上進展がなかったのも、ビジネスにおける縁というものでやむを得ない。
この連載の第1回でも示したとおり、ブロードバンドの最大の特徴は、「見えるコミュニケーション」、あるいは「現場の”見える化”」にある。米シスコシステムズのチェンバース会長が、今年、創業以来初めて赤字を記録した際の理由に、EMS(製造委託企業)における同社の膨大な在庫が読めなかったことを挙げた。つまり、トップマネジメント層がそれを「見る」ことができなかったのだ。
「見えるコミュニケーション」のポイントは、自社内の現場あるいはパートナー企業を含む当事者同士のやり取り(取引)にまで及ぶことにある。現行のSCM(サプライチェーン・マネジメント)もCRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント=顧客管理)も、ここまではカバーできない。
もちろん、この「見えるコミュニケーション」実現には、若干の工夫と労力が必要となる。現時点では、パッケージで対処できるような段階にはない。手作りの要素が今の段階では多くなるし、試行錯誤も発生しよう。しかし、そのためのインフラはブロードバンドで安価に提供される。また、当事者間のコミュニケーションには、P2P(ピア・トゥ・ピア)の仕組みを適用するのがポイントとなる。
●P2Pによるコラボレーションのインパクト
現在、通信会社が提供している専用線は、一定期限だけのスポット単位といった柔軟なサービスも最近では出始めているが、総じて年間単位の利用で高価なものだ。消費者向けの通信サービスが、ADSL(非対称デジタル加入者線)サービスの登場などで価格競争が激化し大幅な値下がりをしている状況からはほど遠い。価格が維持されているうちは、例えば航空業界における「ビジネスクラス」と同様、利益も出る。しかし、「エコノミークラス」に企業ユースがシフトしている昨今、利益を出す従来のビジネスモデルが崩れ、航空業界に再編の拍車がかかっている。同じことが、通信業界にも起こりつつある。
通信業界にとっては厳しい時代だが、ユーザー企業にとっては、IP-VPN(仮想プライベート網)のようなIP(インターネット・プロトコル)系の超高速かつ安価な通信サービスがふんだんに使える状況の到来は朗報だ(下図参照)。セキュリティー面でのグレードは専用線などに比べ多少劣るにもかかわらず、自動車会社やエレクトロニクスメーカーなどでの採用が実際に相次いでいる。
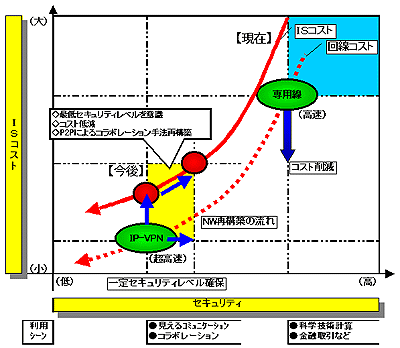
(出所)日本総合研究所ネット事業戦略クラスター(現ICT経営戦略クラスター)
ブロードバンド環境進展の中、企業にとっては回線コストが従来より安価になる一方、「P2Pによる見えるコラボレーション」の仕組み構築のためのコストは加わることになる。しかし、この仕組みを使えば、企業のコア・コンピテンス(中核能力)をより一層引き出すことが可能になろう。IT不況の中で今、わが国企業に求められているのは、企画、設計、開発などの”What”をクリエートする当事者同士の緊密なコラボレーション(共同作業)であり、そのカギを握っているのは、相手(パートナー)があたかも隣にいるかのような「見えるコミュニケーション」だ。
これまでP2Pというと「ナップスター」に象徴されるようにコンテンツの流通が中心で、しかもその流通コンテンツが管理しにくいためにアンダーグラウンド的なイメージがあった。しかし、P2Pの本領は、こうした企業内での「見えるコラボレーションワーク」の仕組み構築にある。IS部門にとっては、こうしたことを踏まえた現場のニーズ補そくやソリューションの提供を通じ、企業プロセスというよりは、このようなコラボレーションワークを可能にする手法を、いかに早く手にできるかが今後問われてくる。

