"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第1回「ブロードバンド時代の情報化を考える」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2001年10月1日
●情報化の意味を取り違えたA社
今春、製造分野のある企業(A社、本社・大阪)幹部から情報化への取り組みについて相談を受け、いささか驚いたことがある。事実関係を一部脚色して紹介するが、A社はだれもが知る優良グローバル企業。しかし、いまだに情報化の方向性が企業プロセスの効率化論議にとどまっていた。
筆者の仕事は、IT(情報技術)分野での企業向け経営コンサルティングだ(製造、通信、金融、官公庁など)。以前は、リサーチを踏まえた経営戦略の立案などが主だった。しかし、特にここ数年、戦略の実行、クライアントとその顧客との関係再構築へと力点がシフトしてきた。これは、クライアント企業が市場での成功を一刻も早く手にしたいゆえのものだ。
情報化は、市場での成功を手にする有力な武器である。特にブロードバンド時代にあって、その武器の用い方いかんでは、企業組織にイノベーション(革新:「How」を超えた「What」の異質な領域)をもたらす。
●効率化一辺倒の罠(わな)
A社の営業部門、マーケティング部門、情報システム(IS)部門の幹部は、「IT革命」のさなか、はやりの情報化に余念がない。はやりとは、SCM(サプライ・チェーン・マネジメント)、CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント=顧客管理)などのERP(統合基幹業務システム)と呼ばれるパッケージ、あるいはDWH(データウエアハウス)などの導入・適用のことだ。
これらの導入だけでも一筋縄ではいかない。米国企業の中には、名門デルコンピュータなどのように2年の歳月と100億円近い費用をかけ、その導入・適用に失敗・断念したところはいくつもある。今年8月、筆者はハーバードビジネススクールのオースチン教授と面談したが、その中でもこの件に関して少なからず示唆を受けた。
また、導入といっても、企業プロセスの効率化を目指すSCMだけでは、市場の需要(ひいては顧客のニーズ)を把握するにも不十分だ。CRMなどの顧客の動きをつぶさに把握できる仕組みが構築できなければ、適性な在庫調整、リードタイム短縮化などの所期の目的は達成できない。
A社ではこうした目的の実現が急務であった。しかし、IT不況の真っただ中では、その熱も冷めようというものだ。そんなに効率化しても、A社期待の携帯電話事業は不調。そもそも、今は電子部品の需要が相当に落ち込んでいる。情報化推進へのはしごを外されたというわけだ。
●IT革命第2幕(ブロードバンド時代)における情報化
問題は、市場原理に不可避な需給調整の波をどう平準化し、いかなる時、いかなる状況にも適切な対処ができるかどうか、そして、そのための羅針盤をもつことだ。IT不況の今こそ、企業のばねにエネルギーを蓄積する時である。この対処の仕方で次の戦いは決まる。
IT革命は今春以降、第2幕を迎えた。第2幕はブロードバンド時代の幕開けと重なる。第2幕のビジネスインフラと情報化の意味合いについては、下の表をご覧いただきたい。第2幕は、第1幕の単なる延長上に来るものではない。いわばITバブルで再び地上に落され、徘徊(はいかい)している時期からのテイクオフを迎えた。
|
比較項目 |
IT革命第1幕 |
IT革命第2幕 |
| サイクル (ポジションは?) |
●草創(離陸準備)期 ●新しい流れの認知時期 |
●テイクオフ(離陸)期 ●発展期 |
| 市場の特徴 | ●ネットビジネス、eビジネスなど新種のビジネスの登場 | ●実体経済 ●実ビジネス |
| プレーヤー | ●ベンチャー中心 | ●ベンチャー ●オールドエコノミー(大・中堅企業) |
| ビジネスモデル | ●アイデアベース | ●コア・コンピテンス活用が前提 ●実行力 |
| ビジネスインフラ (使用状況) |
●高価な専用線など ●年額制(一部月額制) |
●ブロードバンド ●スポット料金制(数日単位から) |
| エンドユーザーのインフラ | ●ナローバンド ●従量制 |
●ブロードバンド ●定額制 |
| コマース上のコンテンツ | ●テキスト、静止画中心 | ●テキスト、静止画 ●リアルタイム映像 |
| 情報化および情報システム(IS)の役割 | ●効率性(How) ●SCM、CRMなどのパッケージシステム(ERP)導入とアジャスティング ●管理部門の一つ |
●戦略との結合(Why、What) ●現場とのチーム取り組み(Teaming) ●現場の”見える”化 ●CARV(Cross Activities Relationship Visualizing) ●戦略部門へ |
ネットビジネスやeビジネスを否定するものではない。これからが本番だ。しかし、より実体経済と実ビジネスに重点が移行する。アイデアベースに終始したベンチャーに加え、コア・コンピテンス(企業の中核能力)をもつオールドエコノミーの力量が問われる。
企業活動の基礎になるビジネスインフラは、超高速・大容量かつ低額な光ファイバーなどのブロードバンド環境を駆使するものとなる。単に高価な専用線に接続された情報システムでは駄目だ。ネットワークに行き交う情報(ナレッジ)には、リアルタイム映像も加わる。旧来の無機的なテキスト・静止画情報から、臨場感、現場の”見える”化(可視化)、リアル性が発揮される有機的な情報表現とその活用がポイントとなる。実際、松下電器産業やトヨタ自動車では、その取り組みがすでに始まっているようだ。
●クリティカル・マスを超えた企業の取り組みができるか?
イノベーションを起こせる企業はそう多くない。しかし、上記の状況を実現するブロードバンド環境により、これまで到達できなかったクリティカル・マス(マーケティング用語で「臨界質量」)を超えられる。しかも、それは一握りの企業にとどまらない。中堅・中小・ベンチャー企業もこの恩恵をあずかることとなる。この状況が与件となった本格的な競争が、始まろうとしている。
ブロードバンド時代の情報化の取り組み局面では、企業の情報システムの意味が大きく異なってくる。企業プロセスの効率化(How)を超え、企業の戦略(Why、What)と結合されなければならない。日本企業において、米国風のCIO(チーフ・インフォメーション・オフィサー)のあり方については議論があろう。しかし、このCIO的なポジションの役割がより重要性を増してきた。
そして、IS部門においては管理部門から戦略部門への脱皮・シフトが始まろう。米国企業ではすでに始まっている。彼らは次のステージを眺望している。企業のコア・コンピテンスでない機能のアウトソーシング、また、オペレーション部門(製造、販売、営業、人事・総務など)における日常業務(ルーティンワーク)については、シェアードサービスにより一つにくくられたシステム構築のもと、同サービスの提供が行われている。企業組織内での情報化の意義の変化を下図に示した。
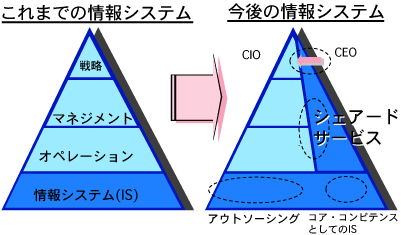
IS部門は、現場オペレーション部門との連携(チームとその取組み)により、プロセスなどの効率化に加え、顧客価値を高められるような新たな取組み(ある種のCRM)に直接関与することが求められよう。ヒントは、自社チームによる重点顧客企業への活動パフォーマンスを2軸のビジュアル化によりはかるCARV(Cross Activities Relationship Visualizing)というコンセプトにある。顧客との間に上がる自社戦略に直結する事案を、ISでいかにうまくさばけるかも競争の源泉になろう。
新しいこと、これまで以上に自社能力を強化すること。これがより現実のものとなってきた。皆さんはどのようにお考えか。
第1回 → 第2回

