"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第2回「IT投資マネジメントを考える」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2001年10月16日
●エレクトロニクスメーカー大手B社の関心事とは?
東京に本社をもつ、わが国を代表するエレクトロニクスメーカーB社は、同社の経営規模の大きさ(売上高で数兆円)や、IT(情報技術)が同社のコア・コンピテンスに直結する性格上、IT投資マネジメントは喫緊(きっきん)の課題となっている(以下、事実関係をデフォルメして説明する)。特に、携帯電話向けの半導体部品や通信ネットワーク機器などが主力製品であるため、その対処の仕方とスピードが経営戦略の上で大変重要になっている。筆者が同社から相談を受けたのは、今年9月のことである。
ちょうどそのころの9月半ば、フィンランドの工科大学出身のヴィータネン博士とIT投資マネジメントについて議論した。彼は東大のM教授の研究室にも在籍していたことがあり、筆者とM教授がたまたま通信問題の研究会で一緒であった関係で、以前フィンランド大使館で同国の諸閣僚やわが国の高円宮ご夫妻を迎え開かれた晩餐会で、M教授から同博士を紹介された。
フィンランドといえば、今やだれもが知るIT産業の戦略国家。同国には携帯電話メーカーの巨人ノキアが君臨する。ヴィータネン博士は同国の持つITノウハウの普及、あるいは同国のIT企業とわが国の研究機関や企業との提携などに力を注いでいる。ナレッジ(智恵)とグローバル市場を組合わせれば、大国でなくとも世界の覇者となれることを、フィンランドは証明している。
また、IT大国の米国ではネットワーク機器の覇者シスコシステムズなど、IT分野のトップ企業が目白押しだ。米国のIT投資については第1回のコラムで、元経営コンサルタントである米国ハーバード大学ビジネススクールのオースチン教授を登場させたが、最近筆者は電子メールで、今回のテーマについて彼と意見交換を行った。
しかし、そのノキアもシスコもともに、現在は通信不況とIT不況に直面している。その膨大なIT投資をどう見るか、またITマネジメントをどのように戦略と結びつけるか。これに関心をもつ読者は多いに違いない。本稿では、B社を例にとって、このことを考えたい。この連載企画では、極力1回ごとに完結させたいので、若干長文になることをご容赦願いたい。
●IT投資マネジメントへの認識レベルはそれでよいのか?
B社のIT投資の規模は、年間1000億円を超える。単体売上高比率(IT投資水準)にして3~4%となる。このIT投資額は、設備投資を除くIT・IS(情報システム)部門に関するものを指す。主に、ハードウエアやソフトウエア(購入費、開発費)、人件費などであり、自前のものとグループ企業や外注とを含んでいる。
わが国の同業他社のIT投資水準は2%前後であることを考えると、B社の投資額は高めである。一方、シスコなどは4%台で、米英の金融機関では10%を超えるところがある(金額にして数千億円)。IT投資は、企業の戦略や財務に直結しなければ、客観的な評価は難しい。同業他社との相対比較に終始するだけでは、何とも寂しい限りだ。
海外ではITの戦略性が取り上げられているというのに、B社の関心事項がこのような相対比較にいまだにとどまっていたことにまず驚かされた。また、欧米競合他社がIT投資マネジメントの手法を策定しトライ&エラーを行っているさなか、このレベルの取り組みはB社では皆無に近い段階と思われた。これでは、どうやって米欧企業の攻勢をはね返すことができるのか懸念される。最近では特に「IT不況」「IT革命の虚妄」などが叫ばれるなか、自社の身のふり方(経営マネジメントの選択)が大いに問われている。
設備投資までを含めたIT投資を読み違えると、構造的な問題を業界全体に作り出してしまい、単なる在庫調整を超えた悪循環にはまり込む。放送大学の森谷正規教授がいうように、昨今のようにITと金融が結びつくと、景気の上昇(ブーム)時のみならず、下降局面においても短期間で、しかもより深く落ち込みが進む。現在のIT業界が陥った状況とは、このようなものだ。IT関連産業では、目下収益の落ち込み、従業員の大幅カットなどの嵐が吹いている。
●インタンジブルITマネジメントとは?
ITあるいはIT投資だけが、企業の活力を取り戻す解ではない。しかし、ITやISを軸にして、それを戦略と直結できれば、再び経営を立て直すことができるのも真実であろう。
「インタンジブル」という言葉がある。「目に見えない、無形の」といった意味である。たとえば、R&D(研究・開発)基盤、ブランド力、知的財産、人材力などを指す。現行の財務指標(B/S=バランスシート、P/L=連結損益)だけでは、将来の企業価値や真の企業力を読むことができない。ただ、インタンジブルな要素を深読みし過ぎると、市場撤退を余儀なくされた、コンセプト(ビジネスモデル)だけの昨今のネット企業のような実体のないものに、投資家が過分な期待をかけてしまうこととなる。
ITやISも「インタンジブル」な経営要素といえる。特に、IT投資はその効果が読みにくい面などから、そうみなされよう。これの社内および社外(投資家など)への可視化(ビジュアル化)が急務だ。
IT投資を評価する際には、従来からいくつかの方法がある。たとえば、(1)個々のプロジェクトなどが生み出すフリー・キャッシュフローの割引現在価値の合計がプラスかどうかを見るNPV(正味現在価値)法、(2)株主資本利益率で測るROI法、(3)NPVがゼロになる割引率を逆算し、その割引率の評価によってプロジェクトの可否を決定するIRR(内部収益率)法などがある。
前述のオースチン教授も、このインタンジブルな要素をどう評価するかで従来手法の限界を感じており、今年末には論文を発表すると先月言っていた。また昨年、米の企業研修会社、ハマー・アンド・カンパニーの創立者で「リエンジニアリング」の提唱者であるハマー氏が、「プロセス・エンタープライズ」という興味深い論文を発表した。ITを活用しながら業務プロセスに注目し、高パフォーマンスの全体最適解を求めようとするものである。
本稿ではこれに加え、結果(output)でなく成果(outcome)測定を、顧客接点を前提とした重要個別プロセスごとのKPI(Key Performance Indicator:主要業績指標)で行うアプローチを示す。これは、さしずめ「インタンジブルITマネジメント」、すなわち、インタンジブル指標測定によるITと戦略の統合マネジメントとも言うべきものだ。
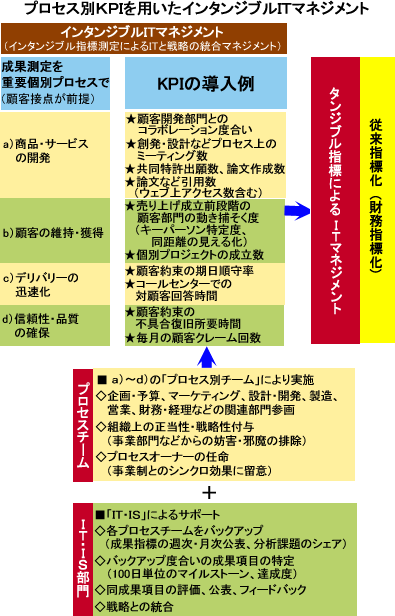
●プロセスごとのKPI導入と経営戦略との連動ができるか?
KPIの導入には、次のa)~d)のプロセスごとに、たとえばエレクトロニクスメーカーであるB社の場合であれば、次のようなものを測定対象とする。
a)「商品・サービスの開発」のプロセスでは、顧客開発部門とのコラボレーション度合い、創発・設計などプロセス上のミーティング数、共同特許出願数、論文作成数、論文などの引用数(ウェブ上のアクセス数を含む)など。
b)「顧客の維持・獲得」のプロセスでは、売り上げ成立前段階の顧客部門の動き捕そく度(キーパーソン特定度、同距離の”見える(ビジュアル)化”)、個別プロジェクトの成立数など。
c)「デリバリーの迅速化」のプロセスでは、顧客約束の期日順守率、コールセンターでの対顧客回答時間など。
d)「信頼性・品質の確保」のプロセスでは、顧客約束の不具合復旧所要時間、毎月の顧客クレーム回数など。
もちろん、これらKPIの例は、当該企業の置かれた業種・業態により異なる。また、KPIに「業績関連」「コスト関連」「マクロ関連」などの階層・区分を設けることも一案だ。
ポイントは、これらa)~d)の「プロセス別チーム」により実施することである。プロセスイノベーションのための規模ともくろみにもよるが、B社の場合は各チームに、企画・予算、マーケティング、設計・開発、製造、営業、財務・経理などの関連部門が参画することを前提とする。
そして、そのチームには、組織上の正当性・戦略性をトップが付与することで、現行事業部門などからの妨害・邪魔の排除を仕組む必要がある。その際にハマー氏のいう、プロセスオーナー(各プロセスごとの責任者)にあたるリーダーの任命が前提となろう。慣れない間は、外部コンサルタントの起用もありうる。このプロセスリーダーは、事業部門との利害調整を行い、事業制とのシンクロ効果やシナジー効果を図る役割を果たせねばならない。このリーダーの権限はさしずめ事業本部長クラスになろう。
さらに「IT・IS」によるサポートを加える。特に”見える(ビジュアル)化”、迅速化において、ITが威力を発揮する。IT・IS部門は、各プロセスチームをバックアップする。同部門でも、たとえば成果指標の週次・月次公表、分析課題のシェアなどを行う。また、100日単位のマイルストーン設置や、達成度バックアップ度合いの成果項目の特定など、同成果項目の評価、公表、フィードバックも重要である。
そして、常にプロセス全体の中での自己のポジショニングを明瞭にしておき、CIO相当の担当者を通じ、自社の経営戦略との統合度合いをモニターしておくことも不可欠である。
これらを実行することは、B社ほどの大企業であれば可能であろうが、普通の企業では少々難しいかも知れない。しかし、これを実行に移せる企業とそうでない企業では、大きな差がつくことは必至だろう。実際、日本と欧米企業との競争力格差は、日本企業の得意な製造プロセスにあるのではなく、こうした内部プロセスのトータルな最適化と、経営トップと各チーム内でのビジュアル化(問題の把握と対処による成果の可視化)において生じているからだ。
このビジュアル化を通じて従来指標の財務指標化が行え、投資家も理解できる言葉・表現としての、タンジブル(目に見える)指標によるITマネジメントが完結する。これは、言いかえれば、自社のコア・コンピテンスの強化・創出戦略、あるいはそれへの統合そのものに他ならない。
以上の全体あるいは部分的適用は、これから市場オンリーワンを目指し、他社に比べて優位なところで差別化を図り、現状の不況を打破したいと考えている中小・中堅企業においても有効に違いない。

