持続不可能な財政 再建のための選択肢
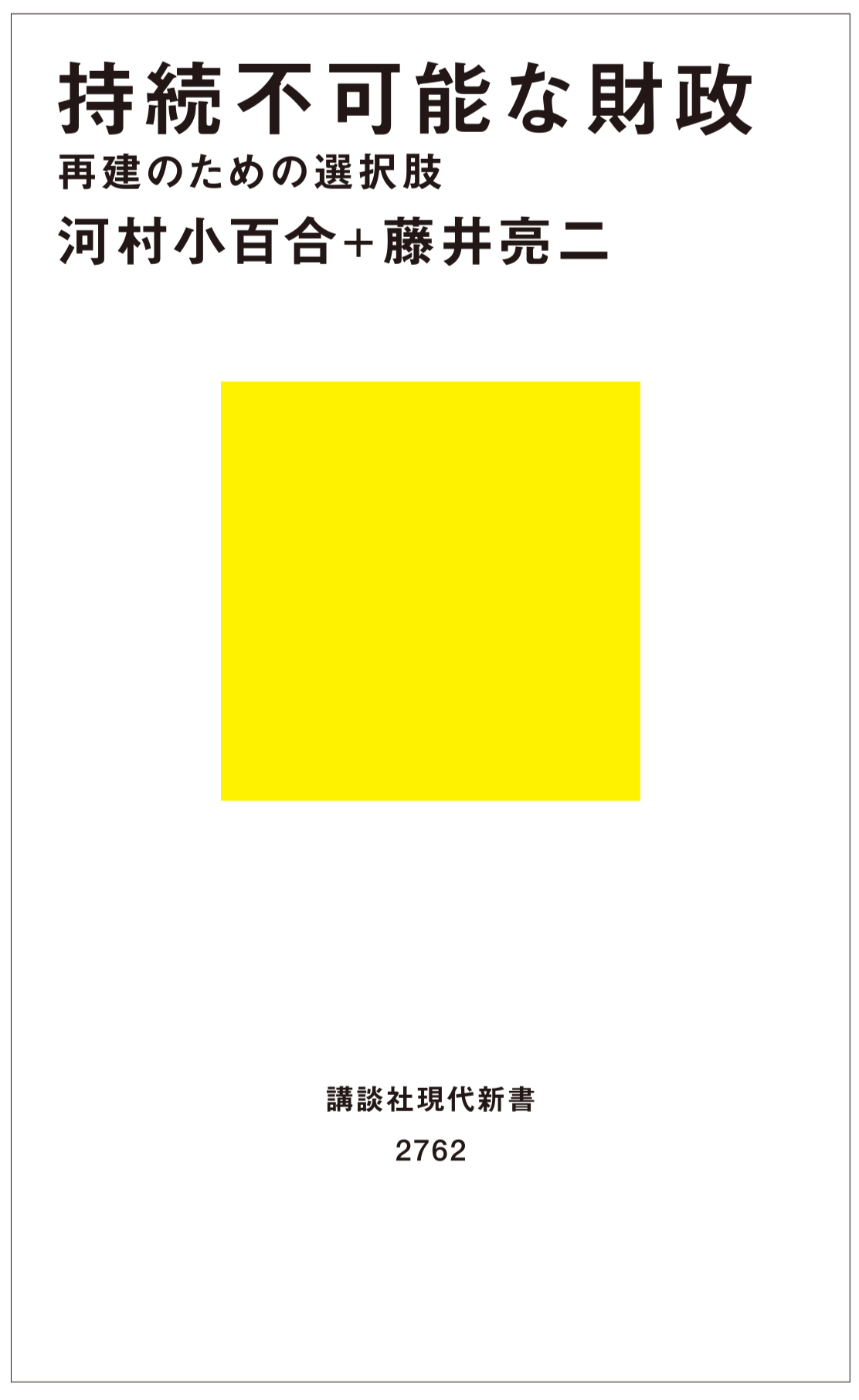
- 著者
- 河村小百合(調査部) ・藤井亮二(白鷗大学教授)
- 出版社名
- 株式会社講談社
- 出版日
- 2025年1月20日
- 価格
- ¥1,100+税
我が国の財政運営は、このままではこの先、何かのきっかけで、いつ何どき、行き詰まってもおかしくない状態にすでに陥っています。にもかかわらず、危機感が高まらないのは、〝客観的・中立的な財政見通し〞が示されていないうえ、〝税財政運営上の問題の真の所在〞や〝改革の具体的な選択肢〞を皆が共有できていないからでしょう。そこを克服し、私たち一人ひとりが考えられるように、手がかりや材料を何とか提供できないか。藤井亮二・前参議院予算委員会調査室長とともに取り組みました。第1部と第2部、第3部の第3章(地方財政)と第5部(財政再建アラカルト)を河村が担当しました。
目次
- 「何も起こらない」のは利払費が増えずに済んだから
- 放漫財政を助長した日銀の国債買い占め
- 日銀を待ち受ける債務超過の危機
- 財政再建努力など不要。財政は自然に改善する」という内閣府の「超」楽観的な見通し
- 内閣府とは対照的なOECDのシビアな見方
- 内閣府の"不自然"かつ"恣意的"な試算の前提条件とは
- 「国債の平均残存期間は約9年だから当面利払費は増えない」は誤り
- 内閣府と財務省の利払費の見通しには5~8兆円もの差が
- 4通りの金利シナリオ-"市場主義経済体制下"を死守
- 国債発行年限の配分は3パターン
- 短期国債中心でも節約できる利払費は限定的
- 国債発行年限の短期化で膨張する財政破綻時の資金ショート額
- 独自試算でわかった「税収増で財政再建」は無理!
- インフレ局面でも名目金額通りに払えば足りる歳出は国債費のみ
- 「インフレで財政破綻は回避できる」という甘言に騙されない
- 財政収支均衡とは「収入の範囲で生活する」こと
- 3-1-1 聖域にはできなくなった社会保障制度
- 3-1-2 増加の一途をたどる医療費
- 3-1-3 もはや現役世代の「仕送り」は限界
- 3-1-4 もし公費が3割カットされたら医療・介護はどうなる?
- 3-1-5 医療保険を持続可能にするには
- 3-1-6 2040年に約1000万人が要介護状態に
- 3-1-7 2040年に介護保険料と自己負担はどれだけ増えるのか
- 3-1-8 欺瞞の少子化対策
- 3-2-1 日本の年金は本当に「100年安心」といえるのか
- 3-2-2 国庫負担が3割削減されたら、年金はどれだけ減るのか?
- 3-2-3 第3号被保険者制度をまだ続けますか?
- 3-3-1 改革を避けては通れない地方財政制度
- 3-3-2 地方交付税制度のからくり
- 3-3-3 中途半端だった小泉政権での地方交付税制度改革
- 3-3-4 地方交付税制度はすでに事実上破綻状態
- 3-3-5 地方財政はコロナ危機で"焼け太り"?
- 3-3-6 人口減少下での改革の選択肢を考える
- 3-3-7 ふるさと納税は"国が認めた課税逃れ"
- 4-1-1 既得権益化する「租税特別措置」
- 4-1-2 金持ちの金融所得の税率は庶民の給与所得の税率よりも低い
- 4-1-3 税を払わないで済んでいるのは誰なのか
- 4-2-1 誰がどれだけ税を負担するのか-資本主義・市場経済国の鉄則
- 4-2-2 経済的な余力のある人や企業に負担してもらうにはどうしたらよいか
- 4-2-3 経済的な余力の乏しい人の負担増を抑えるにはどうしたらよいか
- 4-2-4 公正な課税のためにはどうしたらよいか
- 「30兆円規模」を"極端"と切り捨てるのは"思い上がり"ではないのか
- 家計・企業部門が大幅な"カネ余り"を長年続け、政府部門に借金を積み上げてきた国
- 財政をいかに立て直していくかを、各政党が選挙で問うべき
- 財政再建のための選択肢
- 海外への資本逃避は起きるか
- 問われる"国全体の覚悟"と"日本人の良心"とは

