日本銀行 我が国に迫る危機
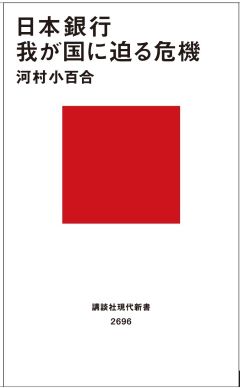
- 著者
- 河村小百合(調査部)
- 出版社名
- 株式会社講談社
- 出版日
- 2023年3月20日
- 価格
- ¥1000+税 2024年10月 第45回石橋湛山賞受賞

日本銀行が2013年に「量的・質的金融緩和」(異次元緩和)を始めてから10年が経過するなか、世界経済の急激な局面の転換によって、我が国は、この“超低金利状態”を維持できるかどうかの瀬戸際に立たされています。これまでの放漫財政路線を安易に継続し、異次元緩和を強引に押し通し続けようとすれば、我が国は遠からずどういう事態に陥るのでしょうか。最悪の事態を回避するためには、私たちは何をなすべきなのでしょうか。
目次
- 高インフレ局面への急転換
- 唯一、超金融緩和を“死守”する日銀
- ひずみで円安が進展
- 市場からの警鐘
- 日銀の頑なな姿勢の本当の理由
- 規制金利時代から市場金利誘導へ
- 世界金融危機前の引き上げ誘導の手法
- 福井総裁時代には、“銀行券ルール”遵守で4ヵ月で正常化完了
- 量的緩和で様変わりした引き上げ誘導の手法
- 日銀は利上げ局面に入ればほどなく赤字に転落
- <コラム>日銀保有国債の時価評価と、先行きの赤字幅(付利コスト)の関係
- 赤字・債務超過転落で国債買い入れは続行不能に
- 歳出一律4割カットの悪夢
- 矢野財務次官の警告の意味
- 財政健全化努力を怠ってきた国の末路
- そもそも金融緩和でどうやって景気を刺激できていたのか
- 量的緩和の効果の現実
- 突如、マネタリーベース・ターゲティングを採用した黒田日銀
- マイナス金利政策で民間銀行に負担を転嫁
- 金利政策としての効果は希薄だったイールド・カーブ・コントロール政策
- マネタリーベースは採用しなかったFed
- 新たな手段は期限付きで試行
- 初期から正常化手法を検討し、出口戦略を説明
- コロナ危機後は後手に回るも、前回対比倍速で資産縮小
- 政策委員会で侃々諤々の議論を行うECB
- 欧州債務危機を救ったECBの“血も涙もない対応”
- マイナス金利政策を先行させた背景
- 少数意見の尊重が金融政策の質を高める
- 着手当初から出口局面での損失発生を見越していたBOEの制度設計
- 出口戦略のコストも公開
- 政府の損失補償があるからこそ進められる高インフレ下での正常化
- <コラム>主要中央銀行は「マイナス金利政策」や「イールド・カーブ・コントロール政策」をどう評価しているのか
- 主要中央銀行のマイナス金利政策に対する評価は消極的
- 日銀のマイナス金利政策は効果なし、がFedの評価
- YCCに至っては、Fedは一刀両断に却下
- 財政運営の危機感を欠いていた安倍政権
- 放漫財政助長の道具と化した異次元緩和
- 1990年代末から減少基調に転じた利払費
- アベノミクスの8年で国債残高240兆円をあっさりと積み増し
- 日銀の債務超過転落は、国民が免れてきた利払費の後払い
- ETF買い入れで人為的な株高を演出
- <コラム>国の借金(国債)にかかる先行きの金利変動リスクを誰が負担するのか
- 巨額の低金利の内国債を抱えて財政は行き詰まり
- 「取るものは取る、返すものは返す」
- 国民の資産を、貧富の差なく、徴税権行使の形で吸い上げた「財産税」
- 皮切りは「預金封鎖」で国民の資産を差し押さえ
- 戦時補償も踏み倒し、預金は切り捨て
- 現在の我が国への教訓
- 通貨が流通するのは価値が安定しているからこそ
- 通貨のもう一つの顔―財政運営の手段
- 国外への資金流出が止まらなくなったら
- アイスランドの悲劇
- “国際金融のトリレンマ”
- ギリシャの厳しい資本移動規制
- 我が国の財政運営が行き詰まったら
- 財務省はなぜ大規模な円買い介入に踏み切ったのか
- 担税力のある層は相応にいるのに合意形成ができない国、日本
- 過去の借金の返済に真面目に取り組まない国、日本
- 市場メカニズムの回復と持続可能な金融政策運営基盤の確保が最優先課題
- 日銀の財務は、他の中央銀行と桁違いのレベルで悪化することが不可避
- 金利シナリオごとの財務運営見通しを毎年公表するFed
- 一般国民向けの説明の充実と政府に対する姿勢を見直す必要性

