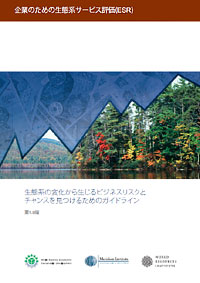企業のための生物多様性Archives/
国内事例
日立化成工業株式会社様
http://www.hitachi-chem.co.jp/
CSR室 社会貢献担当 主任 河野 文子 氏
2010年の生物多様性条約COP10が近づくにつれ、生物多様性の問題を意識する企業が増えてきています。COP10の名古屋開催は、世界に向けて生物多様性への積極的な取組みをアピールできるチャンスである一方で、規制が強化されたりNGOからの監視の目が厳しくなるリスクが高まる可能性もあります。そこで、社会の要求に敏感な企業はチャンスとリスクのどちらにも対応できるよう準備を始めています。しかし、実際に準備を始めるとなると様々な障害にぶつかることになります。自社と生物多様性はどう関係しているのか、どんなリスクがあるのか、何が重要なのか。こうした障害を乗り越えるキラーツールとして期待されるガイドラインが、「企業のための生態系サービス評価(ESR:The Corporate Ecosystem Services Review)」です。2008年10月に公式の日本語訳を公表した日立化成工業にお話を伺いました。
日立化成工業からみたESRの概要
Q.ESRが策定された経緯と日立化成工業の係わりを教えてください。
A.ESRはWBCSD(持続可能な発展のための世界経済人会議)と世界資源研究所(World Resources Institute)及びメリディアン・インスティトゥート(Meridian Institute)にて共同で作られたガイドラインです。WBCSDでは特に注力して取組むべきフォーカス・エリアが設定されており、気候変動・開発・ビジネスロールが挙げられていました。そして、2007年度から生態系(エコシステム)というテーマが4つ目のフォーカス・エリアとして新しく加わりました。ESRはWBCSDが取組んだこのテーマに関する報告書にあたります。
当社はWBCSD設立当初からメンバーとして参加しています。この生態系フォーカス・エリアが取り組むテーマの中では、事務局が作成した案などに対して意見を述べ、最終的な意思決定を行うコアメンバーとして参加しました。コアメンバーには世界中から業種をまたいでバランスを取った企業が入るようになっています。こうすることで、さまざまな幅広い企業で利用可能なツールの作成が可能になるわけです。当社もコアメンバー企業の中の唯一の日本企業として、日本企業を見渡したときに、日本企業が利用しやすくなるようアドバイスをしました。
Q.完成したESRに対する率直な感想をお聞かせください。
A.専門的な知見が集結され、ビジネスの視点からどう取組むかという点も良く考えられた、シンプルで使いやすいツールになったと感じています。企業で生物多様性に問題意識を持っている企業は多数あると思います。しかし、具体的に生物多様性に与える影響を検証したり生物多様性への影響を低減させる取組みにつなげたりするための手法は確立されていなかったため、生物多様性への配慮の多くは社会貢献の域を出ることができなかったというのが現状です。そのような中、ESRは生物多様性への配慮とコアな事業活動のリンクを可能にする大変有効なツールだといえます。今回完成した日本語版を企業や研究者、NGOなどに広く知ってもらいたいと考えています。
例えば、当社はスペシャルティー・ケミカルの分野のメーカーです。つまり、自然にある資源をそのまま製品化する事業分野ではありません。しかし、目に見える関係がないからといって、生態系とまったく関係がないというわけでもありません。社内で試験的にESRを利用してみましたが、生態系と事業の間の複雑な経路の把握・考え方の提供を可能にするという意味で、このツールは非常に有効だと感じています。そして、最終的な戦略の立案に至るまでに、現状のビジネスリスクの把握だけでなくビジネスチャンスを探索することになり、これがESRの大きな特徴になっています。
実際のESRの利用方法
Q.ESRは5つのステップが明確化されていて非常に取組みやすい印象を受けます。一方で、ステップ1の企業がバリューチェーンのどこに位置するのかという選択や、ステップ2の優先すべき生態系の特定など、初めの段階で難しさを感じる企業も多いのではないでしょうか?
A.多くの企業にとって製品はひとつではなく、当社でも多様な分野・アプリケーションを有しています。そうすると、ESRを全社的に利用する難しさは確かにあるでしょう。しかし、ESRは評価を行う人が範囲を決めて実行できる柔軟性があります。例えば、バリューチェーンの位置づけや生態系の特定は部署ごとに行うこともできます。
その際に大切なのは、CSR室のような環境の担当部署で使うのではなく、実際の製品・サービスに近い部署を巻き込むことです。なぜなら、同じ社内でも担当している範囲が違うと、生態系との関連性に異なる意見を持っているためです。さらに、社外の視点を入れるということも大切です。例えば、新しい工場を建設するときには付近住民や有識者との対話がないとうまくいきません。専門家による外からの新しい視点を入れることで、対話がうまくいくということもあるでしょう。プロジェクトが異なれば関連する生態系に対する回答も異なってくるため、生態系との関連性を明らかにするためには多様な視点からの検討が重要です。
Q.サプライチェーンが多岐にわたる企業などは難しさを感じるかもしれません。
A.これもやはり、部署ごとに分けたように、個別製品に切り離して利用してみるのが良いようです。適用方法・範囲を様々に試した上で、うまく利用できるようなら横展開をするという戦略です。
自然の資源に近い業種のほうがESRを利用しやすいかというと、ESRを実施した企業を見る限り、そういう傾向もないようです。生態系との関係性の高低も各社でまちまちです。あまり関係する項目が多くなるようならさらに切り分けて考えるなど、柔軟に利用するといいでしょう。
Q.それぞれのステップに所要時間も設定されているようですが、これはどういった意図があるのでしょう?
A.例えば報告書の中のステップ2「優先すべき生態系の特定」を行うためのツール「依存度・影響度評価ツール」の質問に回答するだけなら10分でできてしまうかもしれません。そうなると、表1に記載のあるステップ2にかかる所要時間の概算(2~3週間)という設定は長すぎると思われるかもしれません。しかし、その回答がはらむ背景を議論するプロセスが重要なのです。異なる部署や外部からの様々な視点からの検討を行い、バックデータを検証することなどを考えると、設定されている所要時間はこれでも短いかもしれません。より多くの時間をかけた方が、ESRから得られるメリットも多いと考えています。
今後のESRへの期待
Q.日立化成工業として今後ESRとどのように係わっていくのでしょうか。
A.私たちはESRに関する取組みの第一段階として、WBCSDのESR策定を支援し、また日本語版の発行に携わってきました。この日本語版ができたのは一つの区切りです。第二段階はその啓発活動だと考えています。考え方を広める鍵はESRの利用実績を増やしていくことだと思っていますので、その説明を、WBCSDSや世界資源研究所と協力しながら、今後行っていきたいと考えています。
日立化成工業の特徴
■企業のための生態系サービス評価(ESR)
生態系と企業活動との関連性を評価し、戦略の立案を行うためのガイドライン。WBCSDで取りまとめられた報告書であり、日立化成工業は唯一の日本企業としてWBCSDの議論に参加、公式の日本語訳を発表しました。
http://www.hitachi-chem.co.jp/japanese/csr/report_esr.html