IT時評:「次の一手を読む」
第7回「通信・放送の融合の切り札!?~“テレビ2.0”の衝撃」
出典:日本経済新聞「NIKKEI NET」 2006年8月30日
通信と放送の融合は、なぜ進展しないのだろうか。竹中平蔵総務相の私的懇談会である「通信・放送の在り方に関する懇談会」では、NTTやNHKの在り方、地上波放送番組の再送信といった既存インフラに関する問題が議論されたが、それだけでは不十分だ。通信・放送の融合は、前回示した「TV2.0」のような新たなメディア出現の下地を整えられるかどうか、そしてそれらが視聴者に受け入れられる機能や操作性を備えているかどうかにかかっているからだ。既存メディアと比較しながら、TV2.0のメディアとしての位置付けをイメージしてみたい。
受動的な機能にまで拡張したWeb 2.0
インターネット上のウェブメディアは、プロアクティブ(pro-active;ここでは「意識的・能動的な」の意)タイプといえる。すなわち、ユーザーが画面アイコンなどをクリックするという、意識的または能動的な行為によって初めて、所望のコンテンツにアクセスできる。
最近のWeb 2.0の分類では、RSS(RDF Site Summary)を含めている。RSSとは、RDF(Resource Description Framework)という情報を提供するための枠組みにより、ユーザーがあらかじめ登録しておいたお気に入りのコンテンツが適宜、自動配信される機能のことだ。このようにWeb 2.0は、パッシブ(passive;「受動的な」)タイプのメディアにまで拡張している。ただし、RSSのコンテンツ配信先は、特定ユーザー自身(personal)である。
ネット技術により分化する不特定層
情報の受発信における不特定層は、インターネット技術により、分化しつつある。最近のブログやSNS(Social Netwoking Service)の普及がそれを物語っている。
これまでのマス層への情報伝達メディアであるテレビでは、人口の1万人程度に相当する「0.01%層」のテレビ登壇者が、情報発信の主役を担っている。「0.01%層」とは、評論家、経済アナリスト、文化人、政治家、専門家士族(弁護士、会計士など)らのことだ。そして、メディアの王様であるテレビ側が、これら一部の人々を選定し、一方向の伝達手段となっている。
しかしいまや、インターネットやウェブが情報発信の機会や場を多くの人々に開放した。もちろん、単に大衆に開放するだけでは、玉石混交となってしまう。しかし、人口の「5~10%層」に当たるこだわりを持つ個人となれば、話は別だ。どの社会やコミュニティー(学校、職場など)においても、この「5~10%層」には魅力的な、または優秀な人材が一握りは存在している。梅田望夫氏も同様のことを「ウェブ進化論」(筑摩書房)で述べている。これまではサイレントであったこの「5~10%層」が、より広範な社会やコミュニティーに向け情報を発信してくるだろう。ブログやSNSがこのまま急速に浸透していけば、コミュニティー内での放送、マーケティング、研究開発(Linuxなどの先例あり)など、さまざまな可能性をもたらすことだろう。
パッシブ軸とこの「5~10%層」の重なる領域から、新たなメディア誕生の予感がする。TV2.0とは、ここにポジショニングされるものだ。この様子を次の図に示したい。
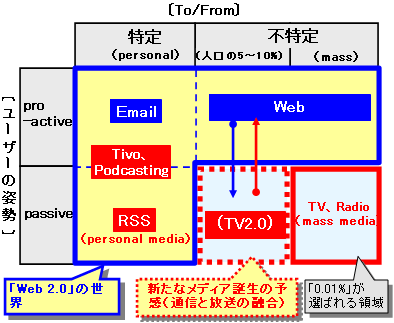
(注1) 「Tivo」は、HDDビデオレコーダーを用いる番組録画システムの総称、あるいはブランド名。ユーザーの好みに合う番組を常に満載でき、番組を見た後で、その番組が気に入ったかどうかを評価できる。
(注2) 「Podcasting」は、ネット上で音声データファイルを扱う手法のひとつ。登録したネットラジオ局の放送が更新された時に、パソコンへMP3などのファイル形式で自動的にダウンロード。iPodなどのポータブルオーディオプレーヤーにファイルを転送して気軽に聞くことができる。
(出所) 筆者(新保豊2006年4月)
マス媒体と競合するTV2.0市場
では、関係業界からみたTV2.0の市場や収益の源泉は、どのようなものになるだろうか。2005年のインターネット広告費は2,772億円(電通総研調べ)とされる。一方、日本の総広告費は5兆9,625億円(電通調べ)。うち、テレビ、新聞、雑誌、ラジオの4媒体はいずれも前年割れで、合わせて0.7%減の3兆6,511億円。テレビ単独では約2兆円の市場だ。
これらマス媒体の市場規模は、おおむねGDPの伸びに規定されている。デフレ経済下で経済成長率がせいぜい1~2%という状況では、もはや大きな成長は期待できない成熟産業となっている。規格大量生産型社会の産業モデルなのだ。
TV2.0は、次の図のようにポジショニングされよう。メディア事業者の視点でみたリーチ(注)の広がりと、利用者の視点でみたリーチの深さの両軸で構成される平面では、中央上部に位置づけられる。つまり、リーチの広さとしては500万~1,000万ほどあり、その到達度は深い。特に後者の到達度は、コンテンツが視聴者に及ぼす影響の度合いを示すもので、視聴者心理(前回の大前研一氏の表現)をとらえるうえで重要だ。
(注) 「リーチ」は、ある一定期間に特定の媒体上の画面やウェブページを視聴した人の割合、あるいは広告にアクセスしたユーザー数のこと。
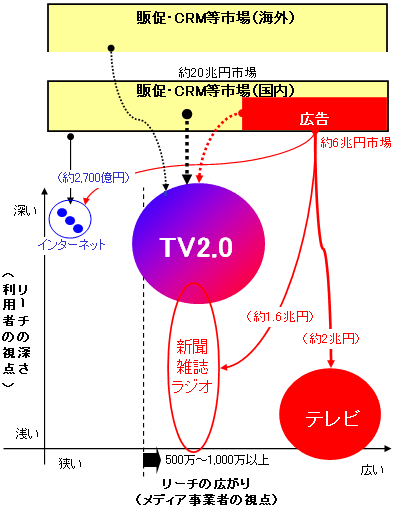
(出所) 筆者(新保豊2006年4月)
TV2.0の魅力が高まれば、従来の総広告費からの流入が期待できる。その場合、テレビ広告の代替となるため、テレビ業界は今からでもTV2.0の研究をしておかないと、近い将来食いぶちにも困ることになろう。他の3媒体(新聞、雑誌、ラジオ)も同様だ。図でTV2.0の領域と重ねて示しているように、3媒体との距離はかなり近く、代替性がある。
広告効果を計るには、例えば視聴者心理を支配する感性、理解、達成、自己顕示などに関する28ほどの欲求(心理学者の斉藤勇氏による「欲求の分類」)に根ざした、消費者行動を研究することが重要になる。広告に対するこうした消費者の反応について、アンケートをとるなどの方法で定点観測し、それらをデータベース化して研究することにより、訴求効果を高めることができる。テレビ業界はこれまでのように、テレビという限られた窓(ある種のプラットフォーム)から垣間見られる視聴者の振る舞いを想定するだけでは、時代に取り残されるだろう。
通信・放送の融合を具現しけん引するTV2.0
TV2.0は、「販促・CRM等市場」からの流入も狙える。この市場は国内だけでも約20兆円(総広告費を除くと14兆円)ほどもある。企業のマーケティングが、このTV2.0という新たなメディアで効力を発揮するようになれば、TV2.0領域は、通信・放送産業の中でも存在感を増すだろう。
TV2.0およびその周辺産業の規模は、知識経済社会に移行する過程で、早晩テレビ産業を上回ることも予想される。これまでは、新たなメディア出現の下地(通信の伝送容量や放送のビジネスモデルなどの供給面)が未整備であったことに加え、既存のメディアが、消費者側の相反する需要(プロアクティブ性かパッシブ性か)にうまく合致していなかったことなどにより、通信と放送の融合が進まなかった。通信と放送の境界領域にTV2.0のような新たなメディアが誕生することによって、両者の融合は一気に加速し、来る知識経済社会において重要な役割を果たすに違いない。

