クオドラプルプレーを目指す米AT&T
出典:日経BPビジネススタイル「ニュース解説」 2006年3月
第1回「米BellSouthの買収」 2006年3月17日掲載
2006年3月6日、米通信大手のAT&Tが、地域通信3位のBellSouthを670億ドル(8兆円弱)で買収すると発表した。ソフトバンクによるボーダフォン日本法人買収の動きとも重なる。日米で大型買収の動きが進んでいる。米国における大型買収は、わが国の情報通信産業の行方に、どのような示唆を与えるのだろうか。解説と展望を示したい。
2強時代の到来
米国では、大型のM&Aが相次いでいる。2004年12月、米通信第2位のSBCコミュニケーションズがAT&Tを統合し、新生AT&Tが誕生した。米国の通信史において常に中心的存在にあったAT&Tは、このときは既に名ばかりの存在になっており、テキサス州をベースにするSBCの軍門に下ったのである。その後、2006年1月、ニューヨーク州に本社がある通信第1位のVerizon Communicationsは、長距離通信大手MCI(旧ワールドコム)の取得を完了した。
筆者は、オースティンにあるSBCも、マンハッタンにあるVerizonも訪れたことがある。2004年末には、NGN(次世代通信網)の件で両社の経営幹部と面談した。この時は、今回の新生AT&TによるBellSouthの買収劇を含め、ここまで市場の再編が進むとは予想していなかった。
2005年11月、FMC(Fixed Mobile Convergence:固定網と移動網の統合)や通信と放送の融合など、「コンバージェンス」をテーマとするカンファレンスが、ベルギーで開催された。そこで筆者は、VerizonやSBCの幹部らと3日間にわたって接する機会があった。しかし、今回の買収劇の具体的な話などは全く出ていなかったように思う。
この買収が成功すれば新・新AT&Tの誕生だ。ライバルのVerizonと並んで、米通信市場は2強時代に入る。補足しておくと、広大な中西部地域にはQwest Communications Internationalが陣取っている。しかし同社は、不正会計問題の影響もあり、業績不振状態が続いている。近くVerizonがQwest買収に出るとの観測もある。
クオドラプルプレーを目指す新生AT&T
新生AT&Tはどうやら携帯通信事業を手に入れたかったらしい。FMCを強化するにも、携帯通信事業の強化がまずは必要ということだ。
固定通信の収益が年々細るなか、携帯通信はドル箱市場であり、さしずめ“金のなる木(cash cow)”と言えよう。その成長は若干鈍化した感があるものの、それでも莫大なキャッシュを生み出す源泉となっている。状況は日本でも同様。
新生AT&Tの経営陣が、今日の飯の種となる「キャッシュの源泉」と、明日の飯の種となる「成長」を手に入れるべく、行動するのは当然のことだ。
米国では、新生AT&TもVerizonも、固定通信、携帯通信、データ通信、ビデオ通信のすべてを網羅するようクオドラプルプレーに突き進んでいる。つまり、範囲の経済性(※)を追求しているということだ。
言い換えると、各種回線サービスをパッケージにして販売することにより、収益力を高めたいのだ。それには通信サービスの品ぞろえの豊富さとそのバランスが重要になる。そこでAT&Tは、BellSouthの持つ携帯通信部門(シンギュラーワイヤレス)が欲しかったのだ。いっぽう、BellSouthからすれば、経営の根幹である携帯通信部門を買収されれば、後は抜け殻も同然の状況。到底生きていけない。それなら、丸ごと身売りしようということになる。これが今回の買収劇となった。
※:複数のサービスや事業を、多角化した企業の内部で同時に行う場合のコストの方が、それら事業を別々の企業が担当した場合にかかるコストの総和よりも低くなる現象のこと。補完性が問題となる。
第2回「買収という選択は正しいか」 2006年3月20日掲載
大型買収は時の政権の顔ぶれに左右される
ただ、この買収が成立するかどうかは予断を許さない。FCC(連邦通信委員会)がどのような裁定を下すかにかかっているからだ。FCCのマーティン委員長は、2006年3月6日に次のような声明を出している(関連情報)。
「私は、申請がなされた時点で、FCCの同僚たちとともに、その申請書を早急に精査することを心待ちにしています。FCCの主要な責務は、提案された取引が消費者の利益にかなっているかどうかを判断することです。私たちは、提供された情報を慎重に評価検討し、個々の市場において具体的な害悪が起こらないかどうか、新たなサービスの提供によって潜在的な便益がもたらされるかどうか、検討するつもりです」(筆者訳)と。
米国の通信規制における判断は、この「消費者の利益」、「個々の市場への害悪の波及」、「新サービスの潜在的な便益」などがキーワードとなる。AT&Tとすれば、料金の高止まりを懸念する消費者団体から、今回の買収を阻止しようとする強い圧力もあるので、「現ブッシュ政権のうちに済ませたい」と考えているのだろう。“駆け込み買い”しようというわけだ。
蛇足だが、ソフトバンクによるボーダフォン日本法人買収事案は、“駆け込み売り”である点は異なるが、竹中平蔵政権(いや小泉純一郎政権)が存続しているうちに済ませたいという事情は似ている気がする。
大型のM&Aが実現するかどうかは、その後の市場形成に多大な影響を及ぼすため、タイミングが問題になる。また、通信における安全保障が議論のテーマになるなど政治マターになりやすい性格を帯びているため、時の政権の顔ぶれにも左右される。光ファイバーの貸し出し義務を緩和策するなど、現ブッシュ政権が地域電話会社(RHC:Regional Holding Company)におおむね好意的であることはよく知られた事実である。
この買収劇は正しい選択なのだろうか?
さて、規制当局からの許可が得られたとして、この買収劇はAT&Tの将来に影響を与える選択として、果たして正しいものなのだろうか。
筆者は、正しい選択と考えている。
経営の効率を追求することは、アングロサクソン流に言えば、「株主に多大な利益をもたらす」行動に違いない。アクセスライン(固定通信)を押さえている会社が、携帯通信事業を強化し、FMCへの備えができれば、トリプルプレー(電話、インターネット接続、ビデオ通信)の先にある、クオドラプルプレー(トリプル+携帯通信)を完成できる。
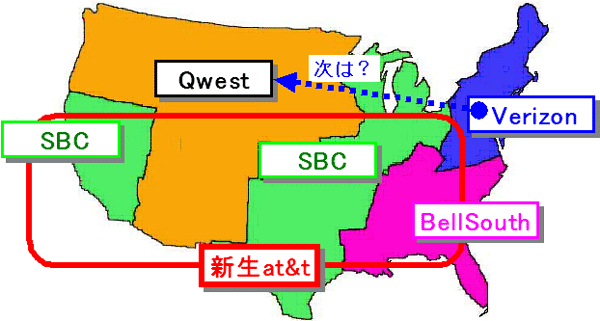
(出所)日本総合研究所作成
図表には示していないが、RHCにおける2強の敵は、コムキャストやタイムワーナーに代表されるケーブル会社(MSO:Multiple System Operator)だ。これらと対抗していく上で、クオドラプルプレーの提供は大きな力を発揮する。MSOが力を持っている点は日本市場と大きく異なる。地域通信会社がケーブル会社と対等な競争環境にある市場は、米国と韓国ぐらいしかない。
旧AT&Tは潮目を読み間違え続けた
旧AT&Tは、地域通信と長距離の相互参入を眼目とした1996年通信法が成立した当時の潮目を「長距離通信」と見た。数年後には、TCI買収(1998年)とメディアワン買収(1999年)を通じ、老朽化していたケーブルテレビ(CATV)設備を手に入れようとした(老朽化問題の深刻さはその後判明)。
しかし、ともに潮目を見誤った施策だった。アクセスラインやモバイル機能を手に入れるために多大な時間とコストを強いられることになり、「非効率経営」の代名詞として扱われる不名誉を得るケースとなってしまった。
この教訓は現在にも通じる。筆者はここ1カ月間ほどの間に、二つのシンポジウム(通信と放送の融合に関するものと、将来の情報通信市場に関する日韓共催のもの)に参加した。10年ほど前まで郵政省の官僚であった中村伊知哉氏(スタンフォード日本センター研究所長)が、おおむね次のようなことを述べていた。
「10年ほど前まで、『通信と放送の融合』という言葉を持ち出すことは郵政省にとってタブーであった。しかし最近では、「融合を積極的に進める」と表明している。感慨深いことだ。技術が進み、そのときは非現実的で亜流だった事象も、やがて本流になる時が来る。だから、いま難しそうであっても、大事なことは言葉にして残しておこう。官僚はやがてそれに向けて動き出す」と。
大変印象深いものであった。
いまの潮目は、恐らくコンバージェンスの方向だろう。なぜか。技術トレンドがそれを指し示しているからだ。また、その方向としてエンドユーザーの大きな需要が見込める。というより、コンバージェンスがもたらす利便やバーゲニングパワーを何が何でも手に入れたいという、消費者(エンドユーザー)の強い欲求が背景にある。言い換えると、消費者がいったん手にした利便性(固定と携帯のどちらのアクセスラインを選択するか、ラインに乗って配信されるコンテンツをどうハンドリングするか、を自分で支配できることなど)と、これまで供給者との間に存在した情報の非対称性を解消できる立ち位置(インテリジェンスが、供給者から消費者へシフトする傾向など)を手放すことは、独裁政権でも生まれない限り、今後ないだろう。
IP技術が100年続くとは言わない。しかし、これを前提としたフレームワークはしばらくの間、10年くらいは続くだろう。こう考えると、この流れに沿ったものに経営資源を傾斜配分することが重要になる。
第3回「BellSouth買収がわが国の通信市場に示唆すること」 2006年3月22日掲載
日本とは異なる産業構造、そして競争構造
AT&TによるBellSouth買収がわが国の通信市場に示唆するものを挙げておきたい。
新・新AT&TもSBCも、ともに地域独占事業(アクセスライン)を持った上で熾烈(しれつ)な競争をしている。そして、データ通信や携帯電話による通信などでは、寡占市場を形成している。つまり、米国の通信産業構造の基本として、「独占+寡占」のフレームがあるのだ。ここはわが国と大きく異なる。
NTT東西とまともに競争できているのは、ADSL市場におけるソフトバンクBBぐらいだ。NTT東西が38%(東21%、西17%)、ソフトバンクBBが35%とシェアが拮抗している(2004年9月時点)。NTTの競合企業が比較的健闘していると言われているFTTH市場でも、NTT東西が59%(東31%、西28%)に対して、電力系すべてを合わせても、たかだか14.5%にすぎない(2004年12月末)。しかも、電力系通信会社の場合は「親会社である電力会社から、内部相互サポートのようなものがあるのではないか」との指摘がある。米国のようなダイナミズムは認められない。
また、CATV会社はとてもNTTの競争相手になっていない。ソフトバンクBBが展開する「BBフォン」や「KDDIメタルプラス」といった直収電話も、いまだ地域通信市場を切り崩すほどの勢いはない。つまり、日本の地域通信市場では、アクセスラインが、NTT東西に事実上押さえられている。NTT東西の独占状況が続いているのである。米国のように、競争の土俵を一にする競争軸は、実際には存在しない。この日米の違いは大きい。
さてここで、「AT&Tの失策の主たる要因は、地域通信を分離したことであった。地域通信網をしっかりと保持し続けることが重要だったのである。だからこそ、地域通信(アクセスライン)を業とするVerizonもSBCも生き残った。したがって、わが国のドミナントキャリアにおいても、地域通信を死守することが不可欠だ」という論について考えてみたい。アクセスラインを分離せよなどと言うのは「周回遅れの見方」である、という論だ。
むしろ「周回“進み”の見方」
この論は的外れだ。賢明な読者であれば、もうお分かりであろう。そもそも日本は、米国と同じレース(公正かつ公平な競争)ができる競技場(市場構造)にはなっていないのだ。もちろん、同じレースを目指すことは大事であるが、同じ競技場(競争構造)を創れるか、創るべきかは、異なった議論だ。
地域通信網のつくりは、地理特性にも大きく左右される。国によって、市場の成り立ちも市場の特性(大きさ、プレイヤーの勢力の大小など)も異なる。例えば米国は連邦国家であり、広大な地域に核となる大都市がいくつも散在している。これに対して英国は、大都市ロンドンがあり、その周りにグレーター・ロンドンが広がっている。さしずめ、東京と周りの首都圏との関係に似ている。通信市場を考えるにあたっては、このような要素も勘案する必要があるのだ。
その英国において、独占的事業者であるブリティッシュ・テレコム(BT)は、2006年1月に組織改革を実施。規制緩和の促進と引き換えにアクセスライン部門を、独立性の高い社内事業部とした。アクセスラインを事実上分離し、競争相手がBTと同じ条件でアクセス回線を利用できることを保証したわけだ。この施策は、オープンリーチ方式と呼ばれている。
自国の国情を考慮し、最適だと考える方式を採用したわけだ。画期的なことだ。そして、BTは賢明だというべきだろう。規制緩和をうながし、自社の経営の自由度を高めるほうが、コンバージェンスの時代には大きな利得が得られるとの判断なのだろう。米国方式が常に正しいということはない。
まとめよう。米国には1)「独占事業者同士の競争」があるが、英国には、BTとまともに競争できる事業者は無い。この前提において英国は、2)「独占事業者(BT)から分離されたアクセスライン上での競争」をうながしている。上述の産業構造や競争構造の違いから考えると、わが国が参考にすべきは、どちらかと言えば英国方式であろう。NTTからアクセス回線事業を分離することは、むしろ「周回“進み”の見方」というべきではないだろうか。
そもそも、アクセスラインの事業を地域別に分割した会社組織や、それを規制する地域別組織は、どちらも時代の潮流からはまったく外れている代物なのだ。
こう考えると、わが国の放送業界もしかり。県域免許などで、ローカル局を守っている実態は、時代錯誤の極みである。変化に順応したものだけが生き残る。生物の進化も企業の進化も共通するところがある。もし放送業界が「通信業界が突きつけられている現状と自分たちは無縁である」と考えているとしたら大間違いだ。放送業界が、変化から取り残された、かつての恐竜の運命をたどらないことを祈りたい。
第4回「新たな競争の始まり」 2006年3月23日掲載
米国の2強時代の幕開けは、新たな競争の始まりでもある。そもそも、新・新AT&TとVerizonは、なぜ巨大化に突き進むのか。それは、1)MSOとの本格的な競争に備えるためだ。次に、2)GoogleやMicrosoftのような巨大なプロバイダーに対して、優先接続サービスの料金値上げをしたいからだ。
まず、MSOへの対抗について。
コムキャストやタイムワーナーのような巨大MSOは、RHCにとって脅威となっている。読書はここでお気づきであろう。2強のはずだったのに、あれ4強なの?と。そのとおり。通信市場は、コンバージェンスの方向をまっしぐらに進んでいる。トリプルプレーやクオドラプルプレーなどにより、消費者が享受できる価値は、狭義の通信サービス(音声電話)からビデオ通信を含む広義の通信に移行しつつある。しかし、巨大な竜はまだ狭義の通信サービスにとどまっている。
コンバージェンス時代には、巨大化が、竜が生き残るためのすべになる。なぜか。外部企業が提供するサービスをレイヤー別に集め、それらを組み合わせてコンバージェンスされたパッケージをつくるアウトソーシングよりも、内部のサービスを組み合わせた方が効率なパッケージをつくることができるからだ。
内部でサービスをつくる垂直統合は駄目だという見方がある。しかし、これは巨大な内部組織で事を成すにあたって、社内調整コストが無視できなくなるときに限られる。外部企業と協力してパッケージをつくる場合は、その外部パートナー企業の裏切りがあったり、信頼を勝ち得るまでの間、パートナー企業同士の調整に多大なコストが発生したりし、必ずしも効率的でない。「連結の経済性」(注)が発揮できなければ、アウトソーシングは意味がない。
注:複数の主体が連結し、あるいは組織と組織が連結して業際化することによって生まれる経済性を、「規模の経済」や「範囲の経済」と区別してと名付けられた【宮澤健一『制度と情報の経済学』(1988年、有斐閣)】。
寡占の後には別の競争がスタートする
次に、巨大なプロバイダーへの対抗について。
通信2強が巨大化を進めることには、GoogleやMicrosoftといった大量トラフィックを発生させている巨大ISPをけん制する意味がある。米国には、どうも巨大な竜がたくさんいる。経済のダイナミズムがわが国とは異なる。
携帯電話事業者しかり、巨大ISPしかり。これらの企業が手にする莫大な富を、通信料金を多く払ったユーザーに優先的に帯域または回線を割り当てるサービス優先接続サービスを導入することで還流させたい(収益の一部を収奪したい)という考えが背景にある。当然だ。
マクロ経済の視点から見れば、消費者の財布の中、つまり支出可能な額は、経済成長程度にしか増えない。そのようななか、通信会社の存在感が高まり、売り手の圧力が強まれば、優先接続サービスから大きな収益を見込めるというものだ。 つまりAT&Tは、同社が持つ通信網を経由して巨大な富を手にしている両社に対して、通信料金を値上げし、これまで以上に大きな収益を確保したいのだ。大量のトラフィックを発生させてている割にはあまり大きな通信料を課せられなかった、両社のような巨大ISPを牽制したい思いがあるようだ。新生AT&Tと巨大ISPのいまの力関係は、大きく変化する可能性がある。
第5回「新生NTTのとるべき道」 2006年3月27日掲載
コンバージェンス時代の「新生NTT」はもっと大きな果実をねらうべきだ
さて、再び連結の経済性のことを、NTTグループにおいて考えてみよう。今般のAT&TによるBellSouth買収の動きが、「NTTグループの今後のあり方にも影響を与える」という見方がある。ただ、これはNTTだけの問題ではない。わが国の通信産業全体の話となる。そこまで突っ込んで考えてみよう。
NTTグループにおける子会社間のサービス重複(例:プロバイダーサービス、無線LANサービスなど)の整理や、分離されている事業(固定通信と携帯通信)の統合化・FMCの動きは、この連結の経済性を追求していることの表れであると言えよう。連結の経済性が発揮できなければ、範囲の経済性を享受できない。コンバージェンスの時代に生き残れない。
こうしたコンバージェンスへの取り組みは、経営戦略の観点から見れば、至極当然である。コンバージェンスに取り組むことによって、自社の周りに独占状況を創り出すことができる。
コンバージェンス時代の「新生NTT」は、例えばアクセスラインを分離して、その代わり、放送進出を含む経営の自由度を手に入れるのが得策なのではないだろうか。中長期的な戦略として、捨て去るべき選択肢ではないと思われる。経営の自由度を確保しつつ、さまざまなオプションを手にできる事業形態を模索する。そのシミュレーションのなかで、持続的に最大の利得が得られる方向を見出すことが賢い企業と言える。
情報通信産業全体の利得の最大化とグローバル競争への備え
時代はデジタル・インターネット時代へ突き進んでいる。そしてわが国にとって、アクセスラインをNTTから分離した上で、その上部に乗るサービスの競争を推進することが、得られる当面の利得を極大化する策であると考える。独占的な位置づけにあるNTTのアクセスライン部門は、全国を地域分割してヤードスティック方式(※)などによる競争の枠組みを導入する。
※:コスト単価やコスト削減努力の程度を示すさまざまな指標を、対象とする事業者間において比べ、その評価に応じて料金査定に格差をつける方式。
ただ縮小均衡にならぬよう、あらゆる手を講じる必要はある。「独占=悪」と論じるのは早計である。米国のようにアクセスライン部門を所有した企業同士が競争することは、わが国では事実上困難だ。それが可能かどうかを考えるのに、時間をかけすぎている。一刻も早く、旧来の競争ステージを脱すべきだ。
縮小均衡を避けるために、いまは「サービス競争」ができる状態にすることだ。サービス競争であれば、対等な競争の核(企業)がいくつも出現することが容易であり、そう期待できる。そのほうが、産業全体を早く進化させられよう。
サービス競争をうながすためにアクセスラインの整備が必要であれば、国がやってもよい。公益インフラの整備が必要であれば、国が主体となって行う。何もおかしなことはない。「民主導」ばかりでは、うまく機能しないのは一目瞭然。地方のもうからない地域に、利潤追求を旨とする民間企業がインフラを整備するだろうか。するはずがない。公的な枠組みが不可欠なのだ。
民間企業同士の競争に委ねる「自由競争」は、ともすれば縮小均衡に陥りやすい。米国でもクリントン政権時代に、「市場の失敗」を経験している。産業政策、つまりグランドデザインをまず描き、その上で民間の総意・工夫を引き出す。この方式が賢明であろう。
民の競争と国の産業政策を組み合わせる。そうすれば、経済的利得の最大化を目指すことができる。さらに、デジタルデバイドなどの情報格差問題も解決できる。民と国の採る施策のバランスを取ることで、経済利得の最大化問題と情報格差問題はどちらも解決されうるのだ。
第6回「通信産業全体の経済的利得最大化が大事」 2006年3月28日掲載
産業が成長し強くなれば、その果実は消費者に返ってくる
ここで二つの視点を提供しよう。この視点は重要だ。一つは経済利得の最大化問題の補足。もう一つは、グローバル競争の強化を通じて実った果実は、結局、消費者の手に戻ってくるということだ。
具体的には、1)わが国の情報通信産業全体を再び成長軌道に乗せる、および2)グローバルでも通用する企業主体を育成・強化する、ことが重要になる。これらの帰結として、消費者も、手ごろな料金で品質の高いサービスを手にするという利益を得られる。
つまり、産業全体の経済的利得の最大化という視点を持つことが重要なのだ。それを実行することが、技術方式やビジネススタイルにおけるわが国の国際競争力を高めること、そして、業界標準を定めるのに必要な足場を固めることにつながる。
「常に消費者が最重要である」といった考え方に過度に立脚すると、国敗れて国民栄える(かつてのイタリア経済)のようになってしまう。
産業が育成・強化できて初めて、リストラも無くなり安心して雇用者は働ける。雇用者と消費者は、コインの裏と表の関係にあり、同じコインの問題なのだ。この視点を見落とすと、わがままな消費者にただおもねるだけの状況となり、企業活動や国の産業政策がおかしくなる。そして、その影響は、よくも悪くも、消費者自身に跳ね返ることになる。
「旧種と新種」の別の競争が産業をさらに進化させる
話を戻そう。「世界の通信市場が再び巨大企業による大競争時代に突入するなか、NTTを再分割することで国益が損なわれないか」との論がある。これは表層的な見方だ。
米国における1984年以降の通信産業史を見るだけでもそう言える。1984年、AT&Tが地域分割された。正確には、AT&Tが所有していた22社のベル系地域電話会社が、7社の地域持株会社の傘下に再編成された。いずれにせよ、1984年以前後で7?22ものたくさんの主体があったのだ。
こうした多数の核が市場にあり、それらが相互の力関係のなかで徐々に集約されていったのである。産業内に適度な数の核があった方が、ダイナミズムや競争は生まれやすい。このダイナミズムがイノベーションをもたらす。そう考えると、先の論は的外れだ。実際は逆なのだ。
生物は、複数の旧種の核が適度にあり、それら旧種が相互に牽制し合っている状況下において進化する。産業も、これになぞらえることができる。あるいは規制緩和などの条件が整って競争を育んでいるとき、一定利益を確保できるビジネス環境が存在するときに進化する。旧種のみに着目すれば、巨大化・効率化するように見える。旧種から新種への交替も進むように見える。
加えて、生物の進化に関する最近のある仮説は、進化・発展の途上では、旧種と同時に新種の核(遺伝子)も存在しており、「旧種⇒新種」のように一つの種が質的に変化することはないと説く。むしろ、「旧種⇒旧種+新種」へと種が一つから二つに増加する。核が複数存在することで、進化が加速する。そして、「優れた、かつ多様な遺伝子の組み合わせを保持することが勝敗を決する」という。
この「新種」を、コムキャストやタイムワーナーのようなMSO、さらにはGoogleやMicrosoftといった巨大ISPととらえてもよいだろう。言い換えると、新しい進化・競争が米国では始まっているのだ。この新たな競争を生み出すダイナミズムがきわめて重要である。
ここに名前を挙げた企業のうち、巨大ISPはいわばサービス競争を行っている。そして、設備競争を行う通信会社やケーブル会社よりも実際に大きな企業価値を生み出している。その意味では、米国は「2周か3周も」わが国よりも進化していると言ってよいだろう。この教訓を今回の買収劇は示しているのではないだろうか。

