"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第68回「Skypeは通信市場へ激震をもたらすか(5):携帯電話等への影響と均衡拡大政策」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2005年8月18日
前回に続き、Skypeからの直接的な打撃を受けると思われる国際電話への影響の程度、さらには2007年頃からは本格的な新規参入も予想される携帯電話市場へのインパクトの大きさは、どのようなものだろうか。また、値下げ競争の段階を脱却し、新たな市場創出とともに情報通信産業全体にとっての均衡拡大政策についても触れておきたい。
(1)国際電話へのインパクトは?
国際電話市場となるとさらにスカイプからの影響は甚大だろう。ただ国際電話市場を他市場と区分することは、最近とくに難しくなっている。何しろ携帯電話で、海外へ電話するほどの時代になっている。1990年代にIDCやITJあるいはKDDといった国際電話サービスの専用キャリアは、いまやNTTグループやKDDIグループのような総合キャリアのなかに組み込まれている。そして、それら企業の有価証券報告書をみても、国際電話に関するセグメント情報については、第三者へは必ずしも十分明瞭に開示されていない。
そこで、TCA(社団法人電気通信事業者協会)データの「距離段階別収入のその他」市場を基に、これまでの"国際電話"の市場規模を見てみよう。それによると2001年4月に同市場は760億円となっている。1990年代の国際電話市場は4,000億円台ほどあったと筆者は記憶しているので、金額ベースの市場縮小は随分と進んでいることが改めて認識できる。そして、2002年4月には686億円(前年比90.3%)に下がり、2003年4月には826億円(同120.5%)に増大、さらに2004年4月には864億円(同104.6%)に再び減少、そして2005年4月には493億円(同57.0%)と大きく落ち込んでいる。恐らく、国際電話の場合には、企業の国際通話コストがデフレ経済に左右され削減されたこと、あるいはそれでも国際電話の必要性からくる実需があったことによる増減だったのではないだろうか。
国際電話とSkypeとの間に補完性はあるだろう。例えば、英国の新規取引先に電話をする際、最初は少なくともレガシーな国際電話サービスを利用することだろう。ただ以降も電話でのコミュニケーションが頻繁に続き、両者にコスト低減意識が強い場合には、Skypeに代替されることも十分考えられる。つまり、初回または頻度の低い使い方の状況下では、両者には代替性といよりも補完性のほうが強く働き、これまでと同様、レガシーな国際電話サービスの需要は依然続くだろう。
しかしながら、例えば、上海に工場をもつ国内本社から国際電話をする際には、初期段階からSkypeを使うメリットがある。つまりこの場合には、Skypeは立派 に代替性を持ちえるわけだ。現国際電話の使い方の大半が、このように同じグループ会社内、または固定的な取引先などとのことであれば、会員ユーザー同士の通話料金がどこでもタダのSkypeに切り替えてしまう必然性が高まる。これまでの国際電話のトレンドを見ると、今後は年度の落ち込み率(堅実トレンド)を、毎年2%程度とみなすことは決して過度な予想ではないに違いない。
同下降トレンドへのSkypeの影響を考慮してみよう。恐らく、追加の年落ち込み率は毎年5%程度になることも十分考えられるのではないだろうか。長距離市場のそれと比較すればその比率はむしろ小さいともみなせる。毎年5%程度の落ち込みであっても、2011年頃には国際電話市場の規模は100億円を切るような事態も考えられる。つまり、一時4,000億円台ほどもあった国際電話市場は、40分の1にも激減するのではないだろうか。こうなると、誰が国際電話サービスを継続するための通信インフラを維持するのだろうか。このことは近々より大きな問題になってくることだろう。
(2)携帯電話へのインパクトは?
最後に携帯電話市場への影響を本稿ではごく簡単に見てみたい。このテーマは読者にとっても、とても大きな関心事であろうから、このSkypeシリーズとは別に近く記述しておきたい。その見通しにはSkype要因だけではなく、さまざまな要因が絡んでくることを考慮すべきだろう。言い換えると、携帯電話ないしモバイル市場には、多種多様のイノベーション(技術革新と経営革新)が今後も持ち込まれる成長性の高い市場であるからだ、といえる。
第66回の「モバイル市場への足がかりをつくれるか」を思い出して頂きたい。本稿では、Skypeがやがて"携帯電話依存モデル"にしたがうというところから考えてみよう。つまり、携帯電話やモバイル端末にSkypeの機能が組み込まれ、屋外のインフラとして主に無線LANが都心部だけでも整備されるようになってくると、ノマディックな通信が現実的なものとなってくる。この時期が来年(2006年)後半からのMNP(モバイル・ナンバー・ポータビリティ)導入後の2007年か2008年頃にはやってくることが予想される。
実際、ライブドアが今夏に東京都内で開始する無線LANサービスと呼応するような形で、Skype携帯電話(PDA型ではなく携帯電話型)が、スカイプ・テクノロジーズ社のニクラスCEOによってVON Canadaで発表されている。
携帯電話・モバイル通信市場への新規参入が実現される際、同市場への参入プレイヤーの出方はどうだろうか。新興キャリアにとって、この市場で失うものは何もない。したがって、低価格で、無線LAN下の定額制のブロードバンド通信、あるいは通信と放送の融合要素(例:テレビ映像、デジタルラジオ)といったさまざまな武器を行使できる。そのとき、新興キャリアのなかには、Skypeやそれと同等の武器を組み合わせて参入してくることもあるだろう。
MNP導入時またはその後の数年間は、わが国携帯電話市場の本格的な戦国時代突入の時期にもなるだろう。現在のレガシーキャリア(NTTドコモ+KDDI・ツーカー+ボーダフォン)の市場シェアは、2013年には堅実シナリオでみても85%ほどに落ち込む可能性がある。これは現在の携帯電話サービスでの年間解約率が22〜23%ほどあることを考えるとそう非現実的ではない。その解約ユーザーの仮に4割ほどが、新興キャリアの魅力あるサービスへ乗り移るといった程度のことを、数年間繰り返すだけで残りのシェア、すなわち15%ほどを容易に収奪できる可能性があるからだ。
図表をご覧頂きたい。
【図表】 携帯電話市場と新規参入およびSkype
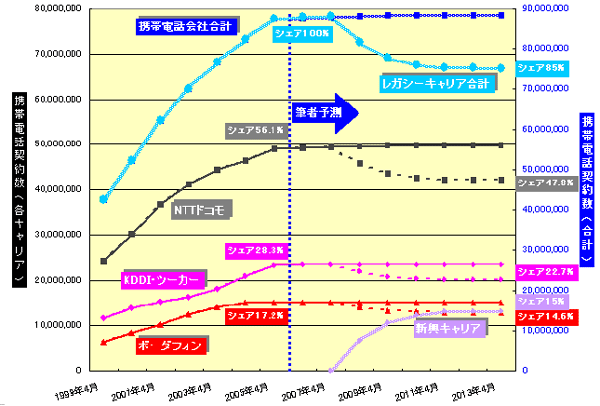
(注)「携帯電話会社(レガシーキャリア+新興キャリア)のシェア」:携帯電話市場のシェア推移の"堅実モデル"に拠る。"悲観モデル"では、レガシーキャリアのシェアは2013年度には75%まで落ちる。
(出所)筆者(新保豊)作成
そのシナリオでは、NTTドコモの現行市場シェア56%が48%ほどへ、またKDDI・ツーカーでは同28%から23%ほどへ、ボーダフォンでは同17%が15%ほどへ低減することも考えられる。これはあくまで市場シェアの話である。金額ベースではもっと激震が走るだろう。つまり、旧来の、または狭義の携帯電話通話サービスにおけるARPUが下がる可能性が十分あるからだ。「契約者数×ARPU」により収入が決定されるいまの仕組みでは、市場シェアを奪われ、安値攻勢をしかけられれば収入はおのずと下がる。これをどうみるか。
(3)求められる経済成長と産業政策
携帯電話市場あるいは情報通信産業全体としての理想は、競争政策と産業政策がうまくマッチングをはかれ、市場の拡大均衡を実現することだ。つまり、エンドユーザーにとってサービスの低価格と使い易さなどの利便が高まることに加え、事業者の利得を高められるかどうかがポイントとなる。ユーザーばかりに寛大な策を講じ続けると、産業全体が立ち行かなくなることが考えられる。
競争至上主義を推し進めすぎると、あるいは事業者側も合成の誤謬から抜け出ることができないと、産業全体の発展に支障が出てくる。産業の均衡のとれた発展のためには、わが国の経済成長が不可欠だ。政策当局のこれまでのやり方では、経済成長との関係がほとんど議論されてこなかったといえよう。需要の喚起がデフレ経済下には不可欠なのだ。
今年(2005年度)の『経済財政白書』で竹中経済財政担当大臣は高らかに謳っている。バブル崩壊後の日本経済の重しだった3つの過剰(雇用、設備、債務)をほぼ解消、負の遺産の清算を終え、新たな成長分野への投資を促進、景気の現状については踊り場から脱却に向かう動きがある、と。しかしながら、これをそのまま信ずることは到底できない。むしろ、これまでの経済政策の無能ぶりを露呈しているだけともいえる。
最近のオールド・エコノミー(素材、エネルギー、海運など)の大復活にしても、血のにじむようなリストラと業界再編を繰り返し強いられてきたものだ。わが国の経済は縮小均衡しているだけであり、家計と企業部門の総所得が増え、消費と企業支出(設備投資など)への意欲が高まらない限り見通しは依然不透明である。つまり、両者の財布の中身が増え、財布の紐が緩まない限り、今後の経済成長も期待薄と言わざるを得ない。財布の中身とその紐に関する問題が解決されない限り、現デフレ経済下では、財またはサービスの低価格化が進むばかりで、産業全体の利得を増やす(拡大均衡を実現する)ことはできない。
"失われた10年間"において、世帯の情報関連支出は月額で2万5,000円程度でずっと変わらない、したがって、今後もいかに多種多様のサービスが登場してもその額に変わりはない。それゆえ、どこからかの市場から富(消費額)が移動するだけであり、金額ベースの情報通信産業全体の大きさは変わらないとする見方がある。あるいは企業の広告支出は今後も大きく変わらないため、通信と放送の融合といったような新市場においても、市場全体として、そう大きな発展はなく悲観視する見方もある。
しかしながら、これらの見方はいずれもマクロ経済的な視点の欠如からくるものであり、経済成長が例えば、年率で3〜4%ほどを達成できる見込みが立てば、今後の状況は大きく変わっていく。デフレ脱却を最大の課題とするマクロ経済対策と、情報通信産業というミクロ経済対策との両輪を明瞭に視野に入れた取組みが大いに求められるところだ。

