"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第66回「Skypeは通信市場へ激震をもたらすか(3):パートナーシップとモバイル市場への足がかり」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2005年7月28日
今回は、Skypeのアライアンス先(ビジネスパートナー)とのかかわりの現状、およびSkypeの将来の行方を決定づけると思われるモバイル市場との接点について、言及してみたい。
(1)パートナーシップが鍵
Skypeはグローバルで、さまざまなアライアンスが模索されている。
例えば、2004年12月には、ケーブル&ワイヤレス(英国)やB3Gテレコム(ルクセンブルグ)がSkypeOutで提携。マネーブッカーズ(英国)とではクレジットカードを使用せず、オンラインで前払い可能にするための協力関係を結んでいる。
また2005年2月には、モトローラ(米国)との間でSkypeを搭載したWi-Fi携帯電話機の開発を発表。すでに、端末メーカーのi-mate(アラブ首長国連邦)が、Wi-Fi無線LAN対応のGSM/GPRS携帯電話機に「Skype」をプリインストールして販売している。Hutchison Global Communications(香港)とでは両社が提携し、香港市場でIP電話ソフトを提供している。
| (注)「Wi-Fi」: | Wireless Fidelityの略。Wireless Fidelity 業界団体のWECA(Wireless Ethernet Compatibility Alliance)が、無線LANの標準規格IEEE802.11bの互換性を保証するために定めた名称。 |
| (注)「GSM」: |
Global System for Mobile Communicationsの略で、欧州で規格が統一された携帯電話機の標準規格。世界的に最も普及しているデジタル方式の第2世代携帯電話。 |
| (注)「GPRS」: |
最大9.6Kbps のGSM方式の携帯電話網を使った、2.5Gのデータ伝送技術のことで、最大115Kbpsにもなる。 |
さらに、2005年6月には、インテル(米国)がSkype内蔵可能な携帯VoIP端末の開発キットを出展している。
わが国においても、通信キャリアと端末機器メーカーとの間で、既に協力関係が模索されている。モトローラ(ボーダフォングループパートナー)やインテルの米国勢が、日本市場でのSkypeの動きに加担することは十分考えられる。パソコン産業初期の頃の名もないマイクロソフト(米国)が、当時のコンピューターの巨人であったIBM(米国)と協力関係を結んだときを彷彿(ほうふつ)させるが、このようなアナロジーを抱くのは短絡的であろうか。もちろん、現在の協力関係の模索状況は、モトローラやインテルが今後の情報通信市場の成長性の点で、モバイル通信もしくはノマディック通信に大きな期待を寄せていることの表れでもあろう。
| (注)「ノマディック通信」: | "遊牧民"を意味するNomadの形容詞Nomadicを冠した通信として、通信ケーブルの制約から解放され、屋内外を問わず駅前、街角、公園などいつでもどこからでも自由に高速データの通信ができることを指す。 |
一方、わが国の関係プレイヤーとしては、Skypeとはかなり早く提携関係を打ち出したライブドアやバッファローが筆頭にあるといえよう。そのほか、京セラ系の携帯端末等メーカーであるKCCS等(ウィルコムパートナー)が、Skypeモバイル端末を投入してくる可能性もあろう。パートナーシップの関係を図表にしてみた。
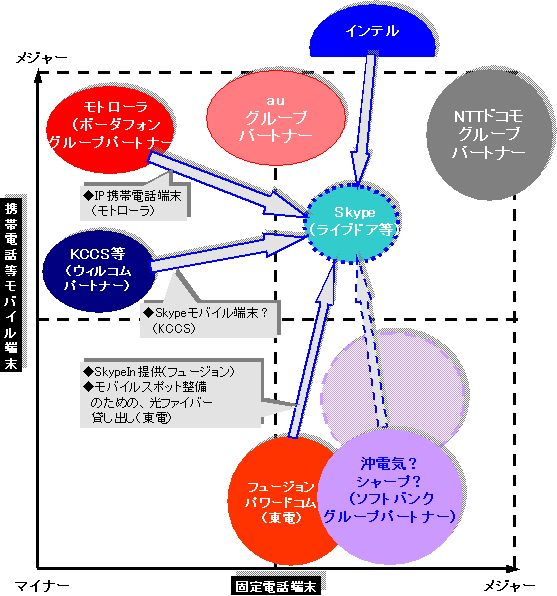 。
。
(出所)筆者(新保豊)作成
実際、ライブドアは2005年末までにSkype携帯電話サービス「SkypeMobile(仮称)」投入することを発表している。堀江貴文社長いわく、「値段もびっくりするくらいの低料金を予定している」、「最初は山手線内限定だけど、好評ならすぐに全国に拡大したい」、「Wi-Fiなら新型ノートPCにはほぼ100%入っている。カードも安くなっている」、「802.11aやnが使える5GHz帯の屋外開放は年末くらいと言われているが、当社の基地局はこれにもすぐに対応できる見込み」、「パソコンに1年分のチケット入りなんかで販売すれば、パソコン買ったら何もせずにネットにつなげるという理想のブロードバンド環境ができあがる」と。
| (注)「無線LAN」: | IEEE802.11という無線LAN(Local AreaNetwork)の規格で、最近では宅内のほか、駅前、街角、公園など屋外のローカルな部分でのネットワークが整備されてきた。 |
このライブドアの「Wi-Fi(無線LAN)構想」は、フュージョン・コミュニケーションズ(パワードコム傘下、東電グループ)との提携関係により、一層戦略性を帯びてきた。2005年秋から、両者が日本国内で割安電話サービス(SkypeIn)を開始予定であることは前述の通り。ただ、ここでポイントは、無線LAN等の基地局(モバイルスポットと呼ぶことにする)を整備のため、安価な光ファイバーの貸し出しにおいて、東電が連携していることだ。Skypeおよびライブドア陣営と東電グループとの関係には当面目が離せない。
ライブドアの無線LAN基地局は光ファイバー直収タイプのものとなっているが、その光ファイバー利用料は3年ほど前と比べ4分の1程度のコストで利用できるらしい。ユーザーの端末側でも、無線LANカードと無線基地局(IEEE802.11a/g/b同時接続対応の無線LAN エアーステーション/ブロードバンドルータ)のセットで、ひと頃に比べ3分の1程度の値段となっている。総務省の電波開放政策を背景に、基地局と端末での機器類の低価格化が、無線LANインフラの整備を加速させるに違いない。
(2)モバイル市場への足がかりをつくれるか
Skypeのモバイル市場への足がかり構築とは、携帯電話依存モデルをつくれるかということだ。これがSkypeの今後の進化には極めて重要な鍵となろう。インターネット依存モデルでは、パソコン中心であるためその普及の度合いは携帯電話依存モデルに比べ限定的であるからだ。単身世帯を含むわが国のパソコン普及世帯は、内閣府「消費動向調査」によれば、3,666万世帯(2005年3月時点で全国4,700万世帯の78%)に過ぎない。
第65回では、≪世界レベルの状況との違いは、携帯電話モデルへの移行時期がやや早めであり、「甚大シナリオ」では2008年から携帯電話依存モデルに基づいていることが挙げられる。2005年4月のインターネット人口は7,070万人程度であり、前年比で109%だ。このときのSkype登録ユーザー数は130万人ほどとされているため、その割合は1.8%となる。2007年4月には同割合8%で471万人に達し、これ以降は携帯電話依存モデルに従い、2015年4月にはSkypeユーザーは携帯電話ユーザーの25.5%を占め、その数は2,635万人ほどに達するのではないか。「非看過シナリオ」では、2007年4月では314万人(インターネット人口の4%)2015年4月に718万人程度(同人口の8%)に及ぶとみなした。≫とした。
すなわち、携帯電話依存モデルに置き換える前の、インターネット依存モデルの適用年では、「甚大シナリオ」で471万人(2007年4月)と想定しており、これは現在のパソコン普及世帯の13%を占める。また、「非看過シナリオ」では314万人(2007年4月)と想定したので、同様に9%を占めることになる。つまり、Skypeの普及速度は大きいものの、その想定ユーザー数は現時点(2005年7月)のMSNメッセンジャーやBBフォン(Yahoo!BB)程度に過ぎない。それ以上の普及の爆発は、パソコン環境という制約から脱することなくしてはありえないだろう。
とはいえ、わずか100名たらずの従業員しかなく、資本力のないベンチャー競合(スカイプ・テクノロジー社)が、自前で携帯電話設備を調達し整備するとは考えられない。したがって、パートナーシップ、さらにはその提携企業が整備しているインフラやこれから整備しようというインフラに便乗する(活用する)ことが重要な経営上のオプション(選択肢)となるわけだ。
次の図表をご覧頂きたい。
【図表】 通信キャリアと端末機器メーカーとの相関
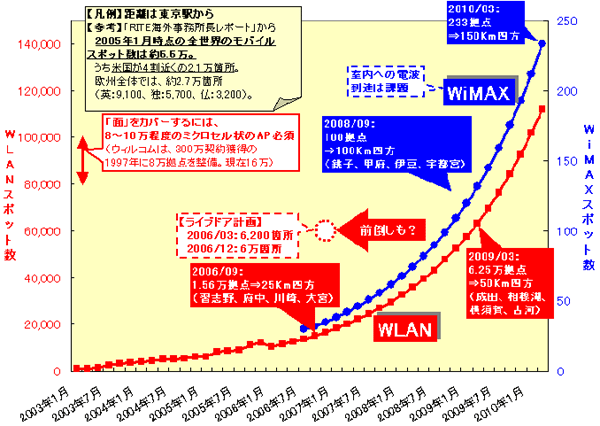
(注)2004年11月までのWLANスポット数については、FREESPOT協議会「FREESPOTの意義とその活用事例」(2004年12月)を、2005年末までは他公表情報を参考にした。
(出所)筆者(新保豊)作成
これまで、NTTグループ(NTT東西、NTTコミュニケーションズほか)をはじめ、ソフトバンク(Yahoo!BB)やFREESPOT協議会(バッファローが主宰:インテル、エプソン販売、京セラコミュニケーションシステム、シャープ、東芝、日本通信、フュージョン・コミュニケーションズ、松下電器産業などの22社が協力関係にある)などが、2004年11月末時点で約6,000のモバイルスポットを設置済みである。現時点では9,000近くのモバイルスポットが存在するものと推定される。過去のトレンドを外挿すると、概ね図表のようなWLAN(無線LAN)の普及が見込まれる。
一方、「RITE(財団法人国際通信経済研究所)海外事務所長レポート」によれば、2005年1月時点の全世界のモバイルスポット数は約5万5,000だ。うち米国が4割近くの2万1,000箇所、欧州全体では約2万7,000箇所(英:9,100、独:5,700、仏:3,200、その他)となっている。
また、日経デジタルコア主催で2005年6月に月例勉強会「無線ネットワークのネクストステージ」が開かれた。筆者もほぼ毎回参加するようにしており、有力な情報源の1つとなっている。当日のスピーカーの1人であった炭田寛祈氏(総務省総合通信基盤局電波部電波政策課)によれば、英国やフランスの携帯キャリアは事実上、投資のかさむ3G(第3携帯電話)は半ばあきらめており、無線LANによるスポット環境の整備に勤しんでいるようである。同氏は日本との違いに言及していた。確かにわが国の場合、既存の携帯電話会社ではなく、既存の固定電話会社やライブドアなどの新興勢力が同環境の整備に意欲を示しているのは、興味深い点だ。
電波オークションで巨額の負担を強いられた欧州勢と比べ、幸い(?)わが国の携帯電話市場は3Gの普及が進んでいる。しかしながら、挑戦者(ソフトバンク、イー・アクセス、ライブドアなど)としてみれば、同氏らが進める1.7GHz帯または2.0GHz帯など電波の新規割り当てとは別に、無線LANによる"面のカバー"には関心の向くところだ。Capex(Capital Expenditure:設備投資または設備の建造にかかる総費用)の点でもOpex(Operation Expenditure:設備稼働後の運転・保守整備にかかる費用)の点でも携帯電話インフラに比べればコスト負担がはるかに少ないからだ。また、総務省は1,200MHz幅の電波開放の多くを無線LANなど携帯電話向け以外に現在準備中である。
このように企業の選択する経済合理性および国の産業政策の観点から、無線LANなどをベースとするノマディック通信が、わが国産業の戦略的なコミュニケーション形態になることが予想される。
図表では、東京駅からの距離によりそのカバー範囲の目安を示す。ご覧の通り、いまのトレンドを仮定すれば2006年9月には1万5,600拠点に達し25Km四方(習志野、府中、川崎、大宮)をカバーすることになる。さらにそのトレンドに従えば、2009年3月には6万2,500拠点ともなり、その範囲は50Km四方(成田、相模湖、横須賀、古河)にも及ぶ。このエリアで、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の総人口約3,400万人のうち6割ほど(この仮定は概算)をカバーするとすれば2,000万人程度へのリーチが可能となる。以上は、ライブドア参入表明前のトレンドを示したものである。
ライブドアは最近、2006年3月には東京都の中心(山の手線周辺)に6,200箇所、そして同年12月には6万箇所の無線LAN整備の計画を発表した。すでに同社本社のある六本木周辺の東電管轄の電柱上にはかなりの数の無線基地が敷設されている。ただ、「面」をカバーするには、8万〜10万程度のアクセスポイントが必須とされる。現ウィルコム(当時のDDIポケット)が、300万契約を獲得した1997年には8万拠点を整備した実績を思い出すと、ライブドアの無線LAN構想は十分ノマッドな環境を整備することになり、都市の至る所でノマディック通信が可能となる。例えば、モバイルスポット環境下では、定額料金で携帯電話よりもはるかに高速なデータ通信や電話ができるようになるのだ。
また、WiMAXといった新しい技術が、わが国に本格的に導入されるようになると、都市程度のエリアをカバーするネットワークが形成されることにもなり、無線通信の利用エリアは格段と拡がる。無線LANの有効到達距離が高々100mであるのに対し、WiMAXでは同5Kmにも及ぶ。すると例えば、2008年9月に100拠点を整備できれば、100Km四方(銚子、甲府、伊豆、宇都宮)を、また2010年3月に233拠点をカバーすれば150Km四方に高速データ通信が可能となる。米国ではインテルが、わが国では鷹山などの新興企業が大きな期待を寄せている。ただし、WiMAXでは室内への電波到達はまだ必ずしも十分ではなく課題がある。それゆえ、都心部などの人口密集地向けには無線LAN、その他遠方ではWiMAXといったような棲み分けが現実的なところだろう。
| (注)「WiMAX」: | World Interoperability for Microwave Accessの略で、高速無線MANに関するIEEE 802.16規格の愛称。MAN(Metropolitan Area Network)とは、都市程度のエリアをカバーするネットワークのことで、現在、DSLや光ケーブルが主流になっている、通信基幹分岐点から宅内あるいは端末までの回線部分をカバー。 |
(3)いずれ規制の対象に?
このように近い将来、Skypeを取り巻くビジネス環境はどんどん有利な方向に進展していく可能性が出てきた。フリーライダー(ただ乗り)であるときには、圧倒的にコスト有利な競争状況がつくれるのだから、普及のピッチも速い。また、Skypeの通話料金が無料である限り、規制の対象とはなりえず、規制当局からの横やりも入らない。安泰であろう。
しかしながら、SkypeOutやSkypeInのかたちで、既存の電話網を利用して収益を稼ぐような状況下では、しかもその市場シェアが無視し得ないほどの大きさとなってくれば、Skypeも立派(?)に規制の対象となってこよう。とくに、携帯電話市場への影響が少なからず認められるような状況下、すなわち具体的には携帯電話のARPU(ユーザー1人当たりの平均利用料金)が下がるとか、市場シェアを奪われるといった場合には、携帯電話事業者との摩擦も出てこよう。
ただ、フリーライダーといっても、現在のところインターネット上での通話サービスであり、また無線LANなどのモバイルスポットインフラをSkypeのビジネスパートナーが提供してくれ続けるのであれば、言い換えると、いわばそのコストを向こうから負担しようということが続くのであれば、そのような言い方は当たらないかも知れない。Skypeに限ったことではないが、いずれにせよSkypeの躍進・発展と規制の網はトレードオフのような関係にあるはずだ。
次回では、「インパクトの及ぶ先と影響範囲」として、現時点での読みとしては少々乱暴ながら、メッセンジャーへの影響、固定電話やIP電話へのインパクト、あるいは携帯電話へのインパクトについて考察してみたい。

