"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第62回「"通信と放送の"融合"から"統合"へ(上):通信会社のテレビサービスは低調」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2005年6月9日
前の第61回では、今回「"新・この国のかたち"【9】道路公団と情報通信インフラ供給会社の比較分析」について記述するつもりであった。しかし、最近通信と放送の融合やFMC(Fixed Mobile Convergence:固定網と移動網の統合)やスカイプなど、新たな動きが出てきたので、タイトルの変更をご容赦願いたい。今回は"新・この国のかたち"を小休止し、通信と放送の融合・統合について2週にわたり考えてみたい。
(1)"通信と放送の融合"最前線の現況は
通信と放送の「融合」とも呼ばれる、ネット回線経由でのTV番組提供サービスが始まった。目下、事業状況は芳しくないように見える。果たして通信と放送は「融合」するのだろうか。実際は棲み分け(固定化)状態が続くか、または市場固定化作用を解除できる条件が整えば、垂直統合と水平統合を経て将来、コングロマリット(複合企業体)が出現するやも知れない。「融合」を技術の可能性のみで推し量ると問題の核心を見誤る。
2002年に電気通信役務利用放送法が施行され、IP(インターネット・プロトコル)通信または映像信号による配信方式のサービスが次々現れた。前者はマルチキャスト通信でありオンデマンド型サービスが主流だ。後者ではIP通信が混在しないとされ、著作権法上"放送"に分類される。それで地上波やBS放送の同時再送信ができる。
前者では、KDDIの「光プラスTV」やソフトバンク系の「BBTV」、NTT系の「4th MEDIA」などがある。後者では、関西電力系の「eoT.V.」やスカパー系の「ピカパー」などがある。
両者ともにアンテナやTVチューナーは不要だ。代わりに光回線等を利用するためPCやTV等で受信する際、月額500円程度でセットトップボックスを借りる。光回線利用料が月額7,000円弱程度、オンデマンド型コンテンツ視聴は1〜3日で各100〜500円程度。旧作であればビデオレンタル店よりも安い。作品数はハリウッド発を含め1,500〜3,000近く。これだけあれば視聴者の多様なニーズを満たしているはずだ。
国内最大の「Yahoo!BB」上で提供される"IP系"の「BBTV」は、「光プラスTV」よりも安価であり(マンション向け月額4,189円)、地上アナログTVが視聴可能な「無線TV BOX」も特徴的だ。これで同時再送信状態ともなる。また"放送"系の「eoT.V.」では、工事費を含め初期に8万8,725円払えば月額3, 675円で79ch分を楽しめるが、初期障壁が何とも高い。
その点「4th MEDIA」では5,229円の契約料のほかチューナーに当初2万6,250円必要だったが、その後1万5,750円に値下げ。「ピカパー」では初期費用が大きく抑えられ、同軸ケーブル1本で全放送サービスが再送信できる。スカパー!のほぼ全チャンネルも楽しめる。映像回線料はマンション1棟で1万8,000円、マンション管理費から利用料が一括徴収されるモデルだ。
(2)通信会社のテレビサービスは目下、低調
これら現TV系サービスについて、開始時からの経過月数とともに契約数を比較してみよう。括弧内数値は、サービス利用に前提となるISP(ネット接続)サービス契約数である。
「光プラスTV」が開始16ヶ月で1.5万(光プラスネット、同18ヶ月で6万)、「BBTV」は同23ヶ月で3万(ヤフーBB、同43ヶ月で490万)、「eoT.V.」は同17ヶ月で2万(eoホーム/メガファイバー、同36ヶ月で22万)、「4th MEDIA」は同9ヶ月で1.4万(Bフレッツ、同44ヶ月で90万)、「ピカパー」は同14ヶ月で1万(Bフレッツなど同左)である。概ね2〜3万契約といったところだ。
全国世帯数を母数とするテレビサービスの普及率と括弧内のネット接続サービスとともに示すと、順に「光プラスTV」が0.03%(光プラスネットで0.13%)、「BBTV」が0.06%(ヤフーBBで10.41%)、「eoT.V.」が0.04%(eoホーム/メガファイバーで0.47%)、「4th MEDIA」が0.03%(Bフレッツで1.91%)、「ピカパー」が0.02%(Bフレッツなどで1.91%)となる。今のところ通信会社のテレビサービスが低調であることが分かる。
【図表】 通信会社のテレビサービスは低調
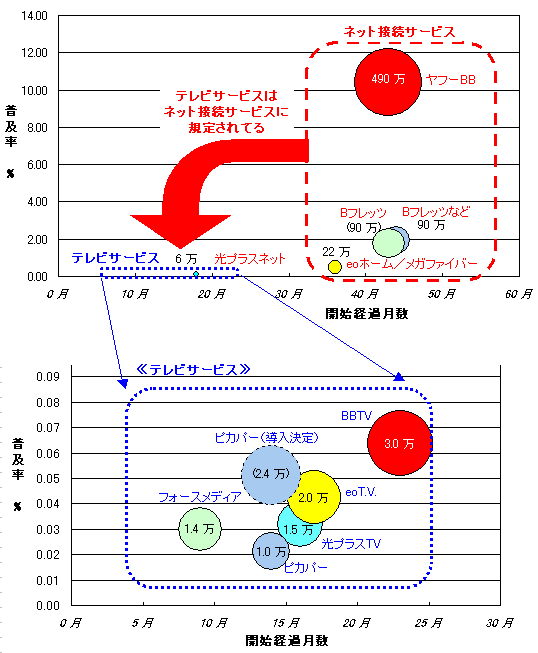
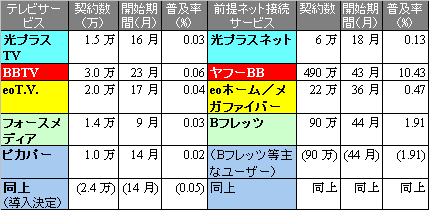
(注)◆普及率は、全国世帯数約4,700万を分母にして計算した2005年4月時点のもの。◆ピカパーの最下段の数値は、導入決定数(2005年4月時点)。
(出所)筆者(日本総合研究所通信メディア・ハイテク戦略クラスター)推定などにより作成
各社が当面の目標とする暫定世帯数(例:首都圏など)を分母にしてみても、0.03〜0.11%程度だ。ただし、分母を各サービスが前提とするISP契約者数とすれば、つまり各社の当面の目標達成度ともみなせるその比率は、15.0%、0.6%、1.1%、2.2%、10.6%と跳ね上がる。ネット上のテレビサービス(IP放送)は、当たり前のことながらネット接続サービスに規定されているのである。
言い換えると、テレビ放送のように、視聴者のテレビ受信機がどこのメーカーであっても、共通のテレビ電波を受けて、テレビ映像を楽しめるのに対し、インターネットテレビでは、ネット接続サービスという入り口が存在し、その入り口の大きさ(間口)により視聴者が制限される構造になっている。この“屋上屋の階層構造”が、通信会社のテレビサービスを低調ならしめているといえよう。
次回第63回では、「通信と放送の“融合”から“統合”へ(下):わが国もコングロマリット化の流れとなるか」として、より問題の核心に迫りたい。

