"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第44回「"新・この国のかたち" 【1】-情報通信インフラの上下分離の意味(下)」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2004年3月25日
第43回で論じた「情報通信版"新・この国のかたち"とは?」、「なぜ上下分離なのか?」に続き、本稿では、「どのように上下分離するか?」、そして「上下分離でどう変わるか?」について概観したい。
(1)どのように上下分離するか?
1996年当時のNTTの分離・分割議論が花盛りであった頃、筆者はNTTの分離・分割には反対もしくはその推進には消極的な態度を表明していた。 NTT電話網の分断は電話ネットワークの一体経営(経営効率性)、電話というユニバーサルサービス、欧米の当時のグローバルキャリア(BT、 AT&Tなど)への対抗上、あるいは株主保護などの観点から問題が多いと考えたからだ。
今、本稿で再び同様の問題をとりあげるなか、当時との最大の相違点は、"インターネット"という商用化間もない技術が、十分認識されていなかったことだ。当時も、インターネット電話について論じられたことがあるが、とても今のような電話端末機で会話が何ら遜色なくできるようなIP電話を想像できなかった。このインターネット(IP技術)という、いわばクレイトン・クリステンセンのいう"破壊的技術"が忍び寄る足音を、誰も聞き分けることができなったということだ。
電話時代の区分であれば、NTTのアクセス網(市内網)との相互接続を余儀なくされる、競争的事業者との相互接続問題は、現有のメタルアクセス網という資産の貸し出しとその利用(卸と小売り)の枠組みの中で処理されることになる。どこの国もそうしている。しかしながら、NTTの交換機を経由せず、競争的事業者が構築した独自網などで、その利用者同士は通話料ゼロというビジネスモデルが出てきており、その利用実態もYahoo!BBのBBフォンのみで 400万に迫ろうとする今日、電話時代の区分は時代錯誤になってきた。
では、どのように上下分離するか。次の図表をご覧頂きたい。これは、鬼木甫氏(大阪学院大学経済学部教授)が示している上下分離のイメージである。
【図表】 情報通信インフラの上下分離のイメージ(理想的な将来の枠組み)
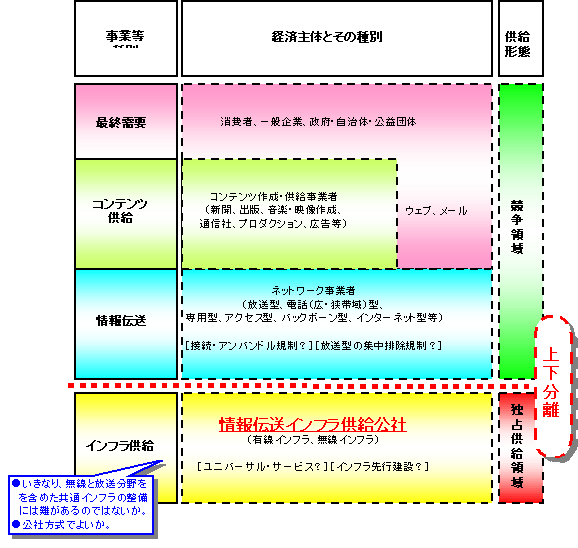
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成
「インフラ供給」層と「情報伝送」層との間を分離している。最終需要との接点は、この層とその上の「コンテンツ供給」層にあるとみなす。概ねこのような区分の仕方に大きな異論はないと思われる。
しかしながら、いきなり、無線と放送分野をを含めた共通インフラの整備には難があるのではないだろうか。情報通信産業の上下分離の問題は、最大の当事者であるNTTグループの再再編の問題にも等しい。無線はともかく、NTT法などの観点から放送事業には直接進出できない現在の条件下、鬼木氏のものを「理想的な将来の枠組み」と呼ぶならば、その前にもう1つステップが必要になるだろう。また、資金調達の効率性や「公社」という国民が持つ時代を逆行するような響きなどの点から、公社方式でよいものか別の手立てもありそうである。もちろん、自然独占性が認められる「インフラ供給」層では、公的なスキームを導入することそのものはおかしなことではないが。
そこで、次の図表に示すような「現実的な将来の枠組み」を考えてみたい。このスキームでは、最下層を「物理網インフラ(FP0)層」とし、ここで分離する。その上に、通信産業のレイヤー構成として「コネクティビティインフラ(FP1)層」と「サービス(SP)層」を置く。また、放送・メディア産業のレイヤー構成として、「コンテンツ制作(CD)層」と「コンテンツプラットフォーム(CP)層」を並置させる。上下分離は、FP0層(管路または conduit的なもの)とFP1層との間、およびコンテンツ系の2層であるCD層(ハード的なもの)とCP層(ソフト的なもの)の間で行う。
【図表】 情報通信インフラの上下分離のイメージ(現実的な将来の枠組み)
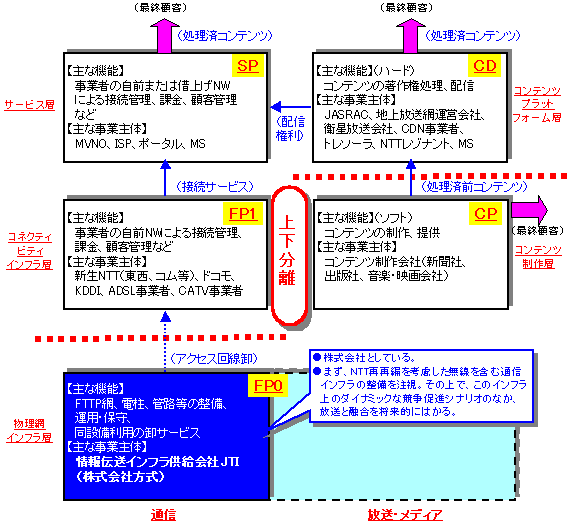
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成
情報伝送インフラ供給会社について、詳細は別の機会に譲るが株式会社方式としている。そしてまず、NTT再再編を考慮した無線を含む通信インフラの整備を注視し、このインフラ上のダイナミックな競争促進シナリオのなか、放送との融合を将来的にはかる。
(2)上下分離でどう変わるか?
情報伝送インフラ供給会社をJTI株式会社(Japan Telecommunication Infrastracture, Inc.)と仮に呼ぼう。放送・メディア産業も、このJTIの提供する共通インフラの上に乗る。放送(Telecommunication)は通信の一形態とみなせるので、ネーミングとしてはJTIでもよいだろう。
JTIは、自然独占性が認められる、概ね管路(conduit)の整備(敷設・運用)を担う。また、整備の対象は、幹線系に加え、建物・施設までの主に FTTP(fiber-to-the-premises)またはFTTH(fiber-to-the-home)領域であるアクセス系だ。ここでJTIが担うアクセス系は「光ファイバー+IP」が中心となろうが、その他のアクセス手段についても、技術革新に応じて柔軟に対処することが求められる。
JTI設立の仕方などについても、別の機会に譲りたいが、JTIの設立目的は、主にアクセス系インフラの整備の前倒しにある。つまり、現在のNTTグループや電力会社などのインフラ提供会社のみの競争では、インフラ整備のインセンティブ(誘因)に欠け、どうしてもその整備に時間がかかる。また、インセンティブの点でコストを回収できそうな都心部中心の整備となるため、ブロードバンド・ユビキタス時代には、ますます深刻となる「デジタルデバイド」問題を解消できない。
(注)「デジタルデバイド」:デジタル技術(いわゆるIT)の普及に伴い、それを使いこなせるかどうかで二極化が起こった状態のこと。とくに地域格差、所得格差などの点で、ITが使えるか、あるいはITインフラ環境が整備されているかで、ますますその格差が開いていく状況が問題視されている。
アクセス系手段として、他の手段を未来永劫認めず、光ファイバーを全面的に採用・固定化するということは、換言すると技術革新(イノベーション)への冒涜(ぼうとく)とも考えられる。アクセス系整備の大半は、今後光ファイバーとなろうが、敷設コストおよび小売サービスの価格において、特に都心部などにおいてはアクセス系手段としては、必ずしも光ファイバーで固定化するものではないだろう。当該エリアの状況や条件によっては、無線LAN、ギガビットイーサネット(Ethernet)などの手段も有効であろう。この場合は、IPネットワークは部分的な適用に留まることも否定できない。ただ、インターネットに見るこれまでのグローバルかつ自律分散的な急速な発展・普及の仕方をみる限り、つまり、IPネットワークの経済性とユーザーの効用の観点から、IP網が基本になることは依然有力だ。
無線インフラをJTIが全面整備するとなると、競合他社が競争上不利になることが考えられるため、無線インフラ機器などはJTIが民間企業から購入し、その設置などの工事やメンテナンスなどを行うといった、あくまで管路conduit的領域に、JTIの持ち分を留めるべきだろう。
明治維新政府は「この国のかたち」をいち早くつくるため、富国強兵策のもと、基幹産業のインフラ整備を行った。同様に今、他国に先駆けてわが国が FP0(物理網インフラ)層を整備しておくことは、今後の情報通信産業の発展や国家競争力の観点などから、きわめて戦略的な事項となってきた。
普及率についてはブロードバンドの定義にもよるが(例えば、米国ではわずか200kbps以上)、わが国のブロードバンドサービスは、実質 1~2Mbps以上の速度を指すのが当たり前になっている。こうしたなか、速度に加えサービス料金の安さの点、あるいは無線LANへの取組みの多様さなどの点で世界No.1になった。2003年12月スイスで開催されたITU(国際電気通信連合)の場で、元サムスン電子社長のチン・デ・ジェ韓国情報通信部長官(大臣)は「ITやブロードバンドにおいて、韓国が日本よりも明らかに優位だったのはわずか2~3年間だった」といったようなことを漏らしていたようだ。それまでトップを走っていた韓国を、わが国は短期間で追い抜いてしまった。
わが国ブロードバンド市場において、他国にも過去にも類をみない市場進展の実現の立役者は、Yahoo!BB(ソフトバンクBB)などの新興勢力であり、NTT東西の電話局舎や光ファイバーなどの設備のアンバンドリング(束をばらすこと)に関する規制緩和であろう。利害関係者との間で紆余曲折はあったものの結果、競争導入と競争促進までの迅速なプロセスは、これまでの規制当局には見られない動きであった。
ADSLサービスであれば、とくに電話局舎内のスペースや敷設済みのダークファイバー(未使用で光が通っていない状態のもの)の開放など、これまで NTTグループが保有してきた資産(設備)のアンバンドリングが競争を促した。これが上下分離のかたちで、より抜本的なアンバンドリング、すなわち管路を中心とする物理インフラを切り離し、新生NTTグループをはじめどの事業者もこの物理インフラにつながるようになれば、よりダイナミックな競争が期待できる。実際、スウェーデンのストーカブ公社では、この方式でブロードバンド市場がここ数年活気付いている。
2003年6月にブロードバンド加入者は1,100万人(世帯数でみて23%)を超えており、市場揺籃期という一定期間、すなわちクリティカル・マスを超えた10数%程度(E.M.ロジャースの普及モデルでいえば16%前後)のラインを既にはるかに超えている。現在もブロードバンドは大いに進展しており、消費者には高速の通信サービスが安価に手に入り大きな便益を享受している。
一方、各事業者は競争の激化とともに収益面で依然苦戦を強いられている。いったいこのような先の見えない状況がいつまで続くのか。事業者にとって収益の柱は見えてきたか。現下のこうした青写真を描けないわが国情報通信産業において、本稿で概観したインフラの上下分離を通じ、物理インフラ(FP0)層というコモンズ(共有地)の上で繰り広げられる、ダイナミックな競争を実現させることにどれほどの意味があるのか。
次の第45回では、スウェーデンのストーカブ公社方式などを例に、「コモンズ上のダイナミック競争」について概観してみたい。

