"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第42回「IP携帯電話市場の展望――新旧企業の攻防」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2004年2月20日
前回の「IP携帯電話市場の展望――IPケータイ市場にもヤフーショック?」に続き、今回は新興3G事業者(マルチメディア総研、ソフトバンク、NTTコミュニケーションズ、アイピートークなど)の挑戦と、それを受けてたつレガシー 3G事業者(NTTドコモ、KDDIau、ボーダフォン)との攻防に関する見通しやポイントなどについて概観してみたい。
(1) 設備増強などのキャパシティー計画をどうするか?
既存3G事業者においては、前回の3つの点(音声品質、サービスカバーエリア、追加設備負担)が解決され、または新興3G事業者にとって一定シェアを確保できる目算が成り立つとしても、次の点がまだ大きな課題となろう。
|
● |
新規参入がある場合のキャパシティー計画において、これまでの見通しを立てることができない点。 | |
|
◇ |
一定シェアを奪われかねないという点で、「加入者数」をこれまでのように、設備増強などのキャパシティー計画をリニア(線形)に見通すことはできない。 | |
|
◇ |
加えて、IP携帯電話では、前述の1人当たりのコストが大幅に軽減されることから、本格的な定額制度の導入も視野に入ってくる。従って、1人当たりのトラフィック(通信量)予測も立てにくくなる。 | |
|
● |
既存3G事業者は、現行のスィッチング費用障壁をいつまでも保持できないのではないかという点。 | |
|
◇ |
同 事業者は、これまでの事業展開で蓄積した結果として、「ネットワークの外部性」、「システムのコントロール」、「インストールドベースの獲得」などを通 じ、高い「現行3Gスィッチング費用」障壁を築いてきた。この壁を破る本格的な動きが新興の挑戦者から果たして出てくるだろうか。 | |
続けて下の図表をご覧いただきたい。上段にこのことを示している。
【図表】 キャパシティ計画と新規参入事業者のスィッチング便益増大アプローチ
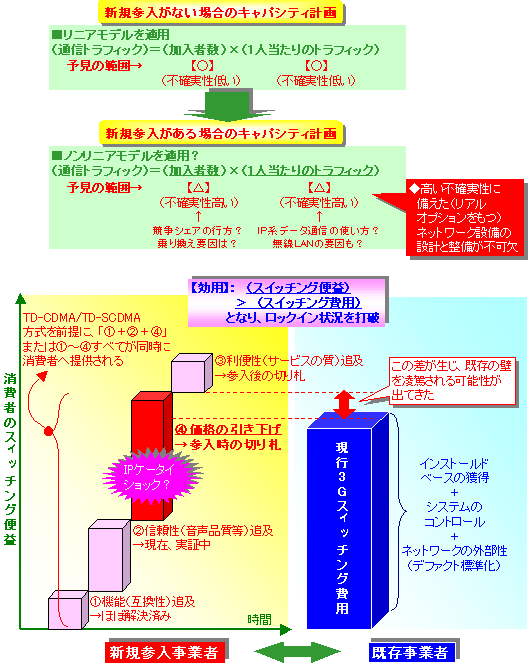
|
(注) |
◆「リアルオプション」:不確実性の高い事業環境下の投資において経営が持つ選択権(オプション)のことであり、金融工学におけるオプション理論を実物資産やプロジェクトの評価に適応したアプローチとなっている。◆「3G」:第三世代携帯電話のこと。◆「スイッチング費用によるロックイン」:契約、訓練と習得、データ変換、探索費用、ブランド変更費用のこと(Shapiro, Carl and Varian, Hal R.〔1998〕)。◆「インストールドベース」:累積ユーザー数、シェアのこと。◆「①機能、②信頼性、③利便性、④価格」:米ウィンダミア・アソシェーツの購買階層モデル。◆「ネットワークの外部性」:加入者の需要および便益がシステムの加入者数やネットワークの規模それ自体に依存すること。主に加入者数に加え、提供エリアの拡がり、およびそこでの参入事業者数などのを指すネットワークサイズにも関係する。 | |
|
(出所) |
日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成 | |
(2) スィッチング費用障壁を打ち砕くためのカードとは?
下段では、新興3G事業者の戦い方を示している。新興3G事業者は、レガシー3G事業者の顧客を奪うためにかかるコストである、「現行3Gスィッチング費用」の障壁を打ち砕くためのカード(切り札)を手に入れつつある。例えば、次のようなものだ。
|
● |
一般的に新規サービスの普及は、従来、(1)機能追求、(2)信頼性の追及、(3)利便性の追求、(4)価格の引き下げといった"購買階層モデル"に概ね従ってきたようだ。携帯電話市場においても例外ではない。しかしながら、新興事業者においては、この順番に従わず、これら4つの要素を3つまたは4つすべてをほぼ同時に消費者に提供し、一気に市場シェアを奪うアプローチに出ることも予想される。 | |
|
● |
現在、上記のステップ(1)はほぼ解決済みであり、同(2)は検証中といったところだ。この検証が済めば、同(3)の前に、ステップ(4)価格の引き下げ(最初から低価格)で参入することが予想される。これにはADSLサービス普及の初期段階における、"ヤフー・ショック"(価格破壊)のようなアナロジーが働く。 | |
|
● |
こうなれば、消費者にとっての効用(便益)において「(スイッチング便益)>(スイッチング費用)」となり、既存事業者にロックイン(固定化)されている状況を打破することができるかも知れない。 | |
|
● |
さらに、一定規模の消費者を確保でき(顧客基盤を獲得し)、また一定規模のサービスエリアでの展開が可能となれば、範囲の経済性も発揮できることとなり、同障壁を大きく越すほどの便益を消費者にもたらす。そうなれば、一定の消費者が新興サービスに移行することも考えられる。 | |
|
● |
現行の設備やシステムをIP携帯電話向けの設備・仕組みとして、将来、無線LANとの組み合わせやADSL固定サービスとのバンドリングなど利便性の追求(サービスの質向上)ができるように柔軟に設計しておくことで、そのカードを切る際にその時点の追加コストや以降の運用コストを大きく下げることが可能だ。 | |
|
(注) |
「範囲の経済性」:複数のサービスや事業を同時に、多角化した企業の内部で行う場合のコストの方が、それら事業を別々の企業が担当した場合にかかるコストの総和よりも低くなる現象などのこと。 | |
このように、新興3G事業者は顧客確保のためにあらゆる手段をとると考えられ、既存3G事業者の市場シェアを確実に奪うことになっていくのではないだろうか。既存3G事業者にとって、特に下位オペレーターにとっては、これほどの悪夢はないだろう。
(3) "儲け過ぎ"が目立ってきたのか?
一方、規制当局において、消費者の利益や携帯電話産業全体のメリット(利得)を最大化にするための競争政策として、新興3G事業者に対して一定シェアを与えるような方策を講ずることが予想される。これは、ちょうどADSLブロードバンド市場において、新しい市場を喚起するためにとられたやり方といえる。こうなると既存3G事業者にとってはさらなる向かい風となる。果たして、本当に戦々恐々としたことは起こるのだろうか。
既存3G事業者の儲け過ぎ(超過利潤性)はこれまで何かと話題になってきた。総務省が2002年9月から進めてきた、IP等分野における競争評価手法に関する研究会などでも、このことが何度か出てきたように思い出される。その場にいた筆者は、携帯電話事業者が今の利潤の正当性を声を大にして主張していたことを幾たびか目撃した。ADSLを含む固定電話事業との比較において、携帯電話事業者のパフォーマンスが最近特に目立つようになってきたことは否めないだろう。
規制当局が単に感覚的なことで、競争状態やそこから生まれる儲けを判断することはないだろうが、今回のIPケータイが価格"破壊的"な結果をもたらすとすれば、既存市場のシェアや既存事業者の利益に大きな影響を及ぼすことは必至となる。本稿では特にADSL市場で起こったアナロジーをかついで、この新しいマーケットを概観してみたが、読者はどのようにお考えになるだろうか。

