"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第41回「IP携帯電話市場の展望――IPケータイ市場にもヤフーショック?」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2004年2月20日
ケータイ(携帯電話)IP電話という言葉が、最近やたらと雑誌や新聞に登場してきた。およそこの1年間で横綱級の話題となった「IP電話」は主にADSL の上にのる固定電話のことだ。一方ケータイIP電話とは、今や8,000万人超のユーザーに支持される携帯電話の仕組みを、IP(インターネットプロトコル)で置き換えたもの。NTTドコモやauなどが占有してきたマーケットに、ADSLで見られたようにまたも、"定額制"と"ヤフーショック(価格破壊)"はあるのだろうか。このことをICT(情報通信)分野のイノベーションの動きにおける、興味深い実ケースとして概観してみたい。
(1)ケータイIP電話で3社寡占の携帯電話市場に風穴があく?
IPケータイが本格化しそうになった事の起こりは、2003年11月に始まった。
総務省はITU(国際電気通信連合)で認められている3G(第三世代携帯電話)規格であるTD-CDMA(Time Division Code Division Multiple Access)方式の国内技術基準策定に関し、情報通信審議会に諮問した。3Gとは、例えば、auのCDMA 1X(最大データ通信速度毎秒144キロビット)やドコモのFOMA(同384キロビット)のことだ。ドコモやauは現行3G端末の一層の高速化をはかるため、次期技術を既に採用している。それはauであれば、CDMA 1X WIN。これでEZwebとEメールなど携帯電話内で行うパケット通信に限ってとはいうものの、いよいよ月額4,200円の定額制プランが登場した。携帯電話での定額制は難しいと言われ続けてきたにもかかわらず、だ。
そして、携帯電話既存3社(NTTドコモ、KDDIau、ボーダフォン)とは別に思いがけないダークホース(イーアクセス、ソフトバンクBBなど)が登場した。現在、同諮問によると新たに15MHz分(2,010MHz~2,025MHz)がTD-CDMA用に割り当てられることになっている。わが国の電波周波数問題は、「周波数不足の解消に『市場原理』の導入を」(金正勲氏)にも書かれているとおり。今回の15MHzそのものは、お世辞にも大きな割り当てとはいえないが、TD(時分割)方式は後述のとおり、電波周波数の使用効率が高く、かなりの追加的利用者をここに取り込めることが期待されている。
同審議会の規格実用化の決定までには、半年から1年がかかるとみられており、また免許交付事業者は新規に3社程度といわれている。しかし、こうした動きが本格化すれば、既存3G事業者が占有していた大市場に、いよいよ風穴があくこととなる。市場規模7.9兆円(2002年度通期)、ユーザー数8,121 万人(2003年度の予想)という数字はとてつもなく大きい。風穴があくだけでも大事件だ。筆者はこうした技術革新全般のことを、かなり楽観的にみている。利用者がこうなりたいと願うことがあれば、大概のことはそれを技術的に解決できないことはない、と。いいすぎだろうか。
さて、3Gユーザーは目下1,300万人(全体の16%)ほどに過ぎないが、今の携帯電話全体ユーザーの大半は数年以内には3Gユーザーとなるだろうから、2007年度に仮にそのシェアを10%としても、920万人ほどのユーザーを確保できる算段となる。16%という割合は、ロジャース(米国の社会学者)の"イノベーション普及モデル"によれば、その後一気に普及するライン上にある数字だ。1,000万人に近い市場が近々によそ者の手に渡るとれば、既存事業者にとっては"くしゃみ"程度の問題としてもはや片付けるわけにはいかない。
(注)「7.9兆円、8,121万人なる大市場」:2002 年度通期でNTTドコモの売上高が4兆8,091億円(前年度比3.2%増)、KDDIは1兆6,263億円(同6.7%増)、J-フォンが1兆 4,610億円(同8.1%増)となり、各社とも1ケタ台の伸びにとどまるとはいうものの、計7.9兆円の大市場(2003年度の予想ユーザー数 8,121万人)となっている。また、2003年度の各社の予想によると、NTTドコモ4,576万人、KDDIauグループ1,965万人、ボーダフォン(旧J-フォン)1,580万人の合計8,121万人。2007年度には9,200万人に達すると見られる。
(2)中国の携帯電話市場でも注目されるTD-SCDMA方式
目下、米IP Wireless社の技術を利用したTD-CDMAシステムに関し、マルチメディア総研、ソフトバンク、NTTコミュニケーションズ、アイピートーク等が実験を開始している。一方、2004年1月30日開催の総務省「IMT-2000技術調査方策作業班」会合にて、シーメンスジャパンから「TD- SCDMA」、イーアクセスから「TD-SCDMA(MC)」の2つの方式が新たに提案された。前者は次の中国での動きが鍵を握るだろう。後者はTD- CDMAよりも優れているとの評価もあり、何が本命かこの半年程度で明確になってくるに違いない。
中国政府は、チャイナモバイル(中国移動)とチャイナユニコム(中国連通)なる2つの携帯電話オペレーターが支配する既存市場に、近々このTD- SCDMAを加えた新規参入促進の意向を以前から表明している。政府が固執するのは、中国独自の知的財産権を有する3G標準だからだ。ただ最近では、この 2つのオペレーターからは見限られた感があるものの、"アジアのビッグボス"(中国)市場でこの新方式がもし採用されるとなれば、部品調達価格など主にコスト構造の点で、日本には"風邪"以上の劇的なインパクトが押し寄せるに違いない。
(3)エリア拡大とコスト負担のトレードオフ(鍵はアクセス網の設備負担)
参入を表明している新興3G事業者が、ADSL事業者でもある点を考えると、これまでの3G事業者とはコスト競争やサービス競争などの点で戦い方も大きく変わってくるだろう。次の図表をご覧いただきたい。ADSLとTD-CDMA/TD-SCDMAのアクセスネットワークを比較した。
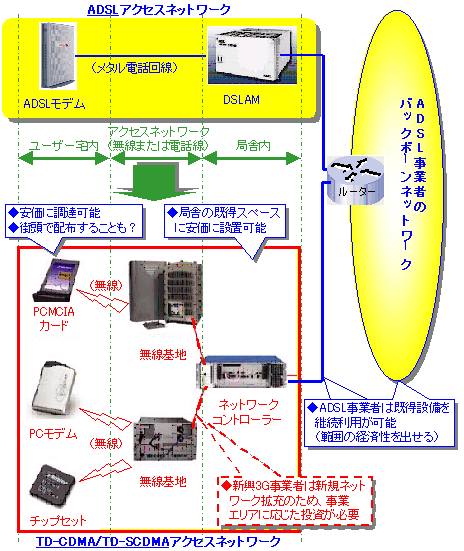
(注)◆「TD-CDMA」:Time Division Code Division Multiple Accessの略。◆「TD-SCDMA」:Time Division Synchronous Code Division Multiple Accessの略。◆「DSLAM」:DSL Access Multiplexerのこと。◆「3G」:第三世代携帯電話のこと。◆「PCMCIA」:Personal Computer Memory Card International Associationの略。
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成
ADSL事業者は、自身のバックボーンネットワークからADSLモデムにいたる設備を保有または利用できる。これは2000年頃から、ADSL事業者らが総務省に談判しさまざまに働きかけた結果として、勝ち取った本格的な規制緩和のたまものだ。
この際、新興ADSL事業者が獲得したNTT局舎内のスペースに現在DSLAMや専用電源などが置かれているが、そのスペースを利用して3G携帯電話事業向けにネットワークコントローラーを置くことが可能となる。この先に接続する無線基地までの設備負担として、新興3G事業者の新規ネットワーク拡充の程度に応じた新規投資が必要となる。一般的に携帯電話事業の参入には1兆円以上の設備投資が不可欠とされるが、新規方式では少なくともその数十分の1程度で足りるのではないかと筆者は考える。具体的なデータでモノをいうべきだが、もっと少なくていけるかも知れない。
そもそもTD-CDMA方式は、従来規格と大きく異なる点として、a)1つの周波数で送受信を同時に行え、同じ周波数を別の話者との間で共有できるため電波の使用効率性が高い(1人当たりコストが格段に下げられる)、さらにb)インターネットとの親和性が高い(インターネットと接続したADSL設備などの多くを転用できる)から、である。この2つの特徴は大変意義深い。日本発で以前からあったTD-SCDMA技術は、今の本格的なインターネット時代にあって、まさに破壊的なインパクトを既存市場に投げかけようとしているのではないか。少なくともそのような予感がする。
ただADSL市場での新興事業者のようなかつてのアナロジーは、例えば、次のような点で適用できないだろう。
| ● | IP携帯電話の方が、ADSLベースのIP電話よりも、音声品質を確保するのが難しいと思われる点。 | |
| ◇ | これは、昨年頃から大きな話題を呼んでいる固定IP電話の音質確保の点で、多大かつさまざまな努力を事業者は強いられたことを思い出せばよい。 | |
| ● | IP携帯電話事業を新興3G事業者が行うにあたり、サービスのカバーエリアが小さすぎる点。 | |
| ◇ | 携 帯電話の代替、または少なくとも補完機能を有すると思われたPHSが、電話サービスとしては事実上、退出を迫られたように、通信サービスにおけるカバレッ ジ要素の意味は大きい。もちろん、これまでのサービス利用状況とは異なった市場を創造できると思われるため、その場合には、限定エリアであるが一定のユー ザーを確保することは可能であろう。この限定エリアと一定ユーザー数がどれほどかが重要となる。 | |
| ● | カバレッジを広げる場合、同図表のネットワークコントローラーから無線基地までの設備負担が大きそうである点。 | |
| ◇ | 両者の間をつなぐため新規事業者には、拡充エリアに応じた新規投資が強いられよう。 | |
次回では、このIP携帯電話市場の展望の続きとして、NTTドコモやKDDIauさらにはボーダフォン各社のレガシー3G事業者と、それに向かっていく挑戦者との攻防についてのポイントを眺望してみたい。

