"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第40回「電話加入権は光時代に新たな価値ある資産となる」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2004年2月6日
(1)電話加入権なぜ今廃止論議?
日本経済新聞(2004年2月1日付け)の"エコノ探偵団"に、電話加入権(施設設置負担金)に関する問題が取り上げられていた。見出しの「電話加入権なぜ今廃止論議?」は"エコノ探偵団"からの引用である。先週、筆者のところへ2度ほど取材があったので、この記事のためにいくつかの点をコメントした。本稿では、そのコメントをもう少し補足してみたい。電話加入権問題は日経紙上や『日経コミュニケーション』などの雑誌でもいろいろ記事になっているが、もっと本質的なことが触れられていないように思われる。
それに触れる前に、最近の論議のポイントを整理しておきたい。電話加入権問題において総務省が悪役を引き受けるとの見方もあるが、既存ユーザー(消費者+企業)、取引事業者およびNTT東西にとっては、マイナス面の要素が大きい。各関係者の立場は次のとおりである。
- 【総務省】:2000年9月をピーク(6,308万人)に固定電話加入の減少の歯止めがかからないため、総務省はNTTの加入電話(固定電話)のてこ入れ策として、「電話加入権」の廃止案を模索している。総務省(および情報通信審議会)は2004年中にも結論を出すようであるが、数年かけて段階的値下げの後ゼロにする公算が高いと見られている。一方で、麻生太郎総務相は「流通しているもの(加入権)を一方的にやめるわけにはいかない。(廃止するのは)それほど簡単にはいかない」としており、関係者間の利害調整では難航しそうだ。
- 【消費者】:既に施設設置負担金(現在は7万2,000円)を支払っている消費者と、それがゼロになった場合の新規消費者との間で不公平感が生じる。電話加入権は財産権であるため、私的財産権の侵害に当る可能性がある。
- 【企業】:バランスシートに既に加入権を資産計上しているため、それがゼロになれば(あるいは、メタル電話回線が会社全体の共有財産として稼がない資産とみなされれば)、2006年3月期の決算から義務付けられる"減損会計"の基準から、その絶対額は軽微であったとしても評価額を切り下げる必要に迫られる。
- 【取引事業者】:加入権ゼロにより、全国電話取引業協会(全電協)の会員である取り引き事業者にとっては、大きな痛手を被る(300の会員の中には経営困難または廃業に追い込まれる)のは必至である。
- 【NTT東西】:加入権ゼロにより、固定電話への歯止めがかかるとの期待もあるが、NTT東西は設備維持のため年間300億円投下しており、うち100億円を負担金で賄っている。ユニバーサルサービスを担うNTT東西にとっては、痛し痒しであろう。
(2)電話加入権問題の近視眼的な論点と新たな価値とは?
「光網への中継ぎ」を行い、今はメタル(銅線)であっても"固定電話加入状態(固定網接続状態)"を維持することは、もし本来的な価値を十分認識できていれば、何も国が笛を吹かなくとも国民は自ら所有し続けるであろう。将来の光ブロードバンド社会で国民が豊な生活を享受するためには、"固定網接続状態"でいることが不可欠な生活環境("ブロードバンド社会の切符")になるはずだ。メタルケーブルに価値があるというよりは、"固定網接続状態"そのものに価値があるわけだ。今はメタルであるがそのうち、それが光ケーブルに置き換わると、"固定網接続状態"は新たな価値を生み始める。
従って、現下では家庭(または個人)ユーザー向けの大半を占めるメタル回線を維持することは、本格的な光ブロードバンド時代には国家戦略としても極めて重要ということになる。光ブロードバンド時代の前倒しは、現在のNTTや電力会社ほかによる市場競争("競争政策")のみでは、投資に見合う回収面などにおいてインセンティブは必ずしも高くなく、難しいだろう。米国などの他国を見れば一目瞭然である。一方例えば、スウェーデンのストーカブ公社などの公的主体がドライバーになったやり方をわが国にも導入し一気に光ファイバー整備を加速することは、Burgelmanの"Framwork Policy"など"産業政策"に通ずるもので大きな意義がある。それに関連したことは、第30回「NTTの再再編問題を考える(上)――光0種会社の意義」で述べたとおりである。ADSLサービスに見られるような価格競争政策と併せて、次の時代の骨太の産業政策が今こそ求められる。
話を戻そう。下の図表をご覧頂きたい。加入者線交換機(LS)から地下ケーブルを通って、きせん点で地上の電柱に上げられ、架空ケーブル経由で各家庭や事業会社のオフィスなどにメタル加入者線が引かれている。大半の家庭まではメタルケーブル("MTTH":Metal to The Home)となっているのが現実である。
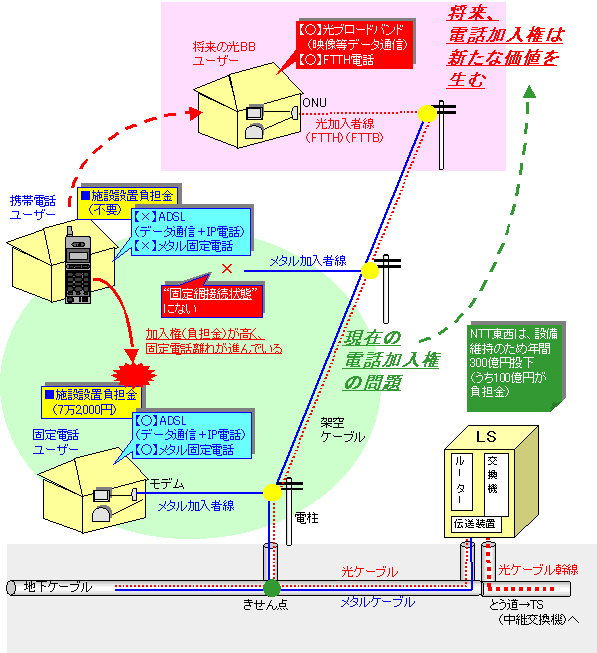
(注)◆「LS」:加入者線交換機(Local Switch)。◆「ONU」:Optical Network Unitの略で、 光ファイバーを通ってきた光信号をパソコンへ接続する信号(100BASE-TXのEthernet信号)に変換する装置。◆「FTTH」:Fiber to The Homeのこと。◆「FTTB」:Fiber to The Buildingのこと。◆「BB」:ブロードバンドの略。
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター(新保豊〔2004年1月〕)作成
日本に限らず米国などでも、携帯電話サービスへのシフトが急ピッチで進んでいる。わが国では固定電話への加入権(負担金)が高く、同シフトと合せて、固定電話離れが進んでいる。米国など海外ではわが国の"一時金"としての施設設置負担金は存在せず、移転時(引越しなど)での費用が、おおむね5,000円前後かかるのみである。電話網(インフラ)の整備状況は、米FCC(連邦通信委員会)電気通信政策局長のロバート・ペッパー氏も指摘するように「国によってその発展の形態は異なる」ため、わが国の施設設置負担金そのものを、単純に悪玉にすることはできない。
日本の大学生や新社会人で、意外と多くの人がパソコンを持っていない半面、携帯電話を持っていない人はもはや珍しい。携帯電話経由でインターネットに6,781万台(2003年12月時点で前年比14%増)も接続されているため、メタルケーブルなどは不要と考えるユーザーが増えているのもうなずける。これら携帯電話のみのユーザーがさらに、ブロードバンドサービスを受けようとすると、一時金とはいえ7万2,000円の追加負担などが必要になる。
携帯電話もできてブロードバンドもしたいというユーザーにとって、この一時金よりも毎年負担する携帯電話料金のほうがはるかに高いことは、あまり意識されていないのだろう。携帯電話会社の月間ARPU(1人当たりの平均収入)を8,000円とすれば、各ユーザーは年間9万6,000円も支払っているわけだ。例えば、過去5年間支払ってきたとして、48万円も負担していることになる。携帯電話会社の超過利潤性がやがて、今回の固定電話加入権問題でも浮上してくるだろう。
固定電話ユーザーのみならず携帯電話ユーザーがもし、さまざまなブロードバンドサービス(高画質の映像、放送コンテンツ、高度な対戦ゲームなど)の享受には、やはりケーブルが不可欠(または経済的)であることを知れば、現下の加入権について新たな価値を見出すに違いない。表示画面の大きさや通信速度などの点で、携帯電話では決して十分には味わえないコンテンツやサービスが現実に存在するし、今後ますます出てくるだろう。
(3)〝加入権はブロードバンド社会の切符〟とは?
続けて下の図表をご覧いただきたい。上段は、固定電話契約数(加入電話+ISDN)の推移を見たものである。現在はメタル固定電話から光固定電話への世代交代が進んでいる。 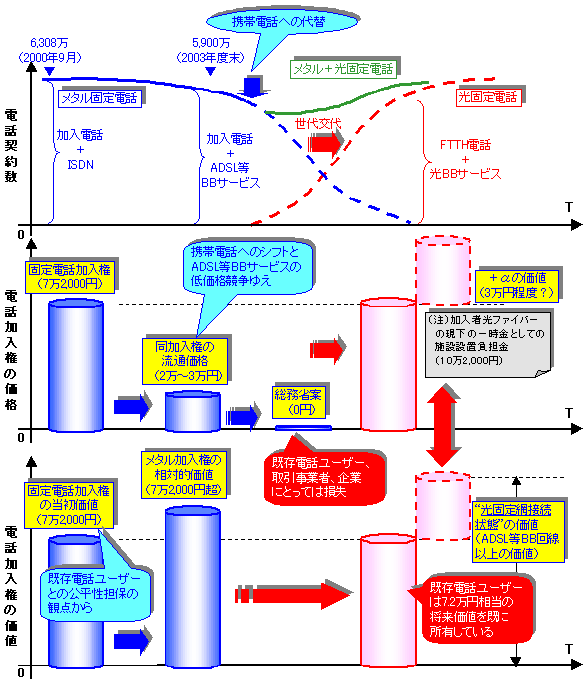
(注) ◆「BB」:ブロードバンドの略。
(出所) 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター(新保豊〔2004年1月〕)作成
中段では電話加入権の価格の予想推移を示した。メタル回線は、ユーザーにとってはADSLの登場で大きな意義(価値)が見出されているにもかかわらず、前述の携帯電話の代替的影響とADSLサービスの低価格化により、固定電話加入権("メタル固定網接続状態")の流通価格は現在2万~3万円程度で取引されている。
下段では電話加入権の価値(バリュー)の予想推移を示した。メタル回線から光ブロードバンド回線への世代交代が本格的に進むとすれば、"光固定網接続状態"の価値が出てくるはずだ。現在、「加入者光ファイバーの施設設置負担金」が10万2,000円相当であることにかんがみれば、"光固定網接続状態"の価値はそれに近いものとみなすこともできよう。"+α(アルファ)の価値"見合いの対価を原資として、光固定網の本格的整備に振り向けてもよい。この価値は、光ブロードバンド社会へはこれなしには参加できない"切符"であるという根拠から生ずるものである。この"切符"は、光ブロードバンド社会という共有地(ローレンス・レッシングのいう「コモンズ」)への、わが国全世帯のアクセス権利ともいえよう。
(注)◆「加入者光ファイバーの施設設置負担金」:接続専用サービスには施設設置負担金を一時金で支払うサービス(10万2,000円)と、一時金は不要とするが施設設置負担金に相当する部分を月額料金として支払うサービスがある。両者の負担の公平性を担保するために、2芯の場合、一時金で支払う金額に相当するものとして、月額942円と設定しているものがある。【NTT東西プレスリリース「加入者光ファイバ接続料金等の見直しについて」(2003年7月)から】
光ブロードバンド社会に向け、"固定網接続状態"の再定義が求められる。"光固定網接続状態"へのアクセス権に大きな価値が見出される一方、"メタル固定網接続状態"の存在価値は将来ゼロにもなろう。ちょうど地上デジタルTV放送の法制度化において、アナログ放送廃止(アナログ放送の価値ゼロ)となったように、とのアナロジーも浮かぶ。
結局、近く実現するであろう光ブロードバンド社会に向けた、この"固定網接続状態"の再定義こそが、現在の電話加入権問題でのステイクホルダー(関係者)を巡る不公平な論点を解決することにつながるのではないだろうか。目下の総務省案のように、加入権("固定網接続状態"へのアクセス権)をゼロにしてしまうのは横暴であり、総務省案と本稿案との違いは、将来の事の本質(アクセス権という考え方)についての見方の違いに起因するものといえよう。

