"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第38回「ITを駆使する研究開発戦略(上)――研究者の知を高める仕掛け」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2003年12月26日
(1)NHK「地球市場:富の攻防」に見るナレッジネットワークが持つ意味とは?
2003年12月21日に放映されたNHKスペシャル「地球市場:富の攻防・命をめぐる覇権」(抗がん剤開発、遺伝子特許獲得競争)を大変興味深く視聴した。海外のこうしたすさまじい動きの中で、わが国民間企業または国の研究機関の研究者にとって「知の攻防・覇権」は、どのような状況にあるのだろうか。
ゲノム創薬は今や膨大な利益をもたらす。番組では、スイスの大手製薬ノバルティスファーマ社が、ゲノム創薬第1号とも呼べる、慢性骨髄性白血病の治療薬を開発し、世界で5万人の患者の命を救ったということが紹介された。筆者が興味を覚えたのは、特に研究者個人同士の激烈な新薬開発競争や、最先端かつ最高のナレッジ(知識)が集まる条件・仕組みに関する点だ。
ノバルティスファーマ社のあるトップ研究員A博士が、極めて重要な遺伝子特許に関する論文を、科学界では最高の媒体とされる英科学誌『ネイチャー(Nature)』に、1番乗りで掲載しようとしている時のことだった。ほぼ同様の結果(アウトプット)を別途手に入れた米国人のある研究者B博士が、マスコミも参加の公けの場で先駆けてそれを披露することが判明した。雑誌掲載に間に合わないとみたA博士は、その場に乗り込み、B博士の発表中に割り込み聴衆の関心を自身に引き寄せることに成功。2人の将来の明暗が分かれる契機となった。やがてB博士は職場を去ることになる一方、その時以来業績の評価が固まったA博士率いるノバルティスファーマ社は、2002年860億円の売上高を記録することになった。A博士が数年前に手に入れた研究結果(アウトプット)が、財務的価値をもたらすほどの明瞭かつ大きな成果(アウトカム)となった記念すべき年となった。売れっ子作家による経済小説のような話だった。
最先端かつ最高のナレッジを集めるには、「ダイナミックなナレッジネットワーク」に関する考察が不可欠だ。当該分野のトップクラスの研究者は極めて野心的である。何が何でも成功したいという成功願望が尋常ではない。この点で日本人研究者の多くは見劣りがするといえよう。
(注) |
「ダイナミックなナレッジネットワーク」:米ペンシルベニア大学ウォートン校のロリ・ローゼンコフ(Lori Rosenkopf)教授が定義する、"次数中心性"や"媒介中心性"の概念などともに研究されている。 |
|
そして、研究者個人やその組織が、高度な知を集積しようとするエネルギーはすさまじい。例えば、優秀な人材を多額の報酬で引き抜いたり、優秀な人材同士が触発されるような場の醸成などにおいてである。"場"(創発空間)で繰り広げられるさまは、自然発生的なものとはほど遠く、ピストン式火花点火内燃機関のようだ。1950年代末の米シリコンバレー「Wagon Wheel」のような非公式な適度な空間、かつてのサロン的な雰囲気とはイメージが重ならず対照的だ。
まるで、ピストン(組織指示系統)による、「吸入(人材・資金の獲得)→圧縮(最高の研究施設を思う存分利用させる)→爆発(研究者の知識を昇華)→排気(昇華した知識を成果として取り出す)」の工程を経て、動力を発生(キャッシュフロー産出)させているようだ。
(注) |
「Wagon Wheel」:米シリコンバレーにあるカフェ・レストランの名前。米サンタクララバレーにショックレー半導体研究所が設立された翌1957年に、ロバート・ノイスをはじめとする若手研究者"8人の侍"が集団退職、フェアチャイルドを設立。ここに彼らがかつて集ったこともあるとされる。 |
|
一般的に資金調達やリスク管理ノウハウなど目に見える、タンジブルなビジネスインフラの欠如から陥るとされる「デスバレー」も、A博士にはさほど関係のない世界なのかも知れない。また、目に見えにくい(マネジメントにおいて意識されにくい)、インタンジブルなビジネスインフラと呼ぶべき、組織内での意思決定の仕組みが貧弱であるゆえに引き起こされる「デスブランチ」問題についても、効率的に乗り越える術を持ち合わせているのだろうか。
(注) |
「デスバレー(Death Valley)」:死の谷のこと。米国ネバダ州とカリフォルニア州の境界にある谷で、開拓時代の移民の多くがこの地を越えられずに死んでいったという。研究開発では次のような条件で、デスバレーに入り込む、つまり、初動時にパス・ディペンデンス(経路依存)が決定されることにもなる。
|
|||||
(注) |
「デスブランチ(Death Branch)」: 研究開発の対象となっているテーマや技術などが、当該組織内での理解を得られるかどうか、すなわち組織での的確な意思決定次第で、それがたとえ将来にポジ ティブな潜在性をもったものであっても、死に至る(製品化されない)ことでビジネスの機会を失う可能性のある分岐点のこと(造語)。 |
|||||
翻ってわが国の研究開発における、研究者を取り巻くナレッジネットワークはどうだろうか。【入次数,媒介中心性】という2つの因子で構成されるダイナミックな"ナレッジネットワーク度合い"(=KND、Knowledge Network Degreeとでも呼ぼう)を基に、考察してみたい。次の図表をご覧いただきたい。
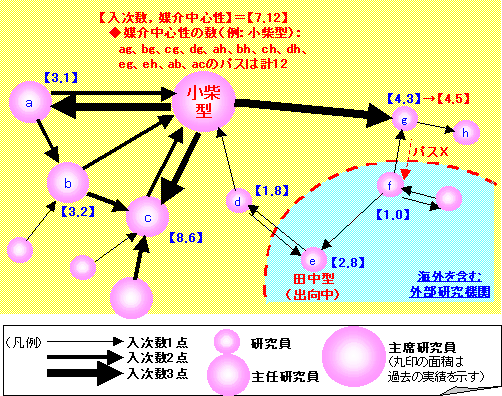
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成
ある研究機関に小柴氏という主席研究者(博士)がいたとしよう。小柴氏は文部科学省からも大きな予算を獲得している、わが国でもトップ級の研究者であり、組織内での人望も厚い。若い研究員にはメンター的な役割も果たし、組織の活性化にも日頃、大きく寄与している。自ずと彼の回りには、知のクラスター(束)が生成され、主任研究員や若い研究員クラスの知もさまざまにつながっている。
小柴博士の入次数は、直近の直接的な1研究テーマだけでも【7】ポイントになる。つまり、彼というノードには多くの情報源が連結し、有益な大量の情報量に接する条件が形成されている。もちろん一朝一夕でできたものではない。そして、媒介中心性の数は【12】にもなる。これはナレッジネットワークにおいて、小柴博士がネットワーク全体の価値にどれだけ寄与しているかを測る度合いを示すと同時に、そのネットワークから小柴博士がさまざまな知的刺激を触発される目安を示すものでもある。小柴博士のKNDは【7,12】となる。
さて他の研究員はどうか。組織(研究員の管理側)は、主任研究員クラスの知を引き上げ、小柴博士に次ぐ成果(アウトカム)を出してもらいたいと切望している。もちろん若手研究員も今のうちから効率的かつ効果的に育てておきたい。
例えば、研究員g君のKNDは現在【4,3】だ。ここでアドミ側がナレッジネットワークにITを活用することで、あるいは柔軟で適切な情報システムを構築・運用するなどの有効な工夫を施すことで、海外にある外部研究機関の研究員f君とのパスXを作ってあげる。そのことで、g君のKNDは【4,5】に高まることになる。
また、外部研究機関に出向中の研究員e君のポジションは、"田中型"とも呼ぶべきもので注目される。e君のそれは【2,8】であり、若いせいか入次数はそれほど高くないが、媒介中心性はかなり高い。つまり、すでに「トップ級研究者の居場所」にあることも推察される。こうした研究者が具体的な大きなアウトカムをもたらすよう組織内での特別な配慮、例えば、時に逃げ場のないような、より過酷な環境面を含む手厚い条件・支援などを行うことがポイントとなる。もし実際の組織の現場が、過去の日教組的な教育で"悪平等"がまん延していて、そうした措置ができにくい状況だとしたら、そのようなものはいち早く撤廃してしまう。
(2)研究者の参加者価値を高める2つのアプローチがトップ級アウトカムをもたらす
各研究員のKNDを、次数中心性(入次数)と媒介中心性の両軸で表現されるマトリクス上にプロットしてみよう。次の図表をご覧いただきたい。
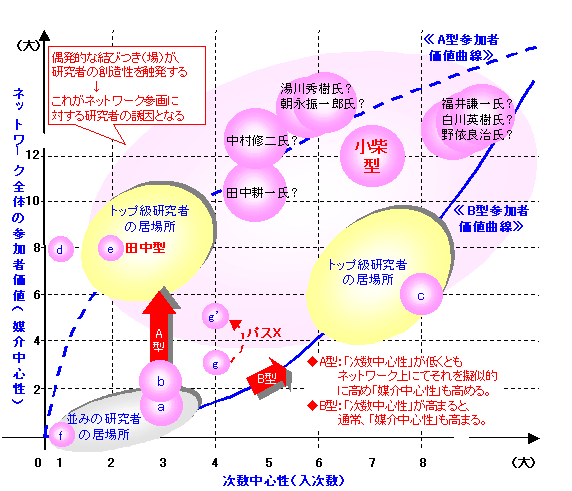
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成
研究者にとって価値あることとは、自身のアウトプットをアウトカムに転じ、さらにその価値を高めることである。アウトカムを高めるには一部例外を除き、おおむね「次数中心性」と「媒介中心性」の両方をを高める(B型参加者価値曲線に沿う)か、「媒介中心性」を高める(A型参加者価値曲線に沿う)ことが必要条件となる。
ナレッジネットワークシステムにより参加者価値を高め、研究者の最大の誘因(アウトカムが高まること)と結びつけば、同システム運用の成功はほぼ約束されることだろう。両曲線に乗せることで、それまでの偶発的な結びつき(場)が、研究者の創造性を触発し、ひいてはこれがネットワーク参画に対する研究者の誘因となるからである。いかに精巧な情報システムを作っても、アドミ側の管理面のみの効率化追求だけにとどまるうちは、決してうまく機能しない。研究者の誘因と管理者の誘因は車の両輪の関係であるからだ。
「並みの研究員の居場所」にとどまる主任研究員a氏と同b氏が、同システムによって、「次数中心性」が低くともナレッジネットワーク上にてそれを擬似的に高め、結果「媒介中心性」も高めることで、A型参加者価値曲線に乗せることができれば、組織の研究開発プロセスを通じたアウトカムは増大することだろう。前述のパスXを構築するということは、同様にA型参加者価値曲線に乗せる手立てにほかならない。
B型参加者価値曲線に乗せるには、絞り込まれた情報源や情報量の蓄積そしてその熟成化を意味する、入次数増大という一定の時間経過が必要となる。従って、ITを駆使したA型参加者価値曲線に沿うような手立てが、多くの研究機関には求められよう。
研究者の参加者価値を高めるA型とB型の、このような2つのアプローチが将来、トップ級アウトカムをもたらし、ひいては組織に財務面でも効果をもたらすことができれば、日本再生につながる。次回では、これらにつながる「アウトカム追跡のかぎ」について簡単に考察してみたい。

