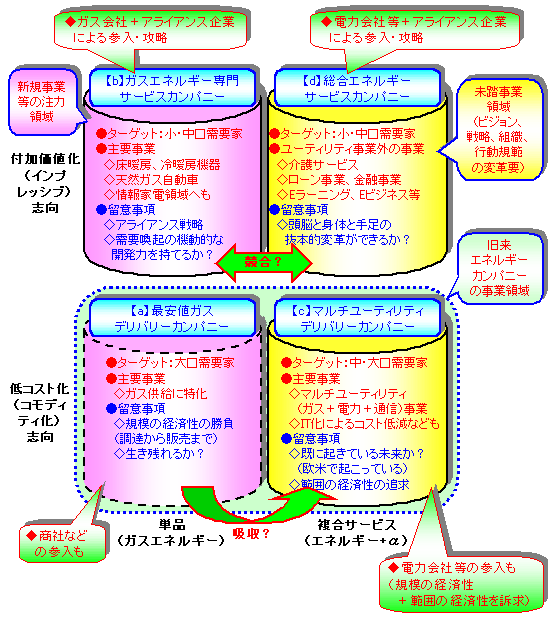掲載情報
"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第37回「エネルギー自由化と情報家電市場での攻防(下)――シナリオ別の勝敗の鍵」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2003年11月20日
(1)4つの戦略シナリオ別のポイント
前回は、「エネルギー自由化と情報家電市場での攻防」について、特に「SWOT分析」を試みた。
今回は、その結果を踏まえたシナリオアプローチのうち、その過程は省き(→具体的なシナリオアプローチの適用例としては、第34回と第35回を参照)、シナリオのみを示したい。
次の図表をご覧いただきたい。シナリオ策定の軸を、単品(ガスエネルギー)と複合サービス(エネルギー+α)、および低コスト化(コモディティ化)志向と付加価値化(インプレッシブ)志向とに分けて、4つのシナリオを例えば次のように描いてみた。
【図表】 4つの戦略シナリオ別のキーポイントと競合他社の出方
(出所)各種資料を基に日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成
● |
【a】最安値ガスデリバリーカンパニー志向市場シナリオ |
|
このカンパニーは、主力ターゲットを大口需要家とし、主要事業は最安値級のガスデリバリーサービスとしてガス供給に特化するものとなる。状況によってはCRMなどの手厚いサービスなどは一切不要であり、ともかく安いサービスが提供される。
ただ、価格競争力を持つには、調達から販売までを含むガスパイプラインにおける規模の経済性を十分発揮できるかが鍵を握る。大小229の現行ガス会社の うち、向こう5年から10年の間に、地元に根を張ってニッチビジネスとして生き抜くところもあるかも知れない。
一方で他業界、例えば、流通や金融、通信分野のように、エネルギー分野においても参入障壁が緩和され、商社などの本格的参入も相次ごうが、ガスエネルギー単品を主力とする事業者の寡占化は進んでいくことになる。
実際、英国では1948年ガス法による国有化以前の1,064社から86社(当初の8%)へ、フランスでは同様に1946年の電気・ガス法による国有化 以前の約500社から18社(当初の4%)へ集約化・吸収された。ビジネス環境の違いにより多少の程度の差こそあれ、わが国の場合も同様のことが起きるこ と必至であろう。 |
● |
【b】ガスエネルギー専門サービスカンパニー志向市場シナリオ |
|
同カンパニーの主要事業として、主力ターゲットを中・大口需要家とし、マルチユーティリティ(ガス+電力+通信)事業を大々的に行うパターンが想定される。
ユーティリティのマルチ化には、スケールメリット(規模の経済性)を発揮しつつ、それらサービスのデリバリーコストにおいても範囲の経済性を追求すべき ものとなるため、IT化によるコスト低減なども不可欠となる。その意味でここは、ガスも電力も含む旧来エネルギーカンパニーにとって、比較的地に足の着い た事業領域となる。
このシナリオは決して目新しいものではなく、欧米で生起しているパターンのように"既に起きている未来"を踏襲するものとなろう。 |
● |
【d】総合エネルギーサービスカンパニー志向市場シナリオ |
|
このカンパニーでは、主力ターゲットを小・中口需要家としたユーティリティ事業に加え、それ以外の事業として、介護サービス、ローン事業、金融事業、Eラーニング事業、Eビジネスなどまで手がけるパターンを想定した。
電気通信分野では、NTTがこれまでの地域会社における11万人相当の人材・人員を、全国約100の会社に放出し、考え付くあらゆるビジネスに目下取り 組んでいる。これを単に雇用の受け皿と見るか、あるいは、全国地域に浸透した膨大な人的ネットワーク、配送網、セキュリティーなどを含むさまざまなノウハ ウ・知見を活かした、新しい事業展開を行うための布石と見るか、その結果は数年以内に判明することだろう。 |
(2)もう1つの主戦場としての情報家電市場での攻防
最後に、エネルギー市場とは別の、あるいは同市場との連携で考えるべき、もう1つの主戦場としての情報家電市場での攻防について、それと関係のありそうなシナリオ【b】、【c】、および【d】について概観してみたい。
● |
【b】ガスエネルギー専門サービスカンパニー志向市場シナリオ |
|
ガス会社の導管へ、一般ガス事業者以外の新興競合他社も公平にアクセスできるようになることがより徹底される。したがって、このシナリオにおいて、これら 新興競合他社の中には、新日本製鉄や東京電力、三菱商事などのように、自グループに強いIT企業(システムインテグレーター)を抱えるところがある。
そのIT系企業の今後の情報家電分野でのノウハウ・知見の蓄積量は、ますます大きくなることが予想される。それゆえ、このシナリオのもとでは、多様かつ 激しい競争が展開されよう。このシナリオ下の適切な事業選定、投資判断に関する意思決定において、ゲーム理論的な基本的なアプローチや、この基本シナリオ のなかでの詳細な事業展開においてリアルオプションのカードを切ることができるような、いわばソフトウエアやマネジメントに関するノウハウの習得が今後、 一層不可欠になってきたようだ。
そして、特に小(家庭含む)・中口需要家市場では、ニーズも多様かつその変化の速いため、戦略パートナーとのアライアンス戦略を通じた、需要喚起の機動的な開発力を持てるかが競争の行方を決することにもなろう。 |
● |
【c】マルチユーティリティデリバリーカンパニー志向市場シナリオ |
|
マルチユーティリティのサービスデリバリーにおいて、規模と範囲の経済性をたやすく両立できそうな筆頭は電力会社だろう。
海外では米タコマパワー社が、自前で敷設した光ファイバーを利用し、そのネットワークを介した自動検針や負荷管理サービスを提供している。
また、UKデータコレクションサービス社は、ガス、電力、電話、水道等のユーティリティサービス全般のメータリングと決済サービスを展開している。同社 はSTAR DateService社が開発したSV90というシステムを利用しているようだが、同種のシステム利用によりわが国の電力会社などが、小口需要家および 家庭市場を、同業他社よりも手堅く制することもあるに違いない。
前回触れたとおり、上位3社平均でガス会社は、売上高にして電力の4分の1程度の経営(体力)規模にあるなか、ガス会社がこのシナリオを想定し勝ち抜くには、M&Aなどを通じた規模の拡大も必須となろう。
特に情報家電市場では、ガス、電力に加え、水道を含むユーティリティサービスが、家庭まで直接行き届いているため、その親和性が高い。これらユーティリ ティ提供の低コスト化を実現し、また米ミズーリ州電力会社Western Resourceが行っているようなホームセキュリティービジネスなども同時に提供できれば、このシナリオ下のビジネスとして、より戦略性が高まることに なる。 |
● |
【d】総合エネルギーサービスカンパニー志向市場シナリオ |
|
ガスや電力などの総合エネルギーサービス事業は、その事業推進者にとっては未踏の事業領域となる。したがって、その企業・事業ビジョンやそれを実現するための戦略、組織、行動規範に及ぶ変革(リノベーション)や革新(イノベーション)が、不可欠なものとなる。
米IBMは1993年頃から"サービスカンパニー"へと路線を転換した。とはいっても、EBITDAマージン(「営業収益+減価償却費」÷売上高)が直 近の3年間ほどで18%の高水準を維持しているのも、コンピューターハードウエアから、システム開発、ソフトウェア、OS(基本ソフト)、運用サービス、 コンサルティングサービスにつらなる「範囲の経済性」の実現による事業間のシナジー(相乗効果)を発揮しているからに相違ない。
あるいは、ウェルチ元会長が率いた米GEは、クロトンビルにあるリーダーシップ開発研修所に幹部を集め、GEの行動規範(企業価値)を徹底周知させるこ とをもって、さまざまな巨大事業が並行して動く大組織全体を、CEO並びにそれを支える幹部が1つのエンティティ(統一体)としてイメージでき、各自が適 切な行動をとれるようにした。ここにGEの凄さがある。新原浩朗氏がその著書『日本の優秀企業研究』(2003年)で同様のことに言及し、GEをむしろ日 本の優秀企業が共通にもつ"企業経営の原点 6つの条件"の例外としていることが興味深い。
情報家電領域を含め、このシナリオ下の企業行動原理は、"総合"である。わが国の総合電機が同EBITDAマージンでわずか5~12%に留まっているこ とを見ると、"総合"の2文字は最近では説得力を欠くようにみえる。しかしながら、新原浩朗氏によれば、その"総合"はこれまでのわが国の優秀企業たる条 件を否定するものではないようだ。
もしこのシナリオを描く企業において、頭脳とアンテナ(シナリオアプローチ+戦略)、身体(組織戦略+スタッフインセンティブ設計+行動規範の変革)、 および手足(導管ネットワークインフラ+IP通信ネットワーク+情報システム)についての抜本的変革ができるのであれば、将来にはこの"総合エネルギー サービスカンパニー&がこのquot;市場の覇権をもつに至っていよう。 |
以上、4つの戦略シナリオに沿って、そのポイントと、もう1つの主戦場としての情報家電市場での攻防について眺望した。
目下のところ、大手ガス会社には、アクセス情報等の目的外利用の禁止や他部門との内部相互補助を防止するための会計分離及び結果公表の義務付けなど、託送供給に伴う禁止行為が規定されている。上記シナリオの【c】や【d】の実現は、利害関係者間の競争状況をモニターしながら、段階的に実施されるなかのオプションに過ぎない。しかしながら、流通、金融、そして情報通信産業で現在起こっている流れを考えると、そうはずれたシナリオではないのではなかろうか。
こうしたシナリオを頭に描き、競争優位なポジションを確保・維持していくためには、内形的なインフラ、すなわちGEの例を出すまでもなく、組織や人に関する行動規範(企業価値)といったソフトウエアや、不確実性下の事業環境にあってのマネジメントに関するノウハウの蓄積と、その利用の仕方が問われている。2003年7月にいみじくも、"e-JapanⅡ"がスタートした。その主たるもくろみは、内外の(IP)インフラの"利用"にあるといえよう。
第36回 ← 第37回 → 第38回