"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第36回「エネルギー自由化と情報家電市場での攻防(上)――SWOT分析」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2003年11月20日
(1)ガス・電力分野の自由化の流れ
第35回では「シナリオアプローチで見る将来通信市場の行方」のうち、具体的な将来図を鳥瞰(ちょうかん)した。今回はガス・電力のエネルギー分野に今後起こるであろう近未来を概観してみたい。
2000年3月、電力の自由化がわが国でもスタートした。具体的には、電力量のシェアで26%相当の特別高圧 2,000キロワット以上(コンビナート、複数施設を有する工場、ホテル、デパート、大学、オフィスビル等)の部分自由化が行われている。現在三菱商事系のダイヤモンドパワーなどが特に大口需要家向けに奮戦している。しかしながら、売電会社が契約した電力量は電力市場全体の0.1%程度、対象電力量の 0.4%程度に過ぎない。
加えて今後、2004年4月をめどに同14%相当の 高圧B 500~2,000キロワット(中規模工場、中規模ビル・施設、スーパー等)を自由化、2005年4月を目処に同5%相当の 高圧A 50~500キロワット(小規模工場、小規模ビル・施設等)自由化、2007年4月以降に同23%相当の低圧50キロワット未満、6,000ボルトまで(町工場、コンビニ等)へ。
また同31%相当の電灯100~200ボルト(一般家庭・商店等)向けの検討を開始することになっている。しかしながら、日本における電力自由化はまだその緒についたばかりといえよう。
本稿ではエネルギー自由化(規制緩和)の流れの中で、電力に比べ業界規模が小さく、より激しく荒波にさらされる可能性の高そうな、ガス業界について分析を行ってみたい。
売上高で上位3社の平均を比べると、ガス業界は電力業界に比べその規模は4分の1程度に過ぎない(ガス業界上位3社の連結ベース平均売上高は2002年度で7,970億円、電力業界のそれは3兆3,700億円)。
一方、燃料電池による新しい需要の発掘やエネルギー業界での綱引き、あるいは家庭・需要家市場のIT化を巡り、それぞれの業界が今後大きな影響を及ぼし合うことが予想される。
次の図表は、LNG(Liquefied Natural Gas:液化天然ガス)の調達から提供までの流れだ。わが国の場合、1次エネルギーの供給量を原油換算すると、1999年度の同エネルギー構成比で石油 52%、石炭17.4%、原子力13%に次ぎ、天然ガスは12.7%であり、2010年には同14%程度に引き上げるとされており、大変重要なポジションを占める。
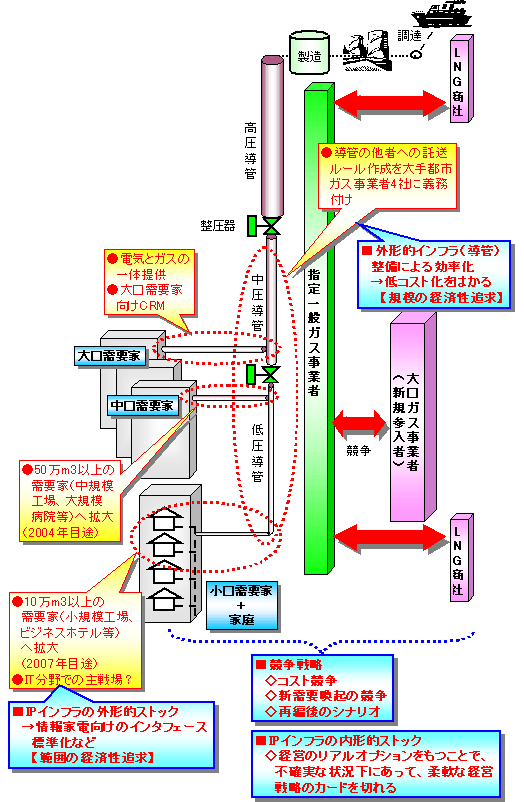
わが国のガス生産は、海外8カ国9基地の供給者からなる。そこから4,000~10,000キロメートルほどの海上輸送を経て、LNG受入基地から配給パイプライン経由で需要家にガスが提供される。このパイプラインは、ガスエネルギーデリバリーの生命線となっている。
一方、世界の天然ガス供給構造をみると、米国では主に国内供給者が5,000社ほどもあり、州際輸送パイプライン経由となる。欧州では域内・域外の違いはあるにせよ、欧州とその近隣大陸との間に張り巡らされた国際輸送パイプラインを通じ、需要地の受け入れ点から配給パイプラインを経て需要家へガスが提供される。
ガス自由化においては、英国が先駆けている。英国は111.6%の自給率を誇り、自由化レベルも100%に達する。これは1998年の自由化完了まで 16年もかけて段階的に実施したものだ。主な内容は、国営独占会社の民営化の一環として導管ネットワーク管理とガス販売を完全に分離(アンバンドリング)したことや、家庭用ガス供給まで自由化したことにある。一方、米国では、自給率は80%を超えた程度であり、自由化レベルは州によって異なる状況にある。
わが国では、導管の他者への託送ルール作成を大手都市ガス事業者4社に義務付けており、外形的インフラ(導管)整備による輸送等の効率化など、低コスト化をはかる規模の経済性追求が模索されている。実際、2002年10月に、東京ガス、静岡ガス、帝国石油は天然ガスパイプラインを静岡県内で連結する連携パイプラインを共同で建設すると発表。2006年末の完成時には延長33キロメートルに及ぶ模様だ。
また、大口需要家向けには電力会社から電気とガスの一体提供がなされており、CRMなどの仕組みも導入されている。ガス会社としては少なからず脅威ともなる動きといえよう。また、2004年を目途に50万立方メートル以上の需要家(中規模工場、大規模病院等)へ拡大するとされる。
一般ガス事業者以外による大口供給は、電力系(東京電力、中部電力、関西電力)、石油系(帝国石油、ネクストエネルギー、石油資源開発)、天然ガス・ LPG系(東北天然ガス、エア・ウォーター、岩谷産業)、製鉄系(新日本製鉄八幡製鉄所)、商社系(三菱商事)などの新規参入事業者を含め39件(新規うち参入者11社)となる。
さらに、2007年をめどに10万立方メートル以上の需要家(小規模工場、ビジネスホテル等)へ拡大するとなれば、この領域はIT分野での主戦場ともなるところであり、さまざまな利害関係者との攻防があるところだろう。そして、IPインフラの外形的ストックの整備状況、例えば、ガス導管ネットワークから、家屋・社屋に隣接して設置され、IP技術によりガス流量が制御あるいは遠隔監視できる燃料電池装置やガスメーター機器などの整備状況と、情報家電とのインタフェースにおける標準化が重要な鍵を握ろう【範囲の経済性追求】。
後述の戦略シナリオで見るように、規制緩和のなか新たな市場への参入も促されよう。電力もガスも、これまで地域独占的な状況のなか、同業同士はおろか、両業界間の利害が直接大きくぶつかることもさほどなかっただろうが、今後は各社の競争戦略の優劣が際立ってくるに違いない。
具体的にはコスト競争、新需要喚起の競争に加え、エネルギー業界再編後のシナリオをどのように描き、どうそれに対処できるかがポイントになる。そのとき、前述の外形的な(文字通りの)インフラに加え、IPインフラの内形的ストック、すなわち経営のリアルオプションをもつことで、不確実な状況下にあって、柔軟な経営戦略のカードを切れるかどうかが、より一層問われることになるだろう。
(2)戦略シナリオ策定のためのSEPTEmber-SWOT分析
ユーザーニーズ、消費者志向などの「Society」、市場競争などを含む「Economy」、規制などを含む「Politics」、「Technology」、地球温暖化対策などを含む「Ecology」から成る"SEPTEmber"と、強み・弱み・機会・脅威からなる"SWOT" によるアプローチを通じ、戦略シナリオ策定のための因子分析を簡単に行ってみよう。
SWOT別に主だった因子として、次のようなものを抽出した。
● |
強み(Strengthness) | |
|
◇ |
給湯需要量の予測によるエネルギー供給の最適化を通じたコスト低減(燃料電池システム) |
|
◇ |
家庭向け固体分子型燃料電池の普及、モバイル機器向けダイレクトメタノール型燃料電池の開発 |
● |
弱み(Weakness) | |
|
◇ |
効率的なユーティリティの供給(規模の経済性+電力会社の送電線利用等による範囲の経済性) |
|
◇ |
電力会社に比べての体力のなさ |
|
◇ |
他部門との内部相互補助を防止するための会計分離及び結果公表の義務付け等 |
● |
機会(Opportunity) | |
|
◇ |
マルチユーティリティサービスのニーズ |
|
◇ |
燃料電池市場でのガス会社の優位性(→2020年頃の電力会社の売上高半減か?) |
|
◇ |
10万立方メートル以上の需要家(小規模工場、ビジネスホテル等)へ拡大 |
|
◇ |
天然ガスは「環境負荷が小さく供給安定面でも優れたエネルギー」 |
● |
脅威(Threat) | |
|
◇ |
ガス、電力、電話、水道等のユーティリティサービス全般のメータリングと決済ニーズ |
|
◇ |
新規事業者の市場参入による再編加速(電力系企業、環境系企業) |
|
◇ |
不確実な将来需要見通しとなり長期契約引取り保証不能ゆえの新規LNGプロジェクト立上げ難 |
|
◇ |
競合他社によるホームセキュリティサービスの参入 |
さらに詳しい関係因子を、次の図表にまとめた。
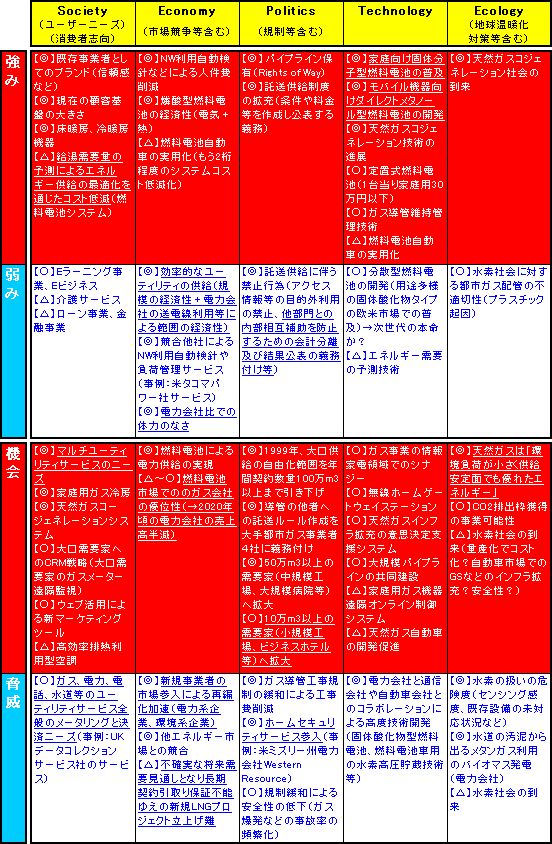
(出所)各種公表資料から日本総合研究所作成 ICT経営戦略クラスター作成
ガスエネルギーの自由化は、弱みや脅威の裏の側面も持ち合わせており、ガス業界には両刃の剣を突きつけられたかっこうになる。次の第37回では、こうした変化・変革因子をもとに、戦略シナリオ案を策定し、それぞれのシナリオでの勝敗の鍵や、将来の主戦場としての情報家電市場での攻防について概観してみたい。

