"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第35回「シナリオアプローチで見る将来通信市場の行方(下)――具体的な将来図を鳥瞰する」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2003年10月16日
第34回では、「シナリオアプローチで見る将来通信市場の行方(上)――決定因子を抽出する」について考えた。今回は、その続きとしてシナリオを描くための本質的な軸を抽出し、「具体的な将来図を鳥瞰」してみたい。
(1)4つのシナリオ(外部環境ストーリー)が起こりうる
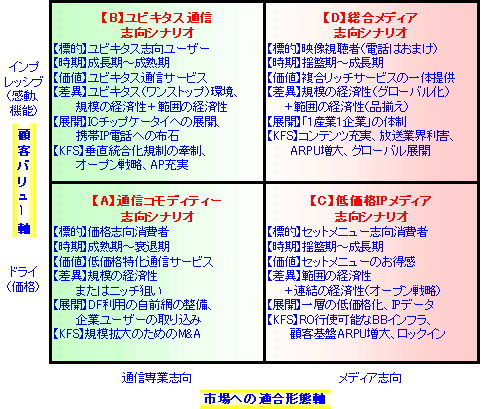
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成
「顧客バリュー軸」の程度・階層は、"インプレッシブ"(感動、機能)、"ドライ"(価格)とした。その中間には、"モデレート"(利便、信頼性)が位置づけられよう。縦軸はBtoC市場での消費者側に立ったものとなる。同様のことは1999年当時筆者が記した次のウェブページが参考になろう。
| 【参考】: | 「ICTマネジメントとは③」 http://www.jri.co.jp/service/special/content2/mg_ictmanagement/ |
これはちょうど、米ウィンダミア・アソシェーツの「購買階層」製品進化モデルと呼ぶ、製品性能サイクルの「機能→信頼性→利便性→価格」の4段階を参考にした。
また「市場への適合形態軸」を"通信専業志向"と"メディア志向"とした。横軸は同市場での供給者(キャリア)側に立ったものとなる。前者は、固定電話市場の今後のシナリオや、日進月歩で進展する次次世代の携帯電話市場のそれを予測するものである。一方、後者はブロードバンド志向の行き着く先がどこか、それは放送・コンテンツ業界との産業融合(Industrial fusion またはInter-industry convergence)を伴う領域なのか、といった視点である。
(注1)「産業融合」:競争関係のなかった従来の産業間で、相互に新たな競争が展開される状況のこと。情報通信産業以外には、エネルギー産業(電気、ガス、石油分野)、運輸産業(会場、鉄道、自動車、航空などの輸送分野)や、金融産業(銀行、証券、保険分野)にその例が見られる。
さらに、各シナリオにおける主要プレイヤー(通信キャリア)の適合度、すなわち当該シナリオにおいて自社の経営上のオプション(切り札)や経営資源との対比を想像した。
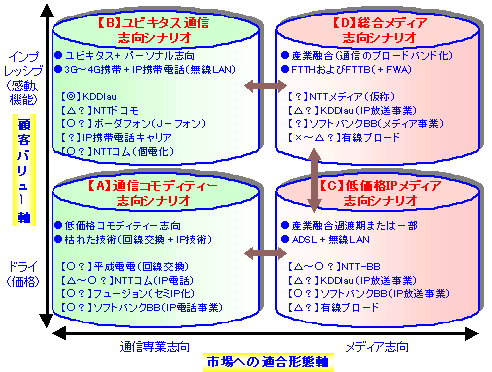
(注)「×→△→○→◎」:この順に適合度が高いと思われる。「3G~4G携帯」:第3世代または第4世代携帯電話。「FTTB」:Fiber To The Building(ビルまで光ファイバーを敷設)、「FWA」:Fixed Wireless Access(加入者系固定無線アクセス・システム)のこと。
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成
以上2つの図表で示した、将来(2010年頃)の4つのシナリオについて、その中身を例えばこのように見た。シナリオの前提となるマクロ経済環境については、現在、日本経済の行方に関し物議をかもしている、数名の論客の大胆ものを参考にした。
(注2)将来のマクロ経済環境については、副島隆彦氏(評論家、常葉学園大学助教授)、大前研一氏(経営コンサルタント)、小野盛司氏(理学博士、日本経済復活の会代表)、丹羽春樹氏(大阪学院大学教授)らの考え・発言や著作などを参考にした。
2004年7月、日本国の新紙幣が発行された。同時にデノミ(通貨単位の変更)が実行された。この新円切り替え後、消費者からは「財産税」(新札交換時の課税のこと)を通じ、自宅や郵便局などに眠らせたままのタンス預金約20兆円の10%以上が吸い上げられた。資産家ないし高齢者層へは、資産目減りのかたちで少なからず打撃となった。政治的に作られた景気ないし株価の水準は2005年頃には失速し、日用品(コモディティー)化したサービスに対する消費者の財布の紐は一層きつくなった。ただ同じ通信サービスであっても、人々に感動や驚きなどの新しい刺激をもたらすリッチなメディアへと変貌を遂げたサービスについては、財布の紐を新たに開く消費者も現れ、購買パターンは2極化した。
一方、企業への財産税についてはデフレ(不況)続きで、これ以上の倒産を回避するため、政府は隠し資産に対する課税に留めた。従って、多くの企業は難局を乗り切った。しかしながら、2003年には大銀行グループへ公的資金が投入されるなど、部分的国有化もなされ、さまざまな統廃合後の2010年には、多くの基幹産業部門でほぼ「1産業1企業」の体制となってしまった。国内競争においても、グローバルな競争においても、特にコスト競争の激しい分野では、これまでのスケールでは戦えなくなってしまったのだ。
通信産業においても例外ではく、消費者市場で生き残ったキャリアは固定電話市場、携帯電話市場、新ブロードバンドメディア市場で、各々2社程度しか生き残れない状況、あるいは大グループの傘下での事業存続形態を選択せざるを得ない状況となった。
以下のシナリオは、リアリティを出すために失礼ながら敢えて固有名詞を出しているが、あくまで架空のストーリーである。
(2)通信コモディティー志向シナリオ【A】
この時の通信キャリアは、商品・サービスの価格に敏感な消費者を標的(ターゲット)にせざるを得なかった。通信サービスの商品サイクルは成熟期から衰退期のままに留まり、市場は縮小傾向。サービスはさらにコモディティー化されていた。つまり、一定の品質さえあれば、電話はつながればよく、どこの事業者が提供してもまったくと言ってサービスの差は見出されなくなっていた。消費者からみたサービスの価値は、徹底して低価格に特化したものだった。
通信キャリアの競合他社との差異ポイントは、規模の経済性の発揮による生産コストの低減、または競合他社との競争がほとんど無いようなニッチ狙いとなる。平成電電が2003年当時行っていた回線交換による枯れた技術の徹底活用による直収ビジネスなどが、後者の例として生きながらえていた。これは巨人キャリアNTTと総務省間における規制緩和(相互接続のオープン化)の賜物であった。一方、フュージョンやソフトバンクBBなどは、安価なIP電話を武器に競争をしかけていた。
ニッチビジネスから規模の経済性を生かした事業展開には、安価なDF(ダークファイバー)利用による自前網の整備がなされた。そして、消費者向けサービスと同時に、やはり低価格戦略を武器にSOHOを含む中小企業ユーザーの取り込みが行われた。
このシナリオでのKFS(成功要因)としては、ニッチで行くか、生産コストの低減維持をはかるにあった。それにはネットワーク(顧客基盤)規模拡大のためのM&Aなどが有効であり、ニッチキャリアにもそうした高度な経営スキルが求められる時代となっていた。
叩き売り同然の交換機電話サービスのようなニッチビジネスに加え、ADSLとセットになったIP電話がこの時の主流のサービスになっていた。ニッチキャリアはある時からNTT圧力に翻弄された。IP電話などの事業の勝敗の分かれ目は、単価の安い顧客を十分獲得できたか、その基盤の大きさであった。
一方、NTT東西のようなレガシーキャリアでは、自前の交換機ビジネスとの間でカニバリズムが働き、このシナリオで十分な収益基盤を確保することは難しく、単なる電話事業からは撤退を強いられた。負け組である。他方、勝ち組は、IPインフラ上で低コストのサービスを提供でき、またいち早く損益分析点をクリアしたソフトバンクBBのようにところ、および消費者の需要に対して常に一定キャパシティを最も安い機器により確保しつつ、ベータ版レベルのサービスの適宜な市場投入により、顧客のリクエストをスピーディーに満たしたフュージョンのような企業であった。
(注3)「規模の経済性」:固定費が大きく変動費がほぼ一定であれば、ある範囲の生産規模で生産量が増えると、その商品・サービスの生産プロセスの中で平均費用が下がり始める(費用逓減)効果のこと。新規参入者の大きな障壁ともなる。
(3)ユビキタス通信志向シナリオ【B】
同じ通信専業の形態をとっても、携帯電話キャリアは固定電話キャリアとは異なり、標的をずばりユビキタス志向の消費者とした。携帯電話の契約者数は 2003年には8,000万弱で頭打ちとなり、2010年には成長期をとうに過ぎ成熟期の後半にあったからだ。ユビキタスという新しい市場を開拓する必要に迫られていたのだ。
キャリアが消費者へもたらす提供価値は、ユビキタス通信サービス。昔はワンストップサービスと言われたものが、技術革新により今ではすっかりユビキタスな通信環境を消費者に提供できた。つまり、消費者はどこか1つの窓口(ワンストップ)を通じ所望サービスを手に入れるというよりも、プレゼンス技術などの浸透もあって、ユーザーの居場所、または通信を受けられる時間かどうか、あるいは健康や心理面での状態(プレゼンス)に応じ、ユーザーが意識せずにサービスにアクセスできる、もっといえば所望サービスに囲まれているといった環境が整った。
この環境をキャリアが提供し競合他社との差異化ポイントとなるのは、数千万の顧客基盤をレバレッジ(梃子)とする規模の経済性に加え、同一設備によりさまざまなケータイサービスを安価に提供できるための範囲の経済性を手に入れたかどうかだった。
(注4)「範囲の経済性」:複数のサービスや事業を同時に、多角化した企業の内部で行う場合のコストの方が、それら事業を別々の企業が担当した場合にかかるコストの総和よりも低くなる現象などのことで、補完性が問題となる。
顧客基盤の一層の強化には、FelicaやタイプBなどの非接触ICチップを組み込んだケータイへの展開により、iモードなどのデータ通信サービスとは別の収益源を確保するに至った。また、レガシーキャリアにとっては諸刃の剣にもなりかねない、携帯IP電話への布石の仕方が鍵を握った。
IP化の流れはユビキタス通信分野においても不可避であった。3G以降のケータイ端末では「Brew」採用など、IPパケットが通るネットワークが不可欠となった。そして、キャリアで異なり、かつ点在するホットスポットのみしか当初利用できなかった無線LANは相互に連結しあい、しだいに面的な広がりを見せ、都心部ではほぼ全域をカバーした。結果、ケータイIP電話が大きな存在感を示し始め、レガシーな携帯網からの置き換えもかなりの程度進んだ。携帯キャリアはもはやIPケータイを無視することはできなくなっていた。
(注5)「Brew」:Binary Runtime environment for Wirelessの略。米クアルコムが提供するcdmaOne/CDMA2000携帯電話向けのアプリケーション開発プラットフォームのこと。ウェブサーバー上に置いたプログラムを、ブラウザフォン・サービスを使って端末にダウンロードして実行する仕組みとなっており、端末のチップセットに直接アクセスできる分、Javaよりも高速で高機能なアプリケーションの開発が容易。また、HTTPしかサポートしていないMIDP(携帯向けJava規格)では分単位のサーバーへの確認が必須であるのに対し、IP上にSocketプログラミングを行えるため、情報をプッシュで受け取れストリーミング映像を流すことも可能。さらに、端末にIPアドレスが振られるため、キャリアのゲートウェイを意識せずに、外のサーバーと通信が行えるなど、IPパケットが通るネットワークが構築できる。
データ通信に加え、コンテンツ分野まで触手をのばし(AP充実)、範囲の経済性を追求したこと、さらにICカードのイシュアー(発行者)にもなったことで ARPU上乗せ余力が高まり、NTTドコモらが規制当局から超過利潤を槍玉にあげられることもしばしばあった。垂直統合化規制への牽制は、このシナリオの KFSとなった。時代はNTTドコモのクローズドな戦略に反し、欧州のGSM携帯電話市場では当り前となっていた、端末とサービスの分離などのオープン戦略が支配的になっていた。前述の「Brew」採用などオープン戦略を徹底したKDDIauが、トップシェアのNTTドコモの牙城を奪っていた。
(4)低価格IPメディア志向シナリオ【C】
メディア志向の市場では、ADSLやFTTHなどのブロードバンドネットワーク上で提供される、IP電話と各種コンテンツなどのセットメニューを低価格で購入できることが求められた。この低価格IPメディア志向市場は、2010年には揺籃期を越し成長期を迎えていた。特に揺籃期では経路依存性(パス・ディペンデンス)が問題になった。
(注6)「経路依存性(パス・ディペンデンス)」:歴史的な偶然として一旦、市場の揺籃期にある経路に落ち込んでしまうと(ロックイン)、そこから出ることが難しい状況・性質のこと。たとえ不合理なものであっても、いつも合理的なものが生き残るわけではなく、この状況にはまり込んでしまう(あるシステムに組み込まれる)と、そのシステムを使うことの効用が増加し(ネットワーク外部性)、その不合理は継続・拡大していくことになる。
キラー機器となったのは、自宅用に加え、ホットスポットやモバイル環境でも仕える、個人向けポータブル映像受発信アシスタンス(仮称:PVA=Portable Video Assistance)であった。大きさはPDA(パーソナルデジタルアシスタンス)程度のハンディ機器に受発信機能が付いており、オンデマンドでもリアルタイムでも使え、有機EL素材でできた折り畳み可能な超薄型の画面(ディスプレイ)とつながっているようなものだった。
さしずめポータブルテレビと携帯電話機の間ようなIPモバイル端末であり、無線LAN環境下で映像を楽しめる。家族や友人の様子だけでなく、ペットやデジタル家電の状態(セキュリティーを含むプレゼンス)も把握できる。ハードウェアは携帯電話並みの価格が決め手となった。IPテレビ電話とゲーム画像や映画など、さまざまなサービスがセットメニューのかたちで手軽に楽しめ(範囲の経済性の追求)、サービス価格のお得感も手伝い、消費者の新たな購買意欲を大いに刺激した。これまでの映像コンテンツと電話サービスとの産業融合の一面を見ることになった。
この時の供給者側の主役は、端末まで自社のコントロール(垂直統合)化に置く携帯電話キャリアではなく、PVAメーカーとのオープンなアライアンス戦略をとった、NTT-BBやソフトバンクBBのような新興キャリア(またはメディア事業者)であった。
競争優位性は、連結の経済性の追求のもとオープンなアライアンス戦略を駆使した事業展開のスピードと一層の低価格化にあった。これについていけないキャリアは次々と脱落していった。
(注7)「連結の経済性」:異なった企業間での経営資源の共有関係で生み出される効果。アライアンス企業間でのバリューチェーンの一部共有化による費用の節約に加え、新規事業の創造などにもつながる経済性概念。>
顧客基盤拡充によるARPUの増大などを目指す際の事業のKFSは、市場の揺籃期において早期にクリティカル・マスを獲得した非最適な戦略や技術が採用され(過剰転移)、さらに持続的なロックイン(過剰慣性)、つまり、消費者の行動を変えるのにかかる費用をスイッチング・コスト、それを利用して相手の行動を自分に有利になるような行動から変えられなくし顧客を囲い込み、長期的な関係を構築するかにあった。このためには、経営のリアルオプション(RO)の行使が可能な、すなわち環境変化に応じスピーディーで柔軟な事業展開がIP技術ベースのブロードバンドインフラの整備・獲得が鍵を握った。
(注8)「リアルオプション」:不確実性の高い事業環境下の投資において経営が持つ選択権(オプション)のことであり、金融工学におけるオプション理論を実物資産やプロジェクトの評価に適応したアプローチとなっている。
次の図表に、機能複合化などの軸とサービスエリアまたは顧客基盤の大きさを軸とした平面上に、4つのシナリオと経済性およびリアルオプションなどの関係を示した。
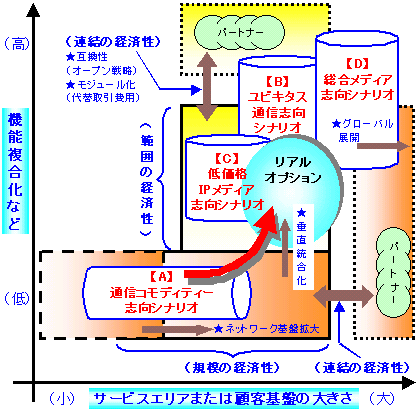
おおむね、【A】通信コモディティー志向シナリオは図表の中央下辺りに位置付けられる一方、その他3つのシナリオについては図表の右上側に位置することになる。つまり、将来の通信キャリアの主戦場がこれらシナリオの通りだとすれば、この位置で戦い勝つためのオプション(経営環境の不確実性に応じ切ることのできる手持ちカード)をいつもで行使可能なことが、求められよう。
具体的には、ネットワーク基盤やグローバル化などの拡大に伴う規模の経済性や、同一設備を用いた機能の複合化(垂直統合化)を志向する範囲の経済性を発揮する仕掛けを基に、新たに連結の経済性の発揮がメディア志向市場では鍵となろう。すなわち、通信事業者とパートナー間で相互に異質な経営資源を共用することで、資源そのものの代替取引費用の低減化やスピードを買うなどの際、やり取りされる資源のモジュール化が進んでいれば、当事者間でシナジーを期待できるというものだ。
(5)総合メディア志向シナリオ【D】
IP 技術ベースのインフラには、あらゆる情報が効率的に乗る。映像コンテンツはこれまで放送事業者の独占的なキラーサービスであった。しかし、2010年には産業融合(通信のブロードバンド化)がすっかり進んでおり、新たなメディア産業が生まれていた。通信キャリアの定義は変わり、もはや音声を運ぶ(carry)するだけの役割はとっくの昔に終わっていた。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れなくてはならない。その皮袋とは産業融合した市場にあった。
産業融合下の情報通信事業者(メディアオペレーターと呼称)のターゲットは、映像視聴者(電話はおまけ)にあった。産業融合の段階は、特に既存の放送業界との軋轢もあって、2010年においても揺籃期から成長期にさしかかっていた。つまり、前述の通り、経路依存性がこの市場の明暗を分ける状況下にあった。
IT分野では韓国の後塵を拝し続けたわが国が、IP技術により放送と通信の意味が無くなった時代にあって、産業融合市場においては世界の先駆者となるため、規制当局はわが国の情報通信産業全体の利得を最大にするための行動に出た。このことは、極めて合理的なものであった。しかしながら、市場揺籃期の鍵を握る経路依存性は、非合理的なことさえ、ある時点でロックインされうる(さしずめ、ボウリングの玉がガーターにはまって抜けられない)ことを示す。
つまり、どのような将来が実現したかは、規制や業界からの反発・確執、キラー商品やキラーサービスの行方など不確実性の高い要素が多く、今にして思えばよくもこの市場が立ち上がったものかと関係事業者は思ったものだ。ここでの最大の影響因子は、新しい産業融合を目指す政策的な観点からの誘導であった。
例えば、このシナリオ実現には、消費者にとってFTTHや高速無線LANなどの超高速ネットワークが手軽に得られる(使える)ユビキタスなブロードバンド環境が不可避になった。そのためには、供給側からさまざまなコンテンツやアプリケーションの創出が求められた。これには、物理的なネットワーク層の上でのダイナミックな競争環境の整備が効を奏した。2010年頃には、光FP(ファシリティプロバイダー)なる事業者が政府の公的な支援もあって、そのバックボーンやFTTHの整備に当たっていたからだ。
(注9)「光FP」:第31回「NTTの再再編問題を考える(下):各プレイヤーの利得最大化のゲーム」で示した「光0種FP」については、あらためてその守備範囲をFTTHなどのアクセス系ネットワークまで含めることが、わが国の情報通信産業あるいはこの産業融合を創出させるためには重要な課題であろう。光FP創設については、その事業の規模の経済性(費用面からみた統合の経済性である劣加法性の十分条件)と範囲の経済性が共に認められるのであれば、競合他社との二重投資的な意味が含まれる競争よりも経済的規制のもと、独占的な供給が効率的生産、および他国に先駆けいち早く戦略的なITインフラを整備するという2つの観点から正当化されうるはずである。
メディアオペレーターは、規模の経済性(グローバル化)と範囲の経済性(品揃え)を同時に追求することで、巨大化していった。わが国が戦略産業を育成するにあたり、自ずと「1産業1企業」体制化の途をたどることになった。国内市場に限定すれば寡占的または独占的な市場となっているが、経済成長の著しい中国をはじめその他アジア圏を新たな舞台とした、新しい企業群が誕生しつつあった。
アジア圏への事業展開では、同一組織内での異なる文化的要素のマネジメント能力が問われた。例えばそれは、豊富かつローカル色も加えたコンテンツの調達に関するノウハウ(著作権問題など含む)や、米AOL・タイムワーナーにおいて2003年当時に業績が失速したAOL部門の問題、あるいはイタリアの新興総合メディア企業(e.Biscom)などのARPU増大のビジネスモデルなど、成功・失敗の数々のケーススタディーから得られたものだった。そのため、このメディアオペレーターは設立当初から、異なる文化や感性やスキルをもった人材を集めた組織作りに成功し、世界に通用するグローバルカンパニーの誕生を見るようだった。
このグローバルカンパニーないしその総合メディア事業が、現在のKDDIau(IP放送事業)、ソフトバンクBB(メディア事業)、有線ブロードなどの企業から生まれるものなのか、それともNTT再再編の後に生まれるNTTメディア(仮称)といったような、これまでとは狙いの異なる企業から提供されるものなのか、前回でみたさまざまな「分岐因子」が左右する。
以上は、BtoC市場でシナリオを概観したものである。シナリオアプローチではどのシナリオにどの程度の確度をもって実現するかは、必ずしも重要視しない。重要な点は、どのシナリオが起こっても、それらにうまく対応できるように、現在の戦略を練り備えることである。従って、常に「共通トレンド因子」と「分岐因子」の洗い出しとその重みを測っておくことが求められる。
BtoB市場では、企業ユーザーの自社情報システムとモバイル(ユビキタス)環境を連結させるなど、斬新な試みがなされ、また将来の競争優位性の鍵を握るコラボレーションなどの取組みには映像アーカイブなどの仕掛けも不可欠となってこよう。BtoB市場について、あるいはBtoC市場の上記シナリオを、各プレイヤー(通信キャリア、通信機器メーカー、放送事業者、コンテンツ事業者、規制当局など)の立場で、もっと細かく精度を高めること、一層の具体化イメージをもつこともできる。機会があれば、そのうちの幾つかでその試みを行ってみたい。

