"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第34回「シナリオアプローチで見る将来通信市場の行方(上)――決定因子を抽出する」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2003年10月9日
(1)産業構造の転換期には不確実性の要素が高まる
日本経済新聞紙上で、2003年9月29日から「電子復興:第1部-脱"総合電機"」なる興味深い特集が5回にわたり行われた。その中で、総合電機の解体・統合が進み、「日の丸通信連合」が近く実現する可能性について論じている。この壮大な構想の実現に向け、昨年12月、経済産業省商務情報政策局長が、実際、日立、富士通、NECのトップ3人と個別に会ったという。
エレクトロニクスや通信産業においても、大きな転換期を迎え何が起きてもおかしくない時代となった。不確実性の高いビジネス環境に今、日本企業は置かれている。第32回と第33回で触れたIIJやCWCなどのケースを「すでに起こった将来」として念頭に置き、今回はシナリオアプローチによって、よりダイナミックな展開を見せるであろう将来通信市場(IT市場)の行方を概観してみたい。
そもそもシナリオアプローチ手法は、第2次世界大戦後、米軍のシナリオ研究に寄与した未来学者ハーマン・カーンが1960年代に、企業の経営戦略手法として応用し始めたとされる。この手法は、SRI(スタンフォード研究所)のピーター・シュワルツが、当時石油メジャーの下位企業に過ぎなかった、英蘭合弁のロイヤル・ダッチ・シェル社からの委託を受け(後にスカウトされ)たことを契機に、本格的に経営戦略へ活用されるようになった。
ピーター・シュワルツは1970年代に起きた2度の石油危機後の石油価格暴落を的中させ、同社をセブンシスターズ(石油メジャー)の上位企業へと押し上げる立役者となった。これでシナリオ分析は、一躍脚光を浴びることになった。
シナリオアプローチの基本は、『シナリオ・プラニング』(1998年)の著者である、英国グラスゴーのストラスクライド大学キース・ヴァン・デル・ハイデン教授またはその訳者でもある西村行功氏によると、MECE(ミーシー:Mutually Exclusive Correctively Exhaustive)に従って、まずは重複すること無く全体集合として漏れ無く、市場支配因子を抽出することから始まる。以下、この両氏の考え方などを参考にした。
(2)シナリオ策定の前の市場支配因子を抽出する
次の図表をご覧頂きたい。これは今回、通信分野のうちB2C市場に絞り、「セプテンバー」(SEPTEmber)、すなわち、Society(社会・文化)、Economy(経済・市場)、Politics(政治・規制)、Technology(科学技術)、Ecology(地球環境)のマクロ環境因子を横軸に、そしてマイケル・ポーターの「5フォース」を縦軸にしたマトリクスにおいて、市場支配因子(ドミナンツ)を抽出したものである。
(注1) シナリオアプローチにおいて、市場支配因子を抽出する際、もう一方の軸に通常必ずしも「5フォース」を持ってくるわけではない。
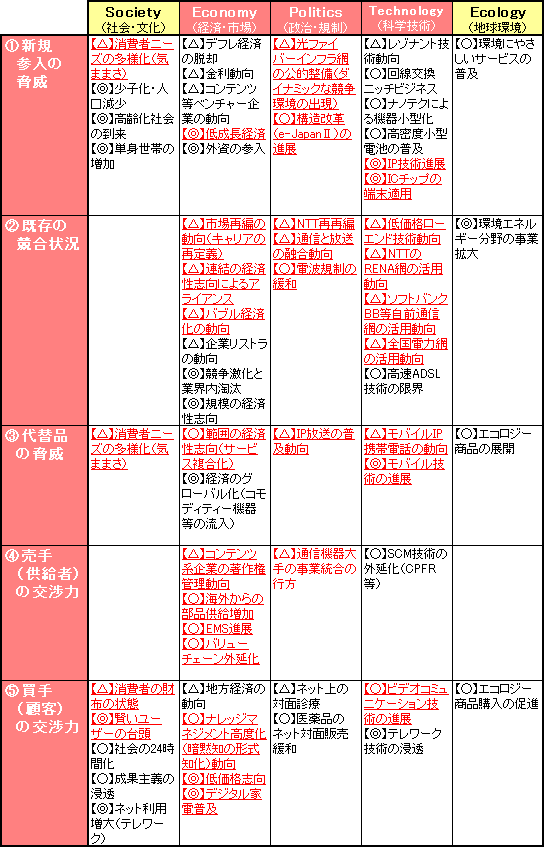
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成
本来であれば、シナリオアプローチでのこれら市場支配因子については、複数人の関係者・専門家により多面的に抽出すべきものであるが、ここでは筆者の日頃のコンサルティング現場での経験や知見により、大まかなものを列挙した。
そもそも現下の不確実性の高いビジネス環境を乗り切る、このシナリオアプローチとはどのようなものか。
(3)不確実性を乗り切るシナリオアプローチとは
前述のキース・ヴァン・デル・ハイデン教授らによると、「予測」が社会・産業の方向性(トレンド)に着目するのに対し、「シナリオ」ではトレンドと不確実性の両方に着目した上で描ける、起こりうる将来ビジネス環境についての複数ストーリーのことである。
人口動態などの持続的変化が統計的に見込めるような例を除き、不確実性の高い事象(未来)を予測しても大概当たらない。筆算にもいろいろ苦い経験が少なくない。もちろん、予測する場合の多くはクライアントなどから請われて行うものであるから、その時は仕方なしに「この予測手法には、幾つかの前提が必要であり、その前提が狂えば自ずと結果も変わってきますよ」といったことを付け加えるのを忘れないのだが…
「前提」とは、予兆(EWS:Early Warning Sign)に基づく市場支配因子的なものである。こうした予測のもと戦略を策定することがセットで行われることが多い。ここで「戦略」とは、自社スタッフらがトップマネジメントのビジョンを踏まえ、外部環境分析(例:3C分析)と自社の内部資源分析(例:強み・弱み分析)によるSWOT分析など行った上で、目標達成のための計画や手段の方向性を決定していくことである。その後の実行手順はライン部門に任せ、スタッフは計画の実行状況をチェックするに留まる場合が多い。
(注3)「SWOT分析」:企業の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)の全体的な評価手法。
「戦略」とは、自社のこうしたいという願望であり、これが強過ぎ固執し続けると、前提から乖離した環境変化に応じられないことが少なくない。経営戦略のポイントは、これまでのような機械的・硬直的な戦略策定とそのモニタリングではなく、将来結果的に対処せざるを得ない事態へのリアルオプションを持てる柔軟な戦略策定にある。
(3)シナリオアプローチにおける決定因子とは
では、不確実な事業環境のもと柔軟な戦略とそのアクションを行うために、準備しておくべきシナリオを考えてみよう。
不確実性の比較的小さい場合の「共通トレンド因子」と、それが大きい場合、すなわちシナリオの時間軸上の要所においてそのシナリオの経路に影響を与えうる「分岐因子」に分け、「不確実性・インパクト」マトリクスにおける決定因子のマッピングを次の図表で行ってみた。
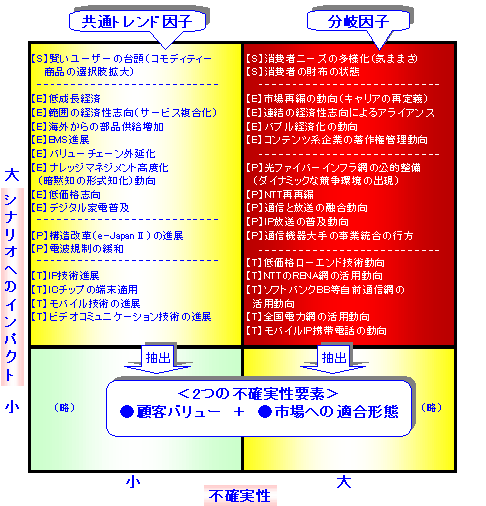
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成
これら因子を、前述の市場支配因子を抽出する際に分類した方法に従って、特にシナリオへのインパクトの大きそうなものを列挙したので、その若干の補足を行いたい。
まず「共通トレンド因子」、すなわちほぼ確実に起こる因子について
|
● |
【E】(経済・市場動向): まず、「低成長経済」は今後もしばらく持続すると思われる。 |
(注5)「範囲の経済性」:複数のサービスや事業を同時に、多角化した企業の内部で行う場合のコストの方が、それら事業を別々の企業が担当した場合にかかるコストの総和よりも低くなる現象などのことで、補完性が問題となる。
|
● |
【P】(政策・規制動向): 2003年7月に発表された「構造改革(e-JapanⅡ)の進展」はわが国では大きな支柱になっている。 |
|
● |
【T】(技術動向): これまでの回線交換技術から「IP技術が進展」し続けるのは時代の趨勢になった。また、「モバイル技術は今後も目覚しい進展」を遂げるだろう。 |
次に「分岐因子」、すなわち不確実性が高く現下の予兆をどう読むかによって、将来準備すべき戦略が大きく異なる因子について。
|
● |
【S】(主に消費者の動向): 気ままで移ろいやすい「消費者ニーズの多様化」はいつの時代も供給者泣かせである。 |
|
● |
【E】(経済・市場動向): 固定電話の収入減少が続き、情報をエンド・トゥ・エンドで橋渡しする「キャリアの再定義」が求められるなど通信市場再編の動向に関係者は大きな関心を寄せている。 |
(注6) 「連結の経済性」:異なった企業間での経営資源の共有関係で生み出される効果。アライアンス企業間でのバリューチェーンの一部共有化による費用の節約に加え、新規事業の創造などにもつながる経済性概念。
|
● |
【P】(政策・規制動向): 本稿の冒頭で触れた「通信機器大手の事業統合の行方」は興味深い。対象となる各社が短期的には利益を出せる体質に変革できたとしても、無効10年間を戦って勝つだけの準備はどうか。 |
|
● |
【T】(技術動向): クリステンセン教授が『イノベーションのジレンマ』で論じた「低価格ローエンド技術動向」はゆっくりと現下のハイエンド技術の領域に忍び寄り込む。いつその主役交代が起こるか常に予測できるばかりのものではない。 |
以上、通信市場ないしIT市場の将来シナリオを左右する決定因子を抽出してみた。多くの因子が予兆として観測できるなか、シナリオを描くための本質的な軸は何か。
次の第35回は「シナリオアプローチで見る将来通信市場の行方(下)」とし、その軸を仮定しシナリオに沿った具体的な将来図を鳥瞰してみたい。

