"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第33回「市場クランチと企業の競争力(下)――CWCの経営破綻を分析する」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2003年9月12日
前回(第32回)では、市場クランチと企業の競争力について、IIJが宿敵NTTの事実上傘下となったことについて考察を行った。市場争奪戦はビジネスウォー(戦争)であるから、厳しい現実もある。しかしなぜ、IIJグループほどの企業が、このような事態に直面せざるを得なかったのか。
(1) IIJグループ(CWC)はいかに競争力を失墜させたか?
伝統的な産業組織論では、独占または寡占市場における競争上の問題を経済学的に考察する。当初、産業組織論が専門であったハーバード大学教授マイケル・ポーターは、企業の経営戦略において特に競争戦略問題を「5つの力」により分析した。
次の図表をご覧頂きたい。本稿では「5つの力」を、「業界内の競争関係」と「バリューチェーンに連なる力関係」に大別した。
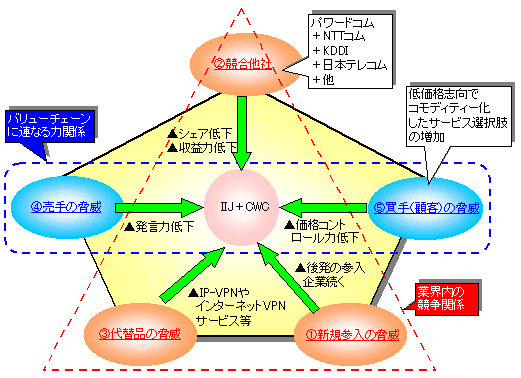
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
業界内の競争関係を、「①新規参入の脅威」、「②競合他社」および「③代替品の脅威」で示すことができる。
IIJやCWCは、インターネット接続サービスやIP系企業データ通信サービスでは先発組であった。CWCは1999年4月の広域イーサネットサービスの開始当時、「市場はポッカリ穴があいており」、いわば競争的独占状態を享受していたといえよう。しかしながら、ミクロ意経済学の教えるところは、超過利潤のあるところには必ず、新規参入がありその利潤を食い合うこととなる。
実際、同市場へ1999年10月に新規参入したNTTコミュニケーションズに加え、パワードコム、KDDI、日本テレコムなどの「競合他社」の参入が相次いだ。CWCは「新規参入の脅威」にさらされた。
また、CWCの広域イーサネット商品(広域LAN)は当初、価格面やサービスの斬新性などの点で差別化要素があったが、やがてIP-VPNやインターネットVPNサービス等の「代替品の脅威」にさられることとなった。
CWCの当初の競争的独占状態では、サービス価格を少々値上げする、あるいは高値設定であっても、そのサービスに特徴があったため、多くの顧客はそのまま同社のサービスを購入し続けたことであろう。ただ市場がより競争的になるにつれ、顧客の一部は競争相手が提供するより安価な類似サービスに流れたことだろう。インターネットVPNなどのサービスはその典型となる。
次にバリューチェーンに連なる力関係を見ると、業界内の競争関係においてその相対的な地位の低下が進むにつれ、売手(回線提供者など)への発言力低下を招き「④売手の脅威」にさらされる。他通信キャリアから追加的な長期回線使用権であるIRU (Indefeasible Right to Use:破棄し得ない使用権)を獲得するにしても、その価格をCWCに有利に設定することが難しくなった状況も予想される。
(注)
「IRU」: 従来、第一種事業者の通信ケーブルは自社で敷設していたが、数十年に渡る資産譲渡を前提に他社のケーブルを使って第一種事業を行うための権利。管理や通信事業に供する際の手続きなどは全て借り手である通信事業者が行うため、保有者が開放しやすいなどのメリットがある。
さらに競争が進展すると、商品の差別化要素が一層無くなり、市場では類似サービスの低価格志向が進み、顧客側ではコモディティー化したサービス選択肢の増加もあり、「⑤買手(顧客)の脅威」にさらされる。つまり、顧客企業への価格コントロール力が低下するといった事態となる。
(2)IP通信市場の激しい揺さぶり(クランチ)に付いて行けなかったのか?
前述とおり1999年4月にサービス開始をするに当たり、CWCは旧テレウェイが高速道路沿いに張り巡らせた光ファイバーをIRUで取得し、DWDM(超高密度多重伝送)とSONET(同期光ネットワーク)技術でインフラを構築。高速バックボーンサービスを1.5メガ~600メガビットの4品目に絞り込み、距離区分も200キロ以内~600キロ超までの3段階にシンプル化。既存事業者とは一味違う方式を打ち出していた。
その料金体系は他の事業者への脅威だった。東京・大阪間(470キロ)を1.5メガビットでつないだ中継回線料金が30万円。45メガビットが360万円、150メガビットが720万円という、当時の業界常識を覆す破格の料金を設定し、価格破壊の先陣を切った。
1999年10月、NTTコミュニケーションズにキャッチアップされたが、同年12月に45メガビットを33%、150メガビットを25%、600メガビットを17%値下げし、依然、価格優位性を保った。
また、バックボーンサービスに次いで広域LANサービスも開始。従来、本社を中心にポイント・ツー・ポイントでスター型に構成されていた企業内ネットワークを、ポイント・ツー・マルチポイントの"面 "としてプラットフォームに統合。通信料金も距離に依存せず、接続ポイント数や利用帯域に応じる体系にした。
CWCが広域イーサネットを開始した当時から2003年8月までの間、通信業界ではIP技術革新が急速に進み、いわばIP通信市場では激しいクランチ(市場の縮小)による撹乱要因がもたらされた。
競争的独占モデルでは、製品や技術に差別化要素があることを前提とする。差別化要素のない企業は、新規参入の激化で、利潤ゼロの価格に直面することになる。たとえ採算割れ販売などを行えたにせよ、大概長期の均衡状態を維持できるものではないため、より高い固定費負担を負った生産者から順番に倒産に追い込まれ、次第に淘汰、撤退に追い込まれる。
採算割れ状態をしばらくの間維持できるのはNTTなどのレガシーキャリアぐらいであり、ベンチャーなどができる代物ではない。実際、IIJもCWCも価格設定においては当初、前述の通り、競合他社との比でかなりの高値設定を行っていたはずだ。非競争状態を創り出し続けることがベンチャー系企業には不可欠なポイントとなる。
では競合品の参入をいかにして合法的に阻止するか。参入障壁をつくるか。
参入障壁には一般的に、学習曲線、標準化、排他的ネットワーク性などを挙げることができる。しかし、CWCは、これら要素が時間を追うごとにどれも際立つほどのものを創出・維持できかった。あるいは次第にその要素は色あせていったことが考えられる。
次の図表をご覧頂きたい。
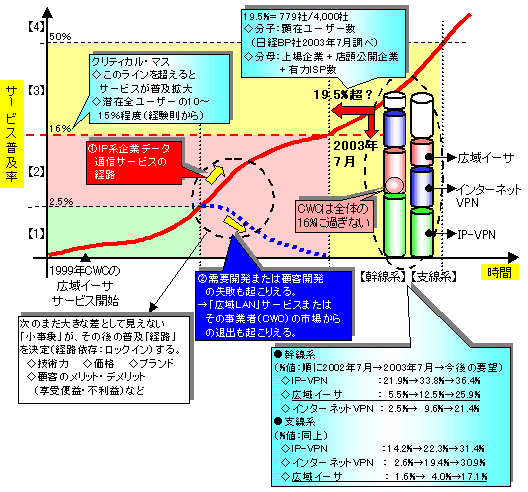
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
時間軸に沿ったサービス普及率に注目したい。ネットワーク外部性が働く通信サービスにおいては、その普及率でクリティカル・マス(経験則から潜在全ユーザーの10~15%程度)を超えるまでの間が勝負だ。企業は2つの岐路に直面する。
(1)IP系企業データ通信サービスのポジティブな経路に連なることもあれば、(2)需要開発または顧客開発の失敗も起こりえる。つまり、「広域LAN」サービスまたはその事業者(CWC)の市場からの退出も起こりえる。
2つのどちらかについては、その時期にまだ大きな差として見えない「小事象」(技術力、価格、ブランド、顧客のメリット・デメリット享受便益・不利益など)が、その後の普及「経路」を決定(ロックイン)する。
クリティカル・マスを超えるとサービスが普及拡大していく。2003年7月にIP系企業データ通信サービス市場は、日経BP社のアンケート調査などのデータから、普及率19.5%(=779社/4,000社)を超えていると思われる。
同サービスの利用実態のうち幹線系では、IP-VPNが2002年7月に21.9%であったものが、2003年7月に33.8%、また同アンケートで今後の利用の要望は36.4%であるのに対し、広域イーサネットでは順に5.5%→12.5%→25.9%だ。インターネットVPNは同2.5%→ 9.6%→21.4%である。IP-VPNの大きな躍進が見て取れる。また、幹線系においても、安価ではあるがバックボーンにインターネットを使う、インターネットVPNも健闘している。
支線系では同様に、IP-VPNが同様に14.2%→22.3%→31.4%であるのに対し、インターネットVPNが2.6%→19.4%→30.9%である一方、広域イーサネットは1.6%→ 4.0%→17.1%に過ぎない。
このようにCWCの主力商品である広域イーサネットは、当初の「ポッカリ穴があいており」の状態から、他類似商品に比しその商品の魅力度を相対的に減じていった。しかも、CWCは幹線系市場全体の16%に過ぎない。これではキャッシュを稼ぎ出すのは厳しい。
(3)外部環境変化と並行して進行する内部要因の変化と問題の顕在化
ここまでは、CWCのビジネスを取り巻く市場環境を中心にみてきた。次は、BSC(バランス・スコア・カード)とスライウォツキーの「プロフィットゾーン」の考え方を参考に、同社の内部的側面に目を転じる。次の図表をご覧頂きたい。
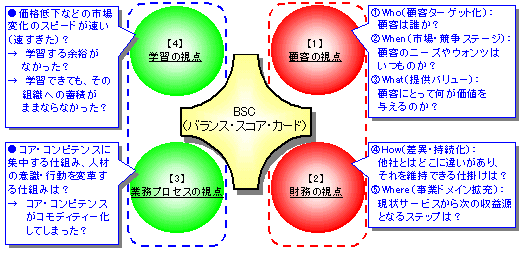
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
BSCでいう【1】顧客の視点は、①Who(顧客ターゲット化)、顧客は誰か、また②When(市場・競争ステージ)、 顧客のニーズやウォンツはいつものか、さらに③What(提供バリュー)、顧客にとって何が価値を与えるのか、という観点で解釈することもできよう。
【2】財務の視点では、④How(差異・持続化)、他社とはどこに違いがあり、それを維持できる仕掛けはどうか、また⑤Where(事業ドメイン拡充)、現状サービスから次の収益源となるステップはどうか、といことが問われる。
つまり、ここ数年のCWCにおいて、この5つの問いに対してどれほど自問し、問題を問題視することができたのか。同社に限らず、これら問いへのソリューションを明確化にすることの難しさはどこにでもあろう。しかしこれが徹底してできなければ、プロフィットを望むべくもない。
加えて見落としがちなことは、【3】業務プロセスの視点である、コア・コンピテンスに集中する仕組み、人材の意識・行動を変革する仕組みだ。コア・コンピテンスがコモディティー化してしまい差別化できにくい状況下での打ち手の問題である。
最後に【4】学習の視点。価格低下などの市場変化のスピードが速く(速すぎて)、学習する余裕がなかった、あるいは学習できても、その組織への蓄積がままならなかったといったことも想像される。
今回の事態の近因は、市場クランチなる激しい揺さぶりであったこと、さらに不幸であったことは、大株主のトヨタやソニーがこのビジネスを見限ったと思えることである。しかし、遠因あるいは本質的な要因は、主に上記【3】や【4】に関する幾つかのことであり、それらが短期間で一度に重なったのではないかと想像される。
すなわち、同社の強みであった技術力を裏づけにした商品の、差別化のレベルが低まった状況に留まった点、さらには幹線系商品に特化した専業型ビジネスモデルが、十分なプロフィットを生み出すほどの市場シェアを獲得するに至らなかった点が挙げられる。結果、市場からの大きな需要を引き出せずに(クリティカル・マスを超える前で)、キャッシュフロー面での脆弱性を露呈せざるを得ない状況に追い込まれた。これらは、特に市場発展の初期段階で顧客開発力に負うところがある。
以上おおまかではあるが、CWCひいてはIIJの周りで起こった尋常でなかったビジネス環境の変化、そして、今にして想像される、それに即座かつ適切に対処できなかった事態を概観した。わが国の通信市場での多面的な競争環境の進展という意味では、今回の事態は重ねて残念なことである。新しいビジネス環境での再起、再興を願いたい。

