"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第29回「IP時代の勝ち組ISPのアライアンス戦略とは(下)――iSPまたはiIPへ」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2003年6月26日
(1)複数層を結びつけるISPのアライアンスモデルとは
前回の第28回では、「アライアンスに影響を及ぼす誘因・支配ルール」について考えた。
今回は4つの領域において、それぞれ「ネットワーク(NW)・物理層」、「プラットフォーム(PF)層」、そして「コンテンツ・サービス層」なる、上段・中段・下段の縦方向のレイヤー要素を付け加えて、IP時代の勝ち組のISPについて考えてみたい。
これら上下3つの層については、2001年12月のIT戦略本部の資料などでも言及されている。旧来の垂直統合化の産業構造または企業形態よりも、水平分離的な産業構造の方が企業活動の効率化がはかれるケースも出てきた。デジタルなIP技術は、さまざまな仕掛けや基盤要素をカプセル化したりモジュール化したりするからだ。
各領域ごとのアライアンスケースでは、これらの上下の層を複数(2つもしくは3つ)持ったり、結びつけることが可能な仕組みを構築することで、下流から上流までの垂直統合的な機能(価値)を持つことになる。
IP技術は水平分離を引き起こす一方、垂直統合の動きを促すドライバーになっている。すなわち、カプセル化ないしモジュール化された各要素を拡大する(足し算)するこで規模の拡充をはかることができる一方、その各要素を再び統合(掛け算)することもできる。
図表をご覧頂きたい。
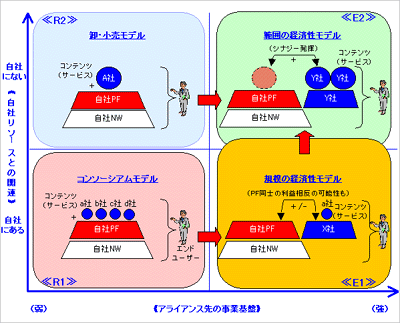
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
R1領域でには、自社のNWまたはPF層に、事業基盤はさほど大きくはないが専門化ないし特有な基盤をもつa、b、c、dの各社のコンテンツまたはサービスが乗っかる様子を示した。
また、R2領域では、自社のPF層に乗り自社にはない資源(コンテンツまたはサービスの種類、異種の価値)を示した。自社とA社の資源や事業基盤が相互補完、つまりwin-winの関係にあることをイメージした。
E1領域では、自社とX社がともにNWまたはPF基盤において広範であり、規模の経済性が発揮できる状況にある一方、自社とアライアンス先がともに重なり合う基盤を持つ場合もあり得、NWやPF同士の利益相反の可能性も出てくる場合もあろう。従って、自社とX社は独立して存在する、すなわち競合関係となることも少なくない。両者が自分たちよりも強大な共通の敵を目の前にしたときには、この規模の経済性モデルの現実度が増してくることになる。
E2領域では、自社が保有またはコントロールするNWやPF基盤に、Y社のもつ強固なコンテンツまたはサービスがうまく機能した場合、しかも、上段(最上位層)においても自社のコンテンツやサービスがあり、それにY社のそれが足し算される(シナジーが出る)ことで範囲の経済性が出てくる。エンドユーザーから見れば、上段・中段・下段のトータルなサービスが、それら3つをばらばらで別の企業から購入するよりも安く手にできる。
(2)IP時代の勝ち組ISPのアライアンス戦略とは
こうしてみると、IP時代の勝ち組ISPの条件らしきものがクローズアップされる。
競争に大きな影響を及ぼす要素はまずはスピード。そして、低価格性だろう。これは多くの企業経営者が強調するとおりだ。
日本の製造業をかつて牽引してきた「総合電機」メーカーは、1960年代から1970年代までの高度経済成長下、事業の規模をどんどん拡大し、さまざまな分野に進出して行った。そのスケールメリットにより実現したコスト構造の競争優位性を基に、やがて多角化の途をたどった。
各分野にてそれぞれの収益を追求し、それらを合算できるモデルを構築したが、それら合算前の多角化分野でのコスト構造は特段、規模の経済性をベースにしたコスト優位性を発揮するものではなく、むしろコスト面での非効率性が出てくるなど逆効果の事態も現れた。従って、顧客がその1社から価格面で有利な商品・サービスを購入することのできる範囲の経済性を享受することもなくなり、多角化は時代にそぐわなくなって行った。
電気通信分野の世界では、携帯電話会社がARPU(Average Revenue Per User:ユーザー1人当たりの平均収入)について、自社が支配権を握った端末(物理層)と自社のプラットフォーム層(課金・決済の仕組み)とで強力な事業基盤を構築した上で、その上にコンテンツを調達するビジネス構造をつくりあげた。
総合電機のように無闇に多角化などを行うのではなく、自社の事業基盤との相互補完性を出している。この様は、「通信キャリア」というよりも、「SP(サービスプロバイダー)」に近い。つまり、NWを提供する通信キャリアによる「通話収入」に加え、通話以外のサービス(iモ―ド、iアプリ、iショットなど)で新たな収益源を追求している。携帯電話ユーザーがわが国だけでも8,000万人を超え、その人口比との割合から通話収入が頭打ちになった今日、当然の帰結かも知れない。
固定電話やIP電話においても同様であろう。IP電話の登場で、激烈に安いまたはタダ同然になった通話サービスが、電話のおまけ状態になった今日、競争の枠組みは「通話サービス+α」あるいは「通話サービス以外」ということにもなってきた。
それを目指しているのがレガシーキャリアに加え、ISPということにもなるが、前述の通り、3層構造での区分で考えると、新たな垂直統合型モデル、すなわち3層を効率的に保有し各層のシナジーを出せるあり方が追求される事情も理解できる。
ただ、最下層のNW物理層を自前で整備することには、時間もかかるし膨大な投資が必要になる。スピードはあっても資金力がないのが新興企業の大半だ。あるいは、資金力はあってもスピードを出せないのがレガシー企業といえる。
従って、両者にとってアライアンス戦略が不可欠となる。本格的なIP時代の勝ち組ISPでは表現を区別し、「IPサービスプロバイダー(iSP)」もしくは「IPインフラプロバイダー(iIP)」などと呼んだ方がよいかも知れない。
ここでは、SPの頭には池田信夫氏の呼ぶ「共有資源」という意味の「I(インターネット)」とせず、プロバイダー自身によるIP技術やIPネットワーク基盤という意味を表すために「i(自身)」を付けている。
つまり、従来の専用線などの企業向けネットワークが単純にインターネットで置き替えられるのではなく、わが国では2000年頃からIP-VPN(IP ベースの仮想プライベート網)や広域イーサネットなどの、いろいろな工夫を施したクローズドな網が急速に顧客から支持されるようになってきた。
クローズドな網とすることで、セキュリティ面や帯域(速度)面でのある種の保証を行っている。ベストエフォートではない、もっと実用に耐えられるしっかりとしたネットワークまたは事業基盤の整備が、競争優位性の点で不可欠になってきたというわけだ。
こうしたユーザー企業のニーズを、前述の3層にわたる価値提供の観点でとらえた「iSP」や「iIP」が新たな勝ち組ISPとして、前述の4つのアライアンス戦略を場面に応じ実行していく。こうした動きが今後、より一層活発化していくに違いない。

