"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第28回「IP時代の勝ち組ISPのアライアンス戦略とは(上)――誘因・支配ルールがある」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2003年6月19日
(1)IP技術は破壊的である
昨今、IT時代になったと言われて久しいが、IT革命の牽引役はIP(インターネット・プロトコル)技術である。
IPがそもそも、単にインターネット・プロトコルという通信の規約を意味するということを知らないで、インターネットの便利さを味わっている利用者も多いことだろう。このIP技術が経済的あるいは産業面での構造変化などへ与える影響は甚大であり、これがIT革命を目下推し進めている。
革命というからには、これまで受け継いできた「レガシー(遺産)的」な仕組みを打ち砕くものである。まさに破壊的な状況があるから革命であるとといった方が正しい。
1997年にハーバード大学ビジネススクールのクレイトン・クリステンセン教授の呼んだ「破壊的技術」の最大級のものがIP技術であろう。当時は、わが国でとくに注目を現在集めているIP電話も登場していなかったが、同教授は「パケット交換通信網」を他の技術群と並び称し、低価格・低機能(ローエンド)な技術を破壊的技術と分類していた。
このローエンド技術はいわばおもちゃ(玩具)であり一見取るに足らないものであるが、その時代の最先端の高価格・高機能(ハイエンド)の「持続的技術」を、いつしか下から追い上げ追い抜いてしまうという。
かつての大手ハードディスクメーカーが、新興ベンチャーのハードディスクメーカーにより、その性能とコスト面での挑戦を受け、その内の大半はやがて市場から退いていった。まさにその下からと上からの攻防が激しく起こったケースである。
IP技術は、RIETI(独立行政法人経済産業研究所)フェローの池田信夫氏が指摘するように、「デジタル化、カプセル化、モジュール化」を強力に推し進めるために、その応用技術や商品・サービスに対して、劇的な低コスト化を実現する潜在性をもつ。実際、最近のADSLやIP電話などのサービスの大幅な低価格化がこの技術により実現した。
これまでのレガシーキャリア(旧来の固定電話網などを遺産として継承する通信会社)は、目下、ハードディスクメーカー業界で起こったような挑戦を受けている。1997年をピークに固定電話離れが加速する昨今、またはIP時代には、固定電話網がこれまでのような価値をもはや生まず(維持できず)、通信キャリアならず、新しいISP(インターネット・サービス・プロバイダー)が主役になっていくのであろうか?
本稿では、IT時代第2幕、すなわちIP技術が主役の現在のビジネス環境において、IPベースの取組みを前提とし、その勝ち組となるためのISPのアライアンス戦略について考えたい。
(2)素早く柔軟な変化を可能とするが勝敗を分ける
なぜ、アライアンスか。アライアンスを通じた取組みなしには、IPによりもたらされる激震の時代を今までのやり方やペースでは乗りきれないからだ。
電気通信市場においては、加入者線(NTTの地域アクセス網)というエッセンシャル・ファシリティーズ(不可欠設備)の存在があり、それがドミナントキャリアの独占的なビジネスの源泉でもあった。
IP時代には、そうした独占は過去のもの(遺物)となり、言い換えれば、これまでのような独占的なビジネスは望めない状況にある。最近のADSLサービスやIP電話では、その加入者線の使用が前提にあるものの、サービス競争は加入者線の上の部分で生ずる付加価値を巡り行われているようだ。
そして、その傾向は強くなっていくに違いない。ISPにとっては、付加価値を顧客に対していかに生み出せるかが重要になってきた。ただ、ドミナントキャリアのようなエッセンシャル・ファシリティーズは存在しないため、競合他社との間に模倣障壁を築きにくい。今までのような特別な設備や資産が無ければ、何か別のバリアーを築いても直ぐに真似られる状況でもある。それは、IT・ネットバブル時代にそれができず、そのバブル崩壊後、露と消えた多数のベンチャー企業と同種の事情にあるのかも知れない。
こうした時代環境では、自社の経営リソース、すなわち人材や資金のほか、コア・コンピテンスを発揮する事業基盤を素早くしかも柔軟に強化・補完することが、競争戦略の上でますます問われてきた。
経済学でいう「自製と購買」において、何もかも「自製」していては時代のスピードについていけない。従って、「購買」つまり、提携などを通じ他からモノやサービスを購入・調達することの意味が一層高まってきた。
最近では「アウトソーシング経営」などとも言われており、企業のバリューチェーンの上流・中流・下流域に配備される経営資源を自前で何でも揃える(垂直統合化する)のではなく、パートナー企業から経営資源(人材や情報システムなど)を購入するマネジメントが有効になってきた。
今や破竹の勢いである、韓国サムスン電子のユン・ジョンヨンCEOは、「素早い変化、若さ、創造的頭脳」こそがデジタル時代の勝利の条件としている(日本経済新聞2003年6月16日)。
IP時代を勝ち抜くISPにも、同じことが言えるのかも知れない。大企業のサムスン電子ができることなのだから、大手のレガシーキャリアであってもできないことはないだろう。また、もちろんベンチャー企業の方が機動性もあり、素早く柔軟な戦略(や経営のリアルオプション)を持つこともできるやも知れない。
IP技術は、従来の収益の源泉を破壊する一方、あらたな収益の源泉を生み出す諸刃の剣のようなものだ。IP時代にはこれまでのものが使いものにならなくなったり、競合他社よりもいち早く競争優位に立つためにも、企業形態の、またはパートナー企業間の水平分離的な取組みが効率を生み出す。
従って、アライアンス(戦略的提携)がクローズアップされてきた。
(3)アライアンスに影響を及ぼす誘因・支配ルールとは
図表をご覧頂きたい。「アライアンスに影響を及ぼす誘因・支配ルール」について示している。
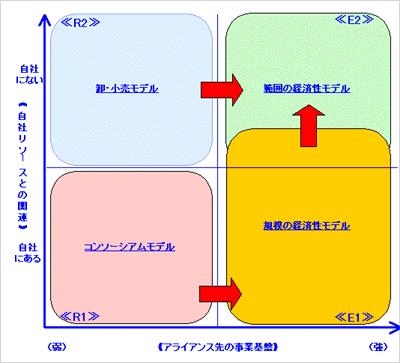
(注)「R」:関係性(Relationship)、「E」:経済性(Economies)、「事業基盤」:アライアンス先のサービスの加盟店数、顧客数、または決済ネットワークシステムなどのこと。4つの領域におけるアライアンスの可否には、同領域内に表示する関係性や経済性が影響ないし支配する。
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
「自社リソースとの関連」を縦軸に、「アライアンス先の事業基盤」、すなわちアライアンス先企業のサービスの加盟店数、顧客数、または決済ネットワークシステムなどを横軸にした平面(マトリクス)を考えてみよう。両者は相互補完にある。
左下の領域R1を「コンソーシアムモデル」と呼ぼう。
つまり、自社に経営リソース(ネットワーク基盤や顧客基盤など)があるため、アライアンス企業においてはそれを梃子(レバレッジ)として、自分たちのコンテンツやサービスなどをエンドユーザーへ安価にしかも早く提供できることになる。小さな企業であっても、ある種のコンソーシアム形態の仕組みを構築することで戦える環境を手にすることができる。一方、キャリアまたはISPにおいては、これら企業を顧客とし、自社の基盤を胴元的に活用してもらうことでビジネスができる。
左上の領域R2は「卸・小売モデル」と呼べる。
キャリアまたはISPにおいて自社は卸(ホールセール)として、自前の通信ネットワーク基盤などを提供し、パートナー企業のもつ、自社にないコンテンツやサービスを「小売(リテール)」としてエンドユーザーへ、上下両層の機能(価値)を提供する。いわば、win-winの相互補完関係を構築できることが、ここでのポイントだ。
右下の領域E1では、アライアンス先企業の事業基盤が強固である、つまり、規模の経済性(スケールメリット)を発揮できる条件にある。規模の経済性は、固定費の非分割性に起因する効果である。
(注)「規模の経済性」:固定費が大きく変動費がほぼ一定であれば、ある範囲の生産規模で生産量が増えると、その商品・サービスの生産プロセスの中で平均費用が下がり始める(費用逓減)効果のこと。新規参入者の大きな障壁ともなる。
とくに、IP網を利用するなどの広い良質のネットワークが事業基盤にある場合には、ネットワークの外部性が作用する。情報通信(ICT)分野では顕著に出る効果である。
(注)「ネットワークの外部性」:一群の利用者のネットワークに新たに顧客が加わると、その顧客は既にネットワーク(やシステム)に属している利用者に対し、消費の補完性としての便益(価値・効用)を生むこと。規模・範囲の経済性のような生産に関するものではない。表計算ソフトをもつソフトウェア会社などの企業間競争のほか、VCRでのVHSやベータなどの異種技術間の競争にも影響を及ぼす。
最後に右上の領域E2を「範囲の経済性モデル」と呼ぼう。
範囲の経済性は、規模の経済性の一種であり、コスト削減(低価格による提供)の効用をエンドユーザーへもたらす。規模の経済性が発揮する状況下でのものであるため、図表中では両領域が多少オーバーラップしている様子で表現している。
(注)「範囲の経済性」:複数のサービスや事業を同時に、多角化した企業の内部で行う場合のコストの方が、それら事業を別々の企業が担当した場合にかかるコストの総和よりも低くなる現象などのことで、補完性が問題となる。
このようにアライアンスの狙いまたは効果により、4つのモデルを想定することができる。自社とアライアンス企業の2者において、それぞれが持つ経営資源の有無または事業基盤の強弱で表そうとしているのだから4つになるのは当然だが。
ポイントはこれら4つの領域に影響を及ぼす誘因・支配ルールを考えることで、アライアンス戦略も変わってくるし、またそのアプローチのイメージアップもはかれるということだ。
その具体的なことは、次回に譲りたい。

