"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第27回「日の丸半導体産業の復権はなるか(下)――どこで戦うべきか」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2003年5月22日
(1)DRAM事業の直面する構造的な問題
わが国のとるべき半導体戦略への示唆として、それではどこで戦うべきかを本稿では示したい。
その前に、帯域の需給ギャップで見たDRAM事業の構造的な問題を取り上げよう。
昨今のDRAM(ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ)集積度の開発ピッチは、当該ソフトウェア上で動くCPU(中央演算処理装置)やI/O(入出力デバイス)の処理速度のそれを上回り、次の図表のとおり、需給ギャップが拡大している。
すなわちDRAMの大容量化が、ソフトウェアやシステム側のメモリ要求を完全に追い抜いてしまっているのだ。
今後、IP・ブロードバンド技術革新が進むなか、エンドユーザーのメモリ需要活発化(同ギャップ縮小)となるか、あるいは同需要沈滞化(同ギャップ拡大)となるかが、DRAM事業の行方を決定する。
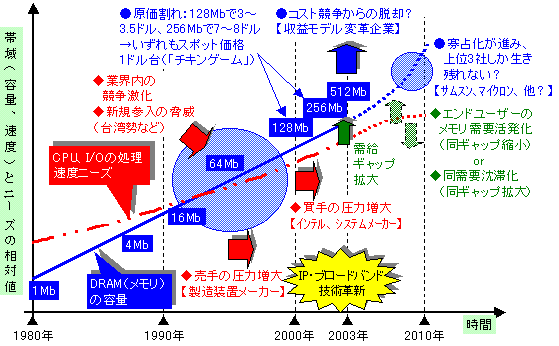
(注)「帯域(容量、速度)とニーズの相対値」:対数スケールでイメージしたもの。昨今のDRAM(ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ)集積度の開発ピッチは、当該ソフトウェア上で動くCPU(中央演算処理装置)やI/O(入出力デバイス)の処理速度のそれを上回っている。「チキンレース」:崖に走っていって何処まで耐えられるか(先に足を止めると負け)とか、ナイフを地面に立てて後ろ向きで何処まで近寄れるかなどの度胸試し。「b」:ビット(メモリの単位)。「IP」:インターネット・プロトコル。
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
マイケル・ポーター(Michael E. Porter)流にいえば、おまけに、1990年代半ば以降、「新規参入の脅威」(台湾勢など)も加わり、汎用DRAMの「業界内の競争」が激化している。128Mビット DRAMの原価は3~3.5ドル、256Mビットで同7~8ドルと言われているが、両製品が投入されてから、1年以内から半年程度でいずれもスポット価格は1ドル台まで急落した。
さらに、インテルやシステムメーカーなどDRAMの「買手の圧力」は増大している。第26回で取り上げたエルピーダメモリからのインテルへの出資要請などの動きは、こうした圧力を助長する動きともなる。
あるいは、DRAM分野での新しい製造工程を開発するためには、今や製造装置メーカーの技術者は有利な立場になりつつある。このまま行けば「売手の圧力」も確実に増大している。
前述の大幅な原価割れ下の競争や、DRAM市場の寡占化のビジネス環境では、韓国サムスンや米国マイクロンなど上位3社程度しか生き残れないとも予想される。
まさにゲーム理論における「チキンゲーム」の様相を呈してきた。
(注) 「チキンゲーム」:崖に走っていって何処まで耐えられるか(先に足を止めると負け)とか、ナイフを地面に立てて後ろ向きで何処まで近寄れるかなどの度胸試しのこと。
(2)どこに活路を見出すべきか
チキンゲームから抜け出すことは、必ずしも文字通りチキン(臆病者)になることではなかろう。この種のゲームでは勝ち組に入らなければプロフィット・ゾーンからの果実を手にすることはできない。問題は過去を断ち切り、新たな収益基盤を模索することで、新たに勝ち組に入ることだ。
かつては汎用メモリを主力としていた米国インテルや米国モトローラは、現在ではそれぞれCPUや携帯電話向け通信用チップなどに、そのプロフィット・ゾーンを変更している。インテルの市場シェアトップが続く一方、モトローラは携帯電話端末機で、世界シェアはノキアに次ぐNo.2のポジションを確保している。当時の日本企業とのチキンレースから抜け出したのだ。
次の図表では2つの例を用いて、脱汎用メモリ事業における収益基盤の5要素とその比較を示している。2例とも収益モデルの変革企業といえる。チェンジマネジメントのケーススタディとなる。
1つ目は、例えばルネサス=日立+三菱電機などの「日の丸新会社B」だ。
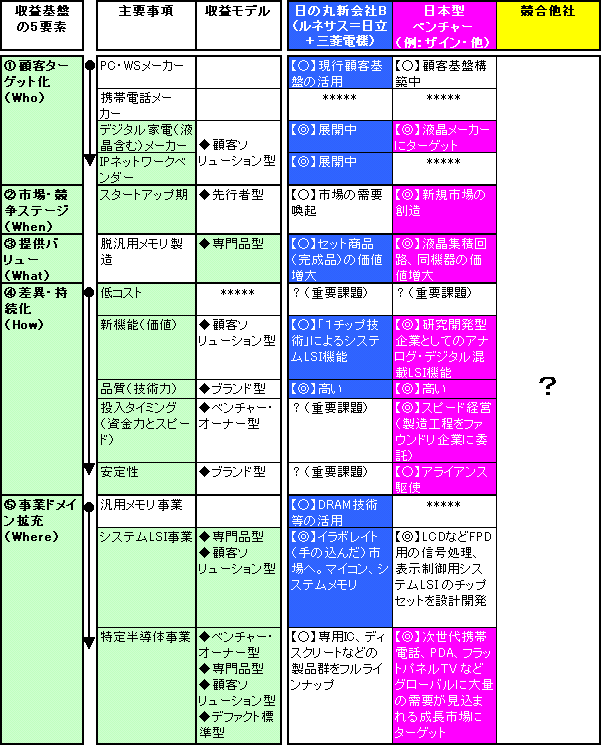
(注)「収益モデル」:Slywotzkyの22の分類(1997年)を参考に、出現率の高い16の収益モデルに集約・補足したものを適用。「上下の矢印」:起点(●印)からの拡大方向。 ★「PC」:パソコン。★「WS」:ワークステーション。★「IP」:インターネット・プロトコル。
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター
日の丸新会社Bでは、これまでのコスト競争からの脱却を目指し、差異・持続化された提供バリューの追求が見て取れる。
具体的にはルネサスなどではまず、セット商品(完成品)の価値増大を「③提供バリュー」としている。また、1チップ技術によるシステムLSI機能の実現により「④差異・持続化」をはかり、マイコン、システムメモリなどのイラボレイト(手の込んだ)市場へ、そして、専用ICやディスクリートなどの製品群をフルラインナップ化するなど、「⑤事業ドメインを拡充」せんとする。
このケースは、日の丸半導体新会社が戦うべきフィールド(またはプロフィット・ゾーン)となろう。東芝が先行しているフィールドでのポジショニングを、ルネサスがどのように築いていけるか。期待されるところだ。
(3) 新しい企業群への期待
2つ目は、「日本型ベンチャー」だ。東芝の半導体技術研究所部長であった飯塚哲哉氏(工学博士)が、1991年に設立したザインエレクトロニクスなどは好例である。詳細は、同氏の著書『脱藩ベンチャーの挑戦(技術者よ 殻を破ってみないか)』(PHP研究所、2003年3月)に詳しい。
ザインの「①顧客ターゲット化」として、液晶メーカーが筆頭に挙げられる。新規市場の創造こそが「②市場・競争ステージ」となる。ザインの顧客は、シャープ、日立、NEC、松下電器、サムスン、LGフィリップスなどの一流大企業のようだ。1998年に事業をスタートさせた。
そして、液晶集積回路や同機器の価値増大、あるいは研究開発型企業としてのアナログ・デジタル混載LSI機能の提供が「③提供バリュー」となる。LCD やPDPなどフラットパネル向けのデジタル画像信号を高速処理するLSIチップなどの開発を通じ、その製品は世界の主要なメーカーのほとんどで採用されている。製品によっては世界シェア60~80%を占める。特に創業初期にサムスン電子との合併が契機となり、液晶ディスプレイに目を向けることになったようだ。
また、「④差異・持続化」要素として、上記のような液晶周りのデジタル・アナログ混成回路における技術の蓄積に加え、ベンチャーならではのスピード経営、あるいは「枯れた製造ライン」の活用が挙げられる。これならすぐに製造に移せるし、低コスト化もはかれ一石二鳥だ。その製造工程の機能確保では、台湾 TSMCやUMCなどのファウンドリ企業、そして川崎マイクロエレクトロニクスやヤマハなどのパートナー企業に委託している。積極的なアライアンスの駆使も重要な要素となっている。
現在の事業ドメインからさらに、LCDなどFPD用の信号処理、表示制御用システムLSI のチップセットを設計開発したり、あるいは次世代携帯電話、PDA、フラットパネルTV などグローバルに大量の需要が見込まれる成長市場をもターゲットにするなど、「⑤事業ドメイン拡充」にも余念がない。
創業2年目~7年目の間では社員10人で売上高3億円ぐらいを前後していた企業が、このような収益基盤の準備・形成を通じ、2001年にはJASDAQ 市場への株式上場を果たした。2003年現在では同120億円にまで成長。しかもこの間、赤字時は1期も出していないというから立派なものだ。
「小が大を手玉にとる」戦略は、ザインにも見られる。サムスンとエルピーダが戦うゲームにおいて、両社が市場での「攻撃または参入継続」のオプションをとる間、ザインは両社の主力製品であるDRAMとは別の、しかし、そのDRAMよりも付加価値が高く、DRAMも組み込まれているデジタル・アナログ混成のシステム機器などの領域で、しっかりとプロフィットを得るという構図である。
ゲーム理論流にいうと、もしも両社が「協調」オプションを選択し、ザインのターゲットとする領域に侵食するとなれば、「多人数型のゲーム」にも変化が及ぶ。ザインの狙う市場が1,000億円を大きく越えるような市場に成長すると、大手企業の参入も出て来よう。もちろんその前に、過去2回本稿で示した、「専門品型」や「デファクト標準型」などの収益モデルを構築してしまえば、そのときもザインはプロフィット・ゾーンに入ったままでいられるだろう。
今後、飯塚氏は2006年までに500億円の売上高規模にまで同社を成長させたいとの構想と戦略をもっている。ベンチャー経営は難しいとされるなか、この企業のケーススタディは日の丸半導体産業の復権のヒントを与えてくれているのではなかろうか。

