ITSはメディア・コンテンツビジネスに取り組めるか
出典:TRAFFIC & BUSINESS 2002年夏号
1.はじめに
道路交通情報における民間市場とは、設備産業としては存在していても、情報そのものについては、雑に言えばゼロ円市場であった。これを大幅に規制緩和しメディア・コンテンツビジネスとして育てていくための制度を整えていくのが、政府懇談会「トラフィックインフォメーションコンソーシアム」(以下文中TIC)である、というのが、委員としての筆者の解釈である。
当該問題に対して筆者なりに一貫して捉えTICでも重ね重ね申し述べているところの視座を本稿であらためて示し、道路交通情報ビジネスの進むべき方向性について一石を投じたい。
2.TIC最大の問題は、動き出さない民間側の鈍さ
光TICは、飯田恭敬座長(京都大学教授)以下、関係省庁、関係民間団体、研究者、有識者等の委員からなり、道路交通情報の担当部署である警察庁交通局交通規制課と国土交通省道路局ITS推進室が共同で事務局を運営している。
2002年6月より施行された改正道路交通法の中に、「交通情報の編集加工、提供について(情報収集は今回対象外)、民間企業の実施を届出制とし、適宜制度上のしばりをつくりながら民間に市場を解放する」という趣旨が盛り込まれている。この新制度の運用ガイドラインと、技術面での安全性確保を規定していくための議論をTICで行っている。本稿が世に出る時点では、2001年11月にプレスリリースされたTICの中間報告の次ステップをどのように進めていくか、具体的にどのようなビジネススキームが出現しどのような歯止めを作らなければならないのか、ケーススタディーでの検討体制をどう作るかという点が詰められたところまで、となっているはずである。
後手に回っているという見方もあるかもしれないが、実際には海外事例の紹介も含めたドラスティックな検討が行われており、建設的かつ大胆な意見も委員から次々に出され、活発に運営されているように思う。
筆者が考えるこの懇談会の最大の問題点は、官の規制対民の要求、の構造ではない。むしろ逆、海外事例の紹介までして参入の仕方を紹介してくれる画期的な政府アウトプットがあるにもかかわらず、プレッシャーをかけたはずの民間団体あるいは各企業の積極的な動きがまったく見て取れないことにある。2015年までのITS市場累積60兆円、関連産業累積100兆円というITS情報通信関連市場(電気通信技術審議会の資料として公開)において、道路交通情報ビジネスが今まさに解放されたならば、我先に民間企業が飛びついて、周到に準備されたビジネススキームをスタートさせ、これまでの多大な先行投資を回収しようと躍起になっていなければおかしい。
ITS業界側の動きはあまりにも鈍い。なぜか。製造物の販売、施設利用の時間単位課金といった収益形態を本業としてきた企業(自動車、電機、通信等)のITS担当者にとって、情報の中身を売って商売にする、という収益形態を、どう準備していいのか、誰がいつまでにいくらかけてできるのか、ということにまったく土地勘がないのである。
3.メディア・コンテンツビジネスとは、ニーズに根ざした経験則である
メディア・コンテンツビジネスの収益源とは何か。面白いものは儲かる、やむを得ず見るしかないものは儲かる、これだけである。つまりニーズに根ざしたものしかビジネスになりえない。消去法的に探せばニーズは必ず見つかり、キラーコンテンツは自動的に導き出せると本気で考える方がITS関係者には実に多い。この業界は製造業、通信事業とまったく違うのである。
テレビ番組にも新聞記事にも雑誌の特集にも大量のボツコンテンツがあり、その潜在的なコストと労力の積み重ねの上に、半分は担当者の経験、半分は偶然による「大当たり」が出現するのが、メディア・コンテンツビジネスの本質である。
道路交通情報は、いまはじめてメディア・コンテンツビジネスの俎上に乗ったのだから、今すぐに最適解を出せる人はどの業界にもいない。しかしメディア・コンテンツビジネスの経験からある程度物言えることがあり、そのことは現在のITS民間側の推進当事者には往々にして欠けている視座であることから、ここで「業界の常識」と言える典型的な論点をいくつか取り上げてみたい。
(1)人は情報に払うお金がない
携帯電話の支出が他のすべての情報支出を圧迫していたことは、もう96、97年頃にはわかっていたはずである。しかも2000年になって、携帯電話の支出が先導していたはずの個人情報支出額そのものが頭打ちになっている。詳細は記さないが10代男性では「情報支出の月ごと総額」が「月ごとの小遣い全額」を上回っており(実際には携帯電話の基本料金は親が家計で支払うのでこうした数値が発生する)、もはや「情報支出倒れ(電通総研報告書より)」は明らかである【図表1】。
【図表1】 情報支出の限界状況
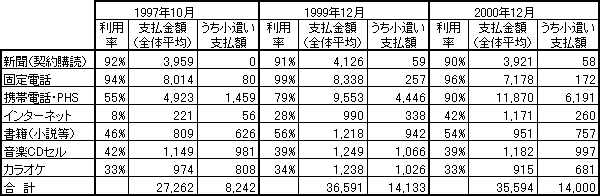
(出所)電通総研「生活者・情報利用調査」(2001年3月)
(2)人は接触時間の長いメディアにしかお金を払えない
有料テレビ放送、DVD映像など、家で長時間かけて楽しめるものなら、ある程度の情報支出を期待できるが、モバイルのニーズに対するメディア・コンテンツビジネスとしての支出は、カーラジオという小規模(国内年額2,300億円市場とは、間もなくインターネット広告市場に追い抜かれる規模)広告ビジネスモデルか、iモードが確立したコンテンツ少額課金ビジネスモデルの2つに収斂してしまっている。そのiモードの有料コンテンツも、不動の双璧を占めているのは「着メロ」と「壁紙」であり、他の情報提供コンテンツは、ダイヤルQ2ビジネスなどを基盤とした、きわめて安い制作費に支えられたニッチマーケットでしかない。
(3)人はカーナビをメディア・コンテンツ受信機だと思っていない
VICSやD-GPSは大きな市場を作っていることは事実だが、使っているほうは自分でこの制度上有料放送であるこのメディア・コンテンツビジネスに対し、情報料を支払っているという感覚はない。日本人が情報課金に疎いということでは必ずしもなく、GPSから得られえる情報が無料で、ROMに焼かれた地図も(スタンドアローンのソフトウェアパッケージではあっても)情報料はタダだ、と思っている人がカーナビユーザーのほとんど全員である。そういう商品だと日本中のユーザーが認識してしまった以上、そこにカーナビ機能の延長上にしかない課金情報ビジネスを乗せてきても「なぜこちらがタダで、こちらが有料なのかわからない」あるいは「私が本当にほしいのはこのタダのほうの情報で、おまけの有料のほうはいらない」ということになる。自動車を運転する上でそれほどに「現在位置と進行方向と周辺地図」はキラーコンテンツであり、これが無料である以上、このサービスと同時に有料で存在しうる情報コンテンツは限定されざるを得ないということになる。
(4)メディア・コンテンツビジネスとは基本的に、労働集約で臨む規模の経済である
規模が大きくなければ情報の配信時の収入には限界があるので、おのずと情報の生成(収集、編集加工)に極端に安いコストのモデルを作らないと成立しない。iモードについては前述したが、これを地図情報になじむ形でエリア別に構築できているのが、リクルートを代表とする情報誌の業界である。リクルートの情報誌的イメージを道路交通情報ビジネスの理想とする考えもあるだろうが、これは極端に安く抑えた情報収集(取材/広告集稿営業)スタッフの人件費と、集まってきた大量の情報を一つ一つ精査し(とくに広告集稿情報は不正なものを探偵的に排除する必要がある)、取材情報については大量のボツコンテンツを発生させている情報編集スタッフの過剰な労働量に支えられている。機械を設置して自動的に情報収集して自動的に編集加工して配信する、といった安易な方策では、まず高付加価値の情報収集ができない。人が直接出向いてくれば、機械から入力されるより明らかによい情報を与えてしまうのが人の常である。
(5)情報消費者は情報生産者にあまりなりたくない
情報収集の労働集約ができなければ自動車側から情報を発信させればいいというので、プローブカーの実験が盛んに行われている。既存の交通量調査の代替手法としては大いに期待できるが、これをもって情報収集ビジネスのモデルとして構築することは、結論としては難しいといわざるを得ない。いくらプライバシーの問題を技術的に解決したとしても、自分の情報を発信するということに慣れていて、かつ戻ってくる統計的情報とバーターの価値を感じることのできる人は非常に少ないからである。
前者については、自分から情報発信してもいいと思っている人とは、いわば情報高感度、高情報リテラシーの人であり、そのような人が自動車交通利用に占める割合は、未来永劫少数派である【図表2】。単にパソコンが使えるといった問題ではなく、脳が高度の情報処理に慣れているか否か、という尺度の問題である。
後者については、多くの人たちは統計的な情報を受け取っても、それが自分だけが得をする情報にならない以上は価値を感じない、という可能性が高い。人がお金を払うというのは人より得することが自分に起こるからである。アンケート調査であれば、通常は参加者に謝礼を払う。全員に得することが起こるときに、我先にお金を払うほど消費者は奇特ではない。
【図表2】 2000.3生活者・情報利用調査
情報リテラシーごとの性別構成 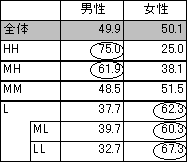
情報リテラシーごとの年代構成
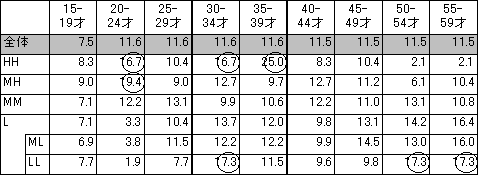
情報リテラシーごとの最終学歴
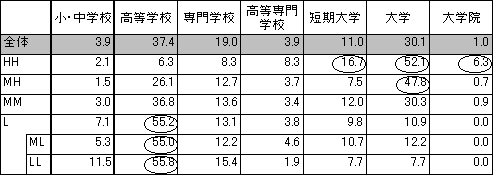
(注)ここでいう情報リテラシーとは、ITツールの利用スキルのみならず情報接触形態における積極性、いわば情報感度の高低も尺度にしてアンケート結果を点数化した電通総研独自の指標である。Hはhigh、MはMidium、LはLowの略で、それぞれ高低の度合いを示す。○は全体平均よりも5%以上高い数値。
(6)「それは明日儲かるのか」に対する直感的な答えが必要
メディア・コンテンツビジネスの世界は、ほんの一部のマスメディア企業を除いて、先行投資という文化に乏しい。したがってITSの随所に見られる官民共同開発や先行技術開発のインセンティブも体力もないのが通常である。新事業への参画を要請する上で一番重要なロジックは「それは明日儲かるのか」「1年2年でユーザーを何百万かにできるのか」「数が増えてから参画するよりもなぜメリットがあるのか」である。ITSで長らく言われている市場規模予測などはまったく通用せず(本来的にこの業界には市場予測を信じる文化がない)、直感的に「イケる」と感じさせるビジネスモデルを提示しなければ、メディア・コンテンツビジネス側は手を貸してくれない。しかしこの知恵と経験を、ITS関連企業として避けて通ることはできない。
(7)編集こそ命。たいがいの素材はもうインターネット上にある
メディア・コンテンツ業界には、もともとTICなどまったく意識しないながらに実現されてきた位置情報サービスがビジネスとして存在している。タウン誌、ミニコミ誌で収集可能な情報は、いま多くがインターネットの地図情報サイトに載り、逆にタウン誌なども地図づくりに工夫をこらし、それらの速報やリアルタイム情報が携帯電話のメールや自動通知サービスで届いてしまう。いくつかの携帯電話では現在位置を画面の地図上に表示することも可能である。ほんのわすかのリアルタイム性を除けば、もうほとんどの情報素材はインターネット上に転がっている。
だから道路交通情報のビジネス化の最後の付加価値は、「気の利いた編集」である。この情報編集とはきわめて属人的、経験的なもので、製造業の文化に本来的になじんでいない。そしてこの編集という作業は非常に高い人件費に支えられないと、比例級数的に質が下がり、情報が商品として売れなくなっていくという点が、この業界では共通している。高人件費でこそ高売上が実現する、つまりは規模の経済なのである。
その他様々な論点を解決せずに、いや何の検討そのものも着手していないからこそ、TICの活動に参画している多くのITS関連企業から、ビジネスに取り組む新しい動きが起こってこないのである。
道路交通情報ビジネス自体が悲観的なのではない。このニュースを知って行動できる人たちにこうした常識が芽生えていない点、こうした常識の持ち主にこのニュースを伝えるべきITS関係者がうまく伝えていない(そもそもまったくニュースとなっていない)点、ぜひ留意しなければならない。
筆者には、小さなゲーム制作会社の若者や、広告代理店のイベントプランナーや、テレビ番組の制作ディレクターが、全国民があっと驚く道路交通情報の遊び方使い方を次々に思いつき、その99%がボツになる姿が目に浮かぶ。そして残りの1%のアイデアがこのビジネスを成功に導く。餅は餅屋、であり、いまITS関係者を自称する方々は、残念ながらこの領域についてだけは、餅屋ではないのである。
4. カーテレマティクス事業の前提が海外と異なる点も留意
加えて道路交通情報ビジネスのなりたちを考えるのに、海外との前提の違いを忘れてはならない。
海外では道路交通情報自体が官庁によって十分に整備されなかった歴史があり、民間がビジネスとしてはじめなければならないニーズがあった。それでも、有力視された北米市場のWingcastは採算見通しが立たず、解散している。日本の道路交通情報ビジネスはこの点で実ははじめから海外より難しいスタートを切らなければならない。
昨年のITS世界会議(シドニー)で、いわゆるカーテレマティクスビジネスを欧米で展開している主要企業の重役クラスのスピーチの中で「日本は官庁が長年道路交通情報自体をハイレベルに整備してきたので、あれは欧米でのビジネスモデルの参考にならない」という発言を複数聞いた。世界に独自と言ってもいい日本の交通情報ビジネス成立のシナリオは、海外事例を見習うといった安易な方向性だけでは、実は得ることができない。TIC中間報告で示されている海外事例は、そこまで含めて解釈していく必要がある。
5.「プロデュース」こそ突破口
本稿のタイトルを「ITSはメディア・コンテンツビジネスに取り組めるか」とした。当然取り組まなければならず、そして結果として成功しなければならない。しかし、ITS関係者自身が成功できなくてもよい。成功できるメディア・コンテンツ業界の人々を「プロデュース」できれば、成功である。
プロデュースとは何か。費用調達の責任と人材調達の責任と結果の責任をとり、そのリスクの対価として多大な報酬を得ることである。その成功と失敗は、きわめて個人に帰属する。残念ながらITS関係企業を自称する会社に、こうした人事評価はなじまない。外部人材が「宇宙人的センス」で取り組むことが必要と思われる。
決して難しい議論ではない。本稿を読まれる方々が、1ユーザーとして感覚的に理解できるものは、ビジネスとして成立するというだけのことである。現時点で筆者などが知る由もなく民間企業が隠して持っているビジネスモデルが、TIC収束後に一気に噴出し、その活気ある取り組みこそが一人歩きするITS市場規模を支え、先導する、という姿を期待したい。

