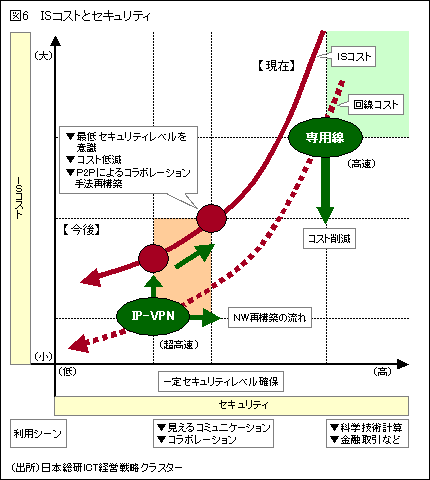"e"の飛躍 ~企業革新を継続するために~
"IT革命第2幕"に乗り遅れるな!
出典:IBMジャパン e-businessレポート 2002年4月23日
近年のブロードバンド化などを受けて、「第2幕」に入ったといわれる“IT革命”。更なる企業改革が期待されるゆえんでもある。当然、IT革命第2幕にどう対応するかによって、今後の各企業のポジションも変わってくるだろう。そこで、第1幕と第2幕の違い、重要とされるキーワードなどについて、日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター長 主席研究員 新保 豊氏にご教示いただいた。
●IT革命“第1幕”と“第2幕
「“IT革命”とひと口に言いますが、2001年春あたりを境に、第1幕と第2幕に分けられると考えています。第1幕と第2幕の一番の違いは、インフラの普及率です。今まで『電子メールも使ったことがありません。インターネットも見たことがありません』、そういう人々が第1幕に初めてそれらのツールに触れ、第2幕ではそれが当たり前になってきた。企業で考えると、『ホームページを開設しました』という状態が第1幕だとすれば、第2幕ではCRMだとかSCMといった、コア・コンピタンスに直結するようなものとしてITが組み込まれてきたのです」
新保氏はこう説明する。
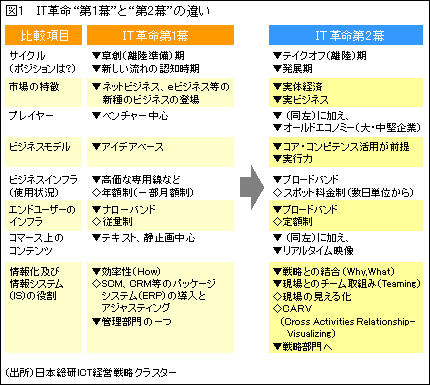
では、インフラが普及した背景には、何があるのだろうか。
「一番の理由はやはり価格でしょう。例えば、法人企業におけるインフラとしては、専用線や法人向けのデータ通信サービスが過去10年以上あります。しかし、これらの中には運用費用も考慮に入れると、年間で数億円、数十億円といったものもあり、高額ですから、上場企業ぐらいしか使えませんでした。それが、インフラの価格が下がったことで、広域イーサネットやIP-VPNといった、通信の階層(図2参照)でいうところの第2レイヤー、第3レイヤーのサービスが急速に普及しています。この1~2年ぐらいの間に普及し始めて、第2幕である今はさらに普及する見通しです」
中小企業・個人向けとしても、昨年から始まったADSLの価格競争を皮切りに、高速で従来に比べれば低価格といえるインターネット接続環境が整い始めた。
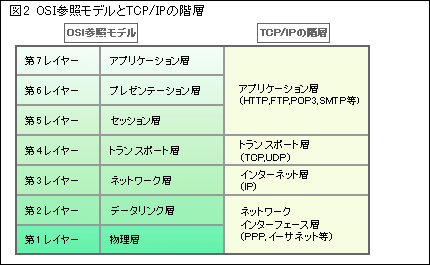
「次にインフラが役に立つ、利便性が高いとユーザーが認めたということだと思います。例えば携帯電話のARPU(Average Revenue Per User:1契約ユーザー当たりの月間平均収入)は減少気味とはいえ、8,000円程度今もあるわけです。結構高いですね。でも、非常に身近で便利だということであれば、携帯電話だけにさえ人は金を払うのです。つまり、ITが本当に役に立つ、利便性が高いということが現実的になったということではないでしょうか」
テキスト
●キーワードは「CRB」「コラボレーション」「IT投資」
日本企業におけるITの取り組みの現状をどう見て、経営コンサルティングをしているのだろうか。
「私たちが『現在の状況はどうですか』と尋ねられた場合、IT分野ということでは米欧の事業と比較することが多いのですが、日本では一部の企業を除いて、取り組みが遅いもしくは下手だという印象は否めません。でも、米国やヨーロッパのまねをすればいいということではないのです。それぞれの文化だとか、仕事の進め方などは異なりますから、単純にERPパッケージを入れればいいんですよ、という話ではありません」
「富の源泉と言いますか、利益の源泉はやはり顧客にある。英国でも米国でもそうですが、“カスタマー(顧客)志向”が非常に強い。イギリスの政界などは、国民をカスタマーと、もう10年以上前のメイジャー首相時代から呼んでいるのです。公共分野といえども大変意識が進んでいると、当時の菅直人氏(現:民主党幹事長)も言っていましたね。また、企業においても、対価を得られる相手先に対する神経やパワーの使い方が、非常に強い。昨年も、米欧の企業幹部や大学・政府関係者と意見交換する場がありましたが、毎年そう感じています」
「日本でも、徐々に産業がサービス化しています。それは、そこにシフトせざるを得ないのです。例えば、労働賃金で1,000万円の年収のある人が、中国やベトナム、インドの人と競争するために賃金の価格を下げることにそう簡単に同意するというわけにはいきません。従って、それらの国が手を出せないような付加価値の高いところを狙わざるを得ない。つまり、お客様志向とかサービスということになってくる」
新保氏は、カスタマー志向を強めるための手法として、CRB(Customer Relationship Building)という観点が必要だと説く。CRM(Customer Relationship Management)よりもさらに進んで、お客様との関係を再構築するのだという意識のもとに生まれた言葉だ。
「CRM(Customer Relationship Management)は、日本語でいえば顧客管理です。しかし、私自身はお客様を管理するという言葉自体にちょっと違和感がある。もちろん、マネジメントというのはそれだけの意味ではありませんが、それらを明確に区別したいという意味であえてCRB(既存顧客関係の強化、および新顧客関係の構築)という言葉を使っています」
「お客様とともに相互のコアになる関係基盤をBuildingする、それは“コラボレーション”を通じてなされます。従来のような上下関係から、対等な関係、あるいは前後関係への移行が重要なのではないかと思います。例えば、お客様がここまでやって、その後を私たちが引き受けますよ、といったパートナーシップは「前後関係」です。さまざまな部門同士のコラボレーションも緊密にやっていけば、強い企業になれるのではないでしょうか」
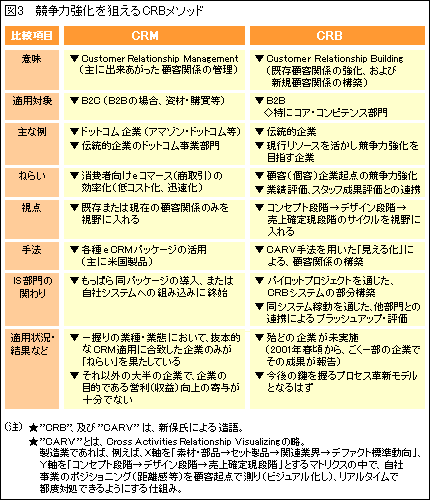
●顧客だけを見るのではなく、もっと広い動きを見よ
では、このIT時代にトップが考えなければならないのはどういったことなのだろうか。
「ハーバード・ビジネススクールのクレイトン・クリステンセン(Clayton Christensen )教授も言っていることですけれども、当初はローテクでマーケットなどほとんどないと思えるような領域から、大きなマーケット、あるいはその分野のトップ企業が切り崩されていくものです」
「売れる商品だとか決定的にマーケットを覆せるようなものがなかなか作れないのは、見ている先が近視眼的なものになっているからでしょう。先ほどカスタマー志向が重要だと申し上げましたが、だからといってお客様ばかりを見ていると足元をすくわれてしまいます。企業のトップには、今起こりつつある技術革新などのイノベーティブな要素を見極める眼力、識別力が必要ですし、できれば事業部長以上にもそういう目を持っていただきたい。 現場のちょっとした社会の動き、お客様、マーケットの動きというものを常に見ている人かどうか。かつ、それでいてその延長にはない洞察やアブダクション(仮説的推論)ができるような力を持っているか持っていないかが、企業の競争力を決定付けるのでしょう」
「経営コンサルタントの大前研一氏は、“構想力”という言葉を使います。見えないものを見て、何かを創り上げていく“構想力”を持つことが大事だと彼は言うわけです。まだ実体の見えないビジネスの世界を“見えない大陸”と呼んでいますが、ITの世界には“見えない大陸”がたくさんあります。それをいかに見極めて、投資するかということが重要です。私は彼の構想力を次のように補完したいと思います。自然科学での発見や発明の時に不可欠であった、先のアブダクションという手法は、今後、経営の中にも重要なものとなっていくに違いありません。これは、部分的な(些末な)事実関係から物事の全体を射貫く、仮設を構築する能力のことです。これまでの帰納法や演繹法とは異なる手法ですね」
「一方で、“IT”というのは、『What』『Why』といったまだ見ぬものを探るものでは決してなく、『How』に類するツールであると考えます。効率化する、時間を短縮する、というのがITの効用であって、そこを取り違えてはいけない。私は『Why』『What』『How』をきちんと区別したいと思っているのです。ITはInformation Technology--情報技術であり、『How』の部分ですから、『Why』とか『What』の部分と結びつけて、考えていかないといけない。今後は、これに“C”を付け加えたいですね。『Communications』のことで、企業活動における内外の関係プレイヤー間のコラボレーションを効果的に実現する基盤(インフラ)的な要素を含む仕掛けです。これが明瞭に意識されて、つまり“ICT=InfoCommunications Technology”を軸に、ブロードバンド時代のマネジメントがいかに行なえるかが鍵を握ることでしょう。“ICT”という言葉は、欧州では普通に使われています」
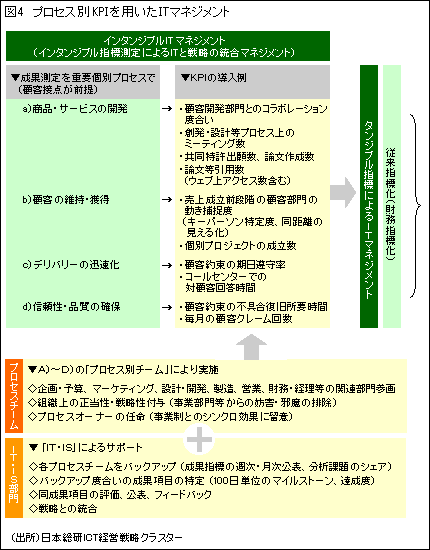
●投資対効果を数字だけで計るのは危険か?
ITを導入する際の最大の関心事は、投資対効果だろう。しかし、数字には表れない一面もあり、計りにくいのも事実だ。
「IT投資をどう計るか、といえばもともとROI(Return On Investment:投資対効果)で評価するのがポピュラーですが、それでもなかなか分からない。昨年夏に会ったハーバード・ビジネススクールの、元経営コンサルタント出身のオースティン(Austin)教授も、『ROIの危機』といった同様のことを言っていました。IRR(Internal Rate of Return:内部利益率)という手法で評価する場合もありますし、BSC(Balanced Scorecard)というような考え方もあります。どの手法においても成果を確認する場合、1年間といったスケールではなく、半年、3カ月ごと、月ごとといった期間に目標を置いて、それをきちんと達成できたかどうかを、要所要所のマイルストーンを基に確認したほうがいい」
「しかし、人間あるいは組織は、数字だけでパフォーマンスが決まるわけではありませんし、一人ひとりの活力は数字だけでは計れないものがあります。また、直接の“IT”ではありませんが、ビジネスマインドといったものが今後の経営には重要になってくると思います。研究所にいても、工場でも、自分のやっていることがビジネスに直結するんだという考え方をきちんと浸透させることが重要でしょう」
「日本の経営者は、ライバル企業や米国などを見て、水をあけられた要因がITなんだと思い込んでいる。だからITをやる、投資もする、といったように、ITありきになってしまう。あくまでITは道具ですから、戦略(または先の仮説)があって、だからITをここにこういう形で使いましょうというふうにならなければいけない。それがIT革命の第2幕以降に問われている問題だと思いますね」
●ブロードバンドのキラーコンテンツとは
「古い話でいえば、ビデオ方式のVHSとベータの戦いであったり、最近ではADSLと光ファイバーの戦いでも分かる通り、必ずしも高性能・高パフォーマンスが勝つわけではありません。そういった例は幾つもあるものです」
「1対多に向けてストリーム技術で送るといったものも、もちろんマーケットとしては大きいと思いますが、テレビ電話や携帯電話に見られるようなかなり狭い特定を相手にしたコミュニケーションのマーケットも依然注目されます。例えば、会話の中で、映画の話になったり、スポーツの話になったときに、画面の中にあるコマンドを打つ。 もしくはボイスで何かキーワードを入れると、詳細情報が出てきたりチケットが買えるといったことも面白いでしょう。シスコシステムズでは、日本のメーカーとのアライアンスを通じ、それに近い、新しい電話端末をすでに作っており、先月、日本のCTOの大和氏に見せて頂いた。実用化されてくると、従来のようなパソコンや携帯電話でのe-コマースとは違った空間が出てくると思います。一方で、パソコンを必要とする場合、やはりパソコンを使える人は限られてくる。音声でメニューが選べるとか、画面が切り替えられるといったような、キーボードフリーの環境、インターフェース、私たちユーザーのすぐ手元の環境という意味では“エッジ”という要素が重要になってきます」
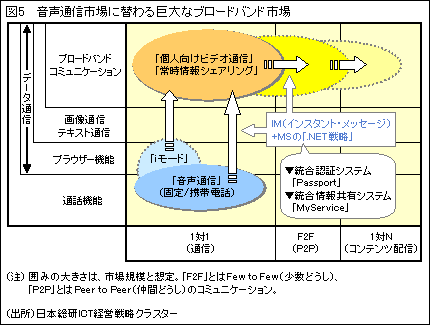
「今の日本企業を見ると、“リセット”がかかったような状況、自信喪失になっている。だから、カルロス・ゴーン氏が日本に来て、大なたを振るって改革しなければ利益が出ないとか、競争力が復活・向上しないといったことが起きている。レガシーな資産、日本の技術やノウハウなどの構造変化は、産業界でも重要です。さらにもう少し広い話をすれば、日本の人口構成も変わってくるのと同時に、中国なども力をつけてきますから、そこに向けて、日本のマネジメント力、ICTのような産業力復活の鍵を握る技術とその基盤形成を通じ、強みを出していかないと日本は10年以内に沈没してしまう」
「英国は“ウィンブルドン現象”などと言われ、英国のマーケットでプレイする企業は外国企業ばかりであり、自国企業はほとんどないと話題になりましたが、日本でも十分にそういったことが起こり得る。しかし、最近の金融市場などを見ると、外国勢からもそっぽを向かれ、ウィンブルドンの場(市場)さえも提供できていない感があります。事態は大変深刻です」
●ブロードバンド第2幕におけるセキュリティーとは
「ITが普及すればするほど、企業においても消費者マーケットにおいても、セキュリティーホールが多く出てきます。セキュアなプラットホームが新しいデジタル社会、ブロードバンド社会におけるインフラになっていくのではないでしょうか。それに、ビジネスチャンスという側面もあると思います。例えば、インターネットという世界は、どこまでいってもセキュリティーホールが存在しますから、ゆくゆくは、管理されたクローズドなネットワーク基盤というのが社会的に重要なものとして出来上がっていく、普及していくのではないかと思っています。お金を預かるところが銀行であるのと同様に、銀行のようにセキュリティーの高い、情報を預かるブロードバンドアーカイブのようなサービスが、今後の社会および産業の新しいデジタルインフラとして不可欠になります」
「もちろん、インターネットで情報を検索する程度のことに、ユーザーが高い費用を払う場面は今後も余りないかも知れません。でも、セキュリティーが重要な金融機関だとか、あるいは研究開発を行なっているようなところでのデータのやり取り、情報のやり取りには、そういう空間が必要とされてくるのだと思います。過去、ネットビジネスが今一つブレイクしなかった要因として、これまでは人が意識して、その情報を選んでいた仕組みだったこともあるでしょう。今後は、機械(パソコンなどの端末)どうしが自動的にやり取りを行う“Webサービス”のような仕組みにより、ユーザーがおのずとインターネット上のコンテンツやサービスに、対価を支払わざるを得ない状況がここ数年の間で徐々に浸透する。そして、それがクリティカル・マスを超えれば事態は一変するでしょう。そうなればB2Bマーケットだけではなく、本来巨大なマーケットでありながら、昨年のネットバブルでほぼ壊滅状態となった消費者市場向けの、B2Cビジネスも再び脚光を浴びることになるでしょう」
「米国のデータセンター事業者などは、そうした動きを少々早く読み過ぎて過大な投資をしてしまい、資金繰りなどの主にバランスシート上の問題ゆえに自滅してしまった印象があります。しかし、長い目で見れば需要はあるでしょう。従来の回線交換に替わる、ブロードバンド時代の新たなゲートウェイ(関門所)の位置付けになるからです」
新保氏はこのようにIT革命第2幕の展望を語った。