投資・競争パターンに沿ったブロードバンド市場戦略
出典:統計情報研究開発センタ『ESTRELA』 2002年10月号
1.ブロードバンド時代の競争とは?
ブロードバンド時代に求められる企業の事業戦略や経営戦略について考えたい。ブロードバンド時代では、何が変わるのであろうか?
「規模の経済」、「範囲の経済」、そして「関連性の経済」(筆者の造語)の3つが、ブロードバンド環境下では効いてくる。
● 「規模の経済」:
生産量の増大につれて平均費用が減少する結果、利益率が高まる傾向のこと。
● 「範囲の経済」:
複数の財・サービスを個々の企業が提供した場合の合計費用より、1企業がそれらを同時に提供した場合の費用の方が低いこと。品揃えによる効果が期待できる。
● 「関連性の経済」:
個々の財・サービスで獲得できる利得(投資案件の正味現在価値NPV:Net Present Value)を合計するよりも、共通インフラに乗った複数の財・サービスにおける相互間の利得は、消費者のライフサイクルの中でシナジー(相乗)効果を発揮し高くなること。
特に3つめに着目することで、当該企業においては、ブロードバンド市場を戦う企業の投資機会と競争のパターンに合わせた戦略は異なってくる。
また、競争監視・規制当局においては、新旧様々な企業の参加により形成されているブロードバンド市場において、どのようなものが最も競争を進展させるモデルであるかをイメージする必要があろう。
限定的な適用ではあるが、企業競争という「人(事業者)」を相手にしたものであるがゆえ有効と思われる「ゲーム理論」(2001年度のノーベル経済学賞の対象)や、競合他社と共有され得る「リアルオプション」について触れてみたい。ブロードバンド新市場では新興競争相手の早期参入により、他社とともに自社もメリットを享受し得るような、正の戦略的バリューが存在し、市場全体のパイ(売上高またはキャッシュフロー)を拡大させることにつながるかも知れない。
2.ADSLが破壊的な技術となって復活した
2000年春、「IT(情報通信技術)・ネットバブル」後あるいはその最中にも、ブロードバンド技術は急ピッチで進んでいた。2000年秋にADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line:非対称デジタル加入者線)サービスが登場したとき、大半の人が現在のようなブロードバンドの進展を予想していなかった。
わが国が最高水準を誇るハイテク光ファイバー関連の技術が、後述のIP(インターネット・プロトコル)系の通信バックボーン(新しいデジタルインフラ)になっていることの意味は大きい。しかし、消費者に大きな影響を与えたのは、どちらかというとローテクのADSLであった。ADSLは10年前の米国で1992年から1994年のビデオオンデマンド(VOD)への期待盛り上がり期に、商業的には失敗に終わったビデオ伝送のインフラ技術として既に姿を現していたものであった。
それが2002年7月末わが国の場合、ADSLサービスへの加入者数は361万人に達し、CATVのブロードバンドユーザー数を合計すると現在では530万人相当となっており、NTTの「ISDNからFTTH(Fiber To The Home)への基本シナリオ」を狂わせ、旧来通信(固定電話)による収入面に対して破壊的なインパクトをもたらしている。
この数はこれまでの主要通信サービスであった固定電話契約者数のほぼ10%に相当する。固定電話や携帯電話など類似サービスの立ち上がり時期における経験則から、ブロードバンドサービスもその勢いにおいてクリティカル・マス(臨海量)を超えたといえよう。2001年をブロードバンド元年とすれば、わずか1年半程度のことだから驚きである。
ブロードバンドの現下の牽引役となっているADSLは、ハーバード・ビジネススクールのクリステンセン教授が呼ぶ「破壊的技術」として復活し、共通のインフラ上でそれを利用したIP電話などの関連サービス普及への弾みをつけた(「関連性の経済」)。
3.シンプルでオープンなIP技術が革命をもたらしている
帯域が広い(高速・大容量)という意味のブロードバンドは、その意味よりも次のことが重要である。
(1)技術革新の視点
ブロードバンド環境とは、IP技術による新たなデジタルインフラであることが根本的に重要である。
この技術により、テキストや動画、TV映像などの情報すべてがIPの上に乗るインフラとなることで、個々のサービスが大幅に安価に提供でき、社会や産業の隅々までその恩恵と革新がもたらされ得る。
(2)消費者行動の視点
実際既に、ブロードバンドサービスが常時接続環境で消費者へ安価に提供されている。
IP技術の簡素な仕組みを利用した事業者の競争促進により、同サービスが定額で提供され出した。これが消費者に与えるインパクトは大きい。
ダイアルアップ従量課金に対する縛りからの開放により、消費者のインターネットに対する浸透度を年々高めている。今やインターネットが生活に不可欠になり(Must要素:ニュース検索や決済など必要な行為)、楽しみ(Wish要素:エンタテイメントなどのコンテンツを欲すること)を得るための現実的な手段となってきた。
加えて、水道、電気、固定電話、あるいは最近の携帯電話のような、手軽に・気軽に・簡単にアクセスできる、ブロードバンドサービスとのインタフェースを担う端末などを含めた仕掛けが、消費者行動においては重要となる。
(3)企業活動の視点
旧来の回線交換(電話交換機)に基づく高価な専用線ベース(米国の約5倍高い)による企業システムから、多くの企業において超高速でシンプルなIP網による提供(IP-VPN、広域インターネット)へのシフトが活発化している。
現在の不況下、企業のTOC(Total Cost of Ownership)を下げることの効用も大きいが、それ以上に、企業内外でのコミュニケーションやコラボレーションが進展するインフラとしての活用の意味が大きい。
ERP(Enterprise Resource Planning)システムやSCM(Supply Chain Management)などのバックエンド系システム導入による商品の在庫コスト削減や販売までのリードタイム短縮の競争は現在までにほぼ一巡し、今やグローバルな企業競争は、新しい戦略的・他社差別的な商品づくりやそのための組織マネジメントやナレッジマネジメントが鍵を握っているからだ。キーワードは、経営(マネジメント)におけるイノベーションだ。
4.市場参画プレイヤーの動きとジレンマ
ではブロードバンド市場は、現在どのようになっているか?同市場の構造(レイヤー)を次のように概観する。
(1)ネットワークレイヤーでの競争
ネットワークレイヤーでは、IP網ベースの通信インフラを経営資源とするサービスが中心である。全国規模の超高速IP網の所有またはその利用により、「規模の経済」発揮がポイントとなる。
ユーザーの足回り部分であるアクセス網でのダークファイバーの開放が、この1年間程度でNTT東西に加え、電力会社、鉄道、道路管理者らからもなされている。これで新興事業者が低コストで自前インフラ網を保有することも可能となった。
NTTグループなどの既存事業者に加え、2003年東京電力系のパワードコムとの統合が決定されているクエスト・コミュニケーションズ(CWC)や、ソフトバンクグループ(Yahoo!BBを実現するギガ級IP網を自前保有)が主なプレイヤーとなる。
旧来事業者にとっては、固定電話やISDN、または専用線などの収益の落ち込みを抑止できず現在、頭が痛い。だからといって、低価格の常時接続環境では一定以上の収益確保のスキーム(道筋)が描けない。
あるいは、新興事業者にとっては、相対的に低いといえどもデジタルIP網への投資負担は決して小さくない。株価も下がり資金繰りは厳しい。
両者とも同じゲームを戦い続ければ、即ち両者がかえって好ましくない「囚人のジレンマ」に陥って問題は解決(利得を最大化)できるのか?
(2)プラットフォームレイヤーでの競争
プラットフォームレイヤーでは、決済や認証、セキュリティー全般に関するノウハウに関するサービスが主なものである。
次の「アプリケーションやコンテンツ」を、ネットワークインフラに乗せて商用化するには、このサービスが不可欠となる。「範囲の経済」が効く分野ゆえ、それを巡る攻防が今後活発になるであろう。
ブロードバンド市場では、人の行為そのものが完結した意味をもつコンサマトリー(Consummatory)なコミュニケーションである「コンテンツレス・コンテンツ」(例:写メールなど含む)、そしてコンテンツホルダーと消費者との仲介(Agent機能)に立ち手数料等をとることで、消費者がそのコンテンツを得やすいようにする「エイジェント・コンテンツ」型プラットフォーム(例:利便を売るポータル、著作権処理機構)が、通信事業者の経営の鍵を握る。
上記新旧の通信インフラ事業者に加え、マイクロソフト、Nifty、SCN(ソニー・コミュニケーション・ネットワーク)、日本ベリサインなどがプレイヤーの例である。
前者と後者ともに、映像(TV電話など)をやり取りすることで、これまでにないコミュニケーション形態の需要を喚起すること、即ち同レイヤーのサービスに消費者をナビゲートする仕組み(通信端末の活用を含め、利用シーンにおける時間と場所を超えた連続性のバリューを提供するなど)に知恵を絞っている。
ただ、従前の電話サービスのようなシンプルなモデルではなく一筋縄ではいかない。電話屋や施設貸し屋といったマネジメントから、自ら脱却しない限り前には進めない。
(3)アプリケーション/コンテンツレイヤーでの競争
アプリケーション/コンテンツレイヤーでは、アプリケーションソフトを含め、狭義のコンテンツである「パッケージ・コンテンツ」(例:映画、音楽、雑誌記事、または消費者向け・法人向け各種ソフトウェアなど)に関するサービスが主なものである。
一つ一つの多様な商品バリューとそのプロモーション(広宣活動)などが事業の優劣を握る。
ブロードバンド市場では、「キラーコンテンツ待望論」が根強い。しかし、コンテンツそのものの扱いやビジネスについては、著作権問題やこの分野の既存参画プレイヤーとのWin-Winモデルが描けず、従来の放送ビジネスのようなモデルが打出せないでいる。
コンテンツ事業者にしてみれば、先の2つのレイヤーが商用ベースでストレスなく用いることができない限り、なかなかブレイクしない。今年6月の日韓サッカー・ワールドカップにおける良質の映像コンテンツも、放送という旧来のビジネスの枠組みが中心であった。一方、「Yahoo!スポーツ」などでは記録的なアクセス数となり、映像コンテンツそのものよりも、ポータルという仕掛け(スキーム)が消費者へバリューを提供していることとなる。
その意味で、携帯電話市場ブレイクの立役者となったiモ―ドはキラーコンテンツではなく、キラープラットフォームといえる。コンテンツがこのようなプラットフォームがあって初めて活かされる証左でもある。
コンテンツ分野のブロードバンド事業者は、同市場が一定のマス(多数の消費者)の規模に到達すれば、一人一人に本人の欲するコンテンツを配信するなどの、ワン・トゥ・ワン的な広告も打て、スポンサーから追加的な収入を得ることもできる。ただ、これにはもう少し時間がかかろう。
(4)「関連性の経済」が威力を発揮するとき
これらの3つのレイヤーが相互に機能し合い出すと、「関連性の経済」が威力を発揮することとなる。この経済性により各レイヤー別のサービス・事業のシナジーを出せない限り、サービスの価格破壊的な状況が進展するなか、市場全体のバリュー(キャッシュフローベース)は低下せざるを得ない。
市場が縮小均衡に留まるようなシナリオをどうしても回避しなくてはいけない。景気低迷で閉塞的な状況が続くわが国においてブロードバンド市場は、同状況を脱し新たな成長シナリオを描きつつ、中国などの近隣諸国との差別化や米欧などとの競争優位性を確保できるかなどの点で、極めて戦略性の高い産業であるべきだ。
2001年から政府IT戦略本部などでは、各レイヤーごとの水平分離(アンバンドリング)が可能な市場構造を模索しているが、ブロードバンド時代には、「新しい垂直統合」の動きも出てこよう。
従来から、米国などでも電気通信市場では、特定事業者が専有する全国ネットワークインフラを基に、その上のサービス(市内、長距離・国際、インターネットなど)を統合する動きが規制当局から牽制され、あるいは旧AT&Tのように事業者自らの経営効率化の判断から、企業の基本機能の分離が実施されてきた。
新たなブロードバンド市場の育成や発展のため、旧来からの枠組み・既成観念を一旦は取り払い、有効的な競争が最も進展するモデルを描く作業が当局には必要となってきた。
5.新たな収入源とその獲得方法をどうデザインするか
消費者から見れば華々しく映るブロードバンドサービスも、事業者にしてみれば現在のところ簡単に収益確保(あるいはキャッシュフロー向上)に結びつかない。どうしてか?
(1)第1段階では少数者しか収益を手にできない
まず、まだ財務的なブックベースの収益規模では、1桁から2桁分、トヨタやソニーなどの大企業には及ばないが、収益を出し事業を安定的に運営している企業も少なくない。
IT・ネットバブル期には、短期間に多くの参入者や資金が多く市場に流入するなか、株式市場やベンチャー・キャピタルなど市場の未整備状況も露呈し、バブル崩壊で大半のベンチャーと既存企業の期待を裏切った。しかし、そもそも、そんなに甘い話しが簡単に転がっているわけはない。倒産や事業不振に陥った企業は、外部環境ばかりを責めても空しいだけである。手厳しいようだが、むしろ自社の経営イノベーション能力やそのマネジメント能力を反省すべきであろう。
一方、同バブル前後のIT革命第1期に、一握りの企業はバブルを乗り越え、成功裏にビジネスを軌道に乗せている。ベンチャーの旗手として、読者にはIIJ、ヤフー(ソフトバンクグループ)、楽天など幾つもの社名が浮かぶだろう。これら企業には、東電、ソニー、NTTといったオールドエコノミーとの戦略的アライアンスの実績もあり、マネジメント能力が際立っている。
ただ前述の通り、これら新興組にはオプション資産バリュー(目に見えないインタンジブルな要素)と株主資本を加えた「時価総額」(豊富な資金力)の大きさゆえに、スピーディーな事業展開ができたという実態があった。これはさらに、インターネット上に出現した完全市場的なからくりにより、いわゆる一人勝ち(A Winner Takes All)の原理が作用したためである。
この原理が、今までのネットの世界でも今後のブロードバンド期(IT革命第2期)の世界でも支配的になる領域が存在し、これを巡る競争は継続・激化していこう。
(2)新たな収入源とその獲得方法
多くのIT・ネット系企業の事業が収益に結びつかないのは、次の2つの点に集約される。
● 市場における顧客数規模の問題:
前述の通り、ブロードバンド市場の浸透度は約10%。残り90%の顧客の争奪戦が今も繰り広げられている。競争・規制問題に関する当局にあっても、わが国において同市場が21世紀を担う力強い産業として育成・発展へと導くには、絞るべき智恵とデザインする戦略の中身が問われることとなる。
● ライフタイムとユビキタス環境でのバリュー提供による収益確保の問題:
これは、一人の顧客へ様々なバリューを継続的に提供することで、何度もそのバリュー見合いの対価をとる仕組みを創れるかがポイントだ。現在展開中の顧客数ベースの収入モデルでは収益確保の点で限界がある。つまり、顧客数Nに規定され、かつ定額的な料金の仕組みをとっている以上、損益分岐点はなかなか見えてこないのが実態であるはずだ。
この問題では、「顧客ライフタイムバリュー(LTV)」という軸と、「ユビキタス(どこでもいつでも)バリュー」という軸に沿ったサービスを通じ、顧客バリューの新たな創出や持続的な増価につなげることができるかが重要となる。
前者でも後者でも、非可逆的・直線的なフローを描くのではなく、「スパイラル性」(螺旋的な発展の可能性)や「周回性」(消費者が当該仕組み内の拠点間を行き来する動き)に基づいたビジネスモデルを描けるかが、競合他社との差別化のコアとなる。
6.ブロードバンド市場における競争戦略
新たな市場を創出するには、全面的ないし部分的な旧来市場の破壊は不可避であろう。旧来市場の破壊に向けた動きとプレイヤーの交替は、部分的に進んでいるように見える。
わが国のブロードバンド市場の発展には、新旧両プレイヤーによる有効的な競争の枠組みをつくることで、同市場全体でのバリュー(キャッシュフローなど)をいかに高められるかが大きな課題である。
(1)主役の交代を巡る攻防
石炭を主原料とした蒸気機関が、石油や電気を燃料とするディーゼル機関や電車に主役を譲った。約100年の歴史をもつ完成された回線交換(交換機)の技術がIP技術に置き替えられるとともに、同技術を基礎にしたインフラが整備され、その上で市場に支持されたサービスが乗り始めた。
前述の通り、2000年秋から本格的に商用化されたADSLサービスにより、消費者はインターネットを身近なインフラとするようになった。今年になってから相次いで登場しているIP電話などもその例といえる。加入者の需要及び便益が当該システムの加入者数や、誰が加入するのかに依存する点に着目した「ネットワークの外部性」が際立つサービスである。
同外部性は需要側にとっては「規模の経済性」のことであり、新たなIPインフラ網を巡る攻防がCWCやソフトバンク(Yahoo!BB)などの新規参入により強まってきた。
(2)ブロードバンド時代の競争戦略
最後に、ブロードバンドの投資・競争パターンに合わせたブロードバンド市場戦略のイメージを描いてみる(図表参照)。
投資・競争パターンとしては、【1】非挑発的(現状維持)、【2】先制攻撃的(価格等差別化)、【3】応戦的(敵の出方次第)、そして【4】一見無防備的(次の手で勝負)、という分類を描いてみる。
これらパターンは、本来、分析対象とする産業の種類やその事情(成長の段階や競争状況など)によって、通常はどれか1つを選択し、そこでの利得(事業者にもたらされる成果であり、投資案件の正味現在価値と置き換える)を最大にする行動を事業者(この場合、A社とB社の2社のみ)別に分析するものである。
パターン別の利得マトリクスにおける各領域(4つのセルで構成される)には、両社の利得の比率を○印の大きさでイメージしている。そして、X軸とY軸の「待つ」「動く」は、各社の投資アクションなどの出方を示すものである。
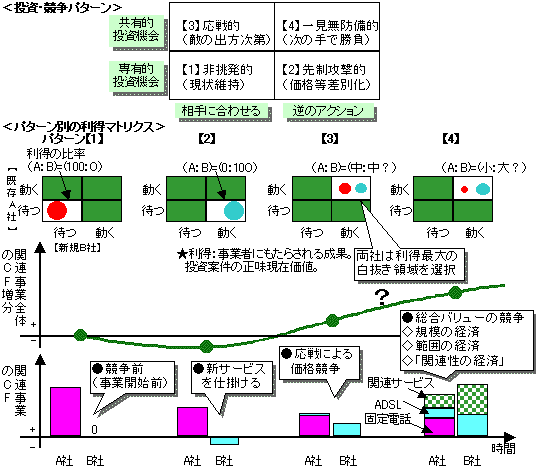
(注) CF:キャッシュフロー。A社の例:NTT(フレッツADSL+関連サービスα1)等、B社の例:ソフトバンク(Yahoo!BB+同α2)等。α1:FTTHやプラットフォーム等、α2:ギガ級IP網ベースのIP電話やコンテンツ等サービス。最上部マトリクス:Trigeorgisの分類参照。
(出所) 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター(新保2002)
例えば、競争前(事業開始前)のパターン【1】では、A社が事業を継続展開している。パターン【2】では、そこへIP技術等を用いてB社が新サービスを仕掛ける行動をとり、A社は待機して動かず(あるいは、その低価格性やスピードにより動けない)。また、パターン【3】では、B社の動きを無視し得ないA社が動き、応戦による価格競争が展開される。最近のADSL戦争はこのパターンゆえの状況を呈しているといえよう。
さらに、パターン【4】では、総合バリューの競争(規模の経済、範囲の経済、「関連性の経済」)となる。このトータルウォーが始まる可能性、即ちこのパターンを正の戦略的バリューと見込む事業者が出てこよう。
これら4つの、プロダクト・ライフサイクルに沿ったパターンが順次選択された場合の、各社の関連事業のキャッシュフローと関連事業全体のキャッシュフロー増分を、それぞれイメージとして示すことができる。
例えばB社の関連事業のキャッシュフローを見る場合、ADSLや、ポータルまたはコンテンツそのものに係る「エイジェント・コンテンツ」が同社の戦略サービス(商品)である。一方A社では、これらに元々のキャッシュフロー獲得手段であった固定電話が加わる。しかし、固定電話資産の追加投資が競争上非効率となる場合には、対抗上、同資産を埋没コストとみなした上での新規投資を迫られ、両者のハイブリッドなインフラを手にすることになる。ただし同投資は、大概一からつくりあげることの方が低コストでできるケースが多く、その経営判断(リアルオプションの評価)には困難がつきまとう。
反対にB社では、迅速な事業展開とダークファイバーなどの低コストで敷設できた新たなIP網を手にすること、そして、その上で効果的に機能し出す可能性のあるADSLやIP電話、さらに自社グループに抱えるコンテンツ回りの多種多様の関連サービスが、A社との最大の差別化ポイント(リアルオプション価値)となる。
(3)縮小均衡市場にならないための政策とは?
以上は、仮のシナリオである。実際には両社がまったく同じタイミングで判断を下すとは必ずしも限らない。両社間での駆引きなど複雑なアクションが絡む。
当事者にとっては、熾烈な攻防が繰り広げられるが、市場が決して縮小均衡のゲームに陥らないようにするためには、関係当局からの一定(最低限)の市場関与が求められよう。
具体的には、将来の市場環境についての不確実性を考慮することで、政策面では計画期間を通じ競争パターンに応じた柔軟性をもたせる(リアルオプション価値を求める)ことが重要である。
さらに、少数が参入するインフラ的競争市場において企業は、自らの利得を最大化しようとするゲーム理論的な動きを通じ、政策の裏をかくことが少なくないことを、当局はよく研究することである。
新たなブロードバンドインフラを巡るケースでは、将来の成長機会への足場につながるバリュー(正味現在価値)をどう描くか、とりわけインフラ型事業に適した「成長オプション」(リアルオプション理論におけるオプションの一つ)、あるいは参画プレイヤーにおいて、固定費が賄えないような環境下で撤退ができるバリューをどのように見出すか(同「撤退オプション」)など、複数のシナリオが描けよう。
いずれにせよ、わが国ブロードバンド市場の発展のため、関係プレイヤーまたは関係ステイクホルダー(当局を含む利害関係者)が智恵を結集して臨むべき問題を、私たちは目の前にしているのだ。

