土木はITSビジネスのどこにいて、何ができるか
出典:土木学会誌 2002年11月号
土木建設業にとってITSとはどのような産業なのか。ビジネスとしてのアプローチは何か。それをはじめて考えるためには、次の3段階を踏む必要があるだろう。
①ITSという政策とITSというビジネスの関係
②ITSビジネスの全体像の中で土木業界の位置
③土木業界にとってITSに取り組むことのビジネス上の意義
そして結論を先に述べてしまおう。土木建設業にとってITSを民需ビジネスとして取り組める領域は広くはないが、取り組むためにはITSについて政策もビジネス環境も含めた全貌を正しく把握しておく必要がある。なぜなら土木建設業が取り組むことになるのは、道路建設ではなく、都市生活の構築だからである。
1.ITSは具体的「新産業創出」段階にあるが‥
ITSは何よりもまず自動車交通問題の解決方策であって、市場拡大のためにITSを取り組むのは本末転倒という考え方も一理ある。しかし社会システムとしてITSを一般市民に使ってもらい交通施策としての効果を示すためには、個人の持つ端末が普及していることが大前提で、それを税金だけでまかなうことは、現在の日本では不可能である。したがって交通施策としてのITSと経済波及効果としてのITSは切っても切り離せない関係にある、と捉えないと具体的な推進はありえない。これをETCという、おそらくITS最大の難物について取り組みが四苦八苦しているのが、交通政策としてのITSの今日現在の状況である。
1998年11月の「緊急経済対策」(経済対策閣僚会議決定)でITSは「21世紀型社会の構築に資する景気回復策」として採り上げられて以来、一次的な効果である交通問題解消よりもむしろ、ITSの整備にともなう経済波及効果に着目することでITSを推進していく、つまり民間企業のビジネスとしての取り組みを前提としてITSという施策を実現させる、という流れになった。
1999年2月に電気通信技術審議会から発表された「2015年までの累積で、ITS情報通信関連市場は約60兆円、関連全産業への効果約107兆円。2015年時点の関連市場7兆円の下で107万人の雇用を創出」という数字が現在も一人歩きを続けている。上記60兆円のうち、公共発注事業の部分は累積10兆円程度に過ぎず、各年ごとにみても1兆円に満たない市場としてカウントされている。しかもこの発注内容は基本的に既存の道路にITS関連電子機器を設置することであり、土木建設業がこれを元請けするにしても、本来的に土木技術の先進性が特別に反映される内容の事業ではない。ITS関連市場全体の成長は主に情報通信サービス産業の応用によってもたらされるものとして考えられており、土木建設業に直接利潤をもたらすものとは考えられていない。
よくITSにおける土木建設業の「出番」として、「ETC導入完成後の、簡易型インターチェンジの増設、既存インターチェンジの省スペース化改築、空きスペースにおける物流センター等の建設」がイメージされている【図表1】。道路交通の政策的目標の実現方策としては確かに有意義であるが、しかしこれはETCが全車普及達成を前提とした話であり、財政削減の潮流の中で道路整備の長期計画として位置付けていくのか、そもそも財源をどうするのか、という点での検討はまだほとんど進められていない。
【図表1】 ETC全車普及がもたらすインターチェンジ、サービスエリアの省スペース化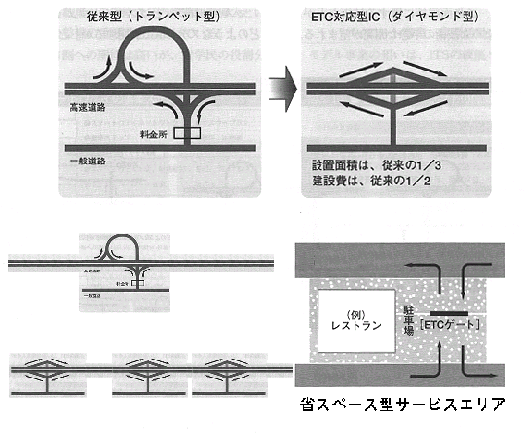
したがって、土木建設業が現在の公共受注のビジネスモデルを中心に据えている限り、ITSビジネスの広がりと成長の恩恵には当面あずかれない、ということになる。それでも上記のとおり、電気工事も含めて包括的に元請けとなる体制を組むことで確実な増益の対象にはなるだろう。そのチームリーダーとなるために必要なことは3.に述べる。
2.「ITSビジネスを創出する」とは「消費者にどう払ってもらうか」
では土木建設業はITSにおいて公共受注以外のビジネスを見つけることができるか。それは結論から言えば、土木建設業がITSに提供できる商品が消費者の消費マインド、あるいは国民の納税マインドを喚起するものかどうか、にかかる。つまり消費者がお金で換算できる魅力がその商品にあるか、ということである。この視点からITS関連業界の広がりを1枚の図にしてみたのが、図表2である。
【図表2】 ITS関連業界の広がり 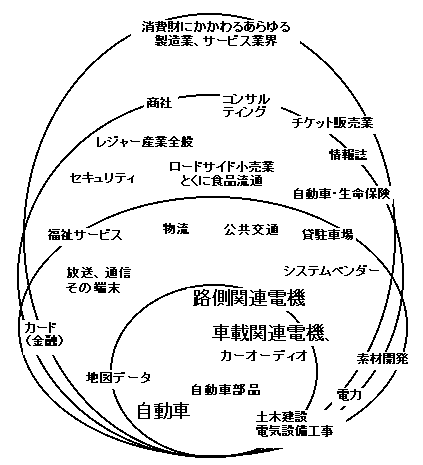
この図の詳細説明は省くが、要するにITSビジネスの広がりとは、土木建設業からいかに離れていくか、道路交通に小売業、サービス業を持ち込めるか、である。では土木建設業はどこに位置するかというと、自動車の走行機能、強電弱電に関わる電気設備、無線電波の通過や遮断に関わる建設素材、といった接点が想定されるに過ぎない。その点から、建設業界はITSについて、大手ゼネコン数社が道路交通シミュレーションソフトの独自開発を競争していることを除けば、あまり積極的ではないのが現状と言えるだろう。
財政が逼迫し、公共事業の前倒しが景気対策として効果をあげないと解釈されている現在、ニーズのないものは作れないというのが公共事業の趨勢である。すでに自治体の施設建設受注などで積極導入されているPFI、あるいは施設運営のアウトソーシングなどの手法も、基本的には行政改革の一部分として施策執行段階でのコストダウンを目指している手法に過ぎない。公共側が利用料を払うということは、公共に利用の意義があるからで、それはつまるところ国民あるいは市民がその施設の利用の意義があるからである。
では土木建設業が提供するITSの一端は、人々に魅力の対価を払わせることができるのか。ETCですら四苦八苦している「魅力と対価の提示」を、土木建設業はできるのか。
3.土木建設業にこそ、ITSシティーを支える構想力が必要
ここまでネガティブ要素が並んできたのは、ITSビジネスを短期的な投資回収の対象として捉えるがゆえである。ITSが整ってきたときに消費者、国民、市民にどういう生活の変化がもたらされるのか、そのために必要な都市とはどういう構造をもったものなのか、についてはほとんど議論されていない。ITSと都市の関係について描いている関係官庁や民間企業のプレゼンテーションもあるが、これらは現在計画されているITSの要素技術の利用シーンをかなり強引に紹介しているに過ぎない。
ITSに限らず、「都市屋」と「情報屋」は往々にして違う未来生活を描く。その違いは視点の広さ長さからくる。土木技術が消費者にもたらさなければならないものは、「近未来生活」の具体像である。したがって、土木建設業はITSについて起こるあらゆる生活の変化について目配せをしていなければならない。
ITSビジネスの関係者がいくらがんばっても、都市構造を直接変えることはできない。都市構造を変え、ITSを魅力的な社会システムとする生活の構造を実現する技術は、土木建設業界しかない。1999年以降、建設省の提唱するスマートウェイ、経済産業省と総務省の掲げるスマートタウンといった「沿道のまちづくりと結びついたITSの導入」の実現に向けて、建設業の役割を描こうとする動きもすでにある。
たとえば、ITSが実現した街での横断歩道とはどういうものになるのか、ガードレールとはどういうものになるのか、ミラーや標識はどういうものになるのか、それらを含めた都市景観はどう変わるのか。道路構造令や道路交通法そのものへの提案も含めた、ITS整備後の都市・沿道地域開発のビジョンを描いて、はじめて土木建設業のITSビジネスが消費者のニーズとマッチしてくる。ニーズにマッチすれば、あらゆるITSの要素技術をプロデュースし消費者に届けるビジネスが成立する。
本来的に土木建設業が得意としてきた構想力を、ITSの個々の要素技術やその効用についてきちんと理解し、ITSと都市生活のプロデューサーとなる資質を身に付けることが、土木建設業の最初の突破口である。

