"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第8回「レガシー公益事業会社のICT統合サービス戦略とは?」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2002年3月14日
●電力自由化の波が市場再編を加速する!
2001年11月から本格的な電力自由化に関する枠組みの議論が、経済産業相の諮問機関(総合資源エネルギー調査会電気事業分科会)で始まった。電力自由化はわが国では1999年にスタートし、発電設備をもったレガシー公益事業会社が、余剰電力を電力会社へ入札を通じ卸売りなどが可能となった。
2002年3月からは2,000キロワット以上の大口需要家への小売りが自由化され、現在までにダイヤモンドパワー(三菱商事系)を始め、サミットエナジー、エネット、新日鉄、丸紅など元気な9社が新規参入した。
わが国では、送電配電部門と他部門のアンバンドリングは、a)会計分離においてさえも不明瞭な部分があるとされる。一方、欧州の中でも電力自由化の先進国である、英国、スウェーデン、フィンランドなどでは、b)経営分離、c)法人格分離、d)所有権分離が既になされている。
1990年半ばに電力自由化の波が襲った英国では、愚策により過去約半数の公益法人が消滅してしまった。
本稿では、東京電力などのレガシー公益事業会社が今後直面する市場再編に対して、ITや情報システムを駆使してどのように乗り切ることができるかを示唆したい。またここでのアプローチは、同様なポジションに置かれている地域系電話会社(NTT東西、NTT-MEなど)にもヒントになるに違いない。
●新興事業会社の参入が本格化してきた!
前述の新規参入会社のシェアは、その1社であるエネットの資料によると、2001年8月時点の特定規模需要において、未だわずか0.39%に過ぎない。
これは現在のところ競争条件が未整備の段階にあるといえるからだ。例えば、託送料金の販売価格に占める割合が22%〜32%もある点、また送電サービス料金が米国との比較で約7倍(金額)と極めて高い水準にある点、あるいは同時同量の原則(小売り託送の場合に需要量と供給量を30分単位で一致させる義務)などの厳しい規制がある点が挙げられる。
これらの規制緩和が一層進展すれば、欧米並みに市場の再編が進み、ちょうど通信の世界でNTTが厳しい競争にさらされているのと同様な状況に直面することも予想される。
現在では契約種別の「特別高圧」の主なユーザーである、大規模工場、デパート、大病院、オフィスビルなどの大口需要家向け市場のみが、小売り自由化の対象である。契約口数は約8千に過ぎないが、同市場規模は約2.8兆円(1999年度の全電力市場規模の19%)にもなる。この市場のパイの奪取が始まったわけだ。
それ以外の市場については、「高圧」市場がある。主なユーザーは中小規模工場、スーパー、中規模ビルで契約口数は約70万口で市場規模は約5.0兆円(シェア34%)。また、「低圧」市場では、同様に小規模工場やコンビニなどのローカル地域にも及ぶSME(中小企業)が主で約660万口、約1.1兆円(同8%)。最後に「電灯」市場では、一般家庭が主なユーザーとなり約6,860万口、約5.6兆円(同39%)となる。
同の大口需要家市場では、1契約口数当り年間3.5億円にも上り、同の場合の約50倍、同の約1,750倍にも上る。すなわち、大口需要家のシェア低下は、レガシー電力会社にとっては経営を直撃するものだ。
●競争のポイントは顧客サービス(CRM&CRB)が鍵!
果たしてレガシー電力会社は、かつて経験したことのなかったこの難局を乗り越えることができようか?
カナダのBCガス、米国のノーディック・エレクトリック、豪州のアドバンス・エナジー、英国のセントリカなどの欧米公益法人が如何に成功したかのケーススタディを通じ言えることは、次の2点に凝縮される。
1)「顧客サービス」の発想に転換すべきである。これは従来「顧客=請求書のための末端メーター」と見るに過ぎず、顧客を研究する姿勢がなかったことからの抜本的転換を迫るもの。
2)送電・配電部門から小売り部門を分離すること、またはその対応を今から徹底検証しておく必要がある。
本稿では特に、同1)についての取組みイメージや戦略を示そう。これには、CRM(Customer Relationship Management)やCRB(Customer Relationship Building。第3回と第4回)が効果を発揮する。IT、正確には情報と通信とを合せた技術を示すICT(InfoCommunication Technology。欧州でよく用いられる表現)を駆使することなしには、新興企業には対抗できない。
CRMは必要条件だ。顧客のダイレクトなリクエスト(支払い・消費情報、アカウント情報など)をネット上で把握する。豪アドバンスでは、商工業分野の顧客が30分間隔で電力消費情報をダウンロードできるため、顧客の利用パターンを分析・視覚化し、異常消費の検出が可能になった。また米ノーディックでは、同時に多数の機器の電源オン時刻をずらすことで、電気代を20%削減した例など枚挙に暇がない。
あるいは、自社受付を尋ねた顧客幹部の略歴情報をオンスポットで参照した上でのハイタッチな対応として、その場でオンライン決済や電子ビリング(請求書)などの顧客提供サービスの反応確認などを行う。また、関係ナレッジの蓄積を行う仕組み、さらにキーパーソンへのスピーディーな情報伝達なども有効な手立てだ。
顧客の懐に入り込むためのCRBが十分条件となる。CRMが顧客接点上の情報収集とその分析結果フィードのツールだとすれば、CRBは顧客との共同開発などを通じた新たな顧客関係の構築だ。例えば、CRMで構築した安価でブロードバンドな広域イーサネット系の顧客ネット(エクストラネット)を通じ、電気自動車や省電力機器や環境機器等分野でのコラボレーションにより、大口需要家との対等な関係を築くことが大事だ。
●レガシー公益事業会社は「ICT統合サービス戦略」を打てるか?
これらCRMやCRBでは、顧客との接点となるネットや物理面での両ポータルづくりが重要だ【図表参照】。すなわち携帯情報機器PDAなどの端末や、Webサービスを通じるもの、あるいは一般家庭向けとなるホームゲートウェイ拠点となるホームサーバー、そしてこれらから上がって来る情報をバックエンドにて集約する顧客サービスセンターは、物理的な地域ポータルセンターの役目を担う。
レガシー公益事業会社は、現在の「エネルギー(E)」から子会社を通じて展開してきた「通信(C)」に加え、「ポータル(P)」領域でのローカルSMEを含む顧客ニーズの徹底的な吸上げを通じ、安全・保全面や環境エネルギー面でのシステム(ソフトウェア)開発や顧客共通のプラットフォーム(課金、セキュリティー等)基盤の構築がポイントとなる。
筆者も直接面識のあるRobert.S.Beason氏(全米最大の発電量を誇るサザンの元CIO。第6回)もこの点を強調する。サザンでは工業系、商業系、一般家庭向けのセグメント別に、コールセンターの音声システムと統合したさまざまなシステムを通じ、顧客サービスを提供。また、全スタッフの研修プログラムの整備や、ICT部門における顧客とのサービスレベル契約締結など、その徹底ぶりには驚かされる。
このように「E&C&P」の各レイヤーを統合的にICTでつなぐ、顧客本位のサービス「ICT統合サービス戦略」を今後打出せるか、また子会社の力・基盤を活かすグループ経営をどのように推進できるかが重要になってきた。それには、最適な組織設計やスタッフ・インセンティブ設計などの、新たな制度設計の手腕も問われる。
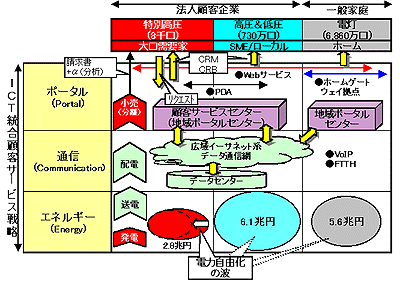
(注)数値は1999年度の契約口数、電力市場規模
(出所)日本総合研究所ネット事業戦略クラスター(現ICT経営戦略クラスター)

