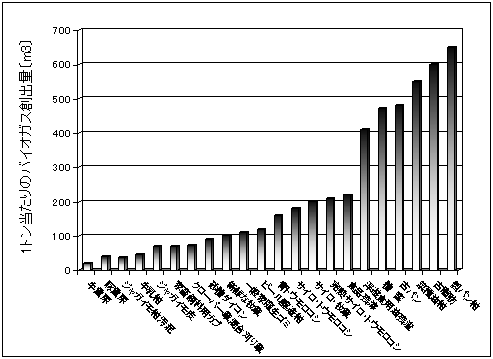PFIが創る環境事業官民協働の地域インフラ:バイオエネルギー
(3)原油換算で年600万キロリットル
出典:日本工業新聞 2002年8月13日
複数を組み合わせ
国内で排出される全廃棄物の約60%は生物由来の有機系廃棄物であり、その量は年間2億8000万トンに及ぶ。廃プラスチックの排出量が年間1000万トンであるのに比べると、生物由来のエネルギー資源であるバイオマス量が多いことが分かる。また、バイオマスは多様であり、その種類に応じて利用方法は異なる。
生物由来の廃棄物は、畜産廃棄物、農業廃棄物、一般廃棄物(生ごみ)、食品産業廃棄物、木質廃棄物の5つに分けることができる。このうち、木質廃棄物以外の廃棄物はメタン発酵に適するバイオマスである。これは全体の88%に相当する。エネルギー資源としてのバイオマスの価値は抽出できるエネルギー量によって決まる。発酵によって生成されるメタンを主成分とするバイオガスの組成は、バイオマスの種類によらずほぼ一定となるので、エネルギー量はガスの生成量で計ることができる。様々なバイオマスの原料1トン当たりのバイオガス生成量を図に示す。バイオガスの生成量は、図に示すとおり、バイオマスの種類に応じて大きく異なる。
ただし、バイオマスの中には単独では発酵が効率的に行なわれないものもある。そこで、通常は複数のバイオマスを適切に組み合わせて発酵を行なう。この際、発酵効率とガス生成率の掛け算によって時間当たりのガス生成率を算出し、これを指標として、様々なバイオマスの組み合わせ方を検討する必要がある。また、ガスの生成率の高いものほど廃棄物として処理委託されるときの収入は低下することが予想される。そこで、経営上は処理委託費も考慮して組み合わせを考える必要がある。
既に、農家によるバイオエネルギービジネスが普及しているドイツでは、ガス生成率の高いバイオマスは逆有償になっている場合もある。菜の花の絞り粕などはその典型例だ。高いガス生成率に加えて単独でも発酵しやすいので、人気の高いバイオマスになっている。
発電量を最大化
バイオエネルギー事業を営む農家は、生産時期を考慮して、菜の花などの複数のバイオマスが年間通して間断なく調達することに工夫をし、発電量の最大化を図っている。
複数のバイオマスを組み合わせる工夫によって、発電量はどの程度得られるのであろうか。大規模農家を想定すると、年間を通じて定常的に入手できる牛ふん尿を10トン/日、生ごみを5トン/日、さらに、季節に依存する菜の花の絞り粕を2トン/日程度処理したときの発電量は約5000kWh/日となる。この量は、約1000世帯の1日の消費電力に相当する。家畜のふん尿と生ごみの日本の排出量全てをエネルギー利用する場合は、原油換算で年間約600万klとなり、2010年の新エネ目標値30%以上に達することになる。バイオマス全体では16%に達する。
このように、家家畜ふん尿と生ゴミだけでもバイオマスはエネルギー量として十分存在する。今後、バイオマスの市場が形成され、流通経路が確保されれば、バイオマス供給が可能となるとともに、年間を通したエネルギー事業者としての安定供給が可能になる。