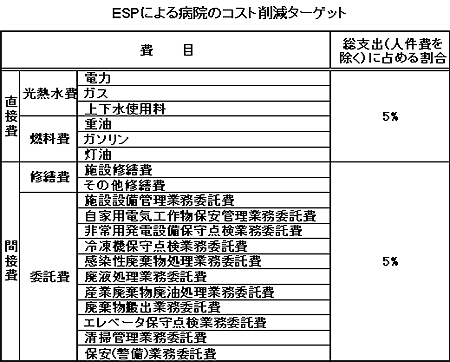PFIが創る環境事業官民協働の地域インフラ
(43)EPS事業
出典:日本工業新聞 2002年8月1日
これまで、電力分野の規制緩和等を背景にエネルギー効率化対策が多様化すること、また、そのうち先行して導入が進むESCO(Energy Service Company)事業について紹介してきた。今回は、第39回で紹介したESP(Energy Service Provider)事業の自治体病院へのサービスについて紹介する。
日本には、約1,000の自治体病院が存在しており、そのうちの約60%は赤字経営である。加えて、昨今の医療制度改革は、医療サービスの標準化、診療報酬体系の見直しなど、医療サービスの質的向上とコスト削減の両立を求める内容となっている。こうした背景から、自治体病院には、早急な経営効率化が求められている。
ESP事業は、自治体病院の経営効率化を支援するビジネスである。病院にとって本業はあくまで医療サービスであり、医療サービスを提供するための環境(電力・ガス・水)を整備することではない。また、そもそも病院にはエネルギー専門家がいないため、エネルギー分野の効率化が遅れている。
そのため、ESP事業者へのエネルギー関連業務の包括的なアウトソーシングは、経営効率化に直結することが期待できるというわけだ。 病院は、多額のエネルギー費用を負担している。300床以上規模では、エネルギー関連費用の負担は5億円/年(総費用のうち人件費を除いた約10%)にも達する。ESP事業者の提供するサービスはこのエネルギー関連費用を削減する。
ESP事業は、メニューがESCO、コージェネレーション導入、MRO(メンテナンス・リペア・オペレーション)サービスなど様々であるため、従来のエネルギーサービスよりも削減のターゲットが幅広くなっているのが特徴である。中でも、病院に対してはMROサービスの導入による間接費の削減効果が大きい。 300床以上規模の病院ともなると50~100もの業務が外部の業者に委託されている。
これは、単年度委託であることを考えると、4~8業務/月のペースで契約を結んでいる計算である。当然のことであるが、経営の苦しい病院では、業務の委託作業に多くの担当者をさくことができない。その結果、一部の委託業務で過大な委託費が支払われるという状況を招いている。
ESP事業のMROサービスは、エネルギー関連業務の委託において、その契約交渉を代行する。専門家であるESP事業者は、適正な委託価格を把握している。その上で、ケース毎に最も効率的な委託方法(委託範囲の見直し、委託期間の適正化、性能発注の導入)を実現することで委託費は抑制される。その効果は、約10~20%程度とも見積もられる。(2,500~5,000万円相当) 加えて、電力自由化の進展に伴って期待できるサービスとして、エネルギープロキュアメントサービスがある。
今後、電力自由化の進展により、工夫次第で同じエネルギーを使用する病院でもその調達価格に差が生じる時代が来る。自由化で先行する米国においては、安価なエネルギーを調達するために病院内にエネルギー調達の専門家をおくか、エネルギー調達を専門業者に委託している病院も少なくない。電力価格の変動する時代においては、必ずしも省エネやコージェネレーション導入がエネルギー関連費用を低減するとは限らない。
ESP事業者の提供する豊富なサービスメニューを組合せることで、はじめてエネルギー関連費用の最小化が実現できるのである。