広域LAN、光ネットワーク 進む個人市場の電子武装化
出典:日経産業新聞 2001年6月22日
●ブロードバンドが身近に
世界最高水準の高度情報通信ネットワークを目指す、政府e-Japan戦略が公表されて約3ヶ月。現在の日本の情報通信ネットワークはどのようになっているのか。
企業向けでは、複数拠点のLAN(ローカル・エリア・ネットワーク)間同士を接続する広域LANサービスの導入が始まっている。これは代表的LAN規格のひとつである、より対線を用いたイーサネット技術を用いたもの。毎秒10メガから100メガ級の広帯域サービスを低料金で利用できる。個人向けでは、通常のダイヤルアップ接続を通じ高速データ伝送を行えるxDSL(デジタル加入者線)サービスが提供され始めた。
同加入者は今春既に10万人を突破(総務省調査)。特に加入者までの伝送のみを毎秒1メガビット程度に高速化したものが人気のADSLだ。
また、CATVでインターネット接続している家庭は現在18万世帯。前年比の約7倍だ。私たちのライフスタイルも大きく変わろうとしている。
●幹線系は「ペタ」の時代へ
企業では毎秒10~100メガビット程度のLAN環境下、さまざまな情報処理が行われている。同処理が複数拠点にまたがる場合、専用線や公衆回線で各拠点を結んでいると、ここでの速度がボトルネックとなる。また、距離に応じて料金が設定されていたため、遠くの拠点ほど高いコストを強いられていた。
今後、この通信環境が一変する。光ファイバー網の普及で、広帯域の通信環境を利用できるからだ。
高速性、地球資源、コスト面で理想的な通信手段といわれる光通信をDWDM(高密度波長分割多重)技術により、幹線系網のさらなる超高速・大容量化が可能となったからだ。今や人類は毎秒テラ(兆)からペタ(1,000兆)ビットの世界を手にした。しかも通信の仕組みが、従来の交換機中心の電話網システムから光スイッチ中心のIP(インターネット・プロトコル)網システムへ抜本的に変わる。後者へのシフトは高速性が加速されるほか、大幅な低コスト化が進むことを意味する。
加入者系の世界でもこの動きが出てきた。ブロードバンドの本命と目された家庭までの光ファイバー接続、FTTH(ファイバー・トゥ・ザ・ホーム)は、従来からの「ラスト・ワンマイル」問題、すなわち最寄りの電話局等から各家庭までの敷設が高コストになる傾向があるため、事実上普及していなかった。
こうしたなか今年3月、国内でもFTTHサービスが登場した。毎秒100メガビットの超高速環境を定額制で月額5,000円程度で提供する低価格なサービスで、沈滞気味だったFTTH市場に風穴を開けようとしている。
同市場に競争原理が作用し出したため、大手通信会社や電力系なども近くFTTHサービスに乗り出す。いよいよ本格的なブロードバンド時代に突入した。
●「オプト・デバイド」も出現
海外での幹線系のブロードバンド化は急ピッチで進んでいる。
通信事業者に通信インフラを提供する新興通信会社は、世界各地に光ファイバー網を整備。一段落した北米市場から、欧州やアジアへ整備網を延ばす。欧州では、光ネットワーク網構築プロジェクトが進行。欧州各国20都市以上を光ファイバーネットワークでつなぐ。
アジアではシンガポールが、高速光ケーブル「シンガポール・ワン」を構築、国際物流拠点である港湾施設のハブ化に活用。一方韓国では、アジア金融危機以降、国をあげてのIT施策が功を奏しxDSLが一気に普及、インターネット普及率がアジア最高水準となったが、光ファイバー網の整備には課題を残している。
今後のIT国家戦略には、21世紀のデジタルインフラ、光ファイバー網の整備が不可欠となってきた。
一方個人ユース(加入者系)では、CATV、xDSLへの需要に加え、より広帯域のFTTHサービスが切望されている。しかし、この需要にサービス供給体制が追いつかない「世田谷デバイド」などの局面も出てきた。サービスの提供地域が、東京都の一部地域に限られているため、光ブロードバンド環境を享受できるかどうかの格差「オプト・デバイド」の象徴と言えよう。
●事業モデル実現の基盤重要
昨今の米国ハイテク不況は「IT革命の第1幕から第2幕への移行がスムーズにいってないため」(ソニー出井会長)と言う。第1幕はパソコン主体であったが、第2幕ではブロードバンドが前提、情報端末など非パソコン系がこれからの主流になるという。この意味を補足しよう。
通信と放送のコンバージェンス(収斂)が起こっている今日、ハード面では能動型端末の王者であるパソコンが、20世紀メディアの王者であるテレビのような受像型端末に変ぼうする。あるいは光ファイバー接続を前提とした新たなオプト系デジタル端末が登場しよう。
通信環境面ではどこにいても、毎秒約2メガビットの高速で情報をやり取りできる"ブルートゥース層" が私たちの周囲の空間を覆う。昨今の携帯電話をはるかに超えた利便性をあらゆる機器で享受できるのだ。これでブロードバンド情報を個人へフィードできる。
たったこれだけの例でもビジネスと生活面の大変革であろう。ここにはケータイ・モバイル景気が影を潜めた、最近の関係業界の閉塞状況を打開するヒントがある。またビジネスの領域がグローバルレベルで、デジタル化された新ホーム市場と、電子武装化された膨大な個人市場へと拡がり、しかもハード機器やサービスなど幾層もの新商品ラインアップ化をねらえるはずだ。
これに向けた戦略的なビジネス・コマース・モデルをいかに描けるか。どのようなアクションを通じ同モデルをかたちにできるか(もうけられるか)。このレイヤーのビジネスインフラ(組織設計、スタッフの成果評価の仕組み等)の整備が、ブロードバンド・ビジネスには求められる。
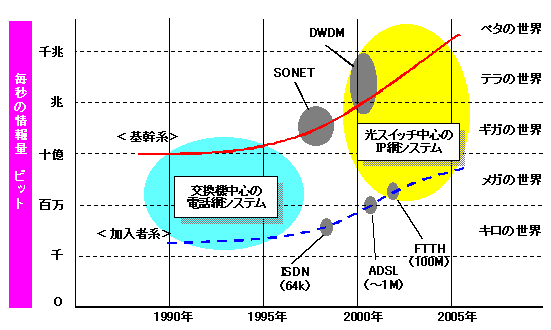
(出所)日本総合研究所 ネット事業戦略クラスター(現ICT経営戦略クラスター)

