「もうかる仕組み」をいち早く構築、
ツール活用のノウハウと組織設計がかぎ
出典:日経産業新聞 2001年6月22日
●現実と期待感が一致
IT革命という言葉がわが国政府で唱えられた少し前の1996年ごろ、インターネットの火種が日本のさまざまな業界へも飛火し、その後急速に広まった。そして、2000年4月(昨春)、「ネットバブル」が弾けた。ITとは情報技術の意味。字義的にはインターネット上陸よりももっと前から、認識されてきた技術・概念であった。
それが最近ではインターネットの衣をまとい革命の勢いを見せている。この革命は産業革命であり、社会革命、そして生活革命にまでおよぶ。その勢いと広がりは過去に例を見ない。歴史的にみて革命とはある種のフィーバーを伴うものだ。つまり、冷静さをどうしても超えた期待(情念)が支配的になる時期がある。
なぜ、ネットバブルとなったのか。昨春のネット株の急落は、1980年末からの「バブル経済」とは異なる。当時、土地本位の成長神話から社会・生活革命を展望することはできなかった。それに比べ昨春のものは、株価の適性水準化、市場の自浄作用ゆえの結果だ。世界のネット市場は私たちの創造を超えて膨大であり、この程度でビジネス機会の縮小はあり得ない。
ベンチャー企業やデイ・トレーディングなどの経営や投資の素人が「ネットブーム」を当て込んで、一度に同じ市場・銘柄に群がった結果の揺り戻しが起こった。見方を変えれば、様々な多くのプレーヤーが一気に短期間になだれ込んだ、従来考えられなかった特筆すべき現象だ。ここまでをIT革命第1幕と総括できよう。
しかし、第2幕は違う。心理的な期待感と現実ビジネスとの乖離(かいり)をうめる基盤が形成されつつあるからだ。つまり、ブロードバンド時代への突入により、ビジネスの基盤が整備されてきた。そして、その活用の仕方が今後の鍵を握る。
●「ペタ」の世界手にする
超高速・大容量通信を意味する「ブロードバンド(広帯域)」に注目が集まる。これがIT革命を本物にする。幹線系では1,000兆ビットを表す「ペタ」、すなわち地球上のテレビ放映量1年間分を1秒間に伝送できる、想像を絶する世界を私たちは手にした。また加入者網(家庭までの支線)系では、非対称デジタル加入者線(ADSL)の毎秒数百キロビット、CATV(ケーブルテレビ)の数メガビット(1メガは100万ビット)、そしてFTTH(家庭向け光ファイバー接続)の100メガビットの環境が当たり前になってきた。しかも定額で月5,000円を切る時代となった。
ブロードバンド時代では、仮想空間にて確かめて(例=試着)買物ができるし、自宅の大スクリーンに投影される専任エージェント(例=名選手)からテニスでの打ち方を矯正してもらい一緒にプレーも楽しめる。テレビの帯域は6メガビット程度。今後はネットでテレビ映像を楽しめる。また個人の情報発信段階から、モバイル環境の拡充もあり、個人のいる場所が放送局のスタジオになる段階となる。電波の希少性ゆえ規制対象となっていた放送のあり方が変わる。
ビジネスでも、ネットをカバン代わりに高速に大容量情報を使いこなせる、いわば私たちの行動範囲がオフィスになり、ポケットの中のイントラに手軽にアクセスできる。この世界を私たちは待望してきた。
●IPとDWDMが主役
これをもたらす主役が、インターネットプロトコル(IP)とDWDM(高密度波長分割多重)の技術だ。この出現で個人・法人を問わずブロードバンドユーザーは大革命を享受する(あるいは強いられる)。同時に通信会社も安穏としてはいられない。それは旧来の交換機中心の電話網システムから、光スイッチ中心のIP網システムへシフトするからにほかならない。
ここに新しいビジネスの種が凝縮している。もっと言えば、過去100年間の産業史上の大転換に乗り遅れてしまうと、企業の生き残りもない。実はIT革命の舞台裏ではこの動きが急ピッチですすんでいるのだ(以上、拙著「徹底図解:光ファイバーのすべて」PHP研究所に詳述)。
●可能性一段と広がる
これまでのeビジネスは必ずしも大ブレイクしなかった。なぜか。それはビジネスインフラの整備状況が、一定のしきい値(クリティカルポイント)に達していなかったからだ。
第2幕でのビジネスの戦略的中軸となるインフラ、は、さしずめ、セキュリティー層、物理ネットワーク層、産業セクター層、ビジネス・コマース層に分類できよう【図表1】。
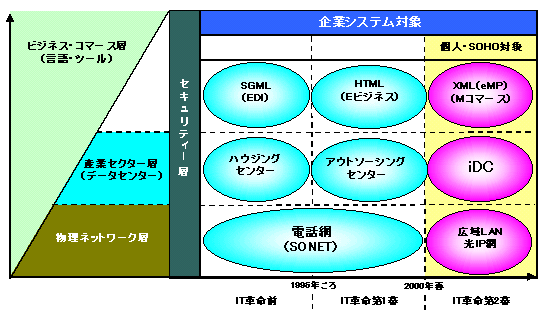
具体的には、セキュリティー層は消費者の個人情報、及び企業システムへの安全性に関するもので、セキュリティー政策なども対象であり、他の層に共通的なもの。次に物理層は、昨年10月のIT国家戦略でも示された超高速で低価格なもの、そしてどこでも簡単に使える身近なネット環境。また産業セクター層は、データセンタ-などの当該産業・業界にてビジネスの効率化等を図るための共通機能を提供するもの。そしてビジネス・コマース層は、もうかるビジネスやコマースのための要素、例えばビジネスモデルそのものに加え、XMLといったツール活用のノウハウ、組織設計の仕組みなどとなる。
詳細は本稿各論にて、順に「データセンター」「セキュリティー」「XML」そして「広域LAN、光ネットワーク」をキーワードに解説する。
今後のIT革命では消費者も企業もブロードバンド環境下に置かれる。ただ、上記ビジネス・コマース層は当該自社の問題だ。サイバー(電脳空間)とリアル(現実)いずれの企業も、この整備拡充が如何に図れその活用ができるか、先のしきい値を超えられることに相当しよう。
実際、今年1月に通称「光コンソーシアム」(総会会長:安田浩東大教授)が設立されている。今月までに外資を含む73企業が会員となり、ブロードバンド・光ファイバー網をベースとする、サービスモデルやシステムモデルの可能性とその現実性に目を付けアクションをとっている。海外にもまだ例がない。
●消費者の完成に訴求
第2幕の市場競争ではインターネット・ビジネスインフラを武器に、ニューエコノミーに加えオールドエコノミー型の大企業や中堅・中小企業も当事者となった。もはや傍観的ではいられない。真に「もうかる仕組み」をいち早く構築できるかが企業の生き残りに直結する。
消費者向け電子商取引(B to C)では、例えばeマーケティング、オンライン販売、カタログ閲覧所などのもうかるモデルに、消費者の感性に訴求できる要素を採り入れることが必須となる。低価格で超高速・大容量の環境にあれば、サービスがより身近かとなりリアリティ性(現実性)が飛躍的に増加する。消費者の周辺に着目すると、これまでの理性型パソコンモデルをブレイクした、感性型テレビ(受信機)モデルを実現し、それが受容される基盤ができてきた。金融、通信・放送、小売などの業種では、これに向けたマーケティング、広告、販売、課金の仕方などに知恵を絞ればよい。
●「e」から「c」へ移行
企業間電子商取引(B to B)では、「e」から「c(コラボレーティブ)」へシフトする。鉄鋼・半導体・化学・石油などの製造、あるいは官庁向け分野でのB to Bの本質が、もともと顧客企業とのリアル面を含む協働プロセスにあるからだ。従って、第1幕では十分機能しなかった、e-CRM(顧客関係のマネジメント)やe-SCM(サプライ・チェーン・マネジメント)は、「c-CRM」「c-SCM」とならざるを得ない。e-MP(マーケットプレイス)も、この中で意味を持ってくる【図表2】。
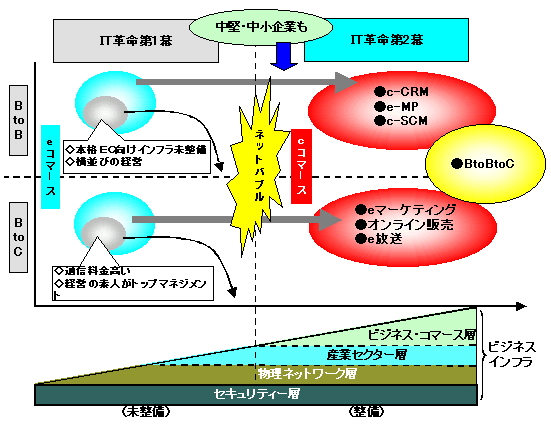
筆者が請け負う経営コンサルティングでも、このケースが増えている。具体的には、資材の調達・購買といった機械的モデルに加え、自社のERM(Employee Relationship Management:従業員どうしの関係マネジメント)基盤を拡充しながら、顧客企業のコア・コンピテンスを担うターゲット個客との直接・リアルなフェイシング(対面機会)の頻度、緊密度、距離感などを向上させるアクションが重要だ。双方の創発段階でのビジネス・コマース関係を再構築することだ。もちろんネットでその契機をつくること、そして一定の関係再構築後はネットに任せた効率的なプロセスを円滑に行えるシステムモデルが不可欠となる。
また忘れてならないのは、同関係構築に向けた組織設計とERMにおけるスタッフの成果評価モデルの設計だ。これらの要素が完備できれば、日本の企業は必ず強くなる。

