本命のFTTH、急伸するADSL、アクセス網の選択肢が一気に拡大
Part2:ブロードバンド向け接続サービスとその受け口
出典:日経コンピュータ 2001年10月15日号
多種多様なブロードバンド向け接続サービス
前述の通り、現在利用できるブロードバンド時代向けの代表的な接続サービスは大きく4つある。FTTH、ADSL、CATVインターネット、無線インターネットである。ここでは、各サービスの違いや特徴を詳しく紹介する。
●FTTH/光ファイバ
光ファイバを利用したサービスにはさまざまな形態がある。その代表例がFTTHである。光ファイバのケーブルを各家庭に引き込んでインターネットに接続する。FTTHは数あるブロードバンド向け接続サービスの中でも最も高速で、かつ安定した通信が可能だ。長い目でみれば、FTTHがブロードバンド時代の大本命のサービスと言える。FTTHサービスの商用化は2001年3月に、有線ブロードネットワークスが先陣を切った。NTT東西地域会社も8月から「Bフレッツ」と呼ぶFTTHサービスを提供している。
FTTHを利用する場合、光ファイバは「ONU(光ネットワーク装置)」と呼ばれる装置につなぐ【図5上】。これは光信号をLAN信号に変換する装置である。さらに、ONUをLANケーブルでパソコンとつなぐ。100Mビット/秒のFTTHサービスを利用するときは、最大速度を出すためにも100BASE-TのLANカードを用意してパソコンとつなぐとよい。
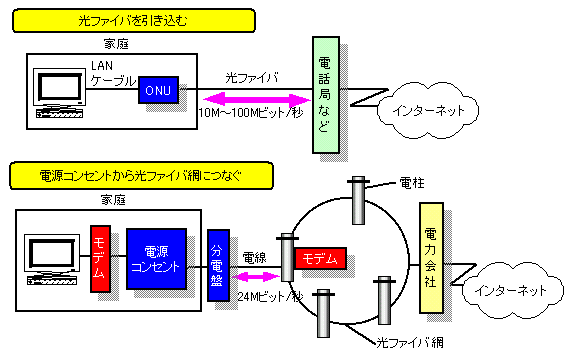
◇光ファイバの引き込み工事が難題
FTTHは大本命のサービスであるが、普及の道のりは遠い。現時点で普及はまだ思ったほど進んでいない。その理由は主に2つある【表2】。
1つは、FTTHサービスを利用できるエリアが東京23区内や大阪市内など大都市の一部に限られていることだ。利用したくても利用できない人が全国に大勢いる。
2つ目の課題は、「ラストワンマイル」の整備である。住居のすぐそばまで光ファイバが来ている都市部であっても、最終的には各家庭にまで光ファイバを通さなければFTTHサービスサービスを提供できない。光ファイバを家庭に引き込むにはそれなりの工事が必要で、費用と時間がかかる。
光ファイバの工事をする場合、利用者が賃貸住宅に住んでいるならば、大家の許可を取りつけなければならない。本人自身が受託を保有している場合でも、マンションのような集合受託であれば、マンションの住人全員で協議する必要がある。
FTTHを積極的に利用したいと考えているのは今のところ、都市部に住む20~30代の人たちが大多数を占める。こうした人たちは、賃貸住宅やマンションに住んでいる割合が高い。FTTHをいち早く利用したいと考えているのに、光ファイバの工事ができずにいるという状況では、加入者の大幅な増加は期待できない。FTTHの提供エリアが増えたとしても、光ファイバの工事の問題が解消しない限り、状況は改善されないだろう。
FTTHの普及を促すためには、通信事業者と建設会社が手を組み、新築マンションには光ファイバをすぐに引き込めるようにしておく、といった取り組みがもっと必要だ。
|
長所/短所 |
内容 |
|---|---|
| 長所 | ●高速で、かつ安定している。通信速度は最大で100Mビット/秒 |
| 短所 | ●光ファイバを家庭に引き込むためには工事が必要。賃貸住宅に住んでいる人は、工事をする前に大家の許可が必要。自分で住居を保有している場合でも、マンションのような集合住宅に住んでいる人は、工事をする前に他の住民との協議が必要 ●サービスを利用できる地域が限られる。現在は23区内や大阪市内などの都市部でしか利用できない ●光ファイバ・ケーブルは強度が他のケーブルに比べて弱いので、取り扱いに注意が必要 |
◇HomePNAや配電線という選択肢も
光ファイバを利用したサービスは、FTTH以外にもある。「HomePNA」を使ったサービスや、関西電力が関連会社などを通じて2002年度中にも開始する予定の、配電線を使った高速接続サービスである。
HomePNAは、既存の電話回線を使って安価で高速な家庭内LANを構築するための標準規格であり、その策定を行う業界団体のことも指す。例えばマンションには、最大100Mビット/秒の通信ができる光ファイバをメディア・コンバータ(変換器)経由でHomePNA規格の装置と接続し、各戸に直接光ファイバを引き込まなくても、高速な通信を実現できる点が大きな魅力である。
配電線を使った高速接続サービスについては、関西電力グループが自らの光ファイバ網を利用して、最大24Mビット/秒のインターネット接続を実現しようとしている【図5下】。このサービスでは、家庭内にある電源コンセントをインターネットへの接続口として使う。実用化すれば、手軽に導入できるブロードバンド・サービスとして一気に浮上するだろう。このように、家庭までのラストワンマイルに既存のインフラを利用すれば、光ファイバは一段と"身近"になる。
●ADSL
ADSLは、数あるDSL(デジタル加入者線)サービスの一つである。DSLとは、既存の電話回線(メタリック線)を使って、高速な通信を実現する技術の総称だ。DSL技術にはさまざまなタイプがあるので、DSLの前に頭文字を付けて区別する。日本で最も普及しているADSLは、非対称を意味するA(アシンメトリック)が頭についたDSLである。
ADSLの特徴は、文字通り通信速度が「非対称」である点だ。データのダウンロードや電子メールの受信といった、利用者側がデータを受けるときの速度(下り速度)と、データのアップロードやメールの送信といった利用者側がデータを送るときの速度(上り速度)が違う。
大多数のインターネット利用者は、Webページへのアクセスや各種コンテンツのダウンロードなど、下りの通信速度を最大1.5Mビット/秒もしくは8Mビット/秒にまで高速化し、逆に通信速度が多少遅くてもかまわない上り速度は最大で512kビット/秒または900kビット/秒程度に抑えている。
ADSLはISDNの後継となる公算が大きい。現時点ではブロードバンドの本命と目されるFTTHを差し置き、急速に加入者を伸ばしている。総務省の調べでは、2001年8月末までに51万人の加入者を集めた。ソフトバンク・グループなどADSLを推進する企業の躍進で、NTTグループでさえもADSL戦略を見直さざるを得なくなった。当初NTTは、ADSLはFTTHが普及するまでの"つなぎ"と位置づけていた。だが、ADSLの急速な普及を見て、「他社のADSLサービスに加入した人を、後からNTT側に呼び戻すのは難しい」と判断。ADSLサービスにも本腰を入れ始めている。
◇導入の手軽さと低料金が魅力
ADSLが快進撃を続ける理由は、通信に既存の電話回線を利用者できることと、Yahoo! BBのような格安で高速なサービスが登場したことが挙げられる【表3】。NTT東西地域会社も、ADSLサービス「フレッツ・ADSL」の月額料金を10月1日に再値下げした。導入の手軽さと低料金が利用者に受け入れられている。
しかし、ADSLには弱点もある。ノイズに弱く、その影響で通信速度が低下する場合があることだ。電子レンジなど他の電子機器から離してADSLモデムを設置したり、接続線はできるだけ短くする、といった工夫が必要になる。これだけでもノイズは減り、より快適なスピードを出せるはずである。
実際にどこまで通信速度が出るかは、使ってみないと分からないというのが実情のようだ。例えばNTT東西地域会社のフレッツ・ADSLでは、実使用上、下りの実効速度が1.5Mビット/秒フルに出ることはまずない。あまりにも実効速度が遅いときは、通信事業者に改善要求を出すこともできる。
ADSLの導入では、もう一つ注意すべき点がある。すでにISDNをアナログ回線に変更しなければならないことだ。その手続きが必要になる上に、アナログ回線に変更すると、電話番号まで変更しなければならないこともある。電話番号の変更を知人に知らせるのは相当な手間となる。
|
長所/短所 |
内容 |
|---|---|
| 長所 | ●既存の電話回線を利用するので余計な工事が必要ない ●月額2,300~4,000円程度で常時接続できる ●インターネットに接続しているときでも電話が使える ●ADSLのサービス・エリアは全国に広がっている |
| 短所 | ●ADSLの下り速度はあくまでも理論値で、実効速度はその数分の1~10数分の1になるときがある ●高い周波数の電気信号を使っているため、遠距離には届きにくい。電話局からADSLの利用場所が遠いと速度が遅くなる ●アナログ回線のため、ノイズに弱い傾向がある。ISDN回線が近くにあったり、電子レンジなどの電子機器が近くにあると実行速度が遅くなることがある ●ISDNを利用している人は、アナログ回線に戻すときに電話番号の変更が必要になる場合がある |
◇ADSLの接続形態は2種類
ADSLの接続形態には、既存の電話回線と共有する「タイプ1」と、ADSL専用に電話回線を引く「タイプ2」がある【図6】。タイプ1とタイプ2のいずれも、ADSLモデムパソコンまでは、LANケーブルまたはUSB(ユニバーサル・シリアル・パス)で接続する。より高速なインターネット接続環境を確保したいなら、LANで接続したほうがよいだろう。さらにタイプ1の場合は、電話のモジュラ・ジャックから音声とインターネットのデータを分岐させる「スプリッタ」と呼ばれる装置が必要になる。
ADSLモデムは市販されているが、ADSL事業者によっては自社で用意したモデムの利用を強く推奨している場合がある。ADSLモデムの導入前に、各事業者に確認したほうがよい。
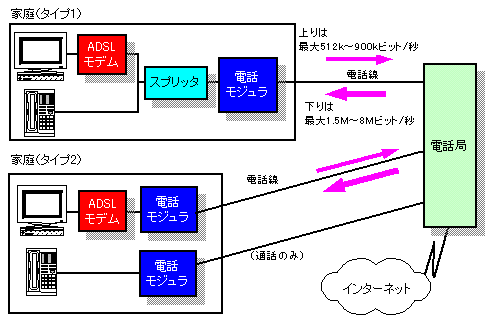
(出所)日本総合研究所の資料をもとに、日経コンピュータ誌が作成
●CATVインターネット
CATVインターネットは、各地域に張り巡らされたCATV放送要のケーブルを使って、インターネット接続を提供するサービスである。最大速度は10Mビット/秒と高速だが、回線の混雑具合によっては実効速度が大きく低下することがある【表4】。同じCATV網を複数の家庭と共有していると、通信が混雑した場合にスピードが落ちる。
|
長所/短所 |
内容 |
|---|---|
| 長所 | ●CATVを利用している家庭はすぐに利用できる ●4,000~6,000円と比較的安価な料金で利用できる |
| 短所 | ●一つの地域に事業者が1社しかないので、他のCATV事業者を選択できない ●CATVのケーブルが敷かれていない家庭では工事が必要 ●速度にばらつきが多く、期待する速度が出ないときがある ●複数台のパソコンには接続できなかったり、接続できても別料金が必要になる場合がある |
◇CATV専用のケーブルで接続
CATVインターネットの場合、回線は電話回線ではなく、CATV用のケーブルを利用する【図7】。この専用ケーブルに、通常のテレビ番組の情報とインターネットの情報を流す。CATVに加入していない人は、まずCATVに加入してケーブルを家庭に引き込まなければならない。その点では、FTTHと同様に不便である。ただ、最近のマンションはあらかじめCATV用のケーブルを導入していることが多い。CATV自体は比較的広く普及しているので、FTTHほど導入障壁はない。
CATV用ケーブルの配線工事は、建物によって異なるものの、1万~3万円程度の費用で済む。工事が完了したら、ケーブルに分配器をつなぎ、分配器にケーブル・モデムを接続する。なお、パソコンが複数台あるときは、2台目以降のパソコンの接続が認められなかったり、別料金がかかる場合がある。
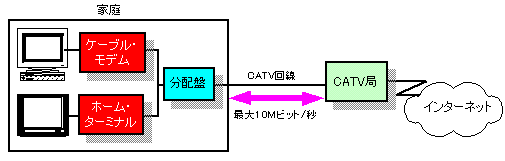
◇ブロードバンドで最多の加入者
他のブロードバンド向け接続サービスと比べてCATVインターネットの有利な点は、CATV網がすでに全国に広がっていることだ。総務省の発表では、2001年7月末時点で全国に232ものCATV事業者があり、6月の時点で約97万人がCATVインターネットを利用している。この加入者は、他のブロードバンド向けサービスと比べて最も多い。早くから定額制と高速通信を売り物にしていたので、ブロードバンドが注目されるようになってからは普及に一層拍車がかかった。
CATVインターネットの利用は、CATV網の広がりから見ても、今後しばらく増え続けるだろう。CATV事業者側は地域に特化したコンテンツを提供するなど、得意分野であるコンテンツ配信に注力して、他のブロードバンド向け接続サービス会社との差異化を図っていくと見られる。
ただし、利用者からすればCATVインターネットはADSLサービスのように自由に事業者を選べないという側面がある。CATV事業者は原則として、一つの地域に1社しか参入できないからだ。そのため、各地域の利用者のニーズを、それぞれのCATV事業者がすべてみたしてくれるとは限らない。
●無線インターネット
無線インターネットは、無線でブロードバンドに接続するサービスのことである。利用者がアクセスを行う区間では光ファイバや電話回線、CATV専用ケーブルなどを一切使わない。無線電波が届く範囲であれば、場所にとらわれず、どこでも使えるという利点がある【表5】。
中でも利便性が高いのは、携帯電話やPHSを使ったサービスだ。エリア内であれば、専用の通信カードをノート・パソコンに差し込むだけで利用できる【図8上】。ただし、現在のところ携帯電話やPHSを使ったインターネット接続には、高速かつ定額制のサービスは存在しない。PHS事業者であるDDIポケットやアステルが一部の地域で定額サービスを実施しているが、通信速度は32kビット/秒と遅く、ブロードバンドとは呼べない。
|
長所/短所 |
内容 |
|---|---|
| 長所 | ●無線の通信エリア内であれば、場所を気にせず利用できる ●光ファイバと組み合わせることで、高速な通信を実現しやすい |
| 短所 | ●雨や雪が降ると通信ができなくなったり、通信速度が遅くなることがある ●比較的高周波数での通信なので、障害物があると通信できなくなることがある ●携帯電話を使ったブロードバンド向けの接続サービスは、当面通信料金が高くなると予想される |
◇第3世代の携帯電話に期待
この10月1日から首都圏の一部で本サービスを開始したNTTドコモの「FOMA」は、世界初の第3世代携帯電話サービスである。FOMAを使えば、64kビット/秒でデータをやり取りするテレビ電話や、下りが384kビット/秒のパケット通信が可能になる。月額の基本料金は3,900~1万5,000円だ。これまでの第2世代携帯電話では、9,600kビット/秒の通信速度が一般的だったので、第3世代は確かに高速になったと言える。もう少し時間が経てば、ブロードバンドと呼べるような2Mビット/秒クラスの本格的なサービスも利用できるようになるだろう。
ただし、料金が大きな課題になる。動画などのブロードバンド向けコンテンツはデータ量が格段に多いので、従量制課金のままでは、動画をダウンロードするだけで多額の料金がかかってしまう。これでは利用者の経済的な負担が大きい。FOMAでは、契約の仕方によってはデータ通信料金がこれまでよりも最高で10分の1まで安くなる。1パケット(128バイト)あたりの通信料は0.02円だ。
それでも完全な定額サービスとは異なる。他のサービスと同様に、携帯電話を使ったインターネット接続も「定額制」になることが望まれる。
◇無線で光ファイバ網までつなぐ
無線インターネットにはほかに、東京電力系のスピードネット(東京都港区)が2001年5月から提供しているサービスがある【図8下】。これは、東京電力が保有する電柱に張り巡らされた光ファイバ網に無線でアクセスし、インターネットに乗り入れるものだ。電柱に無線基地局を設置し、家庭に置くアンテナと光ファイバ網までを無線で通信する。こうした光ファイバと無線の組み合わせは、FTTHの課題となっているラストワンマイル問題を解決し、光ファイバの普及を促進する有効な手段にもなり得る。
スピードネットのサービスを利用する場合は、屋外にアンテナを設置し、アンテナから同軸ケーブルで屋内の無線子機までつなぎ、さらに無線子機からLANケーブルでパソコンまでを接続する。無線は障害物があると通信も邪魔されるので、アンテナの設置場所には工夫がいる。また雨や雪が降っているときには通信速度が低下したり、不通になることもある。
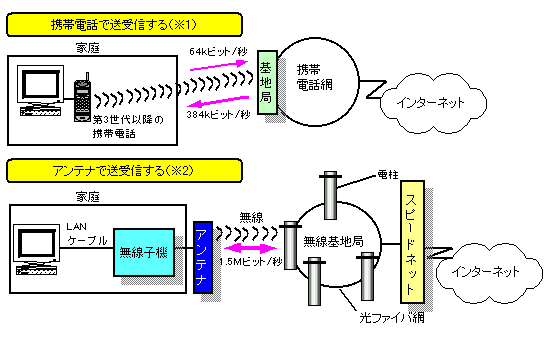
◇"ホットスポット"で無線LAN
最近は、人が集まる駅やカフェで、最大11Mビット/秒の無線LANを使ってインターネットに接続できる「ホットスポット・サービス」も増えてきた。利用者は、インターネット接続業者が提供する認証ソフトをノート・パソコンなどにインストールし、市販の無線LANカードを使ってブロードバンドにアクセスする。
ホテルや空港にも、無線LANで通信できるアクセス・ポイント(基地局)を用意する動きが広がっている。例えば京王プラザホテル(東京都新宿区)のラウンジでサービスが始まった。無線LAN対応のノート・パソコンを持ち込めば、自由に無線インターネットを利用できる。
ほかにも、東京・渋谷の街なかといった広域なエリアでも無線インターネットの実験が進められている。外出先で簡単にブロードバンドを利用できる日が近づいてきた。
ブロードバンドの受け口はパソコンだけではない
ブロードバンド向けに配信されるコンテンツの受け口(ポータル)として今後は何が有望か。これは一般利用者にとって極めて身近な話題だろう。パソコンだけが使われていくとは限らない。ストレスなく、好みのコンテンツにアクセスできるという条件を満たせばよい。
家庭にポータルを作り上げるときには、テレビを利用することも考えられる。今年9月に発売されたソニーのパーソナルITテレビ「エアボード(ブロードバンド対応版)」は、ADSLやCATVインターネットをつかってテレビとインターネットの両方を楽しめる。面倒なキーボード操作は必要ない。無線電波が届く約30mの範囲内であれば、本体からモニターを取り外して持ち運ぶこともできる。今後はさらに、パソコンより格安のSTB(セット・トップ・ボックス)や、双方向型のテレビが普及するだろう。
テレビやパソコン以外のものも考えられる。例えば、数十人が同時にコンテンツを楽しめる「10mのメディア(装置)」があっていい。横幅が10mある舞台装置にブロードバンドを持ち込めば、新しい映像提供環境を作り出せるかもしれない。そのほか、30mのスタジアムがそのまま受け口になることもできる。
本来、コンテンツ(特に映像)を楽しむためには、適切な距離と空間が必要だ。しかし、これまでは伝送可能な映像情報の量に限界があったため、十分なサービスを提供できていなかった。30Mビット/秒以上のブロードバンドを利用すれば、既存の放送網を使わずに映像情報を余すところなく伝送できる。

