新たなビジネスモデルを構築する「モバイルコンピューティング」
Part1:モバイルコンピューティングの動向
出典:日刊工業新聞 2001年10月
(1) 総論
速度向上、セキュリティー強化などに関する基盤技術の進歩、その上にのるサービス(アプリケーション)の拡充、こうした背景のもとモバイルコンピューティングは、もはや企業活動には不可欠になってきた。特に、わが国にとって、この分野は欧米諸国に比べ得意とするところだ。今年3月にまとめた政府の「e-Japan重点計画」を具体化する際にも、あるいはIT不況を打破するためにも、モバイルコンピューティングがカンフル的な刺激と実効的なツールにならんことを期待したい。
(2) 身近になったモバイルコンピューティング
モバイルコンピューティング環境の進展は目覚しいものだ。筆者は現在、携帯電話会社がある溜池山王駅地下のスターバックスで、この原稿を書いている。モバイルの専門語を思い出せなければ、スーツケースに入れたワイヤレス通信用のエッジカード(DDIポケット製)をノートパソコンに差込み、インターネット接続でそれを確認できる。
この後は霞が関へ行き、クライアント役員へのプレゼンテーションだ。気になる箇所は一番町の筆者オフィスのサーバーへアクセスしチェック。その資料を事前に送っておけばよい。明日は別の原稿を恐らく大阪行きの新幹線の中で書き上げ出版社へ送る。1年前はこうはいかなかった。
(3) 市場拡大とその意味
モバイル環境は、携帯電話による本格化モバイル時代の突破口を開き、PDA(パーソナル・デジタル・アシススタンツ)を甦らせ、さらに両者の融合・統合が進むだろう。
MCPC(モバイルコンピューティング推進コンソーシアム)の今春の市場予測では、モバイルコンピューティングの2001年度末の利用者数(テレメタリング等含む)5,180万人(利用率61%)。一方、今年8月末の携帯電話契約数は6,470万。今年度末に7,000万と仮定し、モバイルコンピューティング利用者数と比較すると、携帯電話利用者の74%にもなる。これら数字は企業ユーザ-を含むことから、今や企業でもモバイルコンピューティングの利用は当然になってきた。
(4) なぜモバイルコンピューティングの導入が進むのか?
今、企業でモバイルコンピューティング導入が急ピッチで進んでいる。具体的には、「誰かとコミュニケーションする」から「生活を便利にする・業務を効率化する」、そして「生活をより楽しむ・豊かにする」といったモバイルサービスの領域が拡大している【図表1】。それは、いつでもどこでもといったユビキタスな条件を満たしていること、ビジネスに耐えられるスピードと一定のセキュリティーレベルに達したからだ。ビジネスインフラ環境が整備されてきた。
企業においては、顧客DBと基幹DBを連携・統合したシステム環境整備により、商品の受発注の迅速化や自動化によって収益の向上をはかれる。営業担当者は、iモ―ドほかウェブブラウジング機能搭載の携帯端末(ブラウザホン)などを利用する。社外での営業力強化は当り前になってきた。
以上のようなインフラ環境に加えモバイルコンピューティングの導入には、本社ピラミッド型店舗方式からネットワーク型経営に替わるなどビジネスのシステムが変革されてきていることも寄与している。
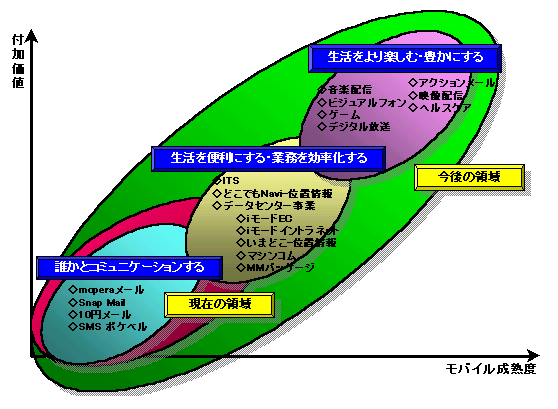
(出所)NTTドコモ資料
(5) どのように導入されているのか?
新規顧客の開拓などでは営業担当者が、SFA(Sales Automation Force)といわれる、モバイル端末などを用いて行う営業力強化の動きが進んでいる。あるいは同端末を通じモバイルインターネット経由で企業内サーバーの所望情報にアクセスできるようになり、業務支援、マーケティング、物流業務に威力を発揮している。また、単なる工場管理から、部品・部材サプライヤーおよび顧客の資材部門を結び付け、需給調整をはかり在庫調整などを行うSCM(Supply Chain Management)などにも利用され出した。
特に最近ではCRM(Customer Relationship Management)を進めるべく、さまざまな手段を通じ得られた顧客・取引情報をコールセンターに移し分析・加工することで、売上拡大などに結び付けている【図表2】。さらに、CARM(Cross Activities Relationship Management)という顧客と自社部門(営業、開発など)との間で行う協働の商品コンセプトづくり、設計・開発といった諸活動を相互に目に見える形で、スピーディーに取り組めるようにした仕組み・モデルが注目されている。ここにモバイル環境の駆使が問われている。
未だモバイルを導入しない企業においては、前述のビジネスインフラが未整備にあること、そして、このような仕組み・モデルに対する研究・取組みが不充分といえよう。
【図表2】 CRMにおけるモバイルコンピューティング 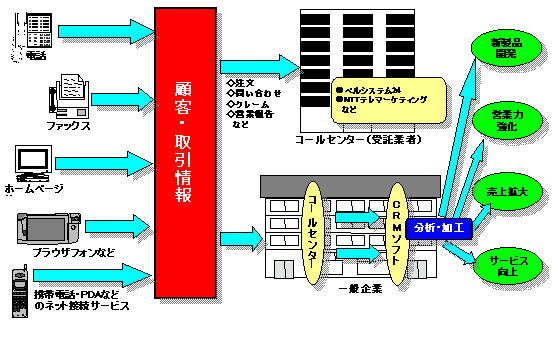
(出所)日本総合研究所ネット事業戦略クラスター(現ICT経営戦略クラスター)
一方、交通渋滞の解消や高速道路の料金収納所のスペース削減などで期待されるITS(高度交通システム)や、GPS(Global Positioning System)を用いた位置情報サービスでも、Javaなどを用いたコンピューティングをフル活用している【図表3】。PHSの128kbpsサービスや次世代携帯電話「FOMA」のスタートで、これらシステムを利用するユーザーの環境も一層充実してきた。
【図表3】 GPSを利用した位置情報サービス 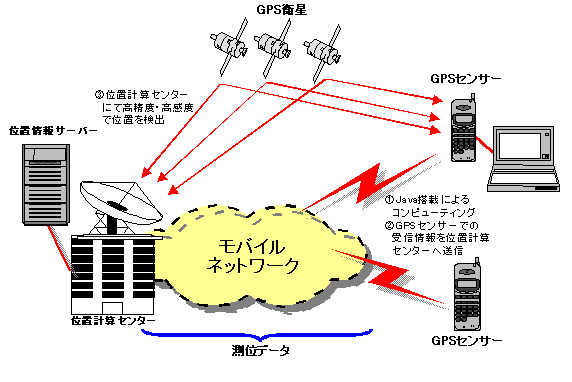
(出所)日本総合研究所ネット事業戦略クラスター(現ICT経営戦略クラスター)
(6) 今後のモバイルコンピューティングの需要は?
今後の移動体通信の需要を、2005年頃に人間同士のコミュニケーションで約1億台(人口普及率80%を仮定)に達すると予測することはそう外れていないだろう。また、NTTドコモ立川社長や東大安田浩教授によると、同じ頃に携帯PCで5千万台、携帯TV(ゲーム機含む)で8千万台、ウェアラブルコンピューター(ヘルスチェッカー含む)で2億台、カーナビを含む自動車で1億台と予測している。
MCPCの今春のモバイルコンピューティング市場の予測では、2001年度の利用者数(テレメタリング等含む)5,180万人(利用率61%)から、2004年度には同6,520万人(同77%)としている。今後のブロードバンド時代の本格化にともない、あらゆる企業活動において、モバイルコンピューティングはより不可欠な存在になってきた。

