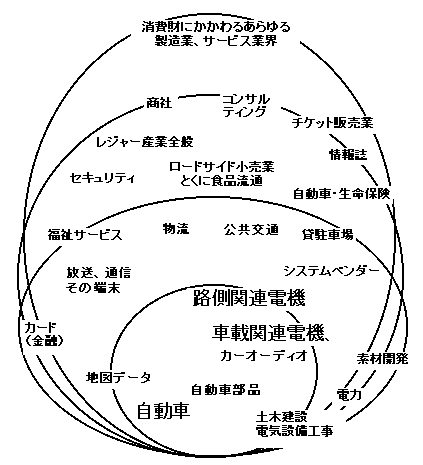ITS産業の未来地図
出典:建設オピニオン 2001年4月号
1.具体的「新産業創出」段階に入ったITS
1998年11月の「緊急経済対策」(経済対策閣僚会議決定)でITSは「21世紀型社会の構築に資する景気回復策」として採り上げられ、新聞の一面を飾ること数回。以来、一次的な効果である交通問題解消よりもむしろ、ITSの整備にともなう経済波及効果に着目することでITSを推進していく、つまり民間企業のビジネスとしての取り組みを前提としてITSという施策を実現させる、という流れになった。
ITSは何よりもまず自動車交通問題の解決方策であって、市場拡大のためにITSに取り組むのは本末転倒という考え方も一理ある。しかし社会システムとしてITSを一般市民に使ってもらい交通施策としての効果を示すためには、個々人の持つ端末が普及していることが大前提で、それを税金だけでまかなうことは、現在の日本では不可能である。したがって交通施策としてのITSと経済波及効果としてのITSは切っても切り離せない関係にある、と捉えないと具体的な推進はありえず、ETC本格運用開始のいま、まさにそのレールを具体的に敷かねばならない時期になった。
幸いにして、現在ITSは一般市民には抽象的かつ肯定的に捉えられてきた。この追い風を活かし、具体的な施策、ビジネスの全体像を描きながら個々の実践に取り組む段階に入ってきているのが、「ITS産業」の現在である。
2.ITSはどの産業に影響を与えるのか
1999年2月に電技審から発表された「2015年までの累積で、ITS情報通信関連市場は約60兆円、関連全産業への効果約100兆円。2015年時点の関連市場7兆円の下で107万人の雇用を創出」という数字が一人歩きをしている。自動車、電機、電子部品、情報通信といったITSに直接かかわるハードウェアとソフトウェア、サービスの世界で60兆円、ITSとして作られたシステムを活用することで新しく発生するビジネス、たとえば新しい自動車保険などを含めた市場が100兆円、という理解をおおざっぱにすればいい。
この市場予測を読み解く上でもっとも重要なことは「ITSの市場とは、システムを多目的につくって、利用してもらって、なんぼ」ということである。官庁発注による公共事業は毎年数千億円規模に過ぎず、それ自体が期待されているのではないことを前提に、ITS業界の広がりを見る必要がある。その全体像を俯瞰してみよう。
ITS産業の中心にあるのは、自動車メーカー、カーナビを含めた自動車部品メーカー、従来の自動車部品以外の電子機器を供給する電機メーカー、である。最初は自動車の付加価値として、普及するにしたがい社会システムとして受け入れられていくことになる。普及に向けて当然法制度も後押しする。確実なビジネスである。
その中でも、電機メーカーがもっとも成長率の高い市場を獲得すると考えられる。それはITSのための電子機器がもともと自動車の中にほとんど盛り込まれていないからであり、その技術のイニシアチブは自動車部品メーカーより電機メーカーのほうにあるからである。もちろん自動車メーカーもOEM(Original Equipment Manufacture;相手先ブランド製品の製造)供給に対して強いイニシアチブを持つことができるが、ITSのシステム構築は路側にも及ぶことから、ETC路側システムなど自動車以外のシステム構築に取り組むか否かが、自動車メーカーとしてのビジネス規模の分かれ道になる。
電子機器メーカーは、料金所のETC(自動料金収受システム)対応など、路側の通信インフラについても、道路管理者である国や自治体に提供していくことになる。
自動車も道路も、ITSによってそれぞれ新しい素材の導入が必要になれば、素材開発メーカーも関わってくることになる。たとえば熱や振動に強いコンピューター部品の開発は、まさにこれからである。
また機器を相互に動かすシステムを構築するシステムベンダー、地図DVD-ROMなどのパッケージソフトウェア制作業、ICカードの印刷業なども、ITSで新たなビジネスを形成することになる。
バスやタクシー、物流などの運輸業界、加えて駐車場業やレンタカービジネスなどは、ITS導入による人件費コスト削減と、効率的に輸送量を拡大できる点で便益を得ることができる。ただし、それが業界の新たな需要をどれほど生み出すかは、未知数ではある。
自動車という移動体の情報システムであるITSには、無線通信が必須である。すでに通信料ビジネスが成立している携帯電話(PHS、衛星通信、IMT-2000含む)事業者は、ITSで発生する新たな通信トラフィックで大きな収益をあげることになる。
同様に、ITSによって消費される電力もかなり多いと予想され、電力会社は確実に潤うことになるが、これはむしろITSの間接的な経済波及効果と言える。
また道路交通政策本来の目的に根ざした車載側の機能として、衝突防止システム、緊急通報システムが実現することは、自動車保険、生命保険に変化をもたらすことになる。運転制御ができたとき、事故の責任分担が大きく違ってくるため、新しい保険料負担と保険金のルールが作られることになる。アイデア次第では新商品による市場の活性化も期待できる。
介護ビジネスは運輸業界同様、人件費コスト削減と効率的輸送量拡大という便益がもたらされる。介護される側も、歩行者や運転者としてITSの恩恵を移動の安全、円滑という形で受け取ることができる。
3.「情報・金融プラットフォーム」事業の成否が市場のカギ
ETCの本格運用開始と、その路側・車載システムの民間利用(DSRC応用システム)を展望する上で、都市立地の新産業創出のカギを握るのが、移動体通信を中心とする情報メディア関連業界と、クレジットカードを中心とする金融業界である。
この両業界は、交通政策としてのITSでは、沿道などの情報提供サービス、ICカードによるETC決済をそれぞれ担うにすぎないが、いずれもシステムが拡張され道路交通外の用途が盛り込まれれば、「消費のための情報プラットフォーム」「消費のときの課金プラットフォーム」にそれぞれ化ける。数千万台規模で同様の規模を持つに至っているインターネット接続の携帯電話やパソコンの機能、まもなく姿をあらわす地上波デジタル放送の技術とも、必然的に融合することになる。
日本の乗用車5,000万台にこのシステムが定着すれば、ITS業界の領域は「自動車交通のための情報通信システム周辺」から「クルマと情報をとりまく生活全体」へと一気に広がり、観光業、レジャー産業、コンビニエンスストアなどロードサイドでの消費形態を大きく変えることになる。すでに電技審などでも、駐車場案内、ドライブスルー決済や沿道情報シャワーなどのアプリケーションが検討されており、ロードサイドビジネス側は、システムとビジネスモデルをうまく構築することで「自分の店を欲している客を確実に呼び寄せることができる」販促策を持つことができる。商品管理データなど小売業側のシステムの改善が必要だが、すでにコンビニエンスストアの多くは高度なシステムを導入しており、ネット事業とも連携した動きが今後注目される。
金融業側から見れば、すでに数年前から高速道路で実現しているクレジットカードのサインレス支払いが拡大するかたちで、高速道路の年間総収入の多くがカード会社の取扱高になっていく。さらにETCシステムの民間利用が実現すると、そのロードサイドの小売業の多くの売上がICカードに関わってくる。当然人口が集積する地域で積極的に取り組まれることになろう。現在のETC用カードは料金支払い専用として設計されており、当面は買い物用カードを車載器で差し替えるなどの使い方になりそうだが、携帯電話での決済とは違う(おそらくより高額の)消費形態に対応する決済プラットフォームとして様々なビジネスが展開されることだろう。
ここが、前述の市場規模予測で最大の割合を占めながらもその具体像が明確になっていない「ITS情報通信サービス市場」及び波及効果の主要部分と考えてよいだろう。つまりITSが情報・金融プラットフォームの主要な一部分を形成することが、60兆円あるいは100兆円市場現出のカギである。
以上、いわばITS業界の地図を駆け足でながめてみたが、ここで十分に説明できていない業界も、今後さまざまなかたちでITSという社会システムにビジネスで参画してくることになるだろう。
4.建設業は、ITSの本質的理解を急げ
さて、土木建設業にとってITSとはどのような産業なのか。
ITSは、情報通信システムの活用によって道路拡張や立体化という「物理的道路容量拡大」を最小限に抑えるための道路交通システムであるから、電気設備工事という付加価値こそ発生するが、基本的には建設業にとって産業構造を変えるほどの大きな需要は創出されない。その点から、建設業界はITSについて、大手ゼネコン数社が道路交通シミュレーションソフトの独自開発を競争していることを除けば、あまり積極的ではないのが現状と言えるだろう。
1999年になって、建設省の提唱するスマートウェイ、経済産業省と総務省の掲げるスマートタウンといった「沿道のまちづくりを結びついたITSの導入」の実現に向けて、建設業の役割を描こうとする動きも起こり、ITS整備後の都市・沿道地域開発のビジョンをどう描いていくが、主な課題である。とくにETCの普及が進んだのち、「スマートインターチェンジ」化(料金所の無人化・キャッシュレス化にともなう、インターチェンジ導線のつけかえ工事、及び省スペース化)による余剰地活用プロジェクトの受注、また新規の小規模インターチェンジの増設工事などが期待されるが、これはETC車載器の普及にかかっており、まだしばらく先のことと捉えておくべきだろう。
建設業には、そうした知見も把握した上で、ITSの技術やその効用についてきちんと理解し、そのために必要になる都市インフラを整備する構想力が求められる。
5.最後は消費者の負担、を忘れず普及の実践を
ITS関連ビジネスにもまた、BtoC(Business to Consumer;消費者向けビジネス)、BtoB(Business to Business;企業向けビジネス)、BtoG(Business to Government;官庁、自治体からの受注)の3通りの収入形態が存在する。現時点では、電子機器メーカーやシステムベンダーによって、自動車へのOEMを中心とするBtoBや、路側通信機能の納入というBtoGが、有望なビジネススキームとして取り組まれている。しかし、結局できあがった自動車あるいは車載端末、もたらされる各種サービスという商品を買うのは市民=消費者であり、道路まわりの公共事業にしても税金を払うのは市民である。
技術シーズや国策先にありきではなく、市民にとって支払い感覚に足るサービスかどうかがBtoBの取引にも大きく左右する、というあたりまえの市場構造がITSにも当然ある。前述したように、官庁発の市場予測は「国策に頼るなよ、自分でチャンスを見つけて稼げよ」と暗に示している。
いまITS関連産業の抱える最大の問題は、ITSの消費財を市民にどう手渡すか、という具体的方策が実践できていないことにある。ここまで説明したITS関連産業において、ITSの担当部署のほとんどがいまだ開発セクションにあり、「売りの具体策」を考え実践する組織と円滑なコミュニケーションがとれていないケースが目立つ。
ITSはもはや技術実験の場ではない。消費者向けマーケティングと政策合意コミュニケーションの両面をもった社会システムの実践である。幸か不幸かITS関係者を含めた市民全員が「道路利用のプロフェッショナル」であり、ITS利用者の声はきわめて鋭く、大きく、リアルなものになるはずである。
この数十年間にクルマ社会が作り出した負の側面を考えるとITSという社会システムはもはや避けて通れない。それだけ深刻でかつ重要なプロジェクトに取り組んでいると言うには、現在語られているITS関連産業の展望は楽観的すぎる。
いまITS関係者すべてに求められるのは、ITSのマーケティング戦略、コミュニケーション戦略を、共有することである。官庁自治体しかり、自動車メーカーしかり、端末メーカーしかり、運輸業者しかり、メディア事業者しかり、である。共有しなければ、市民には必ず「たらい回し感」が生まれ、不信感は悪循環を起こす。
せっかくの追い風を活かすのは今のうちである。現実的な巨大産業であることは間違いない。ITSビジネス、いやITS全体成功のカギはただ一つ、その具体的な進め方である。
【図表】 ITS関連産業の広がり