大競争時代の情報通信産業 「アジアの拠点」へ大幅な規制緩和を
出典:日本工業新聞 「シンクタンクの目」 1996年2月
現在、分離・分割を含めたNTTの経営形態問題が電気通信審議会(郵政省の諮問機関)でまとめられ間もなく最終答申が出される。一方、産業界や学者グループでも本問題を討議、報告書が出されている。この問題の本質はNTTのあり方をどうするかというよりも、大競争時代のわが国電気通信あるいは情報通信産業の活性化・競争力強化、ならびにユーザーへの便益還元をどのように図るかにある。NTT問題をどのように認識したらよいのか。また、どう対処していくべきかを探ってみた。
●「だれでも、どこででも」の視点
NTT分割問題は1982年の第二次臨調基本答申で、電電公社の民営化並びに中央会社と複数地方会社の再編が盛り込まれたことに始まる。1990年には電気通信審議会(以下、電通審)で、長距離・移動体通信の分離と市内通信の再編成が答申された。しかし、当時の政治的判断や株価値下がり懸念などによって実施が見送られた。今月中には、電通審から再び答申が出される運びになっている。
現在のNTT分割問題には様々な利害関係者(ステイクホルダー)の主張が入り交じっている。例えば長距離系NCC(新規事業者)3社は、相互接続交渉に支障あり、として経営規模など競争条件の対等化を求めている。さらにNTT東と西で売上高2.5兆円ずつ、長距離会社で同1兆円程度の規模を想定した分離・分割により、NTTの内部相互補助はなくなり、地域会社間の間接競争が引き起こされる、と主張する。
また、TTNetなど地域電力系電話会社では、NTTの加入者線を公道(国民財産)として開放することを主張、併せて新規参入障壁(電気通信事業法の需給調整条項など)の撤廃を求めている。
一方NTT側は、①分離によって長距離部門からの内部相互補助の構造が機能しないとコストベースの料金体系に改変せざるを得ず、市内通話料金の値上げが起こる、②分割により地域網が固定化し、かえって独占の強化につながる、③世界でも稀な国際と国内という事業区分規制によって国際競争に取り残されていては、欧米の巨大通信会社に対抗できない―などと反論する。
KDDおよび国際系NCC2社は、当然のことながら、国際市場でのNTTの支配力を牽制している。
ステイクホルダーとしては、このほかに約19万人のNTT従業員(組合)、株価を維持したい約160万人の株主がいる。マルチメディアの進展によって、産業構造が変わり雇用シフトが必至であることに加え、NTT経営形態の変更による雇用不安がある。
株問題では、昨年の証券6社のレポートはどれも分割を歓迎する論調だった。しかしこれらのレポートは、規制緩和が前提になっている上に分割コスト要因が十分に考慮されておらず、「分割により株価上昇」とするのは直接的な分割効果とはいい難い。むしろ、株式流動性と株配当の問題が解決されず株価維持をだれも保証できない状況にある。
ユーザーの視点はどうか。分離・分割を行った場合、現行商法では、存続会社からの新会社への資産譲渡額のうち含み益の全額が課税対象となるため、NTTの試算では多額のコスト(約1.6兆円)が発生する。この費用が結局、料金値上げのかたちで跳ね返ってくるのではたまらない。
法人利用者は安く便利に使えること、すなわちマルチメディア時代における企業活動にこれまで以上に重要となる長距離や国際電話さらに専用線の料金の値下げを求めている。
また一般利用者では、インターネットなど通信の個人利用が急増するなかで、固定料金制など使いやすい料金体系を求めている。個人・企業を含めた地方ユーザーに対しては、全国の光ファイバー化の円滑な整備などサービス・料金両面で地域格差のないサービスの維持という「だれにでも、どこででも」という視点が必要である。
●メガトレンドをうまくとらえて
ユーザーの視点を考えると、問題の本質は競争導入・促進によるわが国電気通信市場の拡大と健全な発展にあり、この実現なしにはその便益がユーザーに還元されることはない。とりわけ、電気通信分野においては圧縮変換技術等のデジタル技術、CATV網の活用をも視野に入れた光ファイバーやインターネットによる情報ハイウェイ構築に不可欠なコンピューター・ネットワーク技術、移動体携帯電話などのワイヤレス技術は日進月歩である。
マルチメディアという情報通信の枠組みの中で、このメガトレンドをうまく捉えない限り市場ダイナミズムの創出はありえない。海外キャリアはこの技術革新のなか、放送分野を含めた熾烈な大競争時代を乗り切ろうとしている。
米国では1994年9月に、本体から製造とコンピューター部門を切り離すというAT&Tの3分割が発表された。しかし、これはNTTに比べて制約の少ないAT&Tがあくまで、一企業の経営戦略としてリストラを断行することに真意があったといえる。
通信は迂回を前提として設計された網が基盤にあり、鉄道のように途中下車が許されず利用者の端末同士(エンド・エンド)がつながって意味をなす一体型サービスである。こうした特性をもつ通信網を分断するといった無意味なことを行う国はない。
米国の場合ですら、独立網を保有する数々の電話会社が吸収合併を繰り返した後に旧AT&Tが誕生したこと、そして1984年のAT&Tの分割はもともと分割前に22あった地域会社を7つのBOC(ベビーベル)に統合再編したと見るべきだろう。
このように、各国の市場特性・成り立ちの相違により、これを理想モデルとすることはできない。より注目すべきは、昨年12月に報道されたBOC最大手のナイネックス社とベルアトランティック社の合併の動きに代表される地域市場の相互参入、あるいはAT&Tなど長距離会社やCATV会社の地域市場参入の動きである。
米国では市内と長距離の相互参入(サービスの一体化)が進みつつあり、近い将来現在、キャリア(電話会社)は5社程度に統合されるとの見方もある。1934年の通信法改正がさきごろ米議会で可決されたことは、この実態をいわば追認したものといえる。米国は通信・放送業界の大編成に入っている。
一方、欧州では英国がいち早く通信の民営化および自由化を推し進めた。1984年のブリティッシュテレコム(BT)民営化後、1991年の通信政策見直しにより、国際市場を除く複占体制が終了した。
最近のCATVの目覚ましい普及の加入者のうち、2割はCATV電話サービスを利用していることが注目される。欧州では、国際競争力および雇用の創出などが懸案事項である。米英の動きもあり、欧州単一市場の形成および経済発展のための汎欧州ネットワーク構築の必要性が欧州理事会で指摘され、電気通信自由化の一層の促進が1994年6月のバンゲマン報告に盛り込まれた。
こうした動きに合わせ、ドイツでは、1995年1月にDBPテレコムを民営化し、ドイツテレコム(DT)が誕生した。DTは1996年の電話料金リバランシング、1998年の国内市場自由化をにらみ「エンド・エンド」の一体型サービスを目指している。
フランスでも、競争の枠組みは未定ながらフランステレコム(FT)の民営化の動きがある。イタリアでは、地域、長距離、衛星系を統合し、念願のフラグキャリアを誕生させた。
わが国通信市場と主要諸外国とを比較したのが【図表1】である。
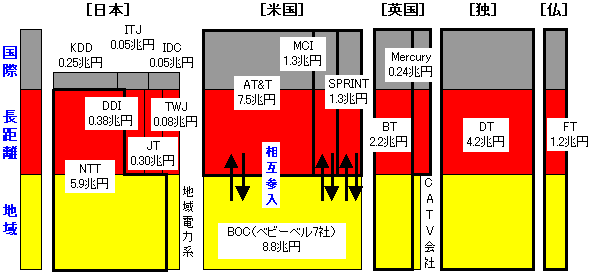
(注)数字は、NTT、KDD、ITJ、IDC、DDI、JT、TWJを1995年3月ベース、AT&Tを94年ベース、BT,DT、FTを93年ベースとして、1ドル=101円、1ポンド=161円、1マルク=88円換算時の売上高
(出所)日本総合研究所作成
わが国では市場が細分化されていること、国際市場が国内市場と切り離されていることが目につく。これに対し、海外ではAT&Tを中心としたグループ、DTとFTを中心としたグループ、BTを中心としたグループといった国際企業同士の合従連衡によるメガキャリア競争が急ピッチで進んでいる。NTTは規制により大きな遅れをとり蚊帳の外に置かれている。
メガキャリア志向は研究開発の点でも自然な方向である。これは、マルチメディアに対応すべくフラット組織で小規模の技術特化した企業の時代とする見方と対照を成す。しかし、主に情報を扱うソフト・コンテンツ型の多数企業群と、依然規模・範囲の経済が有効に機能するインフラ型の少数企業群による合従連衡の二極分化が顕著になったと見るべきだろう。
実際に米国では、7つのBOCによって共同運営されている研究開発会社、ベルコアの売却の動き、あるいはAT&T分割後のベル研究所の基礎研究水準の低下が指摘される。事業特性に合った組織体制の選択が重要である。
●「情報産業省」として将来再編も
わが国の電気通信市場は現在約10兆円弱の規模にある。2010年時の利用者一人当たりの可処分所得に占める通信費が大きく変わらないと仮定した場合、日本総研では市場規模を19兆円程度、と試算した。あくまで参考値だが、郵政省局長の私的「将来像研究会」はかつて、約27兆円と予測した。
また「通信」を含むマルチメディア市場全体では、123兆円(電通審)規模になるとのバラ色の将来像もある。情報通信が高成長分野であることは誰も否定しないが、これら楽観的数字は規制緩和を前提とした市場再編なしには、絵に描いた餅に終わる心配がある【図表2】。
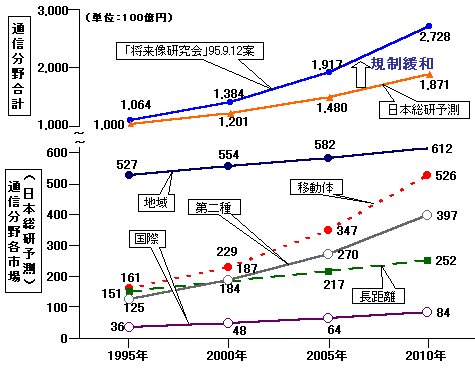
(注)郵政省電気通信局長の私的研究会「将来像研究会」案の書く数字は、1994-2010年の平均成長率を基に算出したもの
(出所)日本総合研究所作成
真の市場ダイナミズムを創出し、通信という戦略分野においてわが国がアジアでの国際ハブ(拠点)の地位を確保するには、国際・国内、長距離・地域、固定・移動体などの規制による細分化市場を改めるなど大幅な規制緩和が不可欠である。加えて国際戦略を明確にした上で、次のような手順で市場ダイナミズムを生み出すことが重要だろう。
第1段階では、昨年9月に公表されたNTTの加入者線開放による地域網接続を促進する。これとセルラー電話やPHS等のワイヤレスによる代替を育成する。
第2段階では、地域電力系電話会社の大連携ならびにCATV電話などの普及を促進する。全国の9電力会社の自前専用回線を相互接続すればNTTの専用回線の約4割に達し、有効な競争および提携等などにより多様なサービスが期待できる。こうした大がかりな競争環境を整備することが急務である。電力系やCATV事業者の「地域」、「長距離」系NCC、「国際」系NCC同士の大連合は最近の米国での動きにも通ずるもので、これによりNTTの事実上の独占である地域網のボトルネックが解消に向かうことが期待される。
第3段階では、NTTの本格的海外進出に加え、外資規制緩和による海外キャリアとの国内競争を進める。このステージの実現で料金並びにサービス競争の真の恩恵をユーザーは享受可能となる。例えば、日本にいてAT&Tサービスで安い国内通話ができ、英国滞在であれば現地でNTTサービスを通じて国際通話ができるなど世界中のサービスが利用できるようになる。
これらはいわば競争促進のための必要条件といえる。市場ダイナミズム創出のやめの段階的施策、競争促進のためには英国のオフテルや米国のFCCのように政策部門と規制部門を機能分離し、競争を監視し調停するための第三者機関の設立が我が国でも不可欠だろう【図表3】。
と同時に、通信とコンピューター産業の融合化が進んでいるなか、それに機動的に対応するために、関係省庁など既存組織を見直し、例えば「情報産業省」として再編することなども将来の検討課題となりそうだ。
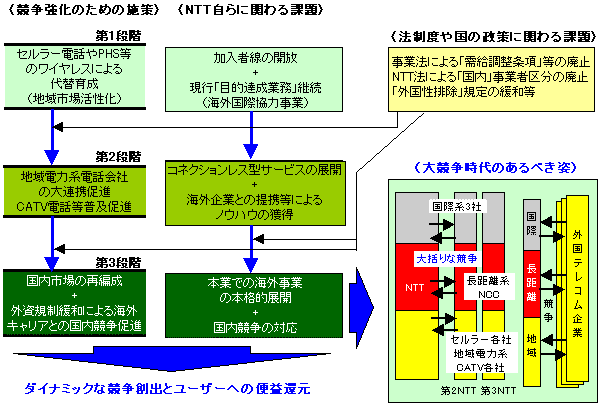
(出所)日本総合研究所作成

